8 女性
日本は、国内外において、「すべての女性が輝く社会」を実現することを標榜(ひょうぼう)し、そのための取組を強化している。
(1)G7伊勢志摩サミットでの合意事項
G7伊勢志摩サミットにおいて、女性分野を優先アジェンダの1つとして取り上げ、教育・訓練を含む女性のエンパワーメント、理系分野における女性の活躍推進や女性・平和・安全保障等に焦点を当て、「女性の能力開花のためのG7行動指針」及び「女性の理系キャリア促進のためのイニシアティブ(WINDS)」の立ち上げに合意した。
(2)国際女性会議WAW!(WAW! 2016)
12月13日及び14日、安倍総理大臣のイニシアティブで3回目となる国際女性会議WAW!(World Assembly for Women、略称:WAW! 2016)を開催し、日本及び11国際機関、26か国から93人の女性分野で活躍するリーダーが集まった。2016年のテーマは「WAW! for Action」で、「行動」を通じて「意識」を変え、あらゆる人が様々な制約を乗り越えて自分らしく活躍できるような社会を目指していこうというメッセージを打ち出した。女性の社会進出を阻む働き方や男女の役割分担意識の変革を訴えることに加え、女性の健康、平和・安全保障における女性の参画とエンパワーメント、地方創生についても議論した。議論された内容は、「WAW! To Do 2016」と題した提言に取りまとめられ、2015年に続き国連文書(番号:A/71/829)として発出された。

また、同会議の初日(13日)には、G7伊勢志摩サミットで立ち上げた女性の理系キャリア促進のためのイニシアティブ(WINDS)の特別イベント「STEM(科学・技術・工学・数学)分野で輝く女性の未来」も実施した。

(3)国際協力における開発途上国の女性支援
安倍総理大臣は、2013年の国連総会一般討論演説において、女性の地位向上を主眼として、①女性の活躍・社会進出推進と女性の能力強化、②国際保健外交戦略の推進の一環としての女性の保健医療分野の取組強化及び③平和と安全保障分野における女性の参画と保護の3分野に、2015年までの3年間で30億米ドルを超す政府開発援助(ODA)の実施を表明し、着実に実施した。2016年5月には、開発協力大綱に基づく新たな分野別開発政策の1つとして「女性の活躍推進のための開発戦略」を発表するとともに、2016年から2018年までの3年間で、約5,000人の女性行政官等の人材育成と約5万人の女子の学習環境改善の実施を表明した。また、同年12月に開催された第3回国際女性会議WAW!において、安倍総理大臣は、開発途上国の女性たちの活躍を推進するため、①権利の尊重、②能力発揮のための基盤の整備及び③政治、経済、公共分野におけるリーダーシップ向上を重点分野として、2018年までに総額約30億米ドル以上の支援を行うことを表明し、着実に実施している。
(4)国連における女性外交
3月に第60回国連女性の地位委員会が開催され、日本からは、武藤外務副大臣(首席代表)、橋本ヒロ子日本代表、各府省庁、国際協力機構(JICA)及びNGOから成る代表団が出席した。会議では、武藤外務副大臣が閣僚級ラウンドテーブルで議長を務めるとともに、女性のエンパワーメントと持続可能な開発との関連性や女性・女児に対する暴力の撤廃及び防止等について、各国代表者との意見交換に参加した。ステートメントでは、国際社会の一員として2030アジェンダの実現に向け責任を果たすことを強調した。
2016年のジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関(UN Women:United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women)に対する拠出金は約3,000万米ドルで、シリア難民女性のエンパワーメントやアフリカにおける暴力的過激主義対策などに使われている。今後とも同機関との連携を一層深めていく予定である。
日本は、「女子に対するあらゆる形態の差別撤廃に関する条約(女子差別撤廃条約)」に基づき、第7回・第8回政府報告を2014年9月に国連に提出した。また、事前の質問事項に書面で回答を提出するとともに、2016年2月16日にジュネーブで開催された政府報告審査には、杉山晋輔外務審議官ほかが出席し、委員からの質問に答え、慰安婦問題等に関し事実関係や日本政府の取組につき説明を行った(44)。なお、日本は、1987年から継続して女子差別撤廃委員会に委員を輩出している。
(5)紛争下の性的暴力に関する取組
安倍総理大臣が2014年9月に国連総会一般討論演説で言及したように、紛争の武器としての性的暴力は、看過できない問題である。加害者不処罰の終焉(しゅうえん)及び被害者を支援していくことが重要であるという観点から、国連アクションや紛争下の性的暴力担当国連事務総長特別代表事務所といった国際機関との連携や国際的な議論の場への参加を重視しつつ、21世紀こそ女性の人権侵害のない世界にするため、日本はこの分野に一層積極的に取り組んでいる。
日本は、2016年、紛争下の性的暴力担当国連事務総長特別代表事務所に対し、270万米ドルの財政支援を行い、支援対象国の警察・司法能力強化等に貢献している。さらに、国際刑事裁判所の被害者信託基金にも引き続き拠出を行っており、2016年は約4万7,000ユーロを紛争下における性的暴力対策にイヤーマーク(使途指定)して拠出し、被害者保護対策にも取り組んでいる。
(6)国連安保理決議第1325号等に関する「行動計画」
より効果的に「平和」な社会を実現するためには、紛争予防、紛争解決、平和構築のあらゆるフェーズで女性の参画を確保し、ジェンダーの視点を入れることが重要である。このため、日本は、国連安保理決議第1325号及び関連決議の履行に向けた「女性・平和・安全保障に関する行動計画」を策定し、2016年から「行動計画」の実施段階に入るとともに、モニタリングを開始し、2016年度末には年次報告書を公表する予定である。
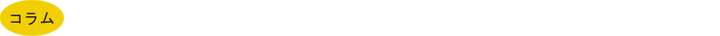
2016年12月13日・14日に日本政府主催で「国際女性会議WAW(ワウ)!」(World Assembly for Women:WAW! 2016)が開催されました。今回で3回目となるWAW! 2016には、26か国・11国際機関から93人の女性分野で活躍するリーダーが集まりました。

2016年のWAW!は「WAW! for Action」をテーマとして、「行動」を通じて「意識」を変え、あらゆる人が様々な制約を乗り越えて自分らしく活躍できる社会を目指していこうというメッセージを打ち出しました。
【モデレーター:マリエット・スクールマン北大西洋条約機構(NATO)女性・平和・安全保障担当特別代表、パネリスト:アウット・デン・アチュイル南スーダン・ジェンダー・児童・社会福祉大臣、スレイトーイッ・スン赤十字国際委員会カンボジア事務所職員、及びソクチャン・シエンバッタンバン女性障害者協会理事/車椅子バスケット連盟コーチ】
スクールマン氏は、2000年の国連安保理決議第1325号について、女性と平和・安全保障を初めて関連付けた「平和・安全保障のあらゆるレベルの意思決定過程への女性の積極的な参画を求める決議」であると説明しました。和平交渉や和平へのプロセスにおいて女性が重要で活発な役割を担っており、女性及び市民社会が関わった場合には、そうでない場合に比べて失敗する確率が64%も低いことや、女性が締結に寄与した和平合意の35%は15年以上維持されることを挙げ、ジェンダーの不平等がない社会ほど対立が少なくなるとして、女性が和平を担うための重要な役割を担っていることを強調しました。しかしながら、現在平和構築プロセスにおける女性の活躍推進に対しては政府開発援助(ODA)の0.4%しか充てられておらず、平和プロセスに携わる女性の割合が、交渉人9%、条約の署名者4%、国連による平和維持活動(PKO)に参加する軍人3%、同警察官10%(国連の目標値はいずれも20%)にとどまっている現状には、「女性を包摂するという考え方の欠如」が存在すると指摘しました。

アウット大臣は、本質的に女性は元々平和主義で、和平調停者でありながらも、地域の慣習によって女性がリーダーシップを発揮しにくい環境が生まれたり、家庭内における男尊女卑の意識によって女性のチャンスが奪われたりしているということが、女性の平和な社会への参画を阻む原因となっているとの考えを示しました。アウット大臣は、南スーダンの村々を自らの足で訪ねる中で、家庭内における男尊女卑の意識が政治にも反映された結果、女性を差別するような政策が存在し、女性は単なる有権者であって主導者にはなり得ないという意識が根付いてしまうことを実感したと述べました。そして、長い間女性が抑圧されてきた結果、女性は消極的になり、自らの権利擁護のために主張しない傾向が見られるため、男性だけでなく女性も考え方を変えるべきであると主張しました。現在、南スーダンでは、選挙の際に格差是正措置が採られた結果、女性国会議員数が100人に及び、和平合意へのプロセスに女性が積極的に参加するようになったことを例に挙げ、「女性は機会さえ与えられれば、手を伸ばして目的を果たそうとするが、ただ機会を待つのではなく、積極的に先導し、推進しなければならない」と力強く述べました。

ソクチャン氏からは、自らが紛争の流れ弾に当たって下半身不随になり、家族や夫から差別や家庭内暴力を受けるなどの苦労をしながらも、2012年に赤十字国際委員会からの支援によって立ち上げた障害者バスケットボール連盟が社会に出るきっかけとなったこと、それにより自信がついたエピソードが紹介されました。

障害者を支援する側のスレイトーイッ氏からは、障害を持つ女性と関わる日々の活動からは、障害があるというのは障壁では決してないこと、そして地域、社会がチャンスさえ与えれば健常者と同様に何でもできると感じるという現場からの声が届けられました。

最後に、スクールマン氏は、「女性が共に手を差し伸べれば世界を変えられる」と締めくくりました。

~女性アスリートを取り巻く環境や女性特有の課題~
【モデレーター:小谷真生子氏、パネリスト:伊調馨選手(リオオリンピックレスリング金メダリスト)、辻沙絵選手(リオパラリンピック陸上銅メダリスト)、成田真由美選手(アテネパラリンピック水泳金メダリスト)、三宅宏実選手(リオオリンピック重量挙げ銅メダリスト)】
伊調選手は、身体的には男性の方が力はあるが、女性には柔軟性があり、さらに精神的にも粘り強いという側面があるため、スポーツ競技を長く続けていく上では女性が秀でていると述べました。
監督としてもスポーツに取り組む三宅選手は、女性の筋肉は脂肪に変わりやすく、練習を少しでも休んでしまうと身体が丸みを帯びてしまうため、男女で練習メニューを変えなければならないことを例に挙げ、女性の特徴を理解した上で指導に当たる必要性を指摘しました。

辻選手は、女性の指導者やスタッフは少なく、ユニフォーム着用の補助を頼んだり、本番に向けた心構えを作る上でも、同性の指導者やスタッフがいることのメリットは多いとの考えを示しました。

伊調選手は、女性特有の体調の変化に関し、月経前後に体重が増加したり精神的に不安定になったりすることは女性アスリートにとって悩ましい問題であることに触れました。症状が重い選手は薬を服用することもあり、コーチやスタッフが男性である場合は理解を得るのが難しいことから、医師に相談したり自分に合った薬を見つけたりすることが重要であると指摘しました。
三宅選手は、結婚や出産に関する女性アスリートならではの悩みについて、オリンピック・パラリンピックに出場するためには練習に集中する期間が3年程度必要であるため結婚や出産と両立させるのは困難ではあるが、その一方で女性アスリートが結婚・出産を経験しても競技を続けていける時代が来ることを望んでいると述べました。
成田選手は、女性アスリートはいつも競技のことや身体のことばかりを考えているため、競技から離れたら女性としてお洒落(しゃれ)やグルメ等を楽しみたいと望んでおり、こうした女性らしさを意識する点もスポーツを通じて学んだことの1つであると述べました。

三宅選手:最近はオリンピックでも多くの女性が活躍するようになるなど、女性が強くなっている時代になっています。身体的な力の差はありますが、女性らしさを生かして自分にしかできないことをしていきたいと思います。
成田選手:2020パラリンピックでは、東京に来て良かったと世界の多くの人に思ってもらえるよう、パラリンピックを成功させたいです。女性が秘めているパワーは大きいですから、私は裏方から女性のパワーを世界に広めていきたいと思います。
辻選手:まだまだ女性が暮らしやすい世界ではなかったり、仕事にもやりにくさを感じたりすることもあると思いますが、スポーツを通して、女性の良さをどんどん伝えていきたいです。それぞれ得意なこと、上手なことなど各分野で一緒に頑張っていけたらよいと思います。
伊調選手:これまでスポーツを通じてたくさんの経験をしてきた一人の女性として、またスポーツ選手として、(様々な課題に関して)社会に問題提起をし、その解決に尽力していきたいです。
44 詳細はhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000136254.pdfの質疑応答部分の杉山外務審議官発言概要参照
