1 米国
(1)日米政治関係
日米両国間では、日本の外交・安全保障の基軸である日米同盟を、首脳・外相レベルを始め、あらゆるレベルでの信頼関係強化と緊密な政策協調を通じ、深化・発展させてきている。
2011年1月、前原外務大臣は米国を訪問し、「アジア太平洋に新しい地平線を拓(ひら)く」と題する講演、日米外相会談、バイデン副大統領への表敬等を行った。前原外務大臣はこの講演において、日米両国に課せられた最優先の課題は変革期のアジア大洋州地域における新しい秩序形成に取り組むことであるとし、具体的には、EASの役割の拡充・強化や、APECにおける連携、成熟した民主主義や市場経済を共有する国々との連携強化による協力システムの構築などを挙げた。また、日米外相会談では、同盟深化の中身を詰めていくことを再確認し、強固な日米同盟に基づき、アジア太平洋の平和と繁栄の観点から地域の諸課題について緊密に連携していくことで一致した。
3月11日の東日本大震災に際し、日米両国は緊密に連携し、未曽有の危機への対応に当たった。発災から僅か1時間半後、米国は諸外国に先駆け、支援の用意がある旨日本政府に対して伝え、松本外務大臣は11日中に正式に支援を要請した。15日には、パリでのG8外相会合の際に日米外相会談が行われ、復旧・復興に向けた日米連携を中心に、緊密な意見交換が行われた。具体的には、松本外務大臣は、震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故に対する米国の支援に対し謝意を表明したのに対し、クリントン国務長官は、米国政府は日本が必要とするいかなる支援も惜しまないと述べ、震災支援に対する米国のコミットメントを改めて強調した(第2章第2節コラム「東日本大震災に際しての米国の支援」参照)。
その1か月後の4月17日、クリントン国務長官は日本との強い絆を示すため日本を訪問した。日米外相会談において、両大臣は、原発事故に関して引き続き緊密に協力していくことで一致するとともに、復興に関する日米官民パートナーシップの推進を発表した。松本外務大臣は、同発表及び米国の諸外国に先駆けた日本への渡航制限緩和が、日本経済にとって前向きなメッセージであると評価したのに対し、クリントン国務長官は、米国からの連帯のメッセージを日本国民に伝え、また日本がビジネス・旅行先としてオープンであることを米国民に伝えることが来日の目的であると応答し、日本が「営業中(Open for Business)」であることを内外に強く示した。
同月29日、松本外務大臣は、米国政府及び米国民からの様々な支援・お見舞いに対し、直接感謝の意を表明するとともに、震災後の対応で一層緊密化した日米同盟を更に深化・発展させるため、就任後初めての二国間訪問として米国を訪問した。外相会談において、両大臣は、復興に関する日米官民パートナーシップにおける日米両国の協力の進め方について一致した。また、両大臣は、震災以外の事項についても、北朝鮮や中国などのアジア太平洋地域情勢、アフガニスタンや中東・北アフリカ情勢といったグローバルな課題について議論を行った。
5月、G8ドーヴィル・サミット(於:フランス)に際して菅総理大臣は日米首脳会談を行った。菅総理大臣は、米国からの支援への謝意を示しつつ、日本は必ず復旧・復興して世界の諸問題につき米国と連携し、一層力を発揮していきたいと述べ、引き続き日米同盟を深化させていく意思を伝えた。オバマ大統領からは、強い日本は非常に重要であり、国際社会における様々な問題に効果的に参加していくというメッセージを評価したい、日本の復興を支援していくとの応答があった。その上で、両首脳は、日米関係の諸課題、さらに中東情勢、アフガニスタン・パキスタン、北朝鮮に関して意見交換を行った。
6月には、ワシントンにおいて、日米の外務・防衛担当の4閣僚が集まり、日米安全保障協議委員会(いわゆる「2+2」閣僚会合)が開催された。この中で日米両国は、これまでの安保・防衛面における同盟深化の協議プロセスの成果を確認するとともに、今後の日米間の安全保障・防衛協力の方向性を示した(第3章第1節1「日米安全保障体制」参照)。
こうした流れの中、7月、ASEAN関連外相会議の際に行われた日米外相会談において、両大臣は、今後「2+2」の成果を着実に実施することが重要との認識で一致し、また、地球規模の課題について引き続き日米で協力すべく、米国が議長を務める2011年のAPECに向けて連携していくことを確認した。また、同会談前には、両大臣は金星煥韓国外交通商部長官を交え、日米韓外相会合を行った(第2章第1節1「朝鮮半島」参照)。
8月には、バイデン副大統領が来日し、菅総理大臣との会談や被災地への訪問等を行った。菅総理大臣との会談において、バイデン副大統領は、米国が日本を支援したことは当然のことであり、むしろなぜもっと日本を支援できなかったかと悔やんでさえいると述べ、米国と共にアジア太平洋地域の国家であり、また同盟国である日本の経済力・政治力が極めて重要であることを強調した。また、バイデン副大統領は仙台空港での演説において、日本が「営業中(Open for Business)」であることを改めて内外に示すとともに、日本人の精神力を称賛し、日本が困難に直面した時、米国は必要なだけ日本を支え続けると明確に述べ、被災地の人々を勇気付けた。
9月、野田政権が発足し、野田総理大臣は、第178回国会における所信表明演説の中で、日米同盟が日本の外交・安全保障の基軸であり、アジア太平洋地域のみならず、世界の安定と繁栄のための公共財であることに変わりはないと明言し、引き続き日米同盟を深化・発展させていく意思を明確に示した。
同月、国連総会に出席した野田総理大臣及び玄葉外務大臣は、それぞれ日米首脳・外相会談を行った。玄葉外務大臣は、外相会談において、新内閣においても日米同盟が日本外交の基軸であり、これを一層深化・発展させていきたいと述べた。クリントン国務長官からは、日米は地域及び地球規模の課題に取り組んでおり、米国としては、日米同盟を更に強化する確固たる意志があるとの応答があった。その上で、両大臣は安全保障、経済、文化・人的交流や子の親権(第3章特集「ハーグ条約」参照)などの二国間の課題、またアジア太平洋地域情勢・地球規模の課題も含め、幅広い議題について議論した。
首脳会談においては、オバマ大統領から、世界の二大経済国として、同盟国である日本と生産的な話合いを行いたいと述べたのに対し、野田総理大臣から、震災復興・原発事故収束が最優先の課題であるが、発災以前からの内政・外政上の課題を解決し、安定した政権を作るのが自分の使命であると述べ、震災の際の米国からの支援を通じ、日米同盟が日本外交の基軸であるという信念が揺るぎないものとなったと伝えた。両首脳は厳しさを増す国際経済情勢についても意見を交わし、野田総理大臣は、日米の経済が強くあることは世界の繁栄・安定に重要であり、両国が経済成長と財政再建を両立させるとともに、G20等多国間枠組みを通じて緊密に連携していくことが重要であると述べ、欧州債務危機についてはまずは欧州の迅速な対処が不可欠であるとの考えを示した。また、両首脳は、ホノルルAPECで具体的な成果が得られるよう緊密に協力していくことで一致した。
11月には、野田総理大臣及び玄葉外務大臣がAPEC首脳会議及び閣僚会議出席のためハワイを訪れ、それぞれ日米首脳会談・外相会談を行った。日米外相会談において、玄葉外務大臣は、クリントン国務長官のアジア太平洋政策に関する論文に言及し、民主的価値を基盤に豊かで安定した世界を築くことが自分の主要な外交目標の一つであり、日米両国で様々な課題に対してリーダーシップを発揮していきたい、その意味で、2011年のAPECやEASが重要であると述べた。その上で、両大臣はAPEC、EAS、北朝鮮、ミャンマーなどアジア太平洋地域情勢について率直なやりとりを行った。
日米首脳会談においては、野田総理大臣からは、アジア太平洋地域における米国の存在感が高まっていることに非常に勇気付けられている、この地域における経済のルールや安全保障秩序の構築などにおいて日米両国で緊密に連携していきたいと述べた。また、野田総理大臣から、TPP交渉参加に向けて関係国との協議に入ることとしたとオバマ大統領に伝えた((2)日米経済関係参照)。そして、両首脳は、EASを翌週に控え、EASを地域の政治や安全保障の課題を扱う主要なフォーラムにすべきとの点で一致した(第2章第1節6「地域協力・地域間協力」参照)。
また、同11月、オーストラリアへの米海兵隊のローテーション展開の発表、EASへの初参加に具体化されたように、米国はアジア太平洋地域を重視する姿勢を改めて明確にした。オバマ大統領は、オーストラリア連邦議会での演説において、米国が太平洋国家であり続け、アジア太平洋地域を最優先とし、地域におけるプレゼンスを維持・強化する方針を表明し、その中で日本を米国の同盟国として、アジア太平洋地域の安全における礎として位置付けると強調した。こうした米国の表明に対して、玄葉外務大臣は、アジア太平洋地域における日米協力を外交の柱の一つとして位置付ける日本にとって大変心強い方向性であると評価し、12月、就任後初となる二国間の文脈での米国訪問に臨んだ。
玄葉外務大臣の米国訪問中、北朝鮮の金正日国防委員長死去が発表された。これを受けて、日米両国は迅速な意思疎通を図った。日米外相会談では両大臣は北朝鮮情勢について突っ込んだやりとりを行い、今回の事態が朝鮮半島の平和と安定に悪影響を与えないことが重要であるとの認識を共有した。また、日米及び日米韓で緊密に連携していくことを確認するとともに、六者会合パートナーと緊密に協調する必要があるとの見解を共有した。また、翌20日朝には、野田総理大臣とオバマ大統領との間で日米首脳電話会談が行われ、両国で緊密に連携していくことが確認された(第2章第1節1「朝鮮半島」参照)。
約2時間に及んだ外相会談では、朝鮮半島情勢に加え、玄葉外務大臣から、様々な共通の課題に中国を交えて取り組んでいくということが重要であるとして、日米中対話を提唱し、クリントン国務長官から賛同の意向が示された。両大臣は対ミャンマー政策について、両国が共通の目標の下で役割分担をしながら緊密に連携することでも一致した。また、玄葉外務大臣からは震災復興の施策の一環として、青少年交流事業「キズナ強化プロジェクト」の立ち上げを紹介し、両大臣は2012年の日米桜寄贈100周年を、日米交流を深める機会としていくことで一致した。


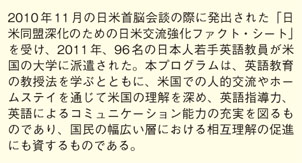
(2)日米経済関係
世界経済情勢が変化する中、日米が、両国経済のみならず、アジア太平洋地域経済、世界経済の新たな成長を実現し、地球規模の課題に対処するため、経済分野における協力を更に強化していくことが重要となっている。
東日本大震災を受け、両国政府は、震災復興に関する協力を進めている。4月17日の日米外相会談後の共同記者会見では、米倉経団連会長及びドナヒュー全米商工会議所会頭も同席の上、松本外務大臣とクリントン国務長官が震災後の復興に向けた官民パートナーシップを進めていくことを発表した。その後、同パートナーシップでは、当面、日本経済に対する国際社会の信認を強化していくことを目指し、まずは、風評被害を防ぎ、サプライチェーンにおける日本の役割の減少の懸念に歯止めをかけることに焦点を当てて協力を進めていくこととし、そのような趣旨にかなうイベントの後援や、米国ビジネス界への説明会などを実施した。米国政府は、本パートナーシップの一環として、日本政府や日米企業などの協力により、被災地の復興や日米間の青年交流等を支援する「トモダチ・イニシアティブ」を主導し、その具体化を進めている(第2章第2節コラム「東日本大震災に際しての米国からの支援」参照)。
米国がAPEC議長を務めた2011年は、アジア太平洋地域の更なる成長や、統合に向けた連携が進んだ1年でもあった。2010年にAPEC議長を務めた日本は、ホノルルAPEC成功に向けて米国と緊密に協力し、2011年11月のホノルルAPECの際の日米首脳会談では、オバマ大統領から、昨年の横浜APEC以来の日本の取組や米国との協力に対し評価の言葉があった。両首脳は、アジア太平洋地域の経済統合実現のため、APECを通じた協力を日米で共に進めていくことで一致した。また、同会談において、野田総理大臣から、①日本政府として、TPP交渉参加に向けて、関係国との協議に入ることとした、②2010年11月に決定した「包括的経済連携に関する基本方針」に基づき高いレベルの経済連携を進めていく、③今後交渉参加に向けて米国を始めとする関係国との協議を進めたく、オバマ大統領の協力を得たい旨を伝え、オバマ大統領からは、日本の決定を歓迎するとともに、今後の協議の中で日本側と協力していきたい旨の発言があった。これを受け、2012年2月には、米国との協議を開始した。
幅広い分野での二国間の対話・協力も進んだ。2010年11月の日米首脳会談を受けて立ち上げられた日米経済調和対話では、日米間の貿易円滑化、ビジネス環境の整備等に取り組むため、2011年に2回の事務レベル会合(2~3月及び同7月)と1回(10月)の上級会合を実施した。これらの会合を踏まえて、2012年1月に発表された協議記録には、経済分野の日米連携の一層の強化に向けて具体的な進展があったことが示されている。このほか、クリーンエネルギー、レアアース、イノベーション・起業、インターネット・エコノミー、高速鉄道、科学技術等、日米両国の新たな成長につながる分野での対話・協力も進展している。
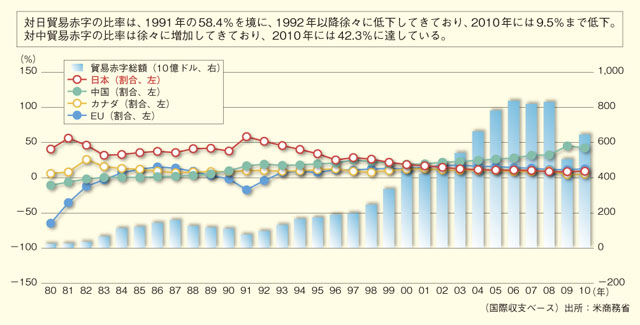
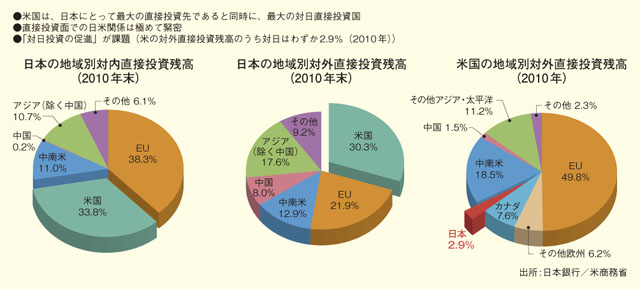
(3)米国情勢
ア 政治
オバマ政権にとっての2011年は、外交・安全保障面では国際的テロ組織・アル・カイーダトップであるウサマ・ビン・ラーディン殺害(5月)、イラク駐留米軍の完全撤退の実現(12月)等国民からの支持を集める成果を上げる一方、内政面では多くの困難に直面した1年であった。
大統領選挙を翌年に控えた政権にとり、景気・雇用対策と財政赤字削減の両立は引き続き内政上の最重要課題であった。2010年11月の中間選挙の結果、ティーパーティー系(1)議員を含む保守派共和党議員の発言力が増大した議会では、景気浮揚と弱者救済のため一定の財政出動は不可避とする政権・民主党と、小さな政府を志向し増税反対・社会保障費を含む歳出の大幅削減を主張する共和党との間でしばしば議論が膠(こう)着した。その結果、4月には連邦政府閉鎖(シャットダウン)の危機が発生し、8月には連邦政府がデフォルト(債務不履行)に陥る可能性が高まるなど、深刻な事態が繰り返し生じた(イ経済(イ)各論参照)。これらの危機はいずれも直前で回避されたものの、現実のものとなれば国民生活や国内外の経済に重大な影響を及ぼし得るものであった。このような危機を繰り返し招いたことで、国民のワシントン政治に対する不信感は一層高まり、オバマ大統領に対する国民の支持率は一時政権発足以来最低の40%にまで落ち込んだ。
2012年11月の大統領選挙に臨むオバマ大統領にとって、国民の最大関心事である景気・雇用問題に対する取組を通じ、国民の信頼を取り戻していくことは、再選への鍵となる。同大統領は、共和党との対立から議会審議がこう着する中、議会を通過させる必要がない行政措置・大統領令を活用した経済対策を実施する等、景気・雇用問題に着実に取り組む政権・民主党の姿を国民に印象付けようとしている(イ経済(イ)各論参照)。
大統領選挙に向けた動向に関しては、オバマ大統領の支持率が低迷する一方、共和党の候補者選びも飛び抜けて有力な候補者が存在しない状況が継続した。6月の正式出馬前から最有力候補と目されていたロムニー前マサチューセッツ州知事が党内保守派の支持を固め切れない中、対抗する有力候補がバックマン現下院議員、ペリー現テキサス州知事、ケイン元ピザチェーン店CEO、ギングリッチ元下院議員、ポール現下院議員、サントラム元上院議員とめまぐるしく替わり続け、2012年1月3日のアイオワ州党員集会から始まる予備選挙を迎えることとなった。
イ 経済
(ア)総論
2008年のいわゆるリーマン・ショック以降、政府による金融機関支援や景気刺激策等の政策効果もあり、GDP成長率は2009年第3四半期以降プラスに転じたものの、2010年後半から低下し、2011年に入るとその回復は大幅に鈍化した。失業率も、2011年半ば以降緩やかに低下し、2012年1月には8.3%と2009年2月以来の水準にまで回復したものの、依然として高水準にとどまっている。高い失業率の継続や住宅価格の下落等、景気回復が停滞するリスクが残るとともに、財政赤字の削減も不可欠であり、経済回復と財政再建の両立が政府の優先課題となっている。
2012年1月の一般教書演説においてオバマ大統領は、優先課題である経済成長、雇用創出及び国際競争力強化のため、製造業振興、輸出促進、エネルギー開発推進及びクリーンエネルギーを始めとするイノベーションを支援する方針を示すとともに、財政赤字削減に取り組む決意を示した。また、富裕層向けのいわゆる「ブッシュ減税」の問題点や「バフェット・ルール」に言及しつつ、公平性確保のための税制改革の必要性を強調した。
(イ)各論
経済回復をめぐっては、2011年1月、オバマ大統領は、ビジネス・リーダー等から成る「大統領雇用・競争力評議会」を設置し、議長をジェフリー・イメルトGE会長兼CEOとする旨の発表を行った。9月には、オバマ大統領は、約4,500億米ドル規模の米国雇用法案を議会に提案した上で、同法案を即座に通過させるよう要請したものの、議会での審議は難航し、最終的に成立したのは、社会保障税減税及び失業給付延長措置の2012年2月末までの延長等、退役軍人の雇用促進策等のみにとどまった。
財政再建をめぐっては、4月に連邦政府閉鎖への期限が迫る中、歳出を前年度水準から400億米ドル削減した2011会計年度(2010年10月~2011年9月)歳出法案が可決された。8月には、連邦政府のデフォルト懸念が高まる中、連邦政府の法定債務限度額を引き上げる法律が成立し、10年間で歳出を9,000億米ドルの歳出削減がなされるとともに、超党派の特別委員会を設立し、更なる財政赤字削減策を検討することとされた。しかし、民主・共和両党の激しい対立の結果、11月、同委員会共同議長は「超党派の合意に至ることは不可能との結論に達した」との声明を発表した。
米国連邦準備制度理事会(FRB)は、2011年8月に開催された米国連邦公開市場委員会(FOMC)定例会合において、「少なくとも2013年半ばまで、フェデラル・ファンド金利の異例な低水準が正当化される可能性が高い」と表明した。さらに、9月には、いわゆるツイスト・オペ(2)の実施、住宅ローン担保証券への再投資を表明した。
通商面では、2010年の一般教書演説でオバマ大統領が提案した「国家輸出イニシアティブ」に基づき、向こう5年間での輸出倍増を目指し、様々な輸出促進策がとられた。ブッシュ政権下で署名後、議会による承認が得られていなかった韓国、コロンビア、パナマとのFTAについては、2011年10月に米国議会で実施法案が可決し、オバマ大統領が署名した。また、TPPについては、11月のホノルルにおけるAPEC首脳会議の機会に開催されたTPP首脳会議において、協定の大まかな輪郭を示す文書が発出された。
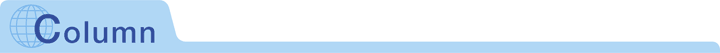
2011年3月11日に発生した東日本大震災に際しての米国からの支援は、その内容と規模において突出しており、多くの日本国民にとって米国との同盟関係を改めて心強く感じさせるものでした。日米両国は、発災当日の首脳電話会談を皮切りに、3月の間に5回に及ぶ首脳・外相間での電話会談を実施するなど、両国政府のあらゆるレベルで緊密な意思疎通を図り、この未曽有の震災に対応しました。オバマ大統領が繰り返し「可能なあらゆる支援を行う用意がある」と表明したように、米国からは震災直後から米軍の展開、レスキュー隊、原子力専門家の派遣など迅速かつ大規模な支援を受けました。また、国民レベルでも、米国各地で多くのチャリティー・イベントが開催され、民間団体や著名アーティスト、幼い子供を含め、多くの米国民からの励ましの言葉が届いたほか、米国赤十字への義援金は2億9,600万米ドルに達しました(注)。こうした東日本大震災への対応・支援を通じ、日米同盟の強固さ、そして日米両国民間の絆の強さが改めて証明されました。ここでは、その中でも、トモダチ作戦及びトモダチ・イニシアティブ(TOMODACHI)に焦点を当て、インタビューも交えつつ、その内容を紹介します。
震災発生直後、西太平洋沖に展開していた空母「ロナルド・レーガン」を始め、米軍は迅速に被災地支援作戦を開始しました。自衛隊との緊密な協力の下行われたこの作戦は、「トモダチ作戦」と命名され、米軍は、最大時人員約2万4,500名、艦船24隻、航空機189機(全て在日米軍公表の数値)を投入するなど、空前の規模で行方不明者の捜索・救助、被災地への物資の輸送・提供、空港の復旧作業、さらには東京電力福島第一原発に関連する様々な支援といった幅広い活動を実施しました。このような米軍の献身的な働きぶりを目にした被災者から感謝の言葉が寄せられるなど、被災地では作戦名の「トモダチ」にふさわしい多くの心の交流も生まれました。こうした活動は、日頃の協力に基づいた日米同盟の強固さを示すものであると同時に、日本にとっての日米同盟及び在日米軍の重要性を改めて認識させるものでした。


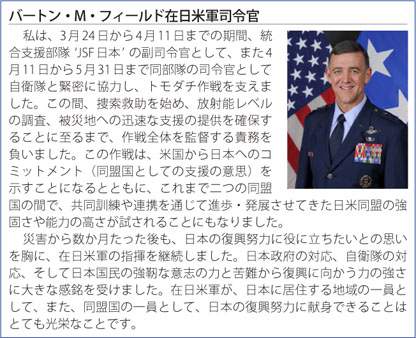
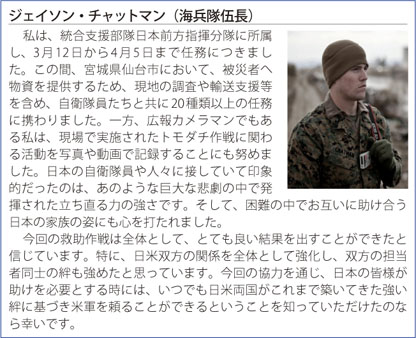


トモダチ・イニシアティブ(TOMODACHI)とは、東日本大震災からの日本の復興を支援するとともに、日米間の文化的・経済的な結びつきを更に強化し、友好を深めるべく、両国の将来の世代に投資する官民の協力です。米国政府及び非営利公益法人の米日カウンシルが主導し、日本政府のほか、日米両国の企業・団体・個人が幅広く支援を行っています。TOMODACHIは、互いの文化や国柄を理解し、日米同盟を支える「TOMODACHI世代」の育成を目指しており、そのために教育、異文化交流、起業支援、指導者育成等のプログラムを実施・支援しています(詳細はhttp://www.usjapancouncil.org/を参照)。
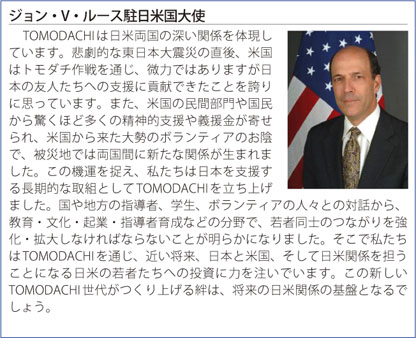


1 小さな政府を主張し、オバマ政権のヘルスケア政策等を批判。全国的な組織を持たない市民運動だが、最近の米国の選挙で大きな影響力を持つ。
2 「オペレーション・ツイスト」ともいわれ、中央銀行が長期証券を購入する操作と、短期証券を売却する操作、若しくはそれぞれの証券の購入と売却を同時に行うことで、通貨の資金量を基本的に変えることなく、長・短期金利を逆の方向に動かす市場操作のこと。

注 米国赤十字社が2011年8月11日現在として公表している米国赤十字社の集金額。