事例2 気候風土に合った校舎デザイン、環境に配慮した資材
学校建設日本民際交流センター(民際)
※NGO:非政府組織(Non-Governmental Organizations)
1994年より、日本の建築家ボランティアとともにラオス国内で、学校や建築物の調査を行った。
ラオス教育省標準タイプの校舎は、レンガ壁で囲い天井を設けにはレンガが使われ、もろいのでモルタルを塗り、ペンキを塗っている。エアコン、電灯があればまだしも、また、レンガを作るのに、大量の木を使って焼いている。高温多湿な風土に馴染まないと感じた。
民際では、ラオスの気候に合った、快適で、耐久性も高い校舎を設計。ラオス国内で、住民が生産できる資材として「インターロッキングブロック」を導入。ブロックは少量のセメントと現地でも広く分布するレテライトソイル(紅土)を混ぜ、人力プレス機で圧縮して造るため、現地で入手可能な材料を使え、かつレンガのように焼かずにすむので、森林伐採などの環境破壊も防げる。97年より南部のカムアン県、セコン県で10校を建設している。
■奨学金、教員養成などと総合的に
また学校建設は目的でなく、子どもたちが基本的な教育を受ける機会を得るための支援の一手段と考えている。学校があっても、通うことができる子どもがいて、先生がいるという条件が満たされなければ、本来の目的は達成でいない。その意味でも、奨学金、教員養成などの事業と総合して学校建設を行っている。さらに校舎は、学校外教育等の場にも活用できるような配慮も必要であろう。
【基本方針】
| 1. | 電気がきていない所でも快適な教室にするために、自然通風、自然採光を確保する。 |
| 2. | 寄付によって賄われる建設資金が現地に還元されるように、できる限り現地の材料を用いる。 |
| 3. | 現地の人が建設に参加できるようにする。またその過程でメインテナンス、補修を自分で行える技術の移転をはかり、耐久性の向上をはかる。 |
<高窓をつけ、自然採光。自然通風に配慮した快適な教室>
| ● | 赤道に近いので、太陽が東から上り、ほぼ真上を通って西に沈む。東西に長く建てると庇で直射日光を遮ることができる。 |
| ● | 高窓をあけ、屋根に当たる反射光を間接光として利用。反射するように扉も白く塗る。 |
| ● | あえて隙間をつくり、光を入れる。 |
| ● | インターロッキングブロックで教室間の境界線を作り、木製トラスを架ける。 |
| ● | 基礎は安全性を高め、コンクリート製とする。日本から簡単な地盤の検査機械を導入。 |
| ● | 周囲に植える木は、育ちが早く、葉が横に広がるものにし、温度を抑える。 |
| ● | 低学年、高学年の体格の差を考え、机は2種類の寸法で作る。 |
<インターロッキングブロック>
| ラテライトソイル(紅土)にセメントを混ぜて作る(セメント1:土6~7)。プレスして4週間寝かせると高い強度が得られる。 10センチメートル×15センチメートル×30センチメートル。上面に凸部、下面に凹部をつくり、玩具のブロックのように積み上げるだけで固定され、モルタルが不要となる。ブロックは、ラテライトソイルによって地元の土の色になる。セメントだけを輸入すればよく、現場で製作できるので、建設費はラオスに還元できる。 |
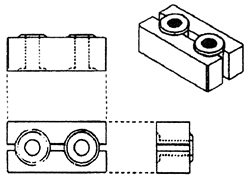 |
<建設にあたって>
●建設費用はいくら?
建設費は、6部屋タイプで約420万円。入札を実施し、資材数量、単価などを監査。教育省標準タイプ校舎の見積もり書と比較し、ほぼ同額でつくっている。
●建築への住民の参加
ブロックづくりの研修をする。熟練が不要なので、住人が製作も壁積みもでき、品質も問題ない。
ただし、良質の校舎を住民だけで建てるのは無理。
●住民の意識は?
住民は、「学校ができればうれしい」という反応。教育省タイプと民際タイプとで、どちらがよい悪いというのではない。重要なのは、むしろ村に学校の受け入れ態勢ができているか、否か。それによって管理体制も変わる。
●政府の意向は?
森林伐採への対策として、ラオス政府は木材の国内消費に規制をかけている。木を使った校舎の建設は難しくなっている。鉄骨も使うように検討するが、10年もたてば錆び始めると思われる。
ラオス政府は、学校数を増やすために校舎の質を下げている。規制外の安い木材を使い、改築しやすい校舎を建てる動きがある。同様に、コストダウンのため、瓦からトタンに変えているが、トタンは2年ももたないと考えられ、夏は暑く、雨音がうるさい。
(建築家、加藤隆久氏のプレゼンテーションから森透が構成)

