3 国際的なルール作りへの参加
(1)G8/G20サミット
日本が自らの取組を国際社会にアピールし、日本にとって望ましい国際的経済秩序を形成していく場として、G8・G20サミットは引き続き重要な役割を果たしている。6月のG8ロック・アーン・サミット(於:英国)では、例年議題となる世界経済、シリア・北朝鮮等の地域情勢に加え、議長国・英国が主要テーマとした3Ts(税(Tax)、貿易(Trade)、透明性(Transparency))、1月のアルジェリア事件を踏まえたテロ対策などについて、首脳間で率直な意見交換が行われた。安倍総理大臣は、アベノミクスについて説明し、成長戦略の実施を通じて成長力を高めるとの決意を表明した。これに対し、各国から高い評価と強い期待が寄せられた。そのほか、アフリカの貿易深化やテロ対策に向けたTICAD Vの成果、税や透明性分野における日本の取組についても、G8諸国からの理解・支持が得られた。

「国際経済協調の第一のフォーラム」であるG20は、リーマン・ショック後の金融危機や近年の欧州債務危機への危機対応を経て、その役割が徐々に平時における協調へと変化してきている。こうした現状を踏まえ、9月のG20サンクトペテルブルク・サミット(於:ロシア)では、世界経済の成長と雇用創出を主要議題として、首脳間で活発な議論が行われた。その際、世界経済をより強固で、持続可能かつ均衡ある成長への道筋に乗せるため、財政再建及び構造改革など、断固とした取組を進めることで一致した。日本の経済政策・財政政策に対しては、G20各国から強い期待と高い評価が示された。また、貿易分野の成果として、新たな保護主義的措置を設けない(スタンドスティル)とのコミットメントの期限が2016年末まで延長された。
(2)世界貿易機関(WTO)
ア WTOとドーハ・ラウンド交渉の経緯
戦後、日本の経済発展は、関税及び貿易に関する一般協定(GATT)/世界貿易機関(WTO)を中心とする多角的貿易体制に支えられてきた。GATTを受け継いだ形で設立されたWTOでは、規律の対象分野の拡大や紛争処理機能の強化などが行われ、WTOの下での多角的貿易体制は今日の世界貿易の礎となっている。WTOの主な役割は、①貿易自由化と新たなルール作り、②協定の実施の監視と紛争解決制度を通じたルール遵守の確保である。2001年に開始されたWTOドーハ・ラウンド(DDA)(7)交渉は8分野(農業、非農産品市場アクセス、サービス、ルール、貿易円滑化、開発、環境、知的財産権)について行われてきたが、新興国と先進国との対立などにより膠着状態に陥った。2011年末の第8回WTO閣僚会議(MC8)では、部分合意等可能な成果を積み上げる「新たなアプローチ」を採用することが合意され、2013年末の第9回WTO閣僚会議(MC9)での妥結を目指して交渉が行われてきた。
イ 第9回WTO閣僚会議(MC9)
2013年9月にブラジル出身のアゼベド新WTO事務局長が就任した。同事務局長の主導の下で交渉が活性化し、同年12月にバリ(インドネシア)で行われたMC9では、DDA交渉の部分合意として①貿易円滑化、②農業、③開発の3分野から成る「バリ合意」が妥結した。これは、WTOの歴史が始まって以来初の全加盟国による多数国間協定となる貿易円滑化に関する協定を含むものである。159にも及ぶメンバーがコンセンサスにより新たなルールに合意したという点で画期的な成果といえる。また、MC9においては、12か月以内にバリ合意以外のDDA交渉の残された課題について作業計画を策定することとされた。これらの結果を受け、今後、多角的貿易体制の下での貿易交渉の進展が期待される。日本はWTOの主要メンバーとしてDDA交渉に積極的に取り組んできており、今後も多角的貿易体制の維持強化に貢献していく考えである。
(ア)貿易円滑化
税関手続の簡素化・迅速化・貿易規制の透明性向上などを規定する貿易円滑化に関する協定の内容について合意された。本協定は、貿易取引の時間とコストを削減し、貿易の促進に資するものであり、先進国のみならず、開発途上国にも利益となるものである。この合意では、2014年7月までにこの協定をWTO協定に組み入れるための改正議定書を採択し、2015年7月まで受諾手続に開放することとされている。
(イ)農業
農業については、以下の3件の提案について合意された。
①食料安全保障目的の公的備蓄に関する閣僚決定:開発途上国政府が食料安全保障を目的に公的備蓄食料を貧困層に提供する際の食料調達に伴う補助金は、農業協定上の補助金の規律に抵触しても紛争解決手続に訴えないことを規定。この規定は、恒久的措置が見いだされるまでの暫定措置。
②関税割当の運用に関する了解(閣僚決定):関税割当(無税又は低関税での輸入枠)の運用に係る透明性向上と未消化分の運用改善を図るもの。
③輸出競争に関する閣僚宣言:農業の輸出補助金などを最大限抑制すべきとするもの。
(ウ)開発
後発開発途上国(LDC)に対する優遇措置と開発途上国配慮条項(S&D条項)のモニタリング制度について合意された。
①LDCに対する優遇措置:LDC向け特恵関税の原産地規則の改善に関するガイドライン、LDCがサービス分野に参入しやすくするための優遇措置、LDC産品に対する無税無枠措置の実施の促進などについての合意。
②S&D条項のモニタリング制度:本制度を「貿易と開発委員会」傘下に創設し、S&D条項の実施に関する分析とレビューを行うことなどを規定。
ウ 有志国による取組
MC8以降、上述のバリ合意についての交渉のほかに、有志国による以下の交渉が行われてきた。
(ア)情報技術協定(ITA:Information Technology Agreement)の品目拡大交渉
WTO情報技術協定(ITA)(8)は発効以来16年間にわたり対象品目の見直しが行われていないため、その間の技術進歩により開発された製品(9)を対象とする品目拡大が急務である。早期妥結を目指し、関心国間の交渉(10)が行われている。品目拡大により、情報技術製品の貿易拡大、情報技術を通じた各国経済の成長・生産性向上の促進が期待される。
(イ)新サービス貿易協定(TiSA:Trade in Services Agreement)交渉
サービス貿易の一層の自由化に向け、米国、EU、オーストラリア等を含む23(11)の有志国・地域(2013年12月現在)による「新サービス貿易協定(TiSA)」が2013年夏以降本格的交渉段階に入っている。同交渉に参加する国・地域の間では、交渉対象から特定分野をあらかじめ除外しないこと、現行のルールを強化し、サービス貿易一般協定(GATS)の内容を進化させることなどで一致しており、日本も議論に積極的に参加している。
エ 紛争解決(DS:Dispute Settlement)
WTO紛争解決制度は、加盟国の貿易紛争をWTO協定に従い解決するための準司法的制度であり、WTO体制に安定性と予見可能性を与える柱として、有益に機能している(12)。日本が当事国である最近の案件には以下のものがある。
- オンタリオ州(カナダ)の風力・太陽光発電による電力の長期固定価格保証制度(Feed In Tariffプログラム)における州産品使用要求(13):2013年5月、WTO紛争解決機関は、カナダの措置を違法と認定し、協定整合化するようカナダに勧告した。
- 中国のレアアース、タングステン及びモリブデンの輸出規制措置(14):現在パネル手続が進行している。
- アルゼンチンの輸入制限措置(15):現在パネル手続が進行している。
- 中国の日本産高性能ステンレス継目無鋼管に対するアンチ・ダンピング税を賦課する措置(16):現在パネル手続が進行している。
- ロシアの廃車税制度導入:2013年7月、ロシアに対しWTO協定に基づく協議要請を行ったところ、2014年1月、ロシアは同制度を改正する法律を施行し、それにより内外差別が基本的に是正された。
- ウクライナの自動車に対するセーフガード措置:2013年10月、ウクライナに対し、WTO協定に基づく協議要請を行った。
日本はまた、DDAの一環として行われているDSU(17)改正交渉などにおいて、手続の明確化等、紛争解決制度の更なる改善に向け積極的に貢献してきている。
オ 保護主義抑止・是正の取組
世界経済の不安定さが増す中、新興国を中心に保護主義的な措置を導入する国が増加している。G20、APECでは首脳レベルで保護主義抑止に合意し、政治的コミットメントを行っている。WTOでは、貿易政策検討制度や紛争解決手続を通じた保護主義的な措置の是正に取り組んでいる。日本は、保護主義抑止・是正に引き続き積極的に取り組んでいく考えである。
(3)経済協力開発機構(OECD)
ア OECDを通じた世界経済秩序形成への貢献
OECDは、経済社会分野のルール作りに不可欠な客観的データの収集と分析を行っており、「世界最大のシンクタンク」として加盟国に政策提言を行っている。また、加盟国間の議論を通じて国際ルールを策定している。日本はOECDの各委員会での議論や財政的・人的な支援を通じて、国際的なルール作りに積極的に貢献している。
(ア)OECDとアジアとの関係強化
日本は、世界経済の成長センターとしてのアジアの重要性が高まっていることを受け、OECDとアジアとの関係強化を積極的に主導している。2013年5月のOECD閣僚理事会では「東南アジア地域プログラム」の立ち上げが決定された。また、12月の日・ASEAN特別首脳会議で発出された「日・ASEAN友好協力に関するビジョン・ステートメント実施計画」においては、「ASEANの経済統合及び繁栄を促進するため、日本が橋渡し役を務めながら、OECDを含む関連国際機関を通じたASEANへの支援を強化する」との文言が盛り込まれた。これにより、日本が今後OECDと東南アジア諸国との関係強化を一層推進する方針が首脳レベルで確認された。
(イ)貿易・租税分野での取組
近年、製品の製造過程に、企画、販売などのサービス過程を加えた国際的なサイクルであるグローバル・バリュー・チェーン(GVC)と、国別の付加価値ベースの貿易統計である付加価値貿易(TiVA)に対して注目が集まっている。OECDでは、2013年にWTO及び国際連合貿易開発会議(UNCTAD)と共同で報告書を発表するなどの取組を行っている。日本は、2013年閣僚理事会において、先進国、新興国、開発途上国の全ての国々がGVCに参画し、利益を享受することが重要であり、OECDの取組を引き続き支援していくと表明した。また、日本はOECD租税委員会議長として、「税源浸食と利益移転(BEPS)行動計画」をとりまとめ、7月にG20財務大臣・中央銀行総裁会議に提出するなど租税に関する国際的な議論をリードしてきている。
(ウ)財政的・人的貢献
日本は、OECDの一部予算(義務的拠出金)の12.88%(2013年、米国に次ぎ全加盟国中第2位)を負担している。また、OECD理事会に次ぐ最高意思決定機関である執行委員会の議長(2010-2013年)やOECD事務局のナンバー2のポストである事務次長も歴代務めている。日本は、このような財政的・人的貢献を通じてOECDを支えている。
イ 日本のOECD加盟50周年と2014年閣僚理事会
2013年4月、安倍総理大臣及び岸田外務大臣は、グリアOECD事務総長に対し、日本のOECD加盟から50周年の節目に当たる2014年の閣僚理事会議長国への立候補を表明した。これに対して、グリア事務総長から歓迎の意が示され、5月の理事会で日本の同議長国就任が満場一致で決定された。

同閣僚理事会では、日本は議長国として、東日本大震災の経験を踏まえ、経済社会のしなやかな強靭さ(レジリエンス)や東南アジアへのアウトリーチなどについて議論するとともに、日本経済の再生を国内外に力強く印象付ける機会とし、東南アジアとOECDとの関係強化を推進していく考えである(詳細については197ページの特集参照)。

50年前の1964年は東京オリンピックが開催され、東海道新幹線が開通した年ですが、同時に日本がOECDに加盟し、名実ともに先進国の仲間入りを果たした年です。日本はOECDで策定された様々な国際的ルールや政策ガイドラインを積極的に活用して、着実に高度経済成長を遂げました。
例えば、OECD加盟と同時期に締結した資本移動と貿易外取引の自由化に関する規約に沿った自由化努力により、資本の自由化が大きく進展しました。環境面では、OECDが示した「汚染者負担原則」を公害関係の各種立法の基本的理念として盛り込み、高度経済に伴い生じた公害の解決を促しました。また、租税分野では、OECDのモデル租税条約を活用して多くの国と二重課税防止条約を締結し、国際的な企業活動の促進を図っています。


2011年3月に発生した東日本大震災の際には、グリアOECD事務総長は、いち早く哀悼の意を表するとともに、同年4月下旬に訪日した際には日本政府に対して早期復興に向けた協力を表明しました。また、同事務総長は、訪日中に「対日経済審査報告書」を発表し、震災による日本経済への悪影響は長くは続かず、必ず回復すると確信しているとの力強いメッセージを発信しました。
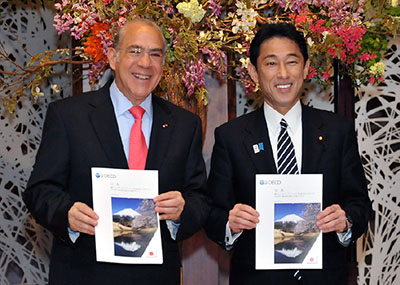
また、東北の復興支援策として、OECD東北スクールプロジェクトが立ち上げられ、被災地の生徒は2014年8月にパリで東北の魅力を発信するべく、様々な取組を行っています。2013年8月に東京で開催された発表会には、皇太子同妃両殿下も御臨席になり、復興のPRに取り組む生徒たちと会話を交わされました。
2013年4月のOECD「対日経済審査報告書」は、「三本の矢」から成る経済財政政策を通して経済を再生するという安倍政権の決意を高く評価しました。また、財政の持続可能性の確保や農政改革、女性や高齢者の労働参加の促進などの現下の課題について、具体的な政策提言を行いました。
OECDは、国の財政から教育、観光に至るまで、幅広い分野の専門家を有しており、以上のような政策提言を継続的に行っています。
日本は、「世界最大のシンクタンク」であるOECDを活用するとともに、国際経済の政策協調やルール作りの場であるOECDにおいて、今後も積極的に主導的役割を果たしていきます。
(4)アジア太平洋経済協力(APEC:Asia-Pacific Economic Cooperation)
APECは、各エコノミー(18)の自発的な意思によって、アジア太平洋の持続可能な発展を目指し、地域経済統合と域内協力の推進を図る枠組みである。アジア太平洋地域の21か国・地域から構成されており、これらは世界の人口の約4割、GDPの約55%及び貿易量の約45%を占める「世界の成長センター」である。総貿易の約3分の2が域内貿易であるなどEU並みの密接な域内経済を構成しており、APEC地域の経済面における協力と信頼関係を強化していくことは、日本の更なる発展を目指す上で極めて重要である。また、APEC首脳・閣僚会議は、経済問題を中心に、国際社会の主要な関心事項について首脳・閣僚間で率直な意見交換を行う有意義な場となっている。
インドネシアが議長を務めた2013年バリAPEC首脳会議では、「多角的貿易体制」、「連結性の促進」及び「衡平性を伴う持続可能な成長」について議論され、APEC首脳宣言「強靱なアジア太平洋、世界成長のエンジン」が採択された。「多角的貿易体制」については、域内の貿易・投資の自由化を一層進め、第9回WTO閣僚会議(MC9)の成功に向けたコミットメントを再認識し、新たな保護主義措置の不導入の2016年末までの延長を含む保護主義の抑止に取り組むとした独立文書が採択された。「連結性の促進」については、アジア太平洋地域の連結性を強化し、地域経済統合へ向けた動きを促進すべきとの認識が共有され、「インフラ開発・投資に関する複数年計画」の策定、越境教育の推進、渡航円滑化の取組などに合意した。特に、「インフラ開発・投資に関する複数年計画」の策定に当たっては、日本の提案により、中長期的な費用対効果(ライフ・サイクル・コスト)、環境への影響、安全性等を踏まえることの重要性が確認された。「衡平性を伴う持続可能な成長」については、女性の経済参画の拡大、中小企業の国際競争力への向上に向けた更なる対策、食料安全保障への取組、クリーン・再生可能なエネルギーの開発の取組の活性化などが合意された。また、APEC首脳会議の機会に、安倍総理大臣は、APECビジネス諮問委員会(ABAC)委員との対話や域内のビジネス指導者が集うAPEC・CEOサミットにおける講演を行い、アベノミクスの推進を通じた日本経済の再生に向けた取組をアピールし、高い評価を得た。
7 正式名称はドーハ開発アジェンダ(DDA:Doha Development Agenda)交渉。
8 正式名称は、「情報技術製品の貿易に関する閣僚宣言」。情報技術製品(半導体、コンピューター、携帯電話、プリンター、FAX、デジタルカメラ(静止画用)等)の関税を撤廃する複数国間貿易協定。1996年作成、1997年発効。現在の加盟国は日本、米国、EU(28か国)、中国、ロシア等78か国。
9 デジタルAV機器(ビデオカメラ、DVD・HD・BDプレーヤー等)、デジタル複合機・印刷機、医療機器(電子内視鏡等)、半導体製造装置等。
10 日本、米国、EU、台湾、韓国、コスタリカの5メンバーにより協議が開始され、2013年12月時点で上記に加えカナダ、オーストラリア、中国等を含む計55か国が参加。
11 日本、米国、EU、オーストラリア、カナダ、韓国、香港、台湾、パキスタン、イスラエル、トルコ、メキシコ、チリ、コロンビア、ペルー、コスタリカ、パナマ、パラグアイ、ニュージーランド、ノルウェー、スイス、アイスランド及びリヒテンシュタイン(EU各国を含めると50か国・地域)
12 他の加盟国によるWTO協定非整合的な措置によって不利益を被ったとする加盟国は、当事国間での協議を要請できる。この協議を通じても紛争が解決されない場合、問題をパネル(紛争処理小委員会)に付託し、問題とされる措置と協定との整合性についてパネルで争うことができる。パネルによる法的判断に不服のある当事国は、最終審に相当する上級委員会に対して上訴を行い、同判断を争うことができる。1995年のWTO発足時から2013年末までの紛争案件数(協議要請が行われた件数)474件のうち、日本が当事国(申立国又は被申立国)として関わった案件は34件。なお、上級委員会は7人の委員で構成されており、委員の任期は4年(再任可能)。日本は1995年のWTO発足以降3人の委員を輩出している。
13 Feed In Tariffプログラムの適用条件として、一定割合以上の同州産付加価値を与えられた発電設備を使用することを求めるもの。
14 2012年7月、米国及びEUと同時にパネル(紛争処理小委員会)設置を要請。輸出税、輸出割当て及びその管理に関する案件。
15 2012年12月、EU及び米国と同時にパネル設置を要請。事前輸入宣誓供述制度、非自動輸入ライセンス及び輸出入均衡要求に関する案件。
16 2013年5月、パネル設置を要請。石炭火力発電所のボイラーなどに使用される高付加価値特殊鋼に関する案件。2012年11月、中国商務部は、日本及びEU産の同鋼管に対するアンチ・ダンピング措置をとるとの最終決定を行った。
17 紛争解決に関する規則及び手続に関する了解(Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes)
18 中国香港、チャイニーズ・タイペイを含めたAPEC参加単位
