2 海外における日本企業への支援
(1)日本企業支援の取組
ア 日本企業支援窓口
外務省は、海外における日本企業のビジネスを後押しするため、「日本企業支援窓口」を1999年から全ての在外公館(海外にある日本の大使館・総領事館など)に設置し、日本企業への情報提供や人脈形成への協力、現地政府に対する行政手続の是正に関する申入れ等を行っている。また、近年は、在外公館において日本企業のビジネス支援のため、日本企業とレセプションを共催するなど、在外公館施設を活用した支援にも積極的に取り組んでいる。具体例としては、日本企業の製品紹介のためのセミナー、展示会及びレセプションの開催等、多彩な取組を世界各地の日本大使館・総領事館で行っている。
最近では、パッケージ型のインフラ海外展開の推進や、東日本大震災からの復旧・復興等の新たな動きへの対応も重要になっている。すなわち、インフラ海外展開のための情報収集体制を強化するとともに、震災及び原発事故後の日本産品に対する諸外国の輸入規制等に対応するため、その緩和・撤廃に向けた情報発信を積極的に行っている(第3章第3節1.(2)「インフラ海外展開」、(4)「原発事故に伴う各国の輸入規制措置への対応」参照)。

イ 投資協定/租税条約/社会保障協定の活用(1)
(ア)投資協定
投資の保護、促進及び自由化について規定する投資協定は、日本企業の海外での活動を支援する効果がある。日本政府は、戦略的な優先順位をもって投資協定の交渉・締結方針を検討していくことを目的とし、政府・民間団体・関係機関が意見交換を行うための場として、2008年に対外投資戦略会議を設置した。同会議は、2011年までに3回の本会議に加え、より具体的な内容について議論を行う連絡会議を9回開催した。同会議では、海外展開する日本企業を支援するためのビジネス環境の整備や投資協定の活用についての意見交換も行われ、投資促進の方法を官民で包括的に検討していく枠組みとして引き続き活用される予定である。
(イ)租税条約
経済のグローバル化の進展に伴い、国際的な経済活動の規模を拡大している日本の企業や投資家がより制約の少ない経済活動を展開できる環境を整備する必要性が高まっている。日本は以前から二重課税の回避等を目的とする租税条約を各国と締結しており、投資交流を促進するという観点から租税条約ネットワークの更なる拡充を図っている。
(ウ)社会保障協定
社会保障協定は、保険料の二重負担や保険料掛け捨てなどの問題の解消を目的とする協定である。社会保障協定の締結は、海外に進出する日本の企業や国民の負担を軽減し得るものであり、相手国との間の人的交流や経済交流を一層促進する効果が期待されることから、相手国の社会保障制度における社会保険料の水準や日本にとっての必要性などを踏まえつつ、今後も優先度の高い国から順次締結交渉を行っていく考えである。
ウ 経済連携協定
日本が締結しているEPAの枠組みの下では、協定全般の運用を扱う合同委員会や、ビジネス環境の整備など特定の分野を扱う多くの小委員会の設置が規定されている。こうした会合を定期的に開催し、海外に進出している日本企業の要望などを踏まえ、EPAの活用、運用改善などに取り組むとともに、協定の運用状況について定期的に見直すこととしている。
(2)模倣品・海賊版対策
模倣品・海賊版は、技術革新などを妨げ、世界の経済成長に悪影響を及ぼすだけでなく、消費者の健康や安全まで脅かしている。日本企業も、海外市場における潜在的な利益を喪失するなど、深刻な悪影響を受けている。
このため、外務省は、政府の知的財産戦略本部が毎年策定する「知的財産推進計画」に沿って、様々な機会を捉えて知的財産権の保護強化及び模倣品・海賊版対策に関する施策に取り組んでいる。例えば、2005年3月以降、全ての在外公館において知的財産担当官を任命し、模倣品・海賊版被害を受けている日本企業を迅速かつ効果的に支援することを目的として、日本企業への助言や相手国政府への照会、働きかけなどを行っている。日本企業から在外公館への相談内容は外務本省に報告され、必要に応じて二国間及び多国間協議(第3章第3節3(3)「知的財産権保護の強化」を参照)の場で取り上げるなど、外国政府への更なる働きかけを行っている。また、知的財産担当官の能力向上を図り、知財侵害対策をより一層深めるために、日本企業の模倣品・海賊版被害の多い地域を中心に知的財産担当官会議(2)を開催している。さらに、相手国政府職員向けに日本企業が主催する、知的財産権保護セミナーへの支援などの取組も行っている。
そのほか、模倣品・海賊版対策における開発途上国の政府職員などの能力向上を図るため、JICAを通じて、専門家派遣、研修員受入れなど、技術協力を行っている。
(3)ビジネス環境改善、貿易・投資の円滑化
日本は、主要な貿易・投資相手国との間で、ビジネス環境の改善などのための協議を行っている。
例えば、EUとの間では、2011年5月の日・EU定期首脳協議において、ビジネス環境の改善のため、貿易・投資を含む日・EU双方の関心事項を取り扱うEPAの交渉のためのプロセスを開始することに合意した。
米国との間では、2010年11月の日米首脳会談を受け、日米経済調和対話を立ち上げた。同対話では、日米間の貿易円滑化、ビジネス環境の整備等に取り組むため、2011年に2回の事務レベル会合(2~3月及び同7月)と1回(10月)の上級会合を実施し、2012年1月には、協議記録を公表するなど、経済分野の日米連携の一層の強化に向けて具体的な進展があった。
中国との間では、「日中ハイレベル経済対話」、「日中経済パートナーシップ協議」等の場を通じて、知的財産権の保護強化、レアアースの輸出規制の改善を含む貿易・投資上の諸問題に関する要望を中国側に提起し、協議を行っている。
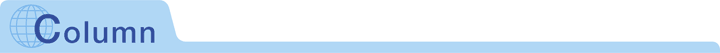
「国酒」という言葉をお聞きになったことがありますか。読んで字のごとしで、国の酒という意味ですが、日本にとっての国酒は日本酒です(日本酒造組合中央会には、歴代総理大臣が「国酒」と揮毫(きごう)した色紙が掲示されているそうです)。フランスやイタリアにとってワインがそうであるように、日本酒は「国酒」として日本の誇りの源泉となり得るのでしょうか。
日本酒は、海外では、日本の「顔」の一つになろうとしています。外務省は、2011年から、毎年ロンドンで開催される世界最大級のワインコンクールである、インターナショナル・ワイン・チャレンジの日本酒部門の受賞酒を在外公館(海外にある日本大使館や総領事館)で活用する取組を始めました。この受賞酒を中心に在外公館に品質の高い日本酒を送り、各国の賓客のもてなしに使っています。さらに、毎年の天皇誕生日祝賀会では、日本酒で乾杯をすることにしました。
なぜ外交の舞台で日本酒を使うのかといえば、外交は人間関係の構築があって初めてできる仕事であり、「食」はその重要な武器となるからです。美味(おい)しい日本酒は外国の賓客に感動を与え、人間関係の潤滑油となります。ワインに比べて複雑な醸造方式、コメが原料なのにフルーツの香りがするなど、日本酒は外国人、特にワイン文化圏の人々との会話を盛り上げるには格好のアイテムです。
また、日本酒は世界に売り込むべき日本ブランドでもあります。世界各地で日本食の人気が高まっているのに比して、日本酒の認知度は道半ばの印象があります。これからも、日本酒を含む日本の食文化のPRのための行事やレセプション等を通じて、日本酒の認知度向上に貢献できればと考えています。
世界のワイン市場の規模は2005年時点で1,000億米ドルを超えています。国酒である日本酒が世界酒となり、同じ醸造酒であるワイン市場の需要を取り込めれば、地域経済の振興にもつながるのです。2011年には東日本大震災によって日本酒の一大生産地である東北地方が大打撃を受けました。震災後、在外公館に多くの被災地産日本酒が発送されており、コメ等その他の被災地産の食材とともに、世界中に震災からの復興に向けたメッセージを伝えています。
在外公館課課長補佐 石井秀明
(現在、アフリカ第二課首席事務官)



1 これらの条約や協定のうち、2011年に締結などの進展があったものについては、第3章第3節3.(2)「投資協定/租税条約/社会保障協定」参照。
2 2011年1月には、中国内在外公館の知的財産担当官を対象に北京で、中東・北アフリカ諸国在外公館の知的財産担当官を対象にドバイ(アラブ首長国連邦)で知的財産担当官会議を開催した。