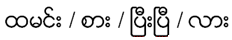世界一周「何でもレポート」
チャレンジ!外国語 外務省の外国語専門家インタビュー
ミャンマー語の専門家 小山さん
平成25年9月5日

(ミンガラーバ)=こんにちは!
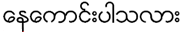
(ネーカウンバーダラー)=お元気ですか?
小山さんは外務省に約10人いるミャンマー語専門家の一人。大学入学当時、アジアに関心があり、一般に知られていない珍しい言語を学びたいと思っていた小山さんはミャンマー語を専攻科目に選びました。大学在学中に初めてミャンマーを訪問し、何とも言えないミャンマーの魅力を感じたそうです。大学で学んだことを活かせる仕事に就きたいと2004年に外務省に入省。研修語は希望通りミャンマー語を指定されました。
5~6世紀にビルマ族がチベットから南下して現在の場所に定住し、西暦1000年頃、初めてビルマ族の統一王朝ができたのがミャンマーの始まり。135の少数民族を抱えた多民族国家で、それぞれが独自の言語をもっているそうですが、ミャンマー語は国内共通の公用語です。
-
 「首長族」として有名なミャンマーの少数民族、パラウン族と記念撮影
「首長族」として有名なミャンマーの少数民族、パラウン族と記念撮影
小山さんによれば、ミャンマー語は日本人にとってそれほど難しくない言語だとか。「おそらくミャンマー近辺の他の言語に比べたら、日本人にはとても学びやすい言語だと思います。文法が日本語とまったく同じなんですよ」。
例えば、part1でご紹介した便利なフレーズ「タミン サー ピービーラー」は、そのまま日本語の語順と同じ。
タミン/サー/ピービー/ラー
ごはん/食べ/終わった/か?
(※現地で「こんにちは」に代わる挨拶の言葉)
「文字と単語を覚えて、後は頭で考えずにそのまま口に出していけばちゃんと文章になるんです。」 とのことですが・・・。
日本発祥の○○○○でミャンマー語を磨く!
東京での研修を終え、2005年にミャンマーを訪れた小山さん。研修先は語学留学生にとってほぼ唯一の選択肢であるヤンゴン外国語大学です。授業内容が初習者向けのため、小山さんは学校と交渉して上級クラスに編入してもらったそうですが、レベルの高い語学教育を求めようとすると各自が工夫する必要があるようです。
-
 ヤンゴン外国語大学での授業風景。大学では基本的には伝統衣装のロンジー(巻きスカート)を着用。
ヤンゴン外国語大学での授業風景。大学では基本的には伝統衣装のロンジー(巻きスカート)を着用。
「日本語と同じ」と言う小山さんですが、やはりミャンマーに来て最初のうちは、なかなか言葉が伝わらずに苦労したそうです。その理由は、発音。ミャンマー語には日本語にはない声調があり、それぞれ正しく発音しないとまったく違う意味になってしまうのです。声調は文字に表記されるため、小山さんは最初の内は文字を頭に浮かべながら発音するようにしていたそうです。さらに正しい発音を身につけるために小山さんが活用したのは、ミャンマーでも大人気のカラオケ!「ミャンマーの歌が大好きだったこともあって、カラオケで楽しく歌いながらミャンマー語を磨きました。カラオケは字幕の歌詞を読みながら、発音もしっかり歌わないといけないのでとてもよい練習になるんです。」 訓練の結果、今でも字幕なしで歌える持ち歌が何曲もあるそうです!
通訳の苦労
2005年から2年間の研修を経て、その後3年間在ミャンマー日本大使館にて勤務していた小山さん。大使館では政務分野を担当する傍ら、要人訪問の際には通訳業務もこなしました。ミャンマーの首都はネーピードーですが、大使館が置かれているのは国内最大都市のヤンゴン。政府の要人と会うためにはネーピードーに出張しなければならず、同行者の人数が限定されるため、通訳+記録+コーディネーターと一人で何役もこなさなければならないことも多かったそうです。東京に帰国してからも、活発化する二国間関係に伴い要人通訳の機会も増えています。
「特に大変だったのは、 昨年、日本政府が派遣したミャンマー文化・スポーツ交流ミッションに同行した時です。大統領に加えて3閣僚、それぞれ一時間以上の会談を、朝から、昼食も抜きで通訳しました。しかもその会談の記録を、その日の内にほぼ全て自分で作らなければならず、あの日は全て終わった後はさすがに灰色になってましたね・・・。」
今年4月、ノーベル平和賞受賞者で世界的な著名人であるアウン・サン・スー・チーさんが訪日した際には、小山さんは担当官として京都日程に同行。アウン・サン・スー・チーさんが京都市内でプライベートの買い物をするため、急遽買い物の通訳を務めることになりました。アウン・サン・スー・チーさんは日本のお菓子が大のお気に入りだそう。彼女の好みに合うようなお菓子を一緒に探した小山さんは、その功績が認められたのか、その後の日程でも「お菓子担当」に任命され、大活躍だったそうです。
ちなみに、ミャンマー語通訳で少しややこしいのは、「私」と「あなた」という単語が、話す人の性別で変わること。男性の場合、「私」は「チャノー」、「あなた」は「カミャー」と言いますが、女性の場合はそれぞれ「チャマー」、「シン」となるそうです。これが意外に通訳泣かせ。男性の小山さんが日本人女性の通訳を受け持つ場合、通訳中はその女性になりきって「チャマー」と女性言葉を使いますが、長時間通訳をしていると、つい普段の「チャノー」という男性言葉が出てしまい、「気をつけていないと途中で主語が女性になったり男性になったりしてしまって、自分でそれに気がついてまたまた慌てる・・・」
意外な苦労があるようですね。
信仰心の篤い国民性
ミャンマーの人口の約90%は仏教徒。とても信心深く、道徳心の強い国民性で知られます。多くの人にとって、現世で功徳を積み、よりよい来世を迎えることが最大の関心事。日常生活にも仏教の教えが深くかかわっています。
5月から10月にかけての雨安居(うあんご)という期間は戒律が厳しくなり、熱心な信者はその時期、殺生された動物は一切食べず、お酒も一滴も飲まないそうです。
4月は仏教国ならではの水祭りの季節。新年にもあたるこの時期は全国的に店も会社も休業となり、人々は一週間、派手に水を掛け合って祝います。路上には水祭り用の舞台が作られ、消防ホースを持ち出す人も。現地では外交団がバスに乗せられ、行く先々で放水を浴びるというイベントが恒例行事だそうです。普段は穏やかで慎ましいミャンマーの人達ですが、この時ばかりは全国的な無礼講を楽しむようです。
民主化を迎えた激動のミャンマー
小山さんが初めてミャンマーを訪れてから12年、同国は大きな変遷を遂げつつあります。一番の変化は2011年に軍事政権が民政移管し、民主的な政府が誕生したこと。
「数年前とはまるで別の国のようです。例えば民主化以前の軍事政権下では、友人の間でも『スー・チー』と名前を出しただけで、ぎょっとするような反応でした。みんな彼女の写真を、誰にも見えない家の奥の部屋や、財布の中に隠しもっていたものです。その後、民政移管から2年ほどたった今は、もう完全に自由。一番驚くのは政府を批判する記事が、新聞に堂々と載るようになったことです。自由を手に入れたという人々の思いがあふれています。
ミャンマーの改革が極めて平和裡に行われたのは、政府も国民も、それぞれが分別をわきまえていて、お互いに耐性があるためではないでしょうか。テイン・セイン大統領にも通訳などで接する機会がありますが、この政治・経済改革はなんとしてでもやり遂げる、という意気込みが如実に伝わってきますし、行政に携わっている人たちもやる気に満ちあふれていますね。」
-
 人気俳優の友人と結婚式にお呼ばれ。民族衣装のタイポン(上着)とロンジーが正装です
人気俳優の友人と結婚式にお呼ばれ。民族衣装のタイポン(上着)とロンジーが正装です
ミャンマー人と仲良くなるには
ミャンマーの人達は、とても親日的。かつてミャンマーが英国の植民地だった時代、旧日本軍が独立の支援をした歴史があり、そこから日本人に対する好意的な感情が続いているそうです。日本製品は信頼性が高く、大人気。日本人を信頼できるパートナーと見ているので、仕事もやりやすいそうです。
ミャンマーの人とつきあうコツは?
「ミャンマー人はけっこうお節介焼きでもあります。日本人の場合、人と人との距離が近過ぎると感じる人もいるかもしれません。ミャンマーの人は現世でよいことをしたいという気持ちが強いので、その厚意をありがたく受け入れて、功徳を積むお手伝いをする、というくらいの姿勢でちょうどいいんじゃないでしょうか。私のミャンマーの友人たちは『ありがとう』と言われるのも嫌がっていたくらいです。彼らとしては、遠慮されているようで水臭く感じるのかもしれませんね。 全世界共通だと思いますが、一度仲良くなったらお互い秘密もなく、思ったことをすぐに言い合うとてもオープンな関係になります。」
そんな小山さんの交流術はずばり「ノミュニケーション」。得意のカラオケを武器に友達の輪を広げ、芸能界にも交友関係を築きました。大ファンだったミャンマーの大物国民的歌手とも家族ぐるみの友人に!一緒にデュエットを歌う夢も叶え、今でも連絡を取り合う仲だそうです。「大使館の広報事業として、のど自慢大会を主催したときにもゲストとして参加してくれ、ミャンマーの人たちは大騒ぎでしたね。個人的に培った人脈が広報行事の成功にもつながって、この時は感無量でした。」
ミャンマーに「早く帰りたい」という小山さん。家族ぐるみで親身に接してくれる友人たちに恵まれ、ミャンマーはまさに第二の故郷だそうです。
好きな言葉 ・便利なフレーズ
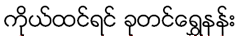
(コーティンイン・ガディンシュエナン)=「自分で思えばベッドでも王宮となる」
「自分の考え方次第で、この小さなベッドでも王宮のように感じることができる、という意味のことわざです。これは尊敬するミャンマー語の先生から教わったことばです。ミャンマー人は我慢強く、現状を受け入れる民族だと思います。これまで軍事政権下で苦労しながらも、町中のミャンマー人は常に明るく見えました。そのミャンマー人の我慢強さや苦境のかわし方というのを、よく表していると思います。自分も『きついなあ』と思ったときにはよく思い出す、心に響く言葉です。 」

(ディーアタインバーベー)=「そんなもんさ」

(マイッテー)=「Coolだね」
-
 隣に立つ青年はクラスメイトだった留学生仲間。前列の子ども達と一緒に得度式を終え、笑顔で記念撮影
隣に立つ青年はクラスメイトだった留学生仲間。前列の子ども達と一緒に得度式を終え、笑顔で記念撮影
ミャンマー豆知識
ミャンマー人には名字がない?
ミャンマーといえばアウン・サン・スー・チーさんが有名ですが、どこまでが名字でどこまでが名前?
「実はミャンマーの人には姓はなくて、全て名前なんです。好きな名前をいくつでも自由に組み合わせられます。お父さんの名前から一文字、お母さんの名前から一文字取る、という方もいます。日本ではよく「スー・チーさん」と短くして呼ばれていますが、本当は全ての名前を呼ばないと失礼にあたります。」
姓がないので、IDカードには個人を特定するために必ず両親の名前を併記するようになっているそうです。また、新聞に名前が載るようなことがあると、父親の名前もセットで報道されるのだとか。。。
あなたは何曜日生まれ?
ミャンマーでは曜日が重要。生まれた曜日に基づいて名前の最初の文字を決めるという習慣があるため、名前を見れば何曜日生まれかが大体分かるそうです。また、曜日によってお寺でのお参りの仕方も違います。
「例えば私は金曜日生まれですが、金曜日の動物はもぐらと決まっているので、お寺では、もぐらの像が置かれているところにお参りにいきます。ちなみに、月曜日はトラ、火曜日はライオン、水曜日は象、木曜日はネズミ、土曜日は竜、日曜日はガルーダ(鳥)です。なお、水曜日だけは、更に午前と午後に分かれており、午前が牙のある象、午後が牙の無い象になります。」
ミャンマーに行く際には、自分が何曜日生まれなのか調べておくとよいですね。
-
 身内から出家者を出すことは大きな功徳を積むことになります。家族は友人知人を呼んでご馳走を振る舞って祝います。先生の親戚が出家した際に招かれたパーティーにて
身内から出家者を出すことは大きな功徳を積むことになります。家族は友人知人を呼んでご馳走を振る舞って祝います。先生の親戚が出家した際に招かれたパーティーにて
ミャンマー料理は「インド料理と中華料理の間」
ミャンマーはお米が主食。大きなお皿にご飯を盛って、いろんな種類のおかずを乗せ、混ぜて食べるのが一般的です。みじん切りにしたニンニク、ショウガ、タマネギをピーナツ油で炒めたものが味のベース。これがほとんどの料理にも使われ、美味の秘訣となっているそうです。「地理的にもそうですが、ミャンマー料理は言ってみればちょうどインド料理と中華料理の間。スパイシーだけど辛すぎず、日本人の口にもよく合ってとてもおいしいです。ただ基本的に油を大量に使うため、カロリーは高いですね。おかずも味付けが濃いのでご飯がすすんでついつい食べ過ぎてしまって、ミャンマーでかなり太ってしまいました。」
小山さんのお薦めは「ウェッター・ヒン」という豚バラの固まり肉を先ほどの味のベースと一緒に炒めたもの。ちなみにミャンマーでは鶏肉が一番のご馳走で、ついで豚肉。牛肉はあまり食べないそうです。「ミャンマーはまだ農作業では機械ではなく牛をつかって耕したりするので、一緒に畑仕事を手伝ってくれるありがたい存在として、食べられないみたいです。」
また、ミャンマーの人は辛いものも大好きで、食事のお供に青唐辛子を生でポリポリ囓るそうですが、これが衝撃の辛さ。小山さんはうっかりこれを囓ってしまい、その日一日、口の中に何も入れられない状態になってしまったそうです。ちなみにこの青唐辛子の名前は「カラオー」。「カラ」はインド人、「オー」は叫んでいる声。つまり、インド人も叫ぶ驚きの辛さ・・・辛いもの好きな方は是非試してみてください!