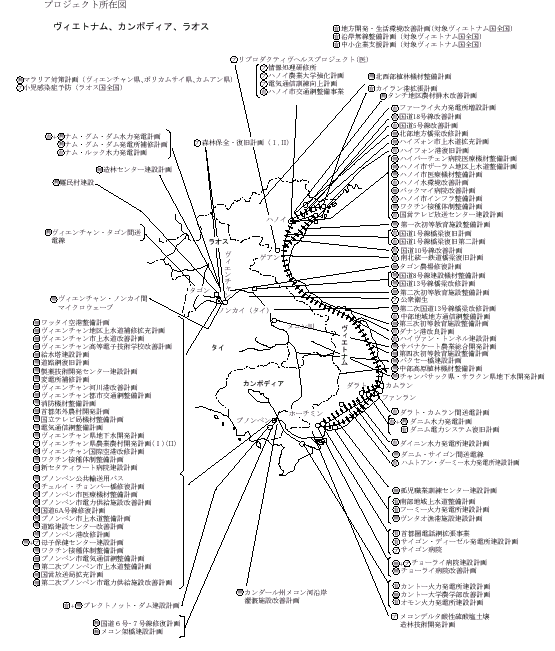国別援助実績
1991年~1998年の実績
[2]ヴィエトナム
(1) ヴィエトナムは、86年より「刷新(ドイモイ)」路線を打ち出し、市場経済原理の導入等経済を中心とする開放化を進めるとともに、IMF・世銀との協調の下で構造調整計画を実施してきている。また、我が国を含む西側諸国や中国との関係改善・拡大を望むとの政策をとっている。
ヴィエトナムは、憲法に定めてある「共産党一党支配」は堅持し、政治的多元主義は導入しないとの方針をとっているが、92年の国政選挙以来共産党等の推薦がなくとも議員に立候補できる制度が導入されたほか、95年には社会主義国で初めて民法を制定している。97年9月末、ヴィエトナム最高指導部の交替によりカイ新政権が誕生した。アジア経済危機の中でヴィエトナム経済の競争力強化を図ることが急務となっており、また、ASEAN加盟国として貿易・投資の自由化促進の義務を負う等、ヴィエトナムは引き続き改革課題を抱えている。
(2) ヴィエトナムは、91年11月に中国との関係正常化を行うとともに、92年7月のASEAN外相会議の場において東南アジア友好協力条約(バリ条約)に加入するなど、近隣諸国との関係改善を急速に進めてきた。また、ヴィエトナムは、世界及び地域経済の枠組みへの参加を積極的に進めている。具体的には、95年1月にWTOに加盟申請し、95年7月のASEAN加盟を受け、96年1月よりAFTA(アセアン自由貿易地域)に参加し、2006年までに共通実効特恵関税(CEPT)協定に基づく関税削減を目指している。96年6月にはAPECへの加盟申請を行い、98年に加盟が認められた。米国との関係改善も徐々に進展し、94年2月の米国の対越禁輸解除決定を経て、95年8月には米国との間で外交関係を樹立した。また、98年12月にはハノイでASEAN公式首脳会議を開催するなど、ASEANのメンバーとしての役割も本格的に果たしつつある。
(参考1) 主要経済指標等
| - | 90年 | 95年 | 96年 | 97年 | |
| 人口 (千人) | 66,473 | 73,475 | 75,355 | 76,711 | |
| 名目GNP | 総額 (百万ドル) | - | 17,634 | 21,915 | 24,008 |
| 一人当たり (ドル) | - | 240 | 290 | 310 | |
| 経常収支 (百万ドル) | - | - | - | - | |
| 財政収支 (百万ドル) | - | - | - | - | |
| 消費者物価指数 | - | - | - | - | |
| DSR (%) | 8.9 | 4.9 | 3.9 | 7.8 | |
| 対外債務残高 (百万ドル) | 23,270 | 25,427 | 26,256 | 21,629 | |
| 為替レート(1米ドル=ドン) | - | - | - | - | |
| 分類 (DAC/国連) |
低所得国/- |
||||
| 面積(千平方キロメートル) |
325.5 |
||||
(参考2)主要社会開発指標
| - | 90年 | 最新年 | - | 90年 | 最新年 | |
|
出生時の平均余命(年) |
63 | 67(97年) | 乳児死亡率 (1000人当たり人数) |
49 | 29(97年) | |
| 所得が1ドル/日以下の人口割合(%) | - | - | 5歳未満児死亡率 (1000人当たり人数) |
65 | 40(97年) | |
|
下位20%の所得又は消費割合(%) |
7.8(92年) | 7.8(93年) | 妊産婦死亡率 (10万人当たり人数) |
120(80-90年平均) | 105(90-97年平均) | |
| 成人非識字率(%) | 12 | 6(95年) | 避妊法普及率 (15-49歳女性/%) |
20(80-90年平均) | 75(90-120 (80-90年平均) |
|
| 初等教育純就学率 (%) |
- | - | 安全な水を享受しうる人口割合(%) | 42(80-90年平均) | 47(96年) | |
| 女子生徒比率(%) | 初等教育 | - | - | 森林面積 (1000平方キロメートル) |
83 | 91(95年) |
| 中等教育 | - | - | ||||
(3) 86年以降採られてきた財政赤字の削減、金利政策の実施、変動為替相場制の採用等、経済面での刷新(ドイモイ)政策の効果が89年頃より現れはじめ、経済的水準は未だ低いものの、概ね良好なマクロ経済の実績を示してきた(92~96年の平均GDP成長率8.9%を達成、97年8.2%)。
しかし、97年のアジア経済危機の間接的影響は免れ得ず、慢性的な貿易赤字基調に加え、自国製品の輸出不振、外国民間投資の大幅減少に伴い失業率、物価が上昇する中で経済成長が大きく減速しており、また、金融システム・国公営企業改革等の構造問題も経済成長の足かせとなっている。これらの問題に対し政府指導部は、外資奨励・輸出促進に関する具体的施策を打ち出す等、現状打開に向けた積極的な努力を行ってきている。98年実質GDP成長率は3.5%に低下した。
また、戦争や投資不足による基礎的な社会経済インフラの未整備ないし劣化・老朽化が今後の経済発展の障害となることが予想され、その整備が急務となっており、今後の経済的課題は、1)社会経済インフラや農業基盤の整備、2)財政、金融面での制度改革、国営企業改革の促進、3)市場経済に適合した法制度整備、人材育成、4)拡大しつつある貧富の差の是正(都市・農村間の格差是正)、5)各種不正行為(汚職、密輸等)の防止、である。
経済に占める農業の割合は大きく、総労働人口の70%以上が農業に従事している。コメについては、89年より輸出が可能となり、現在、タイ、米国に次ぐ世界第3位の輸出国となっている。一方、農業生産の増加による価格低迷も見られる。
外国投資は98年末まで約338億ドル(2,387件)であるが投資環境整備の遅れやアジア通貨危機の影響により、96年約85億ドルに対し97年は約47億ドル、98年は約37億ドルに減少している。主要投資国は、シンガポール、台湾、香港、日本である。
(4) ヴィエトナム政府は、「1996年から2000年の社会経済5か年計画における方向と任務」として以下の主要目標をあげている。
1)一人当たりGDPを90年の2倍に引き上げる。
2)年平均GDP成長率を9~10%とする。
3)年平均成長率を農業生産4.5~5.0%、工業生産14~15%、サービス部門12~13%とする。
4)GDPに占める産業の比率を農業19~20%、工業34~35%、サービス45~46%とする。
5)総投資額の対GNP比を30%とする。
6)人口の年増加率を1.8%以下とする。
(5) 78年末のカンボディア侵攻以降、我が国との関係は停滞していたが、91年10月のパリ和平協定署名の後、我が国とは、本格的な関係強化が進められ、幅広い交流が進んでいる。最近では98年12月のASEAN首脳会議の際に小渕総理大臣が訪越し、これを受けて99年3月にはカイ首相が来日している。
日・ヴィエトナム間の貿易は、従来低い水準にあったが、近年は着実に拡大し、98年は対日輸出が約17.5億ドル、輸入が約13.3億ドルに達した。ヴィエトナムからの主な輸入品目は、原油、海産物(エビ、イカ)、繊維品等であり、我が国からの主な輸出品目は自動車、バイク、機械類等である。
(1) 我が国は、1)ヴィエトナムの安定はインドシナの平和と安定にとり極めて重要であること、人口約7,600万人を有し、また、一人当たりGNPは低く、援助需要が高いこと、更に、経済発展に伴いこの地域における重要性を増していくと考えられること、2)91年10月のカンボディア和平合意を受け、我が国からヴィエトナムへの円借款を再開したことを契機に、両国関係は将来を見据えた新たな発展段階に入り、政治面、経済面のみならず文化面等でも緊密化しつつあること、3)ヴィエトナムは、86年より「ドイモイ(刷新)」路線の下市場経済化を推進するとともに、95年にはASEAN加盟、98年にはAPEC加盟を果たし、我が国を含む域内外諸国との関係改善・拡大を進めてきていること、また、アジア経済危機の影響が徐々に浸透し経済成長とドイモイ政策の維持に困難が生じていること等を踏まえ、援助を実施する。
(2) 我が国は、ヴィエトナムにおける開発の現状と課題、開発計画等に関する調査・研究及び94年10月に派遣した経済協力総合調査団及びその後の政策協議等によるヴィエトナム側との政策対話を踏まえ、以下の分野を援助の重点分野としている。
(イ) 人造り・制度造り(特に市場経済化移行支援)
市場経済化を推進しているヴィエトナムにおいては、人材育成と法制度、税制、金融制度等の制度造りが緊急の課題となっている。このため、(a)新たな経済システムの構築に資する行政分野、市場経済関連分野及び法制度整備分野への協力と、(b)職業訓練関連分野における協力を積極的に行う。
(ロ) 電力・運輸等インフラ整備
輸出指向型経済成長のための外国投資導入に資するインフラ整備を行う。(将来的な需要の増加に対応するための電力分野での協力、各交通形態の特性に応じた運輸分野での協力)
(ハ) 農業・農村開発
ヴィエトナムの主要産業である農業分野では、生産性向上のための農業インフラ(注1)の整備(社会経済基盤の整備が遅れている地域では農業基盤整備に社会経済インフラ整備を伴う農業適地開発)及びポスト・ハーベスト(貯蔵、流通、加工)の向上、並びに農業生産の多様化を図るため農業技術の開発・普及等に資する協力を行い、地方における生活水準の向上を目指す。
(ニ) 教育、保健・医療
ヴィエトナムでは、高い進学率や識字率が社会指標に表れているが、教育環境や医療設備は改善の余地が極めて大きい。(a)教育分野(初等・高等教育機関の施設・設備の整備)、(b)保健医療分野(医療サービス向上のための施設・設備の整備)、(c)人口・エイズ分野を重視する。
(ホ) 環境
環境分野の案件については、(a)自然環境保全、(b)居住(都市)環境の改善、及び(c)公害防止に資する各種協力(注2)をヴィエトナム側の優先度を考慮し、具体的な協力を検討する。また、環境分野で活躍するNGOに対する支援を積極的に検討する。
(注1)灌漑システム等
(注2)自然環境保全:植林事業、森林経営計画策定、生態系保護等
居住環境改善:上下水道・排水設備の整備
公害防止:大気・海洋汚染防止、産業廃棄物処理等
また、援助実施にあたっては、援助吸収能力の向上やインドシナ地域全体の発展を念頭に置く必要がある。
(3) 我が国は91年10月のパリ和平協定署名後、他の先進諸国に先駆けて本格的な対ヴィエトナム経済協力を再開した(92年11月に455億円の商品借款を供与)。以来、93年10月のヴィエトナムの対IMF延滞債務の解消においても主導的な役割を果たしたのをはじめ、支援を拡充してきている。98年12月にパリで開催された第6回対ヴィエトナム支援国会合では参加ドナー中最大の総額約1,023億円(有償880億円、無償60億円、技協65億円、開発調査18億円)の支援を表明した。
(4) 98年には、ヴィエトナムに対し支出純額で3.88億ドル(我が国二国間援助の第6位)、98年までの支出純額累計で総額15.32億ドル(同第13位)の支援を行っている。
有償資金協力は92年から再開。これまでは道路、港湾、電力といった基本インフラを重点的な対象分野としてきたが、今後は環境、上水道等社会インフラも対象としていく方針である。98年度からは、向こう3年間のロングリスト方式(候補案件を列挙しその中から可能なものを採り上げる方式)を採用している。98年度は、ヴィエトナムの市場経済化を支援するものとして、電力・運輸分野の基幹インフラに加えて、新たな分野への協力として中小企業育成支援等、総額880億円の円借款を供与した。
無償資金協力については、92年度に緊急かつ人道的考慮から「チョーライ病院改善計画」に対する協力を実施し、その他の分野においても本格的な支援を再開している。98年度は、「第4次初等教育施設整備計画」、「バックマイ病院改善計画」のほか農業分野等への協力を実施した。また、経済構造改革努力への支援として20億円のノンプロジェクト無償資金協力を行った。
技術協力についても92年度から拡大し、行政分野、市場経済関連分野、職業訓練関連分野をはじめ、保健・医療、農業、教育、植林分野等への協力を行っている。97年12月に発表された「日・ASEAN総合人材育成プログラム」に基づく、人造り面での協力を推進しているほか、「日・インドシナ友情計画」の下、毎年100名のヴィエトナム青年を我が国に招聘するなど、研修生受け入れは95年より急増している。また、開発調査では、援助再開当初、経済社会インフラ整備の分野を中心に、各種開発計画、個別プロジェクトのフィージビリティ調査を積極的に実施していたが、95年度から、マスタープラン策定を通ずる市場経済化を視野に置いたヴィエトナムの開発計画の策定などに対する「対越市場経済化総合政策支援」を実施している。96年度からは、法整備のための「重要政策中枢支援」等のソフト面での協力を実施している。なお、重要政策中枢支援についてヴィエトナムは、越の制度造りに関し、石川滋一橋大学名誉教授を中心に越の市場経済化に向けた政策策定支援「市場経済化支援開発政策調査(石川プロジェクト)」を継続してきており、これまでの第1・第2フェーズにおいて、マクロ経済、財政金融、農業・農村開発等の分野への提言を行ってきており、現在そのフォローアップ研究を実施中であり、今後、フェーズ3を実施する予定である。98年度にはハノイ市の廃棄物処理分野・公衆衛生分野の現状を調査する「都市環境調査」、アジア諸国の経済・経営面の人材育成に貢献していくためビジネス講座や日本語教育等を実施する「人材協力センター設立のための調査」を行っている。
(5) WID(途上国の女性支援)の分野では、95年2月に東京で開催されたインドシナ総合開発フォーラム関係会合のフォローアップのために96年1月「インドシナ地域WIDセミナー」をESCAP及びUNDPと共同で開催した。同セミナーでは「移行期経済における女性の役割」をテーマとし、行動計画が採択された。また、同行動計画を踏まえ、96年5月のヴィエトナム国別ワークショップ(ヴィエトナム女性連合、日本、ESCAP、UNDPの共催)では、国別行動計画が採択された。
|
(1) 我が国のODA実績 |
(支出純額、単位:百万ドル) |
| 年 | 贈与 | 政府貸付 | 合計 | |||
| 無償資金協力 | 技術協力 | 計 | 支出総額 | 支出純額 | ||
| 94 95 96 97 98 |
58.76(-) 98.66(58) 46.37(38) 79.08(34) 55.46(14) |
30.84(-) 45.70(27) 46.67(39) 54.35(23) 45.98(12) |
89.60(-) 144.36(85) 93.04(77) 133.43(57) 101.44(26) |
0.84 37.76 38.13 108.36 293.34 |
-10.14(-) 25.83(15) 27.81(23) 99.06(43) 287.18(74) |
79.46(100) 170.19(100) 120.86(100) 232.48(100) 388.61(100) |
| 累計 | 469.65(31) | 278.39(18) | 748.04(49) | 937.24 | 783.57(51) | 1,531.61(100) |
(注)( )内は、ODA合計に占める各形態の割合(%)。
(2) DAC諸国・国際機関のODA実績(97年支出純額、単位:百万ドル)
|
DAC諸国、ODA NET |
(支出純額、単位:百万ドル) |
| 暦年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | その他 | 合計 |
| 95 96 97 |
日本 170.2 日本 120.9 日本 232.5 |
ドイツ 120.4 フランス 67.3 フランス 63.9 |
フランス 94.1 ドイツ 52.8 米国 48.0 |
豪州 39.8 豪州 47.5 豪州 41.3 |
スウェーデン 34.0 スウェーデン 46.2 ドイツ 40.1 |
170.2 120.9 232.5 |
549.7 469.5 585.5 |
|
国際機関、ODA NET |
(支出純額、単位:百万ドル) |
| 暦年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | その他 | 合計 |
| 95 96 97 |
IMF
91.6 IDA 188.0 IDA 180.2 |
ADB 56.8 IMF 175.4 ADB 147.5 |
IDA 46.5 ADB 26.9 CEC 23.6 |
CEC
23.0 CEC 19.9 UNDP 15.8 |
UNICEF 18.9 WFP 12.6 WFP 13.9 |
42.9 35.8 29.7 |
279.7 458.6 410.7 |
|
(3) 年度別・形態別実績 |
(単位:億円) |
| 年度 | 有償資金協力 | 無償資金協力 |
技術協力 |
||||||||||||
| 90年度までの累計 |
404.30億円 (内訳は、1997年版のODA白書参照、もしくはホームページ参照) |
312.92億円 (内訳は、1997年版のODA白書参照、もしくはホームページ参照) |
24.49億円
|
||||||||||||
| 91 |
なし |
0.18億円
越日クラブに対する視聴覚機材 (0.18) |
1.32億円
|
||||||||||||
| 92 | 455.00億円
商品借款 (455.00) |
15.87億円
チョーライ病院改修計画(1/3期) ハイバーチュン病院医療機材整備計画 (3.51) 中部高原植林機材整備計画 (3.33) 文化・情報・スポーツ省に対する体操機材(0.49) 草の根無償(4件) (0.14) |
3.32億円
|
||||||||||||
| 93 |
523.04億円
93年度円借款 (523.04) |
62.70億円
チョーライ病院改善計画(2/3期) (8.03) |
13.16億円
|
||||||||||||
| 94 | なし |
56.72 億円
チョーライ病院改善計画(3/3期) (8.77) |
23.75億円
|
||||||||||||
| 95 |
1,280.00 億円
94年度円借款 (580.00) |
89.08億円
第二次ハノイ市ザーラム地区上水道整備計画(国債2/2) (12.54) |
32.40億円
|
||||||||||||
| 96 |
810.00億円
96年度円借款 (810.00) |
80.35億円
ヴンタオ漁港施設建設計画(国債II) (16.16) |
33.52億円
|
||||||||||||
| 97 |
850.00億円
97年度円借款 (850.00) |
72.97億円
北部地方橋梁改修計画(国債2/3期) (17.85) |
42.22億円
|
||||||||||||
| 98 |
880.00億円
98年度対ヴィエトナム円借款 (880.00) |
81.86億円
タンチ地区農村排水改善計画(2/3期) (14.91) |
46.36億円
|
||||||||||||
| 98年度までの累計 |
5,202.34億円 (旧南ヴィエトナムに対する援助304.30億円を含む) |
772.65億円 (旧南ヴィエトナムに対する援助134.60億円及び旧北ヴィエトナムに対する援助85億円を含む) |
220.54億円
|
(注)1.「年度」の区分は、有償資金協力は交換公文締結日、無償資金協力及び技術協力は予算年度による。(ただし、96年度以降の実績については、当年度に閣議決定を行い、翌年5月末日までにE/N署名を行ったもの。)
2.「金額」は、有償資金協力及び無償資金協力は交換公文ベース、技術協力はJICA経費実績ベースによる。
3.59年度から90年度までの有償資金協力及び無償資金協力実績の内訳は、1997年版のODA白書参照、もしくはホームページ参照
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/jisseki/kuni/j_90sbefore/901-02.htm)
(参考1) 98年度までに実施済及び実施中のプロジェクト方式技術協力案件
| 案件名 | 協力期間 |
|
サイゴン病院 |
66.4 ~75.3 |
(参考2) 98年度実施開発調査案件
| 案件名 |
|
カントー橋建設計画実施設計調査(第1年次) 運輸交通開発戦略調査(第1年次) ホアラック・ソンマイ地域開発計画調査フェーズ1(第2年次) 全国電気通信整備計画調査(第1年次) ホーチミン市排水・下水道整備計画調査(第1年次) ハノイ市環境保全計画調査(第1年次) 紅河橋(タインチ橋)建設計画実施設計調査(第1年次) ドンタップモイ農業開発計画調査(第1年次) ハロン湾環境管理計画調査(第2年次) 北部地方地下水開発計画調査(第1年次) ドンナイ川中流ドンナイ第3・第4連係水力発電計画調査 タインチ橋建設計画調査(第2年次) カントー橋建設計画調査(第2年次) 中部重点地域港湾開発計画調査(第3年次) 中小企業振興計画調査 タインチ橋/カントー橋建設事業実施設計予備調査 ドンナイ川中流ドンナイ第3、第4連係水力発電計画予備調査 運輸交通開発戦略事前調査(S/W協議) ドンナイ川中流ドンナイ第3、第4連係水力発電計画予備調査 |
(参考3)98年度実施草の根無償資金協力案件
| 案件名 |
|
第4区6月1日学校改築計画 カイヌオック区小中学校再建計画 ビンフオック小学校整備計画 村落保健センター改修計画 タインビン区医療センター機材整備計画 ロンミー区医療センター機材整備計画 ヴィタイン区医療センター機材整備計画 ハイフォン市国道5号線救急救命サービス強化計画 国際赤十字干ばつ災害支援計画 X線検診車による地域肺ガン集団検診計画 ディンモン1小学校増築計画 溶接・切断技能訓練計画 ヴィエトナム中北部3省総合母子保健改善事業計画 ハノイ日本語センター教育設備改善事業 キエンザン省小中学校教室整備計画 ハノイ医科大学歯学部医療教育改善計画 越赤十字社台風災害支援計画 フークオック島医療機材輸送計画 ゲアン省ディエンホア村灌漑施設整備計画 タイフー区小学校・保育園増設計画 レ・チャン区立病院産婦人科改修計画 ダナン市台風災害支援計画 クワンナム省台風災害支援計画 トゥアティエンフエ省台風災害支援計画 |