(3)情報通信技術(ICT)、科学技術・イノベーション促進、研究開発
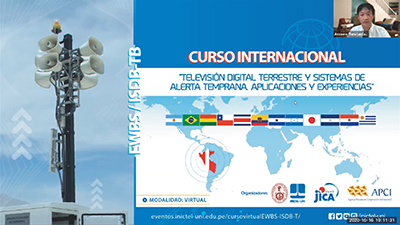
中南米諸国向け地デジおよび緊急警報放送システム(EWBS)に関するオンライン研修で講義するJICA専門家
情報通信技術(ICT)注8の普及は、産業の高度化や生産性の向上、および持続的な経済成長の実現に役立つとともに、開発途上国が抱える医療、教育、エネルギー、環境、防災などの社会的課題の解決に貢献します。さらに、ICTの活用は、政府による情報公開の促進や、放送メディアの整備といった民主化の土台となる仕組みを改善します。また、新型コロナの拡大を受けデジタル・トランスフォーメーション(DX:Digital Transformation)注9の重要性も高まっています。このように、ICTは、利便性とサービスの向上を通じた市民社会の強化、および質の高い成長のために非常に重要です。
●日本の取組
…情報通信技術(ICT)

ベトナムにおける「サイバーセキュリティに関する能力向上プロジェクト」での認定ホワイトハッカー研修の様子(写真:JICA)
日本は、地域・国家間に存在するICTの格差を解消し、すべての人々の生活の質を向上させるために、ICT分野でも「質の高いインフラ投資」を推進すべく、2017年、各国のICT政策立案者や調達担当者向けに、「質の高いICTインフラ」投資の指針を策定しました。
また、開発途上国における通信・放送設備や施設の構築、そのための技術や制度整備、人材育成といった分野を中心に積極的に支援しています。具体的には、日本は、自国の経済成長に結びつける上でも有効な、地上デジタル放送日本方式(ISDB-T)*の海外普及活動に積極的に取り組み、整備面、人材面、制度面の総合的な支援を目指しています。ISDB-Tは、中南米、アジア、アフリカ各地域で普及が進んでおり、2019年3月には新たにアンゴラが採用を決定したことで、同年12月現在、計20か国注10で採用されています。日本は、ISDB-T採用国および検討国を対象としたJICA研修を毎年実施しており、ISDB-Tの海外普及・導入促進を行っています。総務省では、ISDB-Tの海外展開のため、相手国政府との対話・共同プロジェクトを通じ、ICTを活用した社会的課題解決などの支援を推進しています。
ASEAN地域においては、インドネシアやフィリピンを中心とする島嶼(とうしょ)国の遠隔地に低コストで高速のインターネット利用環境を整備しています。アジア太平洋地域では、脆弱(ぜいじゃく)なインフラや利用コストが負担できないことなどを要因としてインターネットが利用できない人々は20億人以上おり、日本は低コストで高速のインターネット利用環境を整備するため対ASEAN海外投融資イニシアティブ(案件紹介も参照)のもと、2,500ドルの融資を行いました。
また、日本は、「防災ICTシステムの海外展開」にも取り組んでいます。日本の防災ICTシステムを活用すれば、情報収集・分析・配信を一貫して行うことができ、コミュニティ・レベルまで、きめ細かい防災情報を迅速かつ確実に伝達することが可能です。引き続き、日本は、防災ICTシステムの海外展開を促進する支援を実施し、途上国における防災能力の向上等に寄与することを目指します(防災について、詳細は「防災協力」を参照)。
加えて、日本は、各種国際機関と積極的に連携した取組も行っており、電気通信およびICTに関する国際連合の専門機関である国際電気通信連合(ITU:International Telecommunication Union)*と協力し、途上国に対して、電気通信およびICT分野の様々な開発支援を行っています。
新型コロナの世界的な拡大を受け、2020年10月、アフリカ諸国を主な対象として、新型コロナの感染拡大の抑止に資するデジタルインフラ強化および利用環境整備のための国家戦略の策定等を支援する、総務省およびITUの共同プロジェクトを開始しました。本プロジェクトには、サウジアラビアも参加し、今後、総務省、ITUおよびサウジアラビアの3者が協力してプロジェクトを進めていきます。
アジア・太平洋地域では、情報通信分野の国際機関であるアジア・太平洋電気通信共同体(APT:Asia-Pacific Telecommunity)*が、同地域の電気通信および情報基盤の均衡した発展に寄与しています。2020年には3年に1度のAPT総会がバーチャルで開催され、日本の議長運営のもと、2021年から2023年のAPT戦略計画や予算等についての審議・決定が行われたほか、次期事務局長・事務局次長の選挙が行われ、近藤勝則(こんどうまさのり)氏が事務局長に選出されました。
日本は、APTの活動の主な目的の1つである情報通信に関する人材育成を推進するため、毎年、APTが実施する数多くの研修を支援しています。2019年度には、ブロードバンドネットワークやサイバーセキュリティ等に関する研修を5件実施し、各加盟国から約50名が参加しました。研修では、各研修生が座学および施設見学で日本の技術を学び、自国のICT技術の発展に役立てています。また、日本の技術システムをアジア太平洋地域に広めることで、日本企業の同地域への進出も期待できます。
また、東南アジア諸国連合(ASEAN)では、2015年11月にASEAN首脳会議で採択された「2025年までの新たな指標となるブループリント(詳細な設計)」で、ICTがASEANに経済的・社会的変革をもたらす重要な鍵として位置付けられ、同年11月に開催されたASEAN情報通信大臣会合において、2020年に向けたASEANのICT戦略である「ASEANICTマスタープラン2020(AIM2020)」が策定されています。さらに、近年特に各国の関心が高まっているサイバー攻撃を取り巻く問題についても、日本はASEANとの間で、情報セキュリティ分野での協力を今後一層強化することで一致しています。
日本は、2016年にサイバーセキュリティ戦略本部に報告した「サイバーセキュリティ分野における開発途上国に対する能力構築支援の基本方針」に基づき、具体的取組として、日ASEAN統合基金(JAIF)*を通じて「日ASEANサイバーセキュリティ能力構築センター(AJCCBC)」を設立する(詳細は「サイバー空間」を参照)とともに、2020年1月には日ASEAN技術協力協定に基づくサイバーセキュリティ研修(詳細は案件紹介を参照)を実施しました。
…科学技術・イノベーション促進、研究開発

SATREPSのもと、ザンビアで実施されている「アフリカにおけるウイルス性人獣共通感染症の疫学に関する研究プロジェクト」にて、夜に捕獲したコウモリを選別している様子(写真:北海道大学)(「匠の技術、世界へ」も参照)
ODAと科学技術予算を連携させた地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS)*は、日本の科学技術に関する支援の主な取組として2008年に始まり、2020年度までに、世界52か国において157件の共同研究プロジェクトが採択されています(「匠の技術、世界へ」も参照)。
また、日本は、工学系大学への支援を強化することで、人材育成への協力をベースにした次世代のネットワーク構築を進めています。
アジアでは、マレーシア日本国際工科院(MJIIT:Malaysia-Japan International Institute of Technology)に対し、教育・研究用の資機材の調達と、教育課程の編成を支援しています。また、日本国内の27大学および2研究機関と連携し、カリキュラムの策定や日本人教員派遣などの協力も行っています。さらに、日本は、タイに所在し、工学・技術部や環境・資源・開発学部等の修士課程および博士課程を有する、アジア地域でトップレベルの大学院大学であるアジア工科大学院(AIT:Asian Institute of Technology)において、日本人教官が教鞭(きょうべん)をとるリモートセンシング(衛星画像解析)分野の学科に所属する学生への奨学金を拠出しており、アジア地域の宇宙産業振興の要となる人材の育成に貢献しています。
エジプトでは、日本型の工学系大学院教育の特徴を活かした、少人数、大学院・研究中心、実践的かつ国際水準の教育の提供をコンセプトとする公的な大学である「エジプト・日本科学技術大学(E-JUST:Egypt-Japan University of Science and Technology)」を継続して支援しています。日本国内の大学の協力を得て、実践的な工学教育や日本式の研究中心等の教育の導入など、大学院・学部の運営支援を行っているほか、アフリカ諸国からの留学生受入れも支援しており、アフリカ・中東地域における産業・科学技術人材の育成に貢献しています。
用語解説
- *重債務貧困国(HIPCs:Heavily Indebted Poor Countries)
- 貧しく、かつ重い債務を負っているとして、包括的な債務救済枠組である「拡大HIPCイニシアティブ」の適用対象となっている、主にアフリカ地域および東アジア地域を中心とする39の開発途上国。
- *地上デジタル放送日本方式(ISDB-T:Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial)
- 日本で開発された地上デジタルテレビ放送方式で、緊急警報放送の実施、携帯端末でのテレビ受信、データ放送等の機能により、災害対策面、多様なサービス実現といった優位性を持つ。
- *国際電気通信連合(ITU:International Telecommunication Union)
- 電気通信・放送分野に関する国連の専門機関(本部:スイス・ジュネーブ。193か国が加盟)。世界中の人が電気通信技術を使えるように、①携帯電話、衛星放送等で使用する電波の国際的な割当、②電気通信技術の国際的な標準化、③開発途上国の電気通信分野における開発の支援等を実施している。
- *アジア・太平洋電気通信共同体(APT:Asia-Pacific Telecommunity)
- 1979年に設立された、アジア・太平洋地域における情報通信分野の国際機関で、同地域38か国が加盟。同地域における電気通信や情報基盤の均衡した発展を目的とし、研修やセミナーを通じた人材育成、標準化や無線通信等の地域的な政策調整等を実施している。
- *日・ASEAN統合基金(JAIF:Japan-ASEAN Integration Fund)
- ASEAN共同体の設立を目指し、域内格差の是正を中心とした統合を進めるASEAN諸国の努力を支援するため、2005年12月の日・ASEAN首脳会議において小泉総理大臣(当時)が総額75億円(約70.1百万ドル)を拠出することを表明したことを受け2006年に設置された基金。その後、2013年の日・ASEAN特別首脳会議において、安倍総理大臣(当時)が「日・ASEAN友好協力に関するビジョン・ステートメント」および実施計画を発出するとともに、①海洋協力、②防災協力、③テロ・サイバー対策、④ASEAN連結性強化を4つの重点事項として同ビジョン・ステートメントおよび実施計画(2017年に実施計画を改訂)を実現するために活用することを想定した「JAIF2.0」に総額1億ドルを拠出することを表明。日本は、2019年および2020年にも「JAIF2.0」に追加拠出をしている。
- *地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS:Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development)→ 「匠の技術、世界へ」も参照
- 日本の優れた科学技術とODAとの連携により、環境・エネルギー、生物資源、防災および感染症といった地球規模課題の解決に向けた研究を行い、①国際科学技術協力の強化、②地球規模課題の解決につながる新たな知見や技術の獲得、これらを通じたイノベーションの創出、③キャパシティ・ディベロップメント注11を目的とし、日本と途上国の研究機関が協力して国際共同研究を実施する取組。外務省と国際協力機構(JICA)が文部科学省、科学技術振興機構(JST)および日本医療研究開発機構(AMED)と連携し、日本側と途上国側の研究機関・研究者を支援している。
- 注8 : Information and Communications Technologyの略。コンピュータなどの情報技術とデジタル通信技術を融合した技術で、インターネットや携帯電話がその代表。
- 注9 : 新たなIT技術の導入が人々の生活をより便利にしたり豊かにしたりすること、新しいデジタル技術の導入により既存ビジネスの構造を作り替えたりするなど、新しい価値を生み出すこと。
- 注10 : 日本、ブラジル、ペルー、アルゼンチン、チリ、ベネズエラ、エクアドル、コスタリカ、パラグアイ、フィリピン、ボリビア、ウルグアイ、ボツワナ、グアテマラ、ホンジュラス、モルディブ、スリランカ、ニカラグア、エルサルバドル、アンゴラの20か国(2019年12月時点)。
- 注11 : 国際共同研究を通じた開発途上国の自立的研究開発能力の向上と課題解決に資する持続的活動体制の構築、また、地球の未来を担う日本と途上国の人材育成とネットワークの形成を行うこと。
