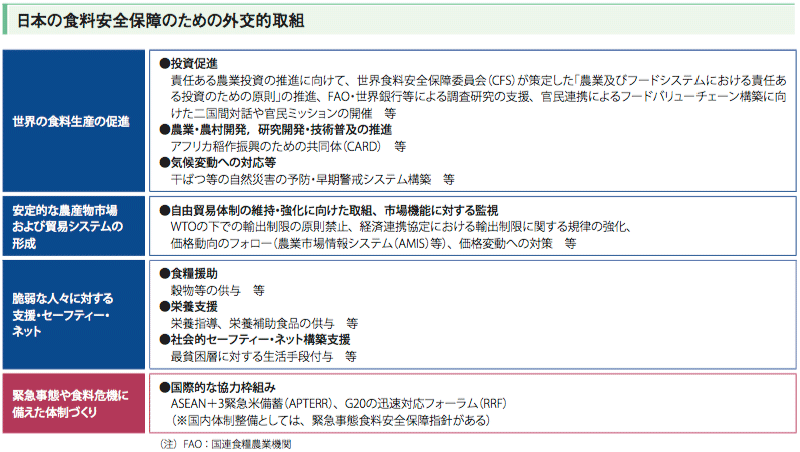(4)食料安全保障および栄養
国連食糧農業機関(FAO)(注105)、国際農業開発基金(IFAD)(注106)、および国連世界食糧計画(WFP)(注107)共同の報告「世界の食料不安と現状2015年報告(SOFI2015)(注108)」によると、世界の栄養不足人口は過去10年間で1億6,000万人以上、1990年~1992年以降では2億人以上減少しているという良好な傾向が確認されたものの、依然として約8億人(2014年~2016年、推計値)が栄養不足に苦しんでいるとされています。
この報告書によれば統計上は未達であったが、開発の観点からは、2015年までに飢餓人口の割合を半減するというミレニアム開発目標(MDGs)は達成したと見なせるとされています。また、社会的セーフティー・ネット(人々が安全で安心して暮らせる仕組み)の確立や栄養状態の改善、必要な食料支援や家畜の感染症への対策など、食料安全保障(すべての人がいかなるときにも十分で安全かつ栄養ある食料を得ることができる状態)を確立するための国際的な協調や多面的な施策が求められています。
さらに、妊娠から2歳の誕生日を迎えるまでの1,000日間における栄養改善は特に効果的であるため、そのための取組が進められています。
< 日本の取組 >
このような状況を踏まえ、日本は、食料不足に直面している開発途上国からの要請に基づき食糧援助を行っています。2014年度には、二国間食糧援助として14か国に対し総額55.7億円の支援を行いました。

ザンビア・ブルング小中学校で給食を受け取る生徒たち(写真:渋谷敦志/JICA)
国際機関を通じた支援では、主にWFPを通じて、緊急食料支援、教育の機会を促進する学校給食プログラム、食料配布により農地や社会インフラ整備などへの参加を促し、地域社会の自立をサポートする食料支援などを実施しています。2014年には世界各地で実施しているWFPの事業に総額1億5,655万ドルを拠出しました。
また、15の農業研究機関から成る国際農業研究協議グループ(CGIAR)(注109)が行う品種開発等の研究にも支援を行うとともに、研究者間の交流を通じ連携を進めています。
ほかにも日本は、開発途上国が自らの食料の安全性を強化するための支援を行っています。口蹄疫(こうていえき)などの国境を越えて感染が拡大する動物の伝染病について、越境性感染症の防疫のための世界的枠組み(GF-TADs)(注110)など国際獣疫事務局(OIE)(注111)やFAOと連携しながら、アジア・太平洋地域における対策を強化しています。さらに、日本は国際的な栄養不良改善への取組であるScaling Up Nutrition(SUN)に深く関与し、支援の強化を表明しました。
- 注105 : 国連食糧農業機関 FAO:Food and Agriculture Organization
- 注106 : 国際農業開発基金 IFAD:International Fund for Agricultural Development
- 注107 : 国連世界食糧計画 WFP:World Food Programme
- 注108 : SOFI2015:The State of Food Insecurity in the World 2015
- 注109 : 国際農業研究協議グループ CGIAR:Consultative Group on International Agricultural Research
- 注110 : 越境性感染症の防疫のための世界的枠組み GF-TADs:Global Framework for Progressive Control of Transboundary Animal Diseases
- 注111 : 国際獣疫事務局 OIE:Office Internationale des Epizooties 通称はWorld Organisation for Animal Health
●マダカスカル
中央高地米生産性向上プロジェクト
技術協力(2009年1月~2015年7月)

ブングラバ県のプロジェクト実証圃場で収穫を行う実証農家。彼らの笑顔は、協力を行う日本人たちにとっての励みとなる(写真:JICA)
マダカスカルの国土は、日本の約1.6倍で、世界で4番目に大きい島です。コメを主食としており、日本人と比べ約2倍に当たる、年間国民1人当たり約120キログラムを消費しています。コメの生産面積は140万ヘクタールで、毎年300万トン前後のコメを生産していますが、サイクロンなどの影響により年間生産量の変動が大きく、自国のコメ消費量の約10%を輸入に頼っています。
国家開発計画であるマダガスカル・アクション・プラン(MAP:2007-2012年)において、最も重要な改革イニシアティブの一つとして、コメの生産量を2005年の342万トンから2012年までに倍増させることが目標とされました。
日本は、マダカスカル中央高地の主要な稲作形態に対応した技術開発と普及支援を行うとともに、稲作関連機関の連携強化を図ることを目的に支援を開始しました。
コメ増産に取り組むに当たり、首都アンタナナリボと第三の都市アンチラベがある人口集中地域の中央高地において、コメの生産量を増大させることは重要な課題でした。このプロジェクトの対象地域5県は中央高地に位置しており、標高は約600メートルから1,500メートルで、多様な自然・生態環境の下、灌漑(かんがい)稲作、谷地田における天水稲作および高冷地における稲作が主な稲作形態です。コメの生産性向上のためには、稲作形態に適し、かつ市場と農家の評価を踏まえた推奨品種の選定、その種子の普及、および品種に適した栽培技術の確立とその普及が欠かせません。
このプロジェクトでは、重点県であるアロチャ・マングル県の灌漑稲作、ブングラバ県の天水稲作、ヴァキナカラチャ県の高冷地稲作といった典型的な稲作条件に対応して、3種類の基本的な技術パッケージを作成し、技術開発から技術の普及へと取り組みました。各県に設置したモデルサイトを中心に周辺農家への普及活動を実施してきましたが、2013年~2014年からはモデルサイト以外の地域での技術普及も本格的に開始しました。さらに、プロジェクトでは品種選定、種子増殖、配布体制の整備を推進してきました。マダガスカルでは農業技術普及員の人材不足が大きな問題でしたが、2013年6月時点では、重点県において技術パッケージを用いた技術指導経験を持つ研修員が、全研修員数119名中104名(87.5%)であったところ、2015年2月の調査時点では、全研修員数228名中217名(95.2%)へと増加しました。
モデルサイトにおけるコメ生産農家のコメの平均単位収量が1ヘクタール当たり1トンの増加という目標においても、2011/12年作期に示された収量増分1ヘクタール当たり0.67トンから、2013/14年作期に示された収量増分は1.50トンへと、単位面積当たりの収量の向上が示されました。この増加は達成指標を満たすものと評価されています。