第2章 持続可能な開発のための2030アジェンダ

ザンビアの特別支援学校リトル・アッシジで、子どもたちにダンスを教える青年海外協力隊(障害者支援)の吉澤雄介さん(写真:渋谷敦志/JICA)
第1節 持続可能な開発のための2030アジェンダに向けた取組
2010年9月に国連で開催されたMDGs国連首脳会合は、各国首脳が「ポスト2015年開発アジェンダ」、すなわち2015年以降のMDGsの後継目標について議論を行う場となりました。そして、翌年(2011年)の6月に日本が国連開発計画や世界銀行などと共催した閣僚級の「MDGsフォローアップ会合」や、同じ年の9月の国連総会の機会に開かれた「MDGs閣僚級非公式会合」を通じて、ポスト2015年開発アジェンダに関する国際社会の議論は本格化しました。検討作業は、次の3つの流れを通じて主に進められていくことになりました(図-1参照)。
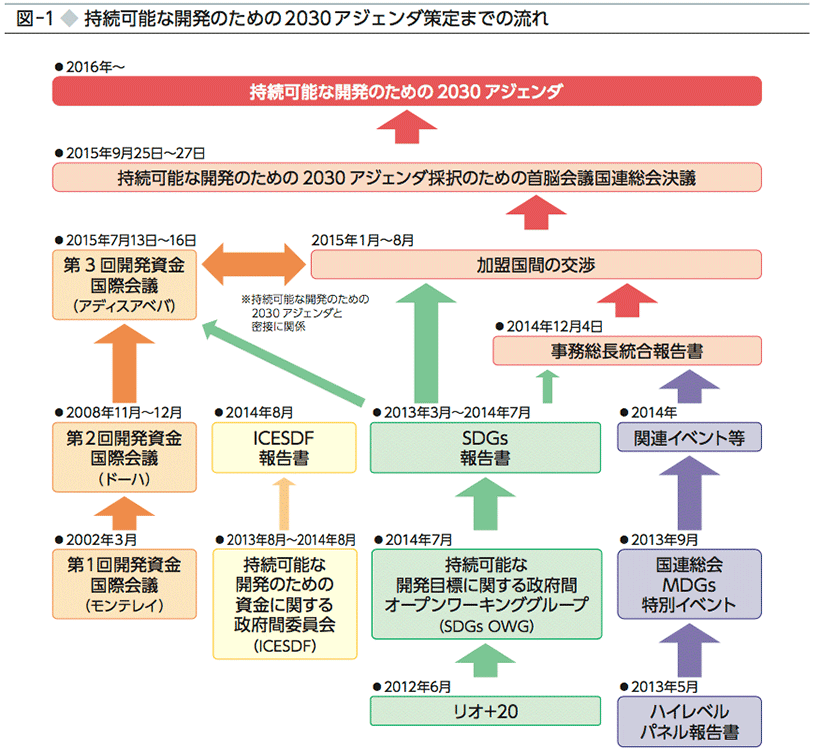
○国連事務総長によるプロセス

2015年9月、持続可能な開発のための2030アジェンダを採択する国連サミットで、2030アジェンダへの日本の取組について述べる安倍晋三総理大臣(写真:内閣広報室)
国連では、2012年7月に潘基文(パン・ギムン)事務総長が立ち上げた27名の有識者から成るハイレベル・パネルで、ポスト2015年開発アジェンダに関する議論が開始されました。このハイレベル・パネルは、2013年5月に、12の目標(ゴール)と54のターゲットから成るポスト2015の目標案を提示する報告書を潘事務総長に提出しました。その後も、2013年9月の国連総会の機会に開かれたMDGs特別イベントや、2014年に行われたテーマ別討論やハイレベルイベントなど、潘国連事務総長が主催する一連の機会を通じ、その後の政府間交渉や採択に向けたタイムフレーム等が定められていきました。
○国連持続可能な開発会議(「リオ+20」)のプロセス

キルギス・ビシュケク近郊チュイ州のパイロット農家で有機栽培のタマネギ畑を視察するJICAの本田知大隊員(写真:鈴木革/JICA)
国連では、従来から、1992年にブラジルのリオデジャネイロで開催された「地球サミット(環境と開発に関する国際連合会議)」などを通じて、持続可能な開発のあり方について議論が進められてきました。その一環として2012年6月に開催された「国連持続可能な開発会議」(「リオ+20」)では、「持続可能な開発目標」(SDGs:Sustainable Development Goals)を策定すること、そして、これをポスト2015年開発アジェンダに統合することが決定されました。これを受けて立ち上げられた政府間オープンワーキンググループ(SDGs OWG)では、ほぼすべての国連加盟国による交渉を経て、2014年7月に、17の目標(ゴール)と169のターゲットから成るSDGsが提案されました。このとき提案されたSDGsは、のちに、ほぼそのままの形でポスト2015年開発アジェンダ(2015年9月に国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」)に組み込まれました。
○開発資金をめぐるプロセス

ケニア・キジャベのモデル農家グループにあいさつをする加藤満広専門家(写真:久野武志/JICA)
ポスト2015年開発アジェンダの検討のプロセスでは、開発の目標やターゲットだけでなく、その達成のために必要な資金の確保や活用も重要な検討課題となりました。この課題を主として扱ったのが、国連が主催する開発資金国際会議のプロセスです。このプロセスの下では、2002年のメキシコのモンテレイでの第1回会議、2008年のカタールのドーハでの第2回会議を通じて、MDGsをはじめとする開発課題の達成のための開発資金について議論が行われてきており、2015年7月のエチオピアのアディスアベバでの第3回会議に向けてポスト2015年開発アジェンダの開発資金を焦点に各国の間で検討作業が進められました。あわせて2012年の「リオ+20」を受けて立ち上がった「持続可能な開発のためのファイナンシング戦略に関する政府間委員会」においてもポスト2015年開発アジェンダのための資金の問題について議論が行われました。
こうした流れを踏まえて、ポスト2015年開発アジェンダや、これに組み込まれる目標やターゲット、指標などの国連加盟国間の正式な交渉が始まったのは、2015年1月のことです。交渉は7回にわたって行われ、基本的な考え方、目標、実施手段、フォローアップ等について、国連加盟の193か国の間で意見が交わされました。また、その過程では、民間企業や市民社会の代表との対話も行われました。こうしたプロセスを経て、日本時間の2015年8月2日、第7回交渉の最終日に、各国は、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」のドラフトに合意しました。そして、9月25日から27日に開催された国連サミットで、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」(以下、2030アジェンダ)が各国首脳によって正式に採択されたのです。これに先立つ2015年7月には、エチオピアで開催された第3回開発資金国際会議で、ポスト2015年開発アジェンダの開発資金に関する「アディスアベバ行動目標」が採択されていました。
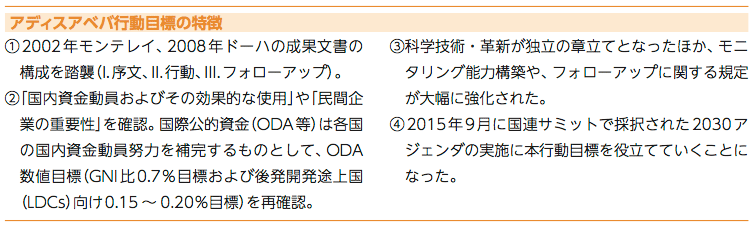
MDGsと2030アジェンダが策定されたプロセスを比較してみると、国連の専門家主導で策定されたMDGsとは対照的に、後者については、多様なプロセスを通じ、国連加盟国をはじめ、国際機関・民間企業・市民社会などの多様なステークホルダー(関係者)の関与の中で進められていったことが分かります。これは、開発途上国も先進国も共に参加し、多様なステークホルダーがかかわるグローバル・パートナーシップを謳(うた)う2030アジェンダの策定にふさわしいプロセスであったといえるでしょう。
日本は、この新しい開発アジェンダの策定のプロセスに、①MDGsの経験と教訓を踏まえること、②地域差・国内格差の課題に目を向け、立場の弱い人々を取り残さないようにすること、③富を創出する源である成長・雇用に十分に光を当てること、④国際社会の変化に対応すること、⑤開発途上国自身のオーナーシップ(主体的な取組)を促進する、との考えの下で積極的に取り組んできました。そのため、先ほど紹介した2011年6月のMDGsフォローアップ会合のほか、2011年12月に立ち上げたポスト2015開発アジェンダに関する非公式な政策対話(コンタクト・グループ)、国連総会やIMF・世銀年次総会東京会合(2012年)での関連のイベント開催等を通じて、日本の考えを説明しながら、国際的な作業の進展への貢献に努めました。

ケニア西部シアヤ郡のミランボ小学校で行われた、「カラドロ西給水計画」の起工式(写真:柴岡久美子/在ケニア日本大使館)

稲作収穫技術に関する研修で来日したガーナの研修員が秋田県大潟村農協の倉庫で出荷前のミニトマトを見学(写真:久野真一/JICA)
