第2章 これからの日本の開発協力

マラウイ・チョロ県病院の薬局で、外来患者と話す青年海外協力隊員(薬剤師)の楠美有紀子さん。薬局では、番号札を作って薬の受け取りを待つ外来患者の混雑緩和を図ろうとしている(写真:今村健志朗/JICA)

キルギスにおける一村一品運動による小規模ビジネス振興を通じたイシククリ州コミュニティ活性化プロジェクト。「無印良品」((株)良品計画)で販売されるフェルト製品の検品をする女性たち。MUJIの品質基準をしっかりとチェック(写真:鈴木革/JICA)
第1章で見てきたとおり、この60年間、日本のODAは、国際環境の変化等に柔軟に対応しながら、日本の平和と安定および繁栄の増進に寄与してきました。それでは、今後のODAはどうあるべきでしょうか。それを示したのが、新しい開発協力大綱です。(新大綱全文は第III部に掲載)
新大綱は、2014年3月以降、約1年をかけ、有識者懇談会での議論およびパブリックコメント、全国各地で実施した意見交換会や公聴会など、様々な場を通じて、経済界、学界、NGOからいただいた意見を踏まえてとりまとめられ、2015年2月に閣議決定されました。
新大綱では、まず、現下の国際社会の状況について鳥瞰(ちょうかん)しています。
第一に、前章で見てきたとおり、グローバル化に伴う課題やリスクがますます増大しています。相互依存が高まって、環境・気候変動問題、災害、食料危機・飢餓、エネルギー、感染症等の国境を越える問題や、国際テロ、国際組織犯罪、海賊等の国際社会の平和と安定に対する脅威はもちろん、紛争中の、あるいは、紛争後の復興段階にある脆弱(ぜいじゃく)国家における人道的課題や地域紛争、政治的不安定に至るまで、世界各地のあらゆるリスクが、世界全体の平和と繁栄に悪影響を及ぼすようになっているとの危機感が高まっています。
第二に、開発途上国の間の多様化、多極化に伴い、開発課題が複雑化しています。国ごとの開発課題や特殊な脆弱性など単純に1人当たりの所得水準からだけではそれぞれの問題の深刻さはとらえきれません。
第三に、その裏腹で、急速な経済成長の結果、開発協力の新たな供与国として存在感を増す新興国の台頭があります。また、多くの開発途上国が新たな投資先・市場として注目を浴びた結果、近年大量の民間資金が開発途上国に流れるようになっています。OECD- DAC(ダック)や世銀の統計によれば2012年にはODAの約2.5倍の民間資金が途上国に流入しました。すなわち、開発途上国の開発は、もはや先進国のODAのみによって実現できるものではなく、民間資金等との連携を図ることが不可欠の状況となっているのです。
新たな開発協力大綱は、我が国がこのような認識に基づき、国際社会の平和と安定および繁栄の確保により一層積極的に貢献することを目的として開発協力を推進していく方針を明らかにしています。そして、こうした協力を通じて、我が国の平和と安全の維持、さらなる繁栄の実現、安定性および透明性が高く見通しがつきやすい国際環境の実現、普遍的価値に基づく国際秩序の維持・擁護といった国益の確保に貢献していくことを示しています。
その上で、新たな開発協力大綱は、日本が60年のODAの歴史の中で築き上げてきた基本的な理念である、以下の3点の哲学を日本の開発協力の「基本方針」として位置付けました。第一に「非軍事的協力による平和と繁栄への貢献」です。非軍事的な開発協力を通じて、国際社会の平和と繁栄に貢献する姿勢は、平和国家としての日本のあり方を体現するものです。新大綱には、国際社会の平和と安定、そして繁栄の確保にこれまで以上に積極的に寄与していくため、「非軍事的協力による平和と繁栄への貢献」という、平和国家としての日本にふさわしい開発協力を推進するとの基本方針が示されています。また、新大綱は、日本の開発協力の実施に当たって、「軍事的用途及び国際紛争助長への使用の回避」や、「民主化の定着、法の支配及び基本的人権の保障に係る状況」に十分注意を払うといった原則にのっとっていくことも明記しています。
第二に「人間の安全保障の推進」です。前章で見てきたとおり、一人ひとりを恐怖と欠乏から解き放ち、個人の豊かな可能性の実現を図るという人間の安全保障の考え方は、日本が国際社会の中でこれまで積極的に提唱してきたものです。新大綱は、日本が引き続きそうした人間中心のアプローチの観点から開発協力を推進していく考えを示しています。特に、女性の権利の保護や地位向上を図るとともに、その国の開発に果たす女性の役割に留意して、その能力強化や参画を推進するための取組は重要であり、実施上の原則としても「女性の参画の促進」を掲げています。
そして第三に「自助努力支援と日本の経験と知見を踏まえた対話・協働による自立的発展に向けた協力」です。第1章で見てきたとおり、日本は、戦争の灰塵(かいじん)の中から、諸外国からの支援を受けつつ、自ら努力して数々の課題に取り組み、戦後の成長を遂げてきました。そうした経験も踏まえ、日本は、一貫して開発途上国の自助努力や「オーナーシップ」を援助の基本原則に据えてきました。新大綱は、日本自身の経験を、あるいは、日本が支援した開発途上国の経験を人から人に伝えるという「人づくり」を重視し、共に考え、共に歩む中で、開発途上国自身の自主性や自助努力を促し、学び合うような協力をこれからも行っていく方針を示しています。

マラウイのムランジェ職業訓練盲学校の生徒たちと共に、収穫したとうもろこしを昼食の材料にしようと学校へ持ち帰る青年海外協力隊(野菜栽培)の小川由さん(写真:今村健志朗/JICA)

ペルー・カハマルカ州小規模農家生計向上プロジェクトの協力農家の紫とうもろこし畑で生育の様子を見る吉野倫典専門家。ペルーでは一般的な飲み物であるチチャモラーダの原料となる(写真:岡原功祐/JICA)

立命館大学では、日本の対インドネシア円借款「第III期高等人材開発事業」の一部として、2009年以来計8回、インドネシア各地の大学教員、行政官等を対象に、日本での公共政策立案研修や防災研修を受託実施してきた。写真は2014年11月の防災研修で行われた岩手県宮古市の防潮堤の視察。東日本大震災の津波は「万里の長城」ともいわれたこの防潮堤を越えて押し寄せた(写真:立命館大学)
このような基本的な考えの下で、新大綱が掲げる、これからの日本の開発協力の重点課題は以下の3点です。
第一に、「『質の高い成長』とそれを通じた貧困撲滅」です。これまで見てきたとおり、日本は一貫して、貧困削減を持続的に実現するためにも成長が必要であり、両者を一体としてとらえるとの考えの下で援助に取り組み、また、そのような方向に国際的な援助の潮流を主導してきました。そうした中、経済のグローバル化の一方で、国内格差の拡大によって取り残される人々の課題、また、一定レベルの経済成長の後に成長が停滞してしまう、いわゆる「中所得国の罠(わな)」等の課題も一層顕著に現れてきています。小島嶼(とうしょ)国等、様々な理由で発展の端緒をつかめない脆弱(ぜいじゃく)国への支援も重要な課題となっています。経済成長はこれらの課題の克服につながるものでなくてはなりません。新大綱が重点課題として明示したのは、そのような「質の高い成長」です。すなわち、誰一人として取り残さず、一人ひとりが開発の果実を享受できるような「包摂(ほうせつ)性」、経済・社会・環境の三つの側面において、持続可能な開発を達成できる「持続可能性」、個人やコミュニティの能力強化、インフラ整備を通じて、紛争や災害、経済危機といったリスクに強い「強靱(きょうじん)性」を兼ね備えた「質の高い成長」が日本の今後の開発協力の目指すところであることを新大綱は示しています。
第二に、「普遍的価値の共有、平和で安全な社会の実現」です。「質の高い成長」による安定的発展を実現するためには、人々が安心して経済社会活動に従事し、社会が公正かつ安定的に運営されることが不可欠です。日本は、このような発展の前提となる基盤を強化するための支援を積極的に行っています。具体的な取組には、平和の構築のための支援や、海上保安等の法執行能力強化、テロ対策、出入国管理などの治安維持能力強化など、安定と安全を維持するための支援が含まれます。また、公正かつ安定した社会の実現のため、自由や民主主義、基本的人権の尊重、法の支配といった普遍的価値の共有が不可欠であり、これにつながる法制度整備支援やガバナンス支援にも引き続き取り組んでいきます。
第三に、「地球規模課題への取組を通じた持続可能で強靱な国際社会の構築」です。グローバル化の進展した現在、環境・気候変動、自然災害、感染症、食料問題など、一国のみでは解決できない問題が山積しており、特にこうした問題は開発途上国の貧困層に深刻な影響をもたらしています。これらの課題は、ポスト2015年開発アジェンダをめぐる議論でも重要なテーマです。新大綱は、日本政府として、これまでの環境・保健・防災等のグローバルな課題への主導的な取組を一層強化し、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(こちらを参照)の推進や防災の主流化(開発協力トピックス参照)の推進などを含め、これらの課題解決に向けて一層積極的に取り組んでいく方針であることを示しています。
さらに、新大綱は、日本政府として外交政策に基づいた戦略的な開発協力に取り組んでいくことも示しています。そのために、開発途上国をはじめとする国際社会の状況、開発途上国自身の開発政策や開発計画および支援対象となる国や課題の日本にとっての戦略的重要性を踏まえ、戦略的かつ効果的な開発協力を展開し、成果についても外交的視点からの評価に努めていくことなどを謳(うた)っています。また、先に述べたように、ODAを規模において遙かに凌駕(りょうが)する民間の資金が開発途上国に流れるようになっている中で、民間のアイディアやソフト面も含む日本の知見を総合的に活用することも含め、官民の連携や、他の援助国との連携、さらに市民社会や地方自治体との連携を一層強化していく方針も新大綱には明記されています。
今回の見直しに際し、これまでの「政府開発援助(ODA)大綱」という名称を、「開発協力大綱」に変更しました。それは、何よりも、日本と開発途上国の関係が、前者が後者に一方的に「援助」をもたらす垂直的な関係にあるのではなく、開発途上国との対等なパートナーシップによる互恵的な「協力」を目指すべきである、という考え方に拠っています。成長する市場としても注目を集めている開発途上国の成長を、開発協力を通じて後押しすることは、日本にとっても市場の開拓などの恩恵があります。
「開発協力」という言葉には、そうした互恵的な関係を示す意味があります。これは、新大綱にも示されている、現在の国際状況を踏まえたものであると同時に、日本が開発途上国の自助努力をパートナーとして支えていくとの従来から一貫した日本のODAの考え方にも合致するものです。このような開発途上国との関係のあり方は、民間企業、NGO、地方自治体も含めたオールジャパンの協力を推進していくとの新大綱の方向性にも適ったものとなっています。特に、開発途上国は、現在、自国の経済成長のため、ODAに加えて民間投資の呼び込みに高い関心があります。政府が民間部門と連携し、開発協力が開発途上国の「質の高い成長」につながる民間投資の「触媒」としての機能を果たしながら、開発における民間投資の役割を高めていくことが不可欠となっています。さらに、先に述べたとおり、OECD-DACのODA統計で使われる単純な1人当たりの所得水準の基準では国際的にODA対象国と分類されないものの、特別な脆弱性を持つ小島嶼国などに対しても、日本として必要な協力を行っていく方針を示すものです。
このように、日本政府としては、新たに策定された「開発協力大綱」の下で、新たな国際状況に対して、より適切に対応するとともに、従来の一貫した日本らしい開発協力の推進を通じて、国際社会の取組をリードし、日本を含む国際社会の平和と繁栄をより確かなものにしていく役割を果たしていきます。

カンボジアで北九州市上下水道局職員の専門家が配水管敷設について技術指導をしている様子(写真:JICA)

ラオスでは、ODAとNGO(JMAS:日本地雷処理を支援する会)、そして民間企業((株)ツムラ)が協力して農村部の貧困削減に取り組んだ。JMASが不発弾探査・除去を行った土地(ラオンガム郡)でツムラが生薬(写真はショウガ畑)の栽培を行っている(写真:(株)ツムラ)
開発協力大綱は、日本の開発協力政策の理念や原則を定めています。この開発協力大綱の下に、国際協力重点方針、分野別開発政策、国別援助方針、そして事業展開計画が置かれます。ここではそうした政策的枠組みについて説明します。
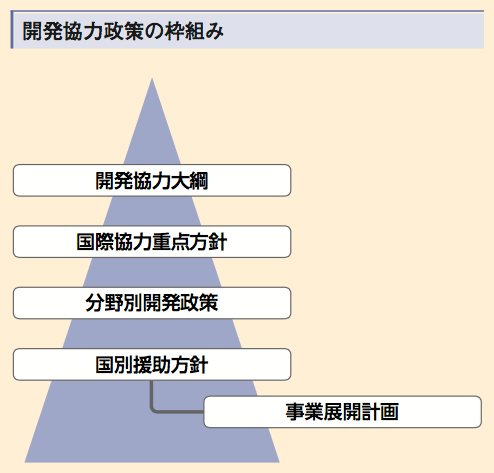
- 国際協力重点方針
- 国際協力重点方針とは、毎年度作成し、当該年度のODAの重点方針を示すものです。2013年度は、開発途上国の開発と成長というODAの目的を達成するため、①自由で豊かで安定した国際社会を実現するODA、②新興国・途上国と日本が共に成長するODA、③人間の安全保障を推進し、日本への信頼を強化するODAという3つの柱の下で、ODAを戦略的・効果的に活用していくこととしました。
具体的には、第1の柱の下、ミャンマーをはじめ世界各地で民主化・国民和解を進めている国の努力の後押しや日本と普遍的価値や戦略的利益を共有する国への支援等を、第2の柱の下、インフラシステム輸出や中小企業・地方自治体の国際展開支援等を、第3の柱の下、第5回アフリカ開発会議(TICAD(ティカッド) V)等を踏まえたアフリカをはじめとする貧困地域での人間の安全保障の促進などを推進しました。 - 分野別開発政策
- 分野別開発政策は、国際社会での議論を踏まえつつ、保健、教育、ジェンダー、水・衛生、環境、防災といった分野ごとのODAを効果的に実施するために策定しています。つまり、分野別の開発イニシアティブの策定を通じ、分野別開発政策をODA案件の計画・立案などに反映させます。開発協力大綱や国別援助方針に加えて「分野別開発政策」を策定することは、日本の開発協力指針をより明確にし、開発協力の取組を分かりやすくしています。
- 国別援助方針
- 国別援助方針は、被援助国の政治・経済・社会情勢を踏まえ、相手国の開発計画、開発上の課題等を総合的に考え合わせて策定する日本の援助方針です。相手国への援助の意義や基本方針、重点分野等を簡潔にまとめ、選択と集中による開発協力の方向性の明確化を図っています。原則としてすべてのODA対象国について策定することとしており、2014年10月までに106か国の援助方針を策定しました。
- 事業展開計画
- 事業展開計画は、国別援助方針の付属文書として、原則として、日本のすべてのODA対象国について国ごとに作成しています。実施決定から完了までの段階において、ODA案件を、開発協力を行う際の重点分野・開発課題・協力プログラムに分類して、複数年にわたって一覧できるようにまとめたものです。事業展開計画は、様々な開発協力手法を一体的に活用し、効率的かつ効果的にODAを企画、立案、実施することに加え、複数年度にわたるODAの予見可能性の向上を図ることを目的にしています。
