第2節 60年でなし得たこと-日本のODAの成果
これまで振り返ってきたように、この60年間、日本は、第二次世界大戦後ほどない復興の時期から今日まで、一貫してODAを通じて開発途上国への援助に取り組んできました。いかなるときにあっても、貧困に苦しみ、疾病にあえぐ人々、明日への希望を持てないでいる世界の人々に支援の手を差し伸べてきました。これは日本がODAに取り組む原点であり、日本という国のあり方の根本にかかわることです。とりわけ、日本が国際社会で主要な責任ある地位を占めるようになった今日、極度の貧困や様々な地球規模課題、平和の構築などの問題に対し、その国力にふさわしい貢献を行っていくことは、日本としての当然の責務といえます。同時に、大国となった日本に対する国際社会の期待に応えるという意味もあります。日本には古くから「恩送り」という言葉があります。誰かから受けた恩をその人に直接返すのではなく、別の人に送ることをいいます。そうすることで恩が世の中をめぐり、社会全体が恩恵を受けるという考え方です。戦後、世界から援助という大きな恩をもらった日本が今度は開発途上国に対して恩を送る立場にあるのです。
もう一つ重要なのは、ODAを通じて、アジア諸国をはじめとする諸外国との関係を強めながら、日本自身の平和と安定および繁栄に必要な国際環境を作っているということです。厳しい財政状況の中で国民の税金を使って行う支援である以上、この点は大切です。世界中で様々な課題が山積する中で、そうした課題への取組を先延ばしにすれば、たとえば、貧困に苦しむ国がテロの温床となったり、地球環境のさらなる悪化を招き、将来の世代に大きな負担をかけることになるかもしれません。こうした問題への対応は、他人事ではなく日本自身にとっても重要な問題です。開発途上国へのODAは、相手の国や国際社会全体のためになるだけでなく、日本の平和と安定および繁栄のためにも貢献しています。
1.日本のODAの特色と成果
前節で見てきたとおり、この60年を通して、日本の開発途上国に対するODAは、第一に開発途上国の自助努力の後押し、第二に経済社会基盤の整備や人づくり、制度づくりを通じた持続的な経済成長の重視、第三に人間の安全保障の視点に立った協力という一貫した考え方に基づいて行われてきました。ここではそれぞれの観点からどのようなODAが行われ、どのような成果を達成してきたのか、具体的な事例とともに紹介します。
(1)自助努力の後押し

カンボジアにおいて、農業技術の改善、灌漑設備の整備による農家の所得向上支援のため、ぬかるんだ田んぼに入って指導をする萩原知専門家(写真:久野真一/JICA)
第一の特色である、開発途上国の自助努力を積極的に支援するということは、日本がこれまで他の欧米諸国に先駆けて主張してきた考え方であり、自国の歴史と戦後復興の経験、さらに東アジアに対する援助の経験をその拠りどころにしています。これは、自助努力に基づいて自国の開発を進めることこそ、その国の経済的自立を促すものである、そして、ODAはそのための手助けに過ぎないという考え方に基づいています。自助努力や「オーナーシップ」は、今でこそ国際社会もその重要性を認めるようになっていますが、日本は、ODAを始めた当初から、これを重視してきました。日本が1993年にスタートさせたTICADのプロセスでも、一貫して「オーナーシップ」と「パートナーシップ」の原則を提唱してきています。

ケニアのアフリカ理数科・技術教育センター(CEMASTEA)で実験を視察するウフル・ケニヤッタ大統領(右端)(写真:JICA)
開発途上国自身の努力を後押しするという日本の姿勢は、開発途上国の人づくりを重視する日本の技術協力にも現れています。時間をかけて人材を育て、その国の開発のあり方を共に考え、共に歩んでいこうとする日本のODAの伝統は多くの開発途上国から高く評価されています。その成果を端的に示す典型的な事例をご紹介します。
ケニアで始まり、アフリカ大陸全体に広がった技術協力プロジェクトがあります。理数科教育強化計画、英語の略称でSMASEといいます。SMASEは、1998年、日本のODAがアフリカで初めて手がけた基礎教育支援プロジェクトです。工業化を目指していた当時のケニアでは理数科教育の改善が差し迫った課題でした。具体的には理数科教員の能力強化です。ケニアの要請に対して日本はODAを通じて日本人専門家を派遣し、中等学校(ケニアの中等学校は日本の中学3年~高校3年に相当)の教員に研修機会を提供する制度をつくる一方で、現地で調達可能な実験器具を使いながら、生徒の主体的な授業参加を促す授業方法の実践を行いました。ケニアの実情に合わせた工夫が効果を上げて、教員の教え方に変化が生じ、生徒の興味や理解とともに成績も向上しました。その後こうした研修の取組は全国に拡大し、2013年までの15年間で、中等学校の理数科教員7万人と校長15,000人、初等学校の教員18万人と校長・副校長7,000人が研修に参加しています。

アフリカ域内理数科教育の第三国研修閉会式での記念撮影。ケニア周辺のアフリカ諸国から多数が参加している(写真:JICA)
SMASEの活動はケニアだけにとどまりません。同様の課題を抱えるアフリカ諸国への普及を目的に、日本は2001年「アフリカ理数科教育域内連携ネットワーク(SMASE-WECSA)」を立ち上げました。現在、アフリカ14か国でケニアの経験を活かした理数科教育の技術協力が実施、または計画されています。そしてケニア政府は日本と協力し、2004年以来、ケニアにおいて第三国研修(注8)を行っており、2014年3月までで、アフリカ30か国から1,749名の教育関係者が参加しました。かつて学ぶ立場にあったケニアの教員たちが、今は他のアフリカ諸国の同僚を指導しているのです。
2014年3月、ケニアの首都ナイロビにある「アフリカ理数科・技術教育センター(CEMASTEA)」の拡張工事が終了して行われた落成式には、ケニアのウフル・ケニヤッタ大統領も出席しました。CEMASTEAは、SMASEから生まれたアフリカ理数科教員の育成拠点として現職教員の研修を担っています。今回の拡張で、これまでの92人から収容人数200人規模の研修施設になりました。日本をパートナーに、ケニアのアフリカ理数科教育への貢献はこれからも続きます。
もう一つアフリカの事例です。東アフリカのタンザニアでは、同国政府が強いイニシアティブを持って、2000年から中央政府の権限や予算、人員を県レベルに移譲して、地方分権化を進める地方政府改革プログラムを実施してきました。しかし、改革は容易ではなく、タンザニアは日本にこの改革を進めるための支援を求めてきました。
日本は明治維新後、欧米の制度を学びつつ、国民の間で議論を重ね、試行錯誤を経て、自国に適した行政システムを築いてきました。そして、第二次世界大戦後、経済開発を進めるかたわら、地方自治の能力を育み、時間をかけて本格的な地方分権化に踏み切りました。ゆっくりではあるものの、着実な改革の経験を持っています。こうした経験がタンザニアにも役立つと考え、日本は次のような5つの支援を行いました。
第一に、地方自治と分権化改革に携わる指導者を日本に招き、問題意識を持ってもらうための研修事業。
第二に、地方分権化が地域住民の生活向上につながるように、分権化された権限や予算を活用させる必要から行う、地方政府職員の能力向上を目的とした研修の仕組みづくりと、自治体がそうした研修を行えるようにするための支援。
第三に、限られた地方行政の人員、予算でサービスを提供するために、地域住民の自助努力を促し、行政と住民の協働を進める「ファシリテーター」と呼ばれる指導員(戦後日本の生活改善運動の「生活改良普及員」に当たるもの)を養成し、地域社会そのものを強化するための支援。
第四に、共同基金への資金拠出。これは、プログラム実施のための予算が日本のODAだけでなく、タンザニア政府、援助国・機関の出資による共同基金として用意されているものです。地方政府職員の研修や指導員の養成のための技術協力も日本のODAだけでなく、こうした基金からの予算を活用します。そうすることで、将来日本のODAがなくとも研修や事業を継続できる仕組みです。

タンザニアのムプワプワ県で、下田道敬専門家とファシリテーター(指導員)たち(写真:下田道敬)
最後に、これまで説明した4つの支援を統括しながら地方自治庁に所属し、課題克服のための助言や指導を行う政策アドバイザーの派遣。この専門家がタンザニア政府高官や地方自治庁の幹部に対し、欧米に学びつつ試行錯誤しながらも「和洋折衷」の行政システムを築いてきた日本自身の経験を説いて、タンザニアの人たちが自ら考え、議論し、自分たちの行政制度をつくり上げるための努力に手を貸すための助言を行いました。
第一の研修(タンザニアでは研修施設の場所にちなんで親しみを込めて「大阪研修」と呼ばれます)には、州と県の地方行政長官も参加しました。日本の行政の歴史を学んだ上で、日本の地方都市を実際に訪れ、地方の現場で行政サービスや住民とのかかわりあいの実態を視察しました。こうした日本での研修に参加して帰国した研修生たちから、自分たちが日本で学んだことを同僚にも伝えたい、という声が上がり、タンザニアのすべての州で、日本での学びを共有するためのセミナーがタンザニア人自らの手で行われました。タンザニア各地でそれらの学びをもとに、地域独自の試みがなされるようになってきています。また、大阪研修参加者のイニシアティブにより、全国の州・県の地方行政長官が一堂に会して地域の成功事例を報告し合い、課題を共に話し合う目的で「タンザニア大阪同窓会」が設立されました。日本の経験が、ODAによる後押しを通じて、タンザニア人自身によって確実にタンザニアの地方の取組に活かされているのです。
(2)持続的な経済成長

タイのレムチャバン港は、同国最大の商業港(写真:ESCO社(Eastern Sea Leam Chabang Terminal Co., Ltd.)
日本のODAの二番目の特色は、持続的な経済成長の重視です。日本は、貧困問題を根本から解決するためには、その基礎となる経済を発展させなくてはならない、との考えに立って、インフラの整備や人づくりを通じた持続的な経済成長の実現を重視してきました。日本の円借款をはじめとするODAによるインフラ整備や人材育成は、開発途上国の投資環境を整え、貿易を活性化し、民間経済の発展の下支えになりました。また、それらを通じて雇用や所得の機会が広がり、貧困削減に大きな効果をもたらしました。たとえば、アジアは日本の協力を活用して経済的な飛躍を遂げ、この地域の貧困問題は解決に向かって大きく前進しました。近年目覚ましい東南アジアの発展にも日本の協力が大きく貢献しています。
タイでは1970年代にシャム湾沖で天然ガス田が発見され、これを機にタイ政府は、首都バンコクの南東、シャム湾に面する東部臨海地域を工業化の拠点と定め、開発に乗り出しました。この開発の実現に日本のODAは大きな役割を果たします。1981年、当時の鈴木善幸総理大臣がタイ訪問時に日本の協力姿勢を表明すると、ODAによる港湾建設専門家の派遣、開発調査などを矢継ぎ早に実施しました。その結果、翌1982年には計16事業に及ぶ支援プロジェクトを策定し、27件の円借款を供与したほか、資金的な支援だけでなく、計画策定支援や技術的助言などもあわせて行い、包括的できめ細かいODAを実施しました。この地域の開発は、天然ガスを利用した重化学工業開発と輸出指向型工業を中心とする工業団地開発、港湾・道路・鉄道などのインフラ整備から成る壮大なものでした。中でもレムチャバン港の建設は、当時、バンコク港の水深が十分でなく、大型化するコンテナ船への対応が限界に近づいていたこともあって、バンコク港を補完し、東部臨海地域の海上輸送を一手に担うことのできる港湾として大いに役立ちました。
東部臨海地域の開発は貧困削減にも効果を上げました。開発と工業化が進むにつれ、地元経済が活性化し、大量の新規雇用が創出されたほか、自治体による工業化や人口増に伴う公共サービス(港湾や工業団地の道路輸送の増大を受けた道路網拡充や維持管理の強化)や社会サービス(初等教育や基礎的保健医療サービス)の改善が実現しました。
現在、東部臨海地域は、タイでバンコク首都圏に次ぐ第二の産業地域へと発展し、GDP成長率や民間投資額、雇用機会などでタイの全国平均を大きく上回っています。レムチャバン港のコンテナ取扱数は1998年にバンコク港を抜いて国内最大となり、2012年には世界ランキングで23位につけています。この開発の結果、東部臨海地域は、一大工業団地に生まれ変わりました。そこに自動車関連をはじめ多くの日本企業が進出し、タイで生産した製品が世界各地へ輸出されるようになっています。
(3)人間の安全保障

ブルキナファソ・ジニアレ近郊の村で、ろうあ者の女性に裁縫技術を教える青年海外協力隊の飯ヶ谷奏さん。彼女たちは身に付けた技術で自立できるようにがんばっている(写真:飯塚明夫/JICA)
日本のODAの第三の特徴として挙げられるのは、前節で説明した人間の安全保障です。これも前節で少し触れたように、冷戦後、世界各地で紛争が頻発したこと、また、グローバル化が急激に進み、世界経済が一体化する中で、貧困、環境破壊、自然災害、感染症、テロ、突然の経済・金融危機といった問題が、国境を越え相互に絡み合いながら、広範囲にわたって人々の命や生活に深刻な影響を及ぼすようになったことで、人間の安全保障の考え方はますます重要なものになっています。人間の安全保障は、TICAD(ティカッド)のような地域イニシアティブや保健、防災、気候変動のような地球規模課題への対策において、とりわけ、脆弱(ぜいじゃく)な立場の人々への対処を考える上でもたいへん有益な視点を与えてくれます。
人間の安全保障の視点に立った支援とは、困難な状況にある人々を、様々な脅威から守り、その人たちの能力強化を通じて、国づくり、社会づくりを進めていくことを手助けすることです。具体的には、教育、保健医療、環境、ジェンダー、平和の定着と国づくりといった分野でこの視点に立ったODAを積極的に推進しています。たとえば、アフリカをはじめとする開発途上国で学校建設などを通じて一人でも多くの子どもたちが教育を受けられるようにする、また、安全な飲み水が簡単に手に入るようにして、人々の生命や健康を守る、子どもや女性を長時間の水汲(く)みから解放し、多くの子どもが学校へ通えるようにする、女性がその能力を十分に発揮できるようにする、といったODAです。
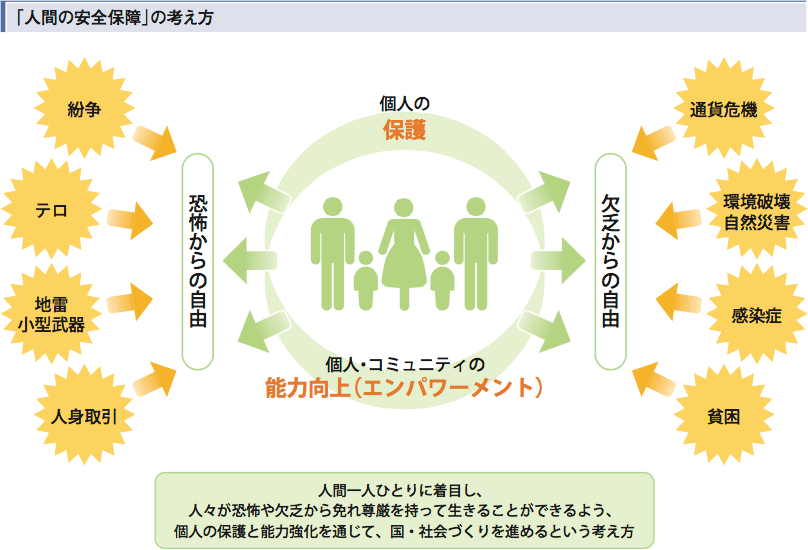

2013年11月、フィリピンにおける台風(ヨランダ)の被害を受けて、被災地(レイテ島)において医療活動を行う国際緊急援助隊の自衛隊・医療チーム

被災したタクロバンにて、日本からの緊急支援物資を受け取るロムアルデス・タクロバン市長(中央)とソリマン社会福祉開発省長官(写真:トレーシー・デセナ/JICAフィリピン事務所)
1997年、南部アフリカのザンビアの首都ルサカはコレラの流行に苦しんでいました。そこで、日本は、最もコレラ発生率の高い、低所得者居住地域を対象に、ODAにより、公共の水洗トイレとシャワーを設置しました。かつてのゴミ捨て場だった場所に設置された施設は、地元の人たちから「KOSHU(公衆)」の名前で親しまれるようになりました。この結果、この地区のコレラ感染数は劇的に減少し、7年後の2004年にはわずか1件になりました。
差し迫った脅威に晒(さら)された人間の救援と保護を目的とする、緊急人道支援も人間の安全保障を実現する上で重要な取組です。
近年、地震、台風などの自然災害が世界各地で頻発しており、その規模はかつてなかったほどに大きなものとなっています。このような災害発生後の緊急事態や紛争などの人道危機(人道支援が必要とされる危機的な状況)に際し、日本は、人間の安全保障の視点に立って、人命救助、人間の尊厳の維持および保護のため、緊急人道支援を行っています。
日本が行った緊急人道支援の最近の例として、2013年11月、フィリピンを襲った台風被害があります。台風ハイヤン(日本では台風30号、フィリピン名は「ヨランダ」)が引き起こした死者・行方不明者7,000人以上の甚大な被害に対し、日本は国際社会と協力して、官民による幅広い支援を行いました。被害発生直後、フィリピン政府の要請を受け、国際緊急援助隊として、医療チームや専門家チームに加え、過去最大規模の約1,100人の自衛隊部隊がフィリピンに駆けつけました。派遣された隊員たちは、被災者の心に寄り添った支援を行いました。被災の影響を心配していた妊婦は、超音波画像で胎児の元気な姿を目にし、笑顔を取り戻しました。また、支援が行き渡りにくい村落への巡回診療も行い、草の根レベルに届く支援に努めました。こうした国際緊急援助隊の支援に加え、国際機関を通じた3,000万ドル(約30億円)の緊急無償資金協力、テントやビニールシート、毛布などの緊急物資供与も行いました。さらに、ジャパン・プラットフォーム(日本のNGO、経済界、政府の三者でつくるNPO)に参加する日本のNGOが、食料・物資の配布、シェルター建設、保健衛生や教育支援などを行ったほか、民間企業による緊急支援など様々な支援がなされました。このような日本からの支援に対して、フィリピン政府・国民や、被災地で活動する他の国際機関からも感謝の気持ちが示されました。国際緊急援助隊派遣を紹介した総理官邸英語版フェイスブックには、世界中から7万を超える「いいね!」が寄せられました。
2.結び-日本のODAの成果と評価
このように、日本の60年にわたるODAは、開発途上国の開発、成長に様々な形で貢献してきただけではありません。日本と開発途上国との間に友情と信頼の確かな絆(きずな)を築くとともに、日本の国際社会における地位の向上に、ひいては日本自身の平和と繁栄をより確かなものとすることに大いに役立ってきました。日本がODAを通じて地道に積み上げてきた協力は、開発途上国を含む国際社会の日本に対する厚い信頼と好感を形づくる上で確実に力となりました。
その上で、60周年を迎えた日本のODAの成果として、まず挙げられるのは、開発途上国の経済開発や福祉の向上への貢献です。この30年間に開発途上国の状況は劇的に改善しました。1日1ドル以下で生活する人の数は19億人から12億人に減少し、割合では全人口比の52%から20%になりました。平均寿命は7年長くなり、乳児死亡率は45%以上も減少しました。開発途上国自身の努力があってこその結果ですが、日本のODAが大きな貢献をしたことは確かです。
日本のODAの成果は、支援する側の日本にも及んでいます。日本が重点的にODAによる支援を行ってきたASEANは、全体のGDPが今や2兆ドルを超える巨大市場に成長し、世界の主要生産拠点として注目を集めるまでになりました。日本にとり極めて重要な市場であり投資先となっています。また、この地域が成長と安定を実現していることは、日本経済を支える物流網がこの地域を通過していることを考えるとき、日本の安全保障にとっても大きな意義を有しています。
もちろん、課題や困難に直面したこともありました。ODA事業に際して、不正が行われたり、不測の事態によって十分な援助効果が上げられない、遅れが生じるといったこともあります。また、環境や地元コミュニティに予期せぬ影響が出たり、累積債務問題が生じたりしたこともあります。さらに、日本の顔が見えにくい、援助目的が達成されていないといったご意見をいただくこともあります。日本政府としては、こうした経験を一つ一つ無駄にせず、将来への教訓とすべく、評価の仕組みを整え、透明性の向上に努め、市民社会を含む幅広い関係者の方々との対話を行うといった努力を続けてきました。そうして、日本のODAが、効果的で無駄のない方法で、開発途上国の人々に真の豊かさをもたらすよう、しっかりとした環境社会配慮の基準や、不正を防ぐ仕組み、受入れ国側との丁寧な対話と調整、また、きめ細かい事業の維持管理やフォローアップのプロセスを整えてきました。今後とも決して慢心することなく、このような努力を不断に続けていかなくてはなりません。
相手国の国民や政府は日本のODAをたいへん高く評価してくれています。苦しいとき、困っているときに日本から支援を受けたことへの感謝の気持ちもあります。加えて、支援の現場で共に苦労しながら働く日本人の姿、そうしたことを通じて形づくられる日本の良いイメージ、これらは国際社会において日本が平和と繁栄を続けていく上で最も大切な資産ということができるのではないでしょうか。開発途上国の政府や国際機関が日本のODAをどのように見ているのか、その一部を以下にご紹介します。

エルサルバドルの首都サンサルバドルで公共インフラ強化のための気候変動・リスク管理戦略局支援プロジェクトを通じ、排水管の調査を行う公共事業省の職員たち(写真:エルネスト・マンサノ/JICA)

2014年7月、訪問先のコロンビアでの首脳会談で、サントス大統領から歓迎の言葉を受ける安倍晋三総理大臣(写真:内閣広報室)
「日本の取組は、世界水準の専門知識の供与と世界的に知られた日本人専門家の派遣を含んでいる。そのリーダーシップにより、日本の活動には五大陸すべてにおいて高度のビジビリティが認められてきた。」(ボコバ・ユネスコ事務局長、2012年2月)
「日本の協力は、エルサルバドル国民の生命を救ってきた。6年前の国連の調査において、エルサルバドルは世界で最も自然災害に対して脆弱(ぜいじゃく)な国の一つに挙げられたが、この5年間の日本の技術協力を受け、その脆弱性に改善が見られた。」(マルティネス・エルサルバドル公共事業大臣、2014年6月)
「日本人はたいへん素晴らしい。地方のプロジェクトでは、ときに不慣れな現地施工業者が案件を実施することがあるが、どのような問題が発生しても日本は解決策を見つける手助けをしてくれる。」(ビヤンダラ・ウガンダ公共事業・運輸大臣、2014年1月)
「日本の協力は、単に資金的な援助を行うだけでなく、人的貢献という意味でも素晴らしい。二国間協力に携わっている日本人は、非常に活発で、職業意識が高く、現場が好きな人々である。そして、日本の青年が協力隊員として我が国に赴任し、ブルキナファソ人と共に生活し、専門的知識を提供することは、非常に人間的であり、人を通じた協力といえる。」(ボリ=バリ・ブルキナファソ国民教育・識字大臣、2013年7月)
2014年7月、安倍総理大臣がコロンビアを訪問し、サントス大統領と会談を行った際、日本のODAで建設した地方の図書館に関するビデオがその場で上映され、その中で地元の子どもたちから安倍総理大臣に対する感謝の言葉が伝えられました。また、図書館を活用している少女からの感謝の手紙が安倍総理大臣に手渡されました。コロンビアでは、長らく非合法武装勢力による活動が行われたことから、地方では多くの子どもが学校に通いたくとも通うことができませんでした。そのため、日本は、これまで初等教育分野へのODAに重点を置き、ODAによる児童向けの図書館の整備に力を入れてきました。そうした日本のODAがコロンビアの子どもたちの心に届いたのです。
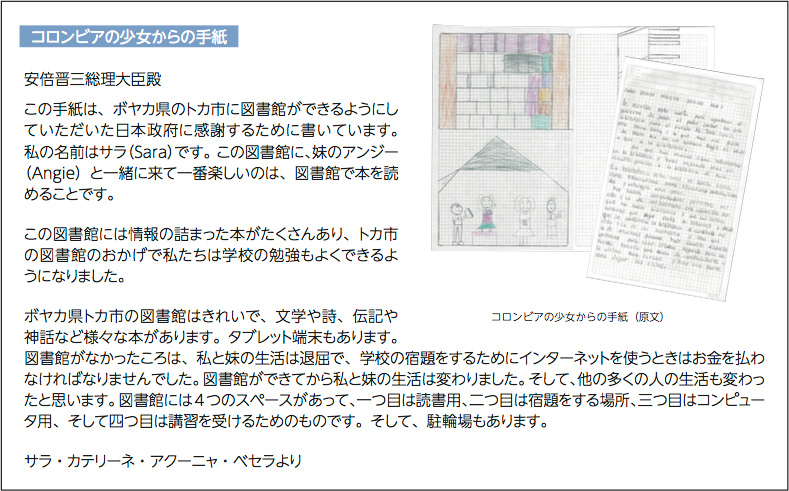

2014年4月、パキスタンのラワルピンディで、ポリオのワクチン接種を受ける子ども。日本は1996年から同国におけるポリオ撲滅に向けた支援をUNICEFと協力して継続的に行っている(写真:共同通信社)
日本のODAは、国際機関からも評価されています。たとえば、OECD-DACは、2014年7月に日本の開発協力相互レビュー(注9)の結果を発表しました。その中で、日本について、明確なビジョンに基づいて、人間の安全保障、持続的経済成長、平和と安定に寄与する開発協力を実施している点、防災や保健分野などの支援においてリーダーシップを発揮している点、民間セクターとの連携や三角協力による包摂(ほうせつ)的な開発を進めている点を評価しています。また、DACは、2014年、開発途上国で広く適用できる革新的な取組を表彰するために、DAC賞(DAC Prize for Taking Development Innovation to Scale)を設けましたが、第1回DAC賞において、日本のパキスタン向け円借款「ポリオ撲滅計画」が優れた案件の一つに選ばれました。この事業ではパキスタン政府が一定の事業成果を達成したことが確認されれば、パキスタン政府による円借款の返済をビル&メリンダ・ゲイツ財団が肩代わりする「ローン・コンバージョン」という手法が採用され、それが革新的な取組であるとして高く評価されたのです。なお、所定の事業成果が達成されたことが確認され、2014年4月に同財団による返済が決定しています。
東日本大震災の後、日本に対して多くの開発途上国を含む世界中の163の国と地域、43の国際機関から支援の申し出があり、24の国と地域から緊急援助隊、医療支援チーム、復旧チームが駆けつけてくれました。そのとき送られてきた支援メッセージには、自分たちが被災したときに日本から受けたODA、自国の開発を支えてくれた日本への感謝の気持ちに触れるものが少なくありません。
「フィリピンが被災した際には常に日本が真っ先に援助の手を差し伸べてくれた。だからこそ、できる限りの支援と協力を行う。」(ロペス駐日フィリピン大使)
このように日本がODAを通じて支援したことを世界の人たちは、決して忘れてはいません。
- 注8 : 過去に日本の技術支援を受けた開発途上国の機関が他の開発途上国から研修員を受け入れて技術指導を行う。日本は資金面、技術面で協力する。
- 注9 : OECD-DACの開発協力相互レビューは、DAC加盟国の開発協力政策や実施状況について加盟国間で互いにレビューするもの。開発協力の経験や手法等に関する相互学習を通じて、より効果的な開発協力の実施に向けた取組を提言することを目的にしている。今回の日本のレビューは、フランスとオーストラリアが担当した。
