9 女性
日本は、全ての女性が個性と能力を十分に発揮し、輝くことができる「女性が輝く社会」の実現に向け、国内外で様々な施策を推進している。
(1)女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム(WAW! Tokyo 2014)
2014年9月12日、13日、安倍総理大臣のイニシアティブで「WAW! Tokyo 2014」(World Assembly for Women:女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム)を開催した。6国際機関、24か国から約100人の招待者を含め女性分野で活躍するトップ・リーダーが国内外から参加した。日本や世界における女性の活躍促進のための取組について議論を行い、「WAW! To Do」と呼ばれる12の提言を取りまとめ、国連文書(A/69/396)として発信した。女性を取り巻く国内外の課題について包括的に議論する場を提供するため、2015年もWAW!を開催する予定である。
(2)国際社会との協力と開発途上国の女性支援
安倍総理大臣は、2013年9月の国連総会一般討論演説において、「女性が輝く社会」の実現に向け、国際社会との協力や開発途上国支援を強化していくことを表明した。具体的には、①女性の社会進出と能力強化、②女性の保健医療分野の取組強化、③平和と安全保障分野における女性の参画と保護の3つの柱を立て、2013年から2015年の3年間で30億米ドルを超すODAを実施する考えを示した。この分野において、日本は1年間で既に約18億米ドルの支援を実施している(2013年暦年実績)。
(3)国連における女性外交と北京+20
ア 日本は3月に開催された第58回国連女性の地位委員会に、「自然災害におけるジェンダー平等と女性のエンパワーメント」決議案を2012年に続き再度提出し、同決議案は、コンセンサスで採択された。同決議では、災害に強い社会づくりと、それに向けた平時からの女性の社会参画の重要性、現在のイニシアティブを第3回国連防災世界会議(於:仙台)、世界人道サミットを含む2015年以降の各種プロセスにつなげていく点が強調されている。
イ また、1995年の第4回世界女性会議で採択された北京宣言及び行動綱領に掲げられた目的や目標に対する成果と課題を実現するため、日本における進捗状況についてのレビューを行った。その結果を、「第4回世界女性会議並びに北京宣言及び行動綱領採択20周年記念における、北京宣言及び北京行動綱領(1995年)並びに第23回国連特別総会成果文書(2000年)の実施状況」として、12月にジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関(UN Women)に提出した。
ウ 日本はUN Womenに対する拠出金を2013年から2014年にかけて5倍に増額した。2015年に東京に開設される予定のUN Women東京事務所を基点に、今後、同機関との連携を一層深めていく予定である。
エ 日本は、「女子に対するあらゆる形態の差別撤廃に関する条約(女子差別撤廃条約)」に基づき、第7回・第8回政府報告を9月に国連に提出した。また、1987年から継続して女子差別撤廃委員会に委員を輩出しており、6月の選挙でも現職の林陽子委員が再選された。
(4)紛争下の性的暴力に関する取組
ア 2014年9月に行われた安倍総理大臣の国連総会一般討論演説でも言及されたように、紛争の武器としての性的暴力は看過できない問題である。武器としての性的暴力を防止するため、また被害者への支援が重要であるという観点から、国連アクションや紛争下の性的暴力担当国連事務総長特別代表(SRSG)などの国際機関との連携や国際的な議論の場への参加を重視しつつ、21世紀こそ女性の人権侵害のない世界にするため、日本はこの分野に一層積極的に取り組んできている。
イ バングーラ紛争下の性的暴力担当SRSGは、9月にWAW!参加のため訪日し、安倍総理大臣や岸田外務大臣などと会談を行った。また、日本は紛争下の性的暴力担当SRSGの専門家チームに初めて215万米ドルの財政支援を行い、第1位のドナーとなった。さらに、国際刑事裁判所(ICC)の被害者信託基金にも初めて拠出を行い、60万ユーロ中40万ユーロを紛争下における女性暴力対策に割り当て、紛争下の性的暴力の被害者に対する対策にも取り組んでいる。
ウ また、紛争下の性的暴力の終焉に向けた世界的機運の醸成を目的として、6月にヘーグ英国外相やアンジェリーナ・ジョリー国連難民高等弁務官特使共催でロンドンで行われた「紛争下における性的暴力の終焉に向けたグローバル・サミット(PSVI)」には、日本から岸外務副大臣が参加し、紛争下の性的暴力の防止に向けて力強いメッセージを発信した。
エ 国内においても、6月、関係省庁(外務省、内閣府PKO事務局)、JICA、国連アジア極東犯罪防止研修所(UNAFEI)、赤十字国際委員会、関連NGOの関係者が一堂に会し、専門家の育成のための取組や協働枠組みを考えるためのPSVIジャパン・プラットフォームを立ち上げた。11月には、赤十字国際委員会(ICRC)との共催で、「武力紛争下における性的暴力 その現状と課題」と題する公開シンポジウムを開催(於:上智大学)した。同シンポジウムには、国際機関、政府、有識者、市民社会から関係者が集い、国際社会における紛争下の性的暴力の現状とその課題について議論を行い、理解を深めた。
(5)国連安保理決議第1325号等に関する「行動計画」
より効果的に平和な社会を実現するためには、紛争予防、紛争解決、平和構築のあらゆる段階で女性の参画が確保され、ジェンダーの視点を主流化することが重要である。このため、日本は2013年9月から、安保理決議第1325号や関連決議の履行に向けた女性・平和・安全保障に関する「行動計画」の策定を進めている。
日本の「行動計画」は、参画、予防、保護、人道復興支援、モニタリング・評価・見直しの5つの柱で構成されており、詳細な指標を含むものである。この「行動計画」の特徴は、策定プロセスで、同行動計画の構成、含めるべき要素、モニタリング・評価作業の進め方について関係省庁だけでなく、市民社会の代表と共に策定作業を行っている点である。さらに、沖縄県を始めとする5か所でも市民社会との意見交換会を開催したのち、パブリックコメントに付した。これら一連の議論を踏まえ、「行動計画」は、2015年初旬に完成する予定である。なお、策定後のモニタリング、見直しなど今後のプロセスでも、市民社会の参加が期待されている。

女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム(WAW!)の前後2週間は、女性に関する様々なイベント(シャイン・ウィークスイベント)が全国各地で実施されました。また、WAW!に参加した外国人参加者も地方でのイベントに参加しました。本特集ではシャイン・ウィークスの広がりをお伝えします。

WAW!が開催された2014年9月12日と13日の前後2週間、シャイン・ウィークスが実施されました。これは、WAW!の趣旨に沿うイベントを広くつなぎ、WAW!の一環として「女性が輝く社会づくり」に賛同していただくことを目的としたものです。また、安倍総理大臣のビデオメッセージもイベントで活用していただきました。どなたでも自由な発想で参加でき、会議はもとより、映画祭やコミュニティの集い、農業女子や宇宙女子など多岐にわたるグループが独自のイベントを企画し、実施しました。これらのイベントはWAW!専用のフェイスブックで公開され、また、外務省ホームページでも紹介されています。最終的に120件以上もの関連イベントが全国各地で自主的に開催され、日本国内での女性の活躍促進への関心の高さがうかがえました。


シャイン・ウィークスの一連のイベントの中でも、特に、WAW!参加者が登壇したイベントは、海外から来られたゲストと地方自治体や大学を結び、地方へのムーブメントの波及を目的としたものです。結果的に、宮城や埼玉、倉敷、福岡などで11のイベントが開催されました。それらのイベントの主催者からは、通常はなかなか呼ぶことのできないゲストを迎えることができ、有益であったことから、是非、来年も実施したいとの感想をいただきました。
WAW!2015においても、日本全国で女性が輝く社会づくりのムーブメントを高めていきたいと思います。
女性参画推進室
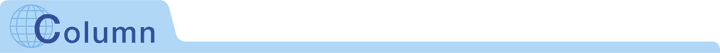
外務省では、多くの女性職員が活躍しており、全職員の約3割を占め、世界を舞台に活躍しています。その中で、今回は、世界各地で日本の「顔」として活躍している5人の現役女性大使に、その仕事観やこれから国際社会へ踏み出そうとする女性へのメッセージを聞いてみました。





(田中)私が赴任しているウルグアイでは、閣僚の3分の1が女性です。各国の女性大使も多く、「女性」であることを意識することは少ないですね。ただ、アジア系の女性大使は他にいないので各国の要人の集まりの中で目立つことは出来ます。
(伊岐)私が勤務しているブルネイはイスラム教を国教としていますが、「女性だからといって特別扱いしない」との政府の姿勢が明確で、気持ちよく仕事ができています。友好国「日本」からの大使として対応も好意的です。
(白石)リトアニアは、大統領も国会議長も女性で、3年ほど前からは、大統領と女性大使の非公式昼食会が開催されるなど、女性大使であることが有利に働いています。ある国の大使は「私の後任は、女性に」と本国に進言したと聞いています。
(西村)外交団の人脈作りという意味では、配偶者も含めた会食の場などで、女性同士の会話ができるのは強みです。また、日本からの初の女性大使ということで、日本のイメージを変えるやりがいも感じます。
(志野)私の赴任しているアイスランドは、ジェンダーギャップが世界一小さい国でありながら、高い出生率を誇っています。子育てをしながら仕事をしてきた私自身の視点で、新たな発見ができるのではないかと思っています。
(西村)業務の面では女性だから苦労したということはありません。確かに外国勤務が長いことや、国会対応などで夜遅くまで勤務しなければならないこともあり、家庭生活との両立には工夫が必要ですが、外務省は、子育てや介護と仕事の両立について理解のある職場だと思います。
(白石)子育てとの両立の面では、家族、ベビーシッターなどたくさんの人の手を借りました。子供を連れて最初の外国勤務は不安でしたが、ベビーシッターも見つけやすく、勤務時間も調整でき、子供と過ごす時間がかえって長かったです。思い切って一歩を踏み出して良かったです。
(志野)外務省には外国勤務があり、育休からの復帰は、外国から日本への異動と感覚的にあまり差が無く、復職しやすいというメリットがあると思います。ただ、いつ、どこで勤務するのかがわからない中、子供の教育環境には苦労しました。特に日本のように悩みを共有できる友人が少ない中で、子供の成長の過程の様々な悩みに親として直接向き合うことも多かったです。
(伊岐)私は厚生労働省出身ですが、子育て期に2度の国内転勤があり、その都度子連れ赴任や単身赴任で対応しました。これから外交の場で女性が輝くためには、女性外交官が子育て期も含めて安心して外国転勤できる支援策の充実が必要だと感じます。
(田中)民間企業勤務での経験から感じることとして、在宅勤務制度は女性にも男性にもメリットが大きいと感じます。また、勤務地など本人の希望に可能な限り柔軟に対処できるようになればなお良いと思いますね。
(田中)国際社会の中でアジア人の女性の強みは、信頼の受けやすさだと思います。国際社会で活躍している日本の女性はまだまだ少数派と思われがちかもしれませんが、それを逆手にどんどん相手の懐に飛び込んでいってほしいです。
(西村)世界のいろいろな場で、多様な人たちと出会い、すばらしい経験をできることは、人生の財産になります。是非大きなステージでチャレンジして、自分自身の成長と新たな世界の発見につなげてほしいです。
(伊岐)「女性だから」「子供がいるから」という理由で自分の仕事の可能性を限定しないこと、同時に「仕事が大変だから」と、結婚・出産といったライフイベントをあきらめないことが重要だと思います。ワークライフバランスが大変な局面でも、貪欲に可能性を追求する気持ちや、次に活躍のチャンスが来た時につかみ取れるよう研鑽(けんさん)を積むことで、道は開けます。
(志野)外務省は女性の職場としては最高だと思います。仕事の中身で性別を意識することはない一方、国際会議で女性ゆえに目を引くことも少なくありません。多様な価値観の中で自分自身が輝ける場があると思います。
(白石)国際社会は、自分の能力を活かすことができるだけでなく、多くの経験を積み、新たな課題を克服する中で、それを磨いていくことができるところです。自分を信じて、可能性を広げていってほしいです。私のモットーは「住めば都」です。それぞれの国に文化と歴史があり、それを学び、多種多様な人と触れあうことはとても楽しいです。
