3 東南アジア
(1)カンボジア
内政面では、日本などの支援を受け2007年に開廷したクメール・ルージュ裁判において、3月に政治犯収容所所長の最高審公判が実施され、また6月に元国家元首を含む幹部4名の初級審公判が開始されたことにより、内外から注目が集まった。
外交面では、2008年のプレアビヒア寺院の世界遺産登録を契機に再燃したタイとの国境問題について、2011年2月から4月にかけ、国境地帯において両国間の断続的な軍事衝突が発生し、双方に死傷者が出るまで発展した。これに対し、ASEAN議長国であるインドネシアが仲介を行った。また、カンボジアが国際司法裁判所に対し、1962年のタイとカンボジアの国境問題に関する同裁判所の判決の解釈を要請したことに対し、同裁判所は7月に暫定的武装地帯からの両国の軍事要員の撤退や、ASEANが派遣する監視団の受入れを含む仮保全措置命令を下した。しかし、8月にタイでインラック政権が成立すると、両国関係は急速に改善に向かい、両国は右仮保全命令の実施に向けた協議を行っている。
日本は、カンボジアの開発努力を積極的に支援しており、2月に伴野豊外務副大臣がカンボジアを訪問した際の、フン・セン首相ほかとの会談や、12月の日・カンボジア外相電話会談において、経済協力や地域協力などに関して意見交換を行った。また、伴野外務副大臣のカンボジア訪問に際しては、日本が支援している、ASEANの南部経済回廊(第2章第1節6「地域協力・地域間協力」を参照)の一部をなすネアックルン橋梁(りょう)建設計画の起工式が執り行われた。東日本大震災に際しては、カンボジア王室や同国政府及び国民から義援金やメッセージなどの支援が寄せられた。その一方で、カンボジアの洪水被害に際し、日本は緊急物資や専門家の派遣等を実施した。10月、日本は両国間の友好関係強化のため、俳優の向井理氏に対し、「日本・カンボジア親善大使」を委嘱した。
(2)タイ
内政面では、2010年に流血の事態にまで発展した、タクシン元首相を支持する勢力と同元首相の復権に反発するアピシット政権を含む勢力との対立構造が解消されないまま、アピシット首相は、2011年5月、下院を解散した。7月3日に行われた総選挙の結果、タクシン元首相の実妹であるインラック氏を比例第1位に推したタイ貢献党が、500議席中265議席を獲得し、アピシット首相率いる民主党に100議席以上の差をつけて第1党となった。その結果、8月10日にインラック氏を首班とする6党連立政権が発足した。同政権は、国民和解、国内の格差是正、内需拡大等を企図した政策を掲げ、政権運営を開始しようとしたが、その矢先の7月から、例年を上回る降雨によりタイ北部及び中央部を中心に大規模な洪水被害が発生したため、同政権は、洪水対策に注力することとなった。この洪水は、タイで約800名の犠牲者を出したほか、アユタヤ周辺の工業団地が浸水したことにより、サプライチェーンが滞り、タイのみならず、日本を含む地域経済全体にも大きな損害をもたらした。その結果、タイ政府は、2011年の経済予測を当初の3.5~4.0%を1.5%に下方修正した。
外交面では、インラック政権は、ミャンマーの国内政治情勢の変化を踏まえ、同国国内におけるインフラ開発を含め経済面での関係強化に関心を高めている(カンボジアとの間の国境紛争についてはカンボジアの項を参照)。
日本との関係では、東日本大震災に際し、タイ王室、政府、国民から物資、義援金、医師の派遣等多大な支援がなされた。一方、タイの大規模洪水被害に対しては、日本政府から、排水ポンプ車チームの派遣、各種専門家、調査団の派遣、緊急物資、緊急資金協力等を実施したほか、国民・企業からの寄附、NGOによる活動など積極的な支援が行われた。11月に野田総理大臣及び玄葉外務大臣が、それぞれインラック首相及びスラポン外相と会談を行い、また、同年12月に日・タイ外相電話会談を実施した際、日本として、タイの洪水被害からの復旧・復興及び今後の治水対策を積極的に支援する方針を表明した。
(3)ベトナム
2011年1月、5年ごとに開催される第11回ベトナム共産党大会が開催され、2020年までに近代工業国家に成長することを目標とする「政治報告」、そのための「10か年発展戦略」などの文書が採択された。共産党の党首である書記長には、グエン・フー・チョン国会議長が選任され、同書記長を始めとする党政治局員14名も確定した。5月に行われた国会議員選挙の結果を受けて7月から第13期国会が召集され、グエン・シン・フン国会議長、チュオン・タン・サン国家主席が選出された。また、グエン・タン・ズン首相が再選され、ズン首相が提案した新閣僚人事案が承認され、一部閣僚が交代した。経済面では、インフレの抑制を最優先課題とし、マクロ経済の安定を目標に、ベトナム政府は2011年2月から金融引き締め政策を行っている。経済成長率は、当初目標(7~7.5%)を下方修正し、2011年の成長率は5.89%となった。
外交面では、2011年5月末に中国船によるベトナムの石油探査船ケーブル切断事件が発生し、一時越中関係が緊張したが、その後、10月にチョン書記長が訪中し、両国が海上問題解決に関する基本原則合意に署名するなど、緊張は緩和されている。このケーブル切断事件を受け、約2か月にわたり、毎週日曜日にハノイ市内で対中抗議デモが行われた。
日本との関係では、東日本大震災に際しては、ベトナム政府及び国民から義援金やメッセージが寄せられた。6月にサン共産党書記局常務(現国家主席)が訪日した際には、日本の要人等と意見交換を行うとともに、被災地訪問等を行った。また、10月にはズン首相が訪日し、野田総理大臣との間で経済、経済協力、文化など幅広い分野で会談を行い、「戦略的パートナーシップ」の下での取組に関する日越共同声明に署名した。ズン首相も訪日中に被災地を訪問した。
(4)ミャンマー
1988年以降、ミャンマーでは軍政が敷かれ、国民の政治参加が著しく制限されていた。しかし、2010年以降、民主化及び国民和解に向けた様々な動きが生じている。2010年11月7日に行われた総選挙は、自宅軟禁措置を受けていたアウン・サン・スー・チー氏を含む政治犯に選挙に参加する権利が与えられない中で行われたことから、同氏の率いる国民民主連盟(NLD)は、総選挙に参加せず、テイン・セイン首相が党首を務める連邦連帯開発党(USDP)が全体で76%の議席を獲得し圧勝した。その後、11月13日には、約7年半ぶりにスー・チー氏に対する自宅軟禁措置が解除され、2011年1月31日には、23年ぶりに国会が召集されるとともに、同年3月30日には、テイン・セイン大統領の下で新政権が発足した。この後、多数の政治犯の釈放、少数民族武装勢力との停戦、テイン・セイン大統領とアウン・サン・スー・チー氏との直接対話、「労働団体法」の公布、「政党登録法改正法」の公布などの措置がとられ、NLDも政党登録及び2012年4月1日に予定されている補欠選挙参加を決定するなど、民主化・国民和解に向けた前向きな動きが見られる。
日本は、ミャンマー政府が人道状況の改善、民主化及び国民和解の更なる進展に向けて、今後一層前向きな措置をとることを期待しており、2011年6月の菊田真紀子外務大臣政務官のミャンマー訪問、11月のASEAN首脳会議に際しての日・ミャンマー首脳会談や12月の玄葉外務大臣のミャンマー訪問などの機会に、ミャンマー政府首脳に働きかけている。また、ミャンマーの改革努力を支援する観点から、人的交流、経済協力、経済、文化交流の4分野で日・ミャンマー関係強化のための施策を講じてきている。同時に、2007年に生じた日本人ジャーナリスト死亡事件に関する真相究明等を引き続き求めている。なお、東日本大震災に際しては、ミャンマー政府から義援金やお見舞いのメッセージが寄せられた。
国際社会では、ASEANが2011年11月、ミャンマーを2014年のASEAN議長国とすることを決定した。欧米諸国は、ミャンマーにおける変化は本物と認識し、対話を強化している。また、クリントン米国国務長官、ヘーグ英国外相、ジュペ・フランス外相など、多くの政府要人がミャンマーを訪問し、民主化の進展に応じて、制裁を緩和する方針を表明している。

(5)ラオス
2011年3月、5年に1度の第9回ラオス人民革命党大会が行われ、2020年のLDC(後発開発途上国:Least Developed Country)脱却への基礎作りを目指す「党大会決議」のほか、「政治報告」「改正党規約」等の文書が採択され、「第7次経済社会開発5か年計画(2011-2015)」が承認された。これら文書は、総じて前回の第8回党大会の決議内容を踏襲し、改革路線の継続を確認しつつ、今後5年間で年8%以上の経済成長率を達成するための四つの「躍進」を打ち出した。今回の党大会では党創設メンバーが全て引退した一方で、チュンマリー党書記長が再選された。また4月には、5年に1度の国民議会総選挙が行われ、6月に新政権が成立し、チュンマリー党書記長が国家主席に再選されたほか、トンシン首相を始め、多くの閣僚が再任された。党大会開催後、ベトナムや中国を始めとして近隣諸国との交流が活発に行われた。
日本との関係では、東日本大震災に際し、ラオス政府及び国民から義援金やお見舞いのメッセージが送られ、ラオス国内で慈善活動が活発に行われた。また、3月の党大会でも、日本との協力関係は「包括的パートナーシップ」に格上げされたとして高く評価され、ラオス新政権成立直後の8月には、トンルン副首相兼外務大臣が訪日し、東北地方の被災地を訪問するとともに、日・ラオス外相会談では、松本外務大臣との間で、経済協力、貿易・投資促進、国際場裏における協力関係等で意見交換を行い、ラオス新政権と引き続き「包括的パートナーシップ」を強化していくことを確認した。これ以外にも1年を通じ、ラオスから閣僚級の訪日が頻繁に行われ、日本からも政府のみならず多くの民間友好団体や企業関係者がラオスを訪問した。
(6)インドネシア
ユドヨノ政権は、10月の内閣改造を経て、引き続き安定的に政権を運営するとともに、堅実な経済運営により欧州の経済危機の影響を最小限にとどめ、順調な経済成長を維持した。
外交面では、ASEAN議長国として、関係国の利害を調整し、ASEAN関連首脳会議を成功させるなど、国際社会にその存在感を示した。日本も様々な機会を通じてインドネシアに対し、日本の考えを提案するなど会議の成功に向け積極的に協力した。
日本との関係では、6月に、ユドヨノ大統領夫妻が訪日し、両国首脳間で防災・災害対応分野で両国が連携していくことを確認したほか、外相間の戦略対話、閣僚級経済協議及び防衛大臣間協議という三つの閣僚級対話を定期化することで一致した。また、同大統領夫妻は、東日本大震災の被災地である気仙沼市を訪問し、200万米ドルを寄附するなど被災者を激励した。10月には玄葉外務大臣がインドネシアを訪問し、マルティ外相との間で第3回戦略対話を行った。2011年はこうしたハイレベル交流を通じ、両国の関係が一層強化されるとともに、戦略的パートナーとして、地域・国際社会の課題における協力が深められた。
日本とインドネシアの戦略的パートナーシップは、具体的な協力としても成果を出しており、3月にARF(ASEAN地域フォーラム)災害救援実動演習(DiREx)を両国で共催したほか、インドネシアの民主化の経験をエジプトと共有するために、日本の支援によりエジプト民主化支援セミナーを10月に開催した。また、12月には第4回バリ民主主義フォーラムを開催し、岡田克也元外務大臣が総理大臣特使として出席した。
経済面でも両国の協力は進展し、5月にインドネシア政府が策定した国家開発マスタープランが重点を置いているインフラ整備については、2010年12月に署名された首都圏投資促進特別地域(MPA)に基づく両国の取組が進展しており、3月及び9月には閣僚級が出席した運営委員会が開催され、ジャカルタ都市高速鉄道(MRT)など具体的な案件の実施に向けて作業が進んでいる。また、日本の経済界のインドネシアへの関心も高まっており、11月には、日・インドネシア経済合同フォーラムが開催され、官民対話を行った。
(7)シンガポール
5月の総選挙において、与党の人民行動党(PAP)は87議席中81議席を獲得して勝利したものの、得票率は60.14%で過去最低となり、外務大臣を含む複数の現職大臣が落選した。また、8月には1993年以来となる複数候補による大統領選挙が行われ、PAPが推すトニー・タン氏が僅差で勝利した。シンガポールの政治体制は引き続き安定しているが、若者を中心とする国民の政治意識の変化が選挙結果に反映される形となった。
日本との関係では、10月に玄葉外務大臣がシンガポールを訪問し、シャンムガム外相ほかと会談した際や、11月のASEAN関連首脳会議の機会に野田総理大臣がリー・シェンロン首相と首脳会談を行った際に、EASでの協力や、アジア太平洋地域での経済連携について、意見交換を行った。4月に第8回日本・シンガポール・シンポジウムがシンガポールで開催された際は、日本側の団長を伴野外務副大臣が務め、両国の各界の有識者が、アジア情勢や地域の経済統合について、掘り下げた議論を行った。
経済面では、多くの日系企業がアジア地域経済のハブであるシンガポールを地域経済活動の拠点として利用しているほか、第三国向けのインフラビジネスにおける両国企業の連携の試みも進められている。また、外務省は、シンガポールをクールジャパンの海外展開(1)における重要拠点の一つと位置付け、9月に現地関係機関を集めた「クールジャパン支援現地タスクフォース」を立ち上げた。
(8)東ティモール
東ティモールは、2006年以降、国軍兵士のデモをきっかけに治安が悪化していたが、国連東ティモール統合ミッション(UNMIT)などの支援も受け治安を回復し、現在は紛争後の復興段階から本格的な経済社会開発段階へと移行している。3月にはUNMITから国家警察への権限移譲が全13県で完了し、7月には2030年までの長期的開発政策の指針である戦略開発計画を策定した。
日本との関係では、8月の菊田外務大臣政務官による東ティモール訪問や10月のグテレス副首相による訪日などを通じ、二国間関係が強化された。日本は、地域の平和と安定、平和構築への貢献という観点から、人材育成・インフラ整備のほか、自衛官のUNMIT派遣等、人的貢献を含めた国づくりを一貫して支援している。

(9)フィリピン
2010年6月に発足したアキノ政権は、約7割という高い大統領支持率を背景に安定した政権運営を行った。内政の最大課題とされる前政権の不正追及に関し、11月、2007年の選挙妨害容疑でアロヨ前大統領を逮捕・拘留した。また、前政権追及の過程で大統領と最高裁判所との対立が顕在化し、12月には、下院が最高裁長官の弾劾を発議し、2012年1月に上院において弾劾裁判が開始された。
ミンダナオ和平に関しては、8月にアキノ大統領とムラド・モロ・イスラム解放戦線(MILF)議長との初めての会談が日本で行われ、その後、8月、11月、12月に予備交渉及び非公式会合が行われるなど、フィリピン政府とMILFとの和平交渉進展が期待される。
経済面では、マクロ経済は2008年の世界経済・金融危機による低迷から回復基調にあるといえるが、7.6%の実質GDP成長率を記録した2010年と比較すると成長は鈍化している。
外交面では、従来、国家安全保障、経済安全保障及び海外フィリピン人労働者保護を3本柱としているが、2月末のデル・ロサリオ外相の就任により、対米同盟関係重視の姿勢を強く打ち出している。
日本・フィリピン関係では、9月にアキノ大統領が訪日し、野田総理大臣との首脳会談で、日・フィリピン両国が基本的価値観と戦略的利益を共有する「戦略的パートナー」であることを確認する共同声明を発出した。また、海洋分野での両国の協力を進めるべく、アキノ大統領訪日に先立ち、9月に第1回日・フィリピン海洋協議を開催した。
また、12月にミンダナオ島北部を襲った台風により死者1,200名を超える甚大な被害が生じたことを受け、日本は、2,500万円相当の緊急援助物資を供与するとともに、200万米ドルの緊急無償支援協力を実施した。
(10)ブルネイ
ブルネイは、石油・ガスといった豊富な天然資源に支えられ、引き続き経済成長を続けた。また、近年は、天然資源への依存脱却のために、経済多角化を進めている。
日本との関係では、5月の菊田外務大臣政務官によるブルネイ訪問や12月のヤスミン・エネルギー相による訪日などを通じ、二国間関係が強化された。また、日系企業が参画したメタノール・プラントの操業により、メタノールが同国における三番目の輸出産品に成長し、ブルネイの経済多角化に貢献するなど、日本とブルネイの経済関係の幅は更に広がりつつある。
(11)マレーシア
ナジブ政権は、経済面で、2010年に相次いで発表した「政府変革プログラム」、「新経済モデル」、「第10次マレーシア計画」及び「経済変革プログラム」を着実に実施し、「ワンマレーシア(国民第一、即実行)」のスローガンの下、国民福祉の充実を図った。
内政面では、7月、NGOグループである「清廉で公正な選挙のためのグループ(Bersih 2.0)」が野党連合と協働して選挙制度の改革を訴え、約6,000人が参加する大規模デモを行ったこともあり、その後、選挙制度や政治的権利に関する様々な改善策が打ち出され、8月に選挙改革委員会が設置されたほか、9月に国内治安法廃止提案、11月に平和的集会法案の国会上程等が行われた。
また、12月、第5代国王を務めたアブドゥル・ハリム・ムアザム・シャー・ケダ州スルタンが2度目となる第14代国王に就任した。
マレーシアは、マラッカ海峡の沿岸国としての地政学的重要性を有し、日本の企業の海外製造拠点や日本に対する重要な天然資源供給地となっている。日本との間では、2012年に30周年を迎える東方政策(2)や緊密な投資・貿易関係に支えられ、良好な関係を発展させてきた。9月には、マレーシア日本国際工科院(MJIIT)が開校し、日本人教員らの協力を得て、日本式工学教育をマレーシアで行う体制を整備している。また、10月には、玄葉外務大臣がマレーシアを訪問し、アニファ・アマン外相との間で、二国間関係の更なる強化に向けて協力していくことを確認した。
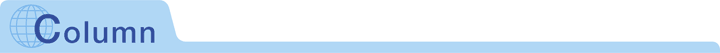
日本は、各国の平和維持能力向上のため、日・UNDP(国連開発計画)パートナーシップ基金を通じて、アフリカに所在する10か所の平和維持活動(PKO)訓練センター等を支援しています。マレーシアPKO訓練センター(MPTC)に対しては、アジアのPKO訓練センターとして初となる支援を行いました。
MPTCでは、アジア・アフリカ地域から集った訓練教官及び要員に対し、平和維持に関する訓練能力と実施能力向上のため、2年間にわたる支援プロジェクトを実施しています。民軍協力とジェンダーは、MPTCが特に主要なテーマと考えており、2011年にUNDPの要請を受け、私たちはMPTCを支援するため、このセンターの民軍協力訓練コースに講師として派遣されることになりました。
民軍協力訓練コースでは、文民専門家の立場から、人道支援やジェンダーなど民軍協力に必要な原則等の講義を行い、現場での活動を想定したシナリオに基づく演習を担当しました。PKOの現場での民軍協力の実態は、状況や任務に応じて様々なものがあります。そのため、講師として、訓練の経験が現場でいかされるように、できるだけ実践的な内容になるように心がけました。アジア・アフリカ地域からの軍人、警察及び文民といった多様な参加者が、文民と軍の間の意思疎通における困難な点や、現場で起こり得る課題に取り組み、その視点の違いを、お互いに率直に話し合うことができたことは、参加者にとってだけでなく、私たち講師にとっても有意義な機会となりました。
また、同年11月には、クアラルンプールにおいて、PKO活動におけるジェンダーに焦点を当てた2日間のセミナーが開催され、パネリストとして、ジェンダー主流化をテーマとして、PKOにおける女性要員の登用の重要性について発表しました。聴衆から活発に質問が出され、セミナー最終日には、PKO活動の質の向上のために、要員派遣国が更にジェンダー主流化に取り組むよう提言が出されました。
平和維持活動の任務の複合化に応えるためには、適切な数のPKO要員を派遣するのみならず、要員の質の向上が求められています。今回のMPTCへの講師派遣では、外務省が中心となり、内閣府国際平和協力本部事務局が有する知見を有効に活用することで、PKO要員の質の向上を目指した支援を行いました。多様な国際社会のニーズに応えるためには、今回のようなオールジャパンの取組を推進していくことが、引き続き欠かせません。
内閣府国際平和協力本部事務局国際平和協力研究員
佐藤美央、与那嶺涼子



1 2010年6月に閣議決定された新成長戦略において、21の国家戦略プロジェクトの一つに位置付けられた。
2 マハティール首相が、1981年の就任直後に提唱。日本及び韓国に留学生を派遣し、両国の技術、労働倫理や経営哲学を学ぶことを目的とする。