チャレンジ41カ国語~外務省の外国語専門家インタビュー~
2007年7月
ハンガリー語の専門家 吉村さん

ドナウ河、流氷、国会議事堂を背景に
Jó napot!(ヨーナポト)=こんにちは!
吉村さんは平成3年に外務省に入省した後、一からハンガリー語の勉強を始めました。
「第5希望にすら入っていなかった言葉でしたから、ハンガリー語に決まったときにはやっていけるかなぁ、とかなり不安を感じました。」
41か国語の中には、希望者のいない言語も相当あるので、みんなが希望どおりの言語の専門家になれるわけではありませんが、思いもよらない未知の言語を習得して、その専門家とならねばならないというプレッシャーは想像に難くありません。
●自由に学べることの意味
そんな不安を抱えながら、吉村さんはハンガリーに到着します。最初の4週間は、ルーマニア国境に近いデブレツェンでサマースクールに通い、その後首都ブダペストでエトヴェシュ・ローランド大学とブタペスト経済大学(旧カール・マルクス大学)に通います。
「私が在外研修を始めたのは1992年で、ハンガリーはその当時、既に体制転換を始めた後でしたので、通う大学や講義を自由に選ぶことができました。日本の大学で学んだ国際法の講義をハンガリーでも聴講できました。体制転換の前は、西側陣営である日本外務省の研修生には歴史、文学等の講座しか開放されておらず、ハンガリー人学生と一緒に政治や経済を学べなかったのです。」
●家庭教師が優秀なわけ
こうして、大学での勉強が始まりますが・・・
「学びたい講義を自由に選ぶことができて良かったのですが、大学の講義は高度で、理解できない部分もかなりありました。それで「国際予備学院」を定年退職した家庭教師を頼んだのですが、その先生のポイントを押さえた指導が非常に分かり易くて、とても助かりました。」
ハンガリーでは「国際予備学院」という外国人向け語学学校を開設し、外国人留学生はまずこの学校でハンガリー語を学ぶという体制を整備してきました。このため語学教師の質が高かったのです。ハンガリーが外国人向けハンガリー語教育に力を入れるのには訳があります。

日本大使館(当時)正門前で
●民主化前も外国人を受け入れていたわけ
ハンガリーは第1次世界大戦で敗れ、国土の3分の2を失いました。そのときに、その土地に住んでいたハンガリー人も一緒に失います。また、第2次世界大戦と1956年ハンガリー革命の結果、多くの人が西側に亡命しました。このため、「外国人」となってしまった元ハンガリー人の子弟などが、夏休みなどを利用して、本当の母国語であるハンガリー語を学びに来ているのです。でも、休暇でハンガリーに来ていたのは、ハンガリーを祖国とする人ばかりではありませんでした。
●政治的観光地
「ハンガリーは、冷戦時代には東西ドイツに引き裂かれていたドイツ人達が逢瀬を楽しむいわば『政治的観光地』でもありました。」
冷戦時代、東側の同盟国であったハンガリーには東ドイツ人旅行者が沢山訪れました。さらに西ドイツからも旅行者がハンガリーに行くことができました。そして、ハンガリーの観光地で東西離ればなれになったドイツ人家族や親戚がつかの間の再会を喜び合っていたのです。
●「ベルリンの壁」とハンガリー
ところで、東西冷戦の象徴だった「ベルリンの壁」は1989年に崩壊しましたが、そのきっかけにハンガリーが関係していることをご存じの方は意外と少ないのではないでしょうか。
「ハンガリー政府が、ハンガリーに来ていた東ドイツの人々にオーストリアへの国境の通過を認めたことも、ベルリンの壁崩壊に繋がる契機の1つとなったのです。」
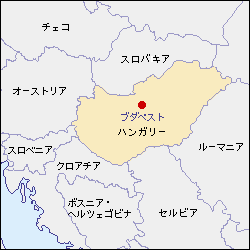
●その名も「ヨーロッパ・ピクニック計画」
冷戦当時、東側のハンガリーは西側のオーストリアとの国境線に防護柵を設け、東側の人々が西側へ自由に出国できないようにしていました。それが1989年にハンガリーが共和国へ体制を転換する中、ハンガリーを訪れていた東ドイツ人がピクニックの名目で国境を越えてオーストリアに脱出できたのです。「ハンガリーからオーストリアへの国境が開かれている」という噂を聞きつけて、その後も東ドイツ人が続々とハンガリーにやってきました。
●「見返りは必要ない」
こうした状況の中、当時のネーメト・ハンガリー首相とコール西独首相がフランクフルトの米空軍基地内で秘密裏に会談します。ハンガリーはオーストリアとの国境防護柵を撤去し、東ドイツ市民の国境通過を認めました。このドイツ人救済に繋がるハンガリーの措置に対して、コール首相は「見返りに何を望むのか」と質しますが、ネーメト首相は「何も必要ない。これはハンガリーが決めたことだ」と答え、コール首相を感動させたと言われています。民族が離ればなれになるという同じような境遇にあったハンガリーだからこそできた英断かもしれません。
「もっとも、ベルリンの壁崩壊後は東西ドイツ人家族の再会の場という『政治的観光地』としての役割は終わり、ハンガリーはそれまでのドイツからの観光客の一部を失うことになったわけですが。」
●味噌汁が突如ハンガリースープに!
さて、ハンガリーに到着して間もない頃の吉村さんは、連日のハンガリー料理に胃が疲れ気味に。そこで下宿のキッチンで、日本から持ってきた虎の子のインスタント味噌汁を作っていました。そこへ下宿のおばあさんがやってきて、その味噌汁の中にラードとパプリカをぽんっ!一瞬のことで止める暇もなかったそうです。
「ラードとパプリカはハンガリー料理の味付けの素で、日本の味噌や醤油みたいなものです。美味しくしてあげようというおばあさんの気持ちは嬉しかったのですが、残り少ない日本の味噌汁が~(笑)」
ちなみにこのおばあさんの下宿にはクーラーがなく、吉村さんは夏は甚兵衛を着て過ごしていたそうですが、その甚兵衛姿はおばあさんに大受けだったそうです。
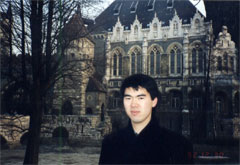
市民公園・ヴァイダフニャド城を背景に
●誰にとっても難しい言葉?
ハンガリー語は、『てにをは』があったり、文章の中で5W1Hの強調したい要素から順に並べたり、主語が明らかな場合は省略するところなど、文法的には日本語と共通する部分があります。ローマアルファベット文字を用いており、母音又は子音+母音で一つの音を表記する点もローマ字と同じです。
―日本人にとって覚え易いのでは?
「う~ん・・・。不規則なルールもたくさんありますし、必ずしも覚えやすいとは言えませんね。正直なところ、私にとっては難しい言葉です。ただ欧州言語の英語、ゲルマン、ラテン、スラブ語圏から集まったサマースクールのクラスメートたちも、文法が難しいと口を揃えて言っていました。」
●勉強法
―最後に吉村さんのお勧めの勉強法を教えてください。
「ラジオ放送を利用しました。同じ内容の短いニュースが1日に繰り返し放送されるのですが、何度も聴いて耳を慣らすようにしました。また、出来るだけテレビのニュース番組を見て、現地の新聞を読むように努めました。」
当初の不安もなんのその、民主主義国家へと体制が緩やかにシフトしていく中で、見て、聞いて、感じたものの全てが吉村さんのハンガリー専門家としての貴重な財産になっているようです。
吉村さんのハンガリー語
●思い出の言葉
Türelem rózsát terem.(トゥレレム ロージャト テレム)
=忍耐が薔薇を作る。(ハンガリー語研修中にこの表現を知り、なかなか語学習得がはかどらなくても努力しようと思いました。)
●便利なフレーズ
Köszönöm.(ケセネム)=ありがとう
Igen(イゲン)=はい
Nem(ネム)=いいえ
Bocsánat(ボチャーナット)=すみません。失礼ですが。
Persze(ペルセ)=もちろん
Értem.(エールテム)=わかります。理解します。
Nem értem.(ネム エールテム)=わかりません。理解しません。
★ハンガリー語を主要言語とする国: ハンガリー共和国

