チャレンジ41カ国語~外務省の外国語専門家インタビュー~
ポルトガル語の専門家 木下さん

Olá !(オラ)=こんにちは!
木下さんがポルトガル語の勉強を始めたのは大学に入学してからでした。
大学でポルトガル語を選んだきっかけは?
「当時はJリーグブーム、ブラジルからの出稼ぎ労働者の再増加などで、ポルトガル語が注目され始めた時期だったんです。」
●学生時代のリスボン
大学3年の半ばから約1年間、リスボン大学に留学した木下さん。どうやらこの時の経験が、外務省に入るきっかけとなったようです。
「ポルトガルはマカオを植民地にしていたので、アジア人を下に見ているポルトガル人が多かったように思いますね。子供に唾を吐かれたり、小石を投げられたりする友人もいました。現地の人と接していて、明らかにお互いに理解不足だと感じました。外務省に入って、この経験を生かして役に立てたら・・・と。」
●日本人の口に合う料理
最初のリスボンの印象はどうでしたか?
「伝統的な街並みが残るきれいなところです。よく隣国のスペインと比較されますが、人々は穏和で素朴です。料理も素朴で、イワシの塩焼きとか、意外と日本人の口に合うものが多いんですよ。ワインも美味しいですね。」
●研修地としてのリスボン
平成8年に外務省入省。その後語学研修のため再びリスボンに赴きます。学生時代と同じリスボン大学に、今度はポストグラデュエート(研究生)として夕方学校に通いました。そして昼間は家庭教師の授業を受けたり、語学学校にも週3回通ったりと、語学学習のために試行錯誤したそうです。
「少しでも多くポルトガル人と交流を持ちたかったんです。大学の同級生は、日中は仕事を持つ社会人でしたから、話していてとても勉強になりました。金融関係の仕事をしているカップルと特に親しくなり、授業が終わったあとによく一緒に食事に行きましたね。」
ここで木下さんは、ポルトガル人相手には、思ったことを全て口に出さなくては伝わらない、日本人同士の会話のように、表情を読み取るとか、「以心伝心」などはない、ということを実感したそうです。

ポルトガルの田舎(ピオダォン)

ポルトガルの田舎の風景
●イエスマンじゃなくなった!
暫くして木下さんは、大学時代の留学の際にお世話になったホストファミリーを訪ねます。ホストファミリーは、成長した木下さんにびっくり。「あなたは当時何を言っても、(こちらの言っていることが理解出来ず、)適当にイエス、イエスばかり繰り返していました。質問もしていないのに、イエスってね。今はずいぶん上手になりましたね。」
この一家とは現在も連絡があるそうです。ホストファミリーにとって、木下さんは彼らの「自慢の息子」となったようです。
●ブラジリアに到着した日は・・・
1年間のリスボン研修の後、木下さんはブラジル外務省からの招待を受け、今度はブラジリアにある外交官養成学校「リオ・ブランコ研修所」に入学することになります。1998年の夏でした。
「ブラジリアに週末に到着したのですが、片側6車線程もある広い道路には、なんと、車が一台も走っていないんです!ブラジリアは車で移動することを念頭に造られた人工都市なので、もちろん歩いている人なんていません。とんでもないところに来ちゃったと思いましたね、その時は。後でわかったのですが、その週末は、ワールドカップ・フランス大会決勝戦のブラジル対フランスの日だったんです。それで、みんな家でテレビにかじりついて、車を運転している人なんていなかったわけです。」
●外交官の大切な財産
古い街並みが残る素朴な雰囲気のリスボンから、人工都市のブラジリアへ。ずいぶん異なった環境ですが、学校はどんなところでしたか?
「リオ・ブランコ研修所は、ブラジル人外交官を養成する機関です。当然ですが、授業は本当に厳しかったですね。とにかく宿題も多かった・・・。国際関係論の授業で、30人ほどのクラスメートの前で発表した時はものすごく緊張しました。」
厳しい授業に耐えたおかげで、ブラジル人の視点を学ぶことができたと話す木下さん。当時のリオ・ブランコ研修所の所長は、なんと現在の駐日ブラジル大使館のアマード大使だそうです。当時のクラスメートも駐日ブラジル大使館で勤務されているそうで、言葉だけでなく、外交官にとってもっとも大切な「人脈」も得ることができて、木下さんにとってかけがえのない財産です。

外交官研修所の級友達と
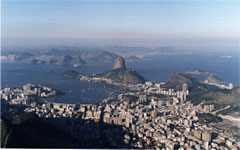
リオ・デ・ジャネイロの美しい景色
●ポルトガルのポルトガル語、ブラジルのポルトガル語
ところで、ポルトガル人が話すポルトガル語と、ブラジル人が話すポルトガル語、どのように違うのでしょうか?
「文字は一緒でも発音がかなり違います。ポルトガル人は口をあまり開かずに、単語と単語をつなげて発音します。正しい文法でないと、例えば男性名詞と女性名詞、単数形と複数形を間違えたりすると、理解してもらえないこともあります。移民が多いブラジルでは、ゆっくり、はっきり発音するのが特徴で、日本人には聞きやすいですね。ポルトガル人にくらべると文法はあまりこだわらないですね。」

●買い物が大変!?
とても順調にポルトガル語を習得していったようですが、苦労などはなかったのですか?
「順調なんてとんでもない。大学時代は、新聞・雑誌や小説を使った授業を受けていましたから、現地では逆に易しい日常会話に苦労の連続。本当に簡単な単語が分からなかったりして。最初の数ヶ月は道順を聞いたり、乗り物の乗り換えを確認したりするのが大変でした。レストランや商店で金額を聞き取るのが難しくて、紙に書いてもらったことも何度もありますよ。」
意外や意外...。でも、その後は政府要人等の通訳をこなすようになります、が・・・
「これも、最初は相当苦労しました。ポルトガル語を日本語に訳すときに、思うように日本語が出てこないんです。英語で言うとThank you for your help(ご支援に感謝します)のような簡単なポルトガル語の文章を、「お助けに感謝します」と変な日本語に訳し、恥ずかしい思いをしたこともあります。また、政治用語、経済用語等の専門用語も出てきますから、通訳業務は今でも苦労しています。」
●アフリカにもポルトガル語が!
実は、木下さんは、現在、アフリカ第2課勤務。ポルトガル語でアフリカ担当?と、思われるかもしれませんが、ポルトガルはアフリカにも植民地を持っていた影響で、今でもポルトガル語が公用語となっている国が5か国あります。木下さんは、その中でモザンビークとアンゴラを担当しています。
「ポルトガルの植民地だった両国がこれまで背負ってきた歴史を考えながら接していかなくては、という気持ちが常にあります。」
●おすすめ勉強法♪
ポルトガルの「素朴さ」と、ブラジルの「人々の明るさ」が好きだと話す木下さん。最後に、ポルトガル語のおすすめ勉強法を聞いてみました。
「音楽を聴きながら、歌詞を覚えるのは効果的です。ボサノバ、サンバのリズムに合わせて声を出して歌う!」
確かに、リラックスしながら心地よく覚えられそうです。

ブラジルミナス州の美しい街並み

ミナス州の教会
木下さんのポルトガル語
●好きな成句
Querer é poder=成せば成る
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura=雨垂れ石を穿つ
Pensando, morreu um burro=考えていて、ロバが死ぬ(「考え過ぎず、行動をおこせ」の意味)
Quem não arrisca, não petisca=危険を起こさないものは者は食べられない(「結果を得るためには、試みる必要がある」の意味)
●便利なフレーズ
Tudo bem ?(トゥード・ベン?) 元気?(Tudo bem!(元気です)と返事をします。)
Obrigado !(オブリガード!) ありがとう。
De nada !(デ・ナーダ!) どういたしまして。
Gosto de~(ゴスト・デ・~) ~が好きです。
Paciência !(パシエンシア!) 忍耐。(「仕方がない」という意味でよく使われます。)
★ポルトガル語を主要言語とする国: ポルトガル共和国、ブラジル連邦共和国、モザンビーク共和国、アンゴラ共和国、ギニア・ビサウ共和国、カーボ・ヴェルデ共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、東ティモール民主共和国

