チャレンジ41カ国語~外務省の外国語専門家インタビュー~
ヘブライ語の専門家 綱掛さん

![]() (シャローム)=こんにちは!
(シャローム)=こんにちは!
綱掛さんは、昭和60年、大学3年生の時に外務省専門職員採用試験に合格。そもそもの志望動機は、家業を継ぎたくなかったから。そして、ヘブライ語の選択動機は、お父さんを説得するには、「これ以外に考えられなかった」!?
●「ダビデ」の屁理屈
綱掛さんの名前は、「太秀」と書いて「ダビデ」と読みます。これは、熱心なクリスチャンのお父さんが「息子には聖書の中で最も偉い人の名前をつけたい!」と言って神父さんに相談してつけられた名前だそうです。とはいえ、「ダビデ」という名前は日本では余りに珍しすぎて、その名前を付けられた当の本人は、幼い時から「変わった名前」というだけでいじめに遭ったそうです。そこで、幼いダビデ君が密かに抱いた決意というのが、「このような視野の狭い日本の中には僕の将来はない。『国際的な名前』をつけられた以上、海外に出て働くしかない。」というものでした。
しかし、お父さんは、そんな綱掛さんの決意も知らず、家業の呉服屋を継がせたかったらしく、大学への進学も卒業後に家業を継ぐとの条件で渋々同意。
綱掛さんは、卒業を目前に呉服屋という余りにもドメスティック(国内的)な家業を継ぐのを少しでも先延ばしにしようと、「卒業後、しばらく外務省に入って旧約聖書の原語であるヘブライ語を勉強したい。」という屁理屈(実は名案!?)を考え出します。
●ユダヤの専門家として
でも、綱掛さんがヘブライ語を選択した本当の理由があります。それは、1973年の第4次中東戦争の時に日本国内をパニックに陥れた石油ショックと関係があります。「当時、私は小学校3年生でしたが、これをきっかけに中東紛争に関心を持つようになりました。そして中東紛争の根本的な原因と言われるイスラエルについては、もっと十分研究すべきだと考えるようになりました。まあ、日本にはユダヤの専門家がほとんどいなくて、当時は、ユダヤ人についてまだ『ヴェニスの商人』のような書物が引用される時代でしたから。『ヘブライ語を勉強してユダヤの専門家になれば、ひょっとしたら名を成せるかも』という下心があったことも事実ですが(笑)・・・。」

●ヘブライ語は3000年の間変わらぬ祈祷の言葉
ヘブライ語は、古代エジプトで当時ヘブル人(=「移り住んできた民」という意味)と呼ばれていたユダヤ人が使っていた言語だったため、この名前がついたと言われています。映画で有名な「十戒」(ユダヤ人の出エジプトを指導したモーセが、シナイ山で神と交わした契約)も、このヘブライ語で書かれていますし、モーセが綴ったその他のユダヤ歴史書(俗に「モーセ五書」あるいは「トーラー(律法)」という。)を含む旧約聖書も原語はヘブライ語です。ですから、ヘブライ語は、ユダヤ人にとっては正に聖なる書物の言葉なのです。このため日常生活で使うなんてとんでもない、ということなのか、イエス・キリストの時代には、人々は日常生活ではアラム語という言葉を使い、ヘブライ語は祈祷にだけ使っていたそうです。こうして、言語としてのヘブライ語は、約2~3000年の間、いわば「塩漬け」になるわけです。
●「国を造りたい」→「国の言葉が必要だ」
―それが復活されたのはなぜ?そしていつ?
「およそ100年前、欧州各地でユダヤ人の迫害が始まりました。このため、ユダヤ人は、民族の維持のためには『シオンの地』に還ってユダヤ独自の国を造るしかないという『シオニズム運動』が活発になり、ユダヤ人が続々とパレスチナに帰還するようになります。この「国を造りたい」という強い思いは、いずれ国として統一独立するためには独自の言語をもつことが必要だ、という考えに発展します。そして、当時欧州からパレスチナに帰還したエリエゼル・ベン=イェフダというユダヤ人言語学者が、研究に研究を重ねて、国語としてのヘブライ語の復活に取り組んだのです。」
●紙発明以前からあった言葉の必然
そもそも、ヘブライ語とはどんな言葉なのか。綱掛さんの説明によると、発音は、日本人に聞き慣れない喉を使う子音がいくつかあるものの、日本語と同様5母音がしっかりしているので、英語に比べるとずっと聞き取りやすく、また文法は、be動詞がないので、組み立てが単純とのことです。例えば「ワタシ+ガクセイ、アナタ+センセイ」で、「私は学生です。あなたは先生です。」という意味になります。つまり名詞を二つ並べるだけで一つの文章になってしまうわけです。また一般的な挨拶として「マ・シュロムハ(=御機嫌いかがですか)?」という決まり文句があるのですが、これを文法的に分解すると「マ(What?)」+「シュロムハ(Your Peace)」といった具合です。
そして、敬語はほとんどなく、装飾的な(無駄な?)言い回しもあまり使わない、とても合理的な言葉だそうです。そして、文章はアラビア語と同じように、右から左に書きます。
「なぜかというと、モーセが文字にした当時は、紙なんてないですから、鑿と槌を使って石に打ち込むんです。すると、右利きの人にとっては、右から文字を刻んでいく方がやりやすいんですよ。」紙の発明以前からあった言語の歴史を感じます。

●移民のための語学学校
―研修はどのような学校で行ったのですか?
「イスラエルはもともと世界中にいたユダヤ人が移住してきて出来た国ですから、移民のための成人教育がかなり行き届いていて、移民のための語学学校が各地にあるんです。教え方はうまいですよー。」
という綱掛さん。語学学校で世界中からやって来るユダヤ人と一緒に勉強しました。授業は外国語を一切使わず、ヘブライ語のみで、わかるまで説明してくれる。こうした学校の授業に加えて、綱掛さんは、ヘブライ語を身体全体で覚えたということですが...。
●子供が言葉を覚えるように...
―身体全体で覚えるとは、どういうことですか?
「例えば、子どもと遊びながら覚える!というか、最初は、私のおかしなヘブライ語に対して真剣に相手をしてくれるのは子どもしかいなかったんですけど(笑)。でもそれが良かったんです。子どもが言葉を習得していくのと同じように言葉を覚えられたんですから。本当に、言葉を体に染みこませる感じで。子ども用の本やマンガを買い込んで読みあさったりもしました。あとは、異性の友だちをつくるとか。とにかくイスラエル人と一緒にいることをこころがけました。」
●戦争を経験していないヘブライ語専門家はいない
イスラエル人は、一度仲良くなると非常に人なつこくて、よく家に招いてくれる、と綱掛さん。イスラエル人の子どもと遊んだり、友人を作ったりとイスラエルでの研修生活は平穏な様子。しかし、イスラエルというと「戦争」というイメージがつきまとうのですが、実際はどうなのでしょうか。
「確かに、外務省ヘブライ語専門家で、戦争を経験していない人はいません。私も、研修に行ったその年(昭和62年)に第1次インティファーダ(パレスチナ人の民衆蜂起)が起こりました。語学学校で知り合ったパレスチナ人に誘われて偶々ガザに遊びに行っていた時に外出禁止令が出て、自宅に帰れなくなったこともあります。そして、一番大きな出来事は、湾岸戦争ですね。自宅のすぐ近くにスカッド・ミサイルが落ちたときには、やはり怖かったですよ。そのときは、遺書を真面目に書いておくんだったと本当に悔やんだくらいです。」
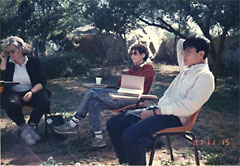
語学学校での野外授業。
●イスラエルは治安の良いところ!
「ただし、イスラエルの治安は良い」、と綱掛さんは続けます。ユダヤ人同士の暴力沙汰は宗教上厳しく罰せられるため、テロを除けば、凶悪犯罪がほとんどないそうです。
「小学生が夜中の2時や3時まで街をうろうろしているくらい安全。違う意味で、大丈夫かって思いますけど!」
●イスラエル人は「地中海性気性」?
そんなイスラエルの人たちについて綱掛さんは、「イスラエルは地中海性気候で、3月から10月くらいまでの乾期は雨が一滴も降らないのです。天気予報は連日晴れ。となると、そこで暮らす人々は天気を気にせず、文字通り『ノー天気』になるというか、カラッとした“いい性格”になる、というのが私の持論です。それに加えて、ヘブライ語の特徴として、敬語があまりない、合理的、もって回った言い方を一切しない。ですから、イスラエル人同士のやりとりは、まるで喧嘩をしているように威勢のいいものです。」
●脳と口が直結すると...
―そんな威勢のいいイスラエル人と付き合う秘訣は?
「暴力は絶対にないのですが、脳と口が直結というか、イスラエル人はとにかく思ったことを率直に言います。そんなイスラエル人に対しては、こちらもはっきりモノを言うと仲良くなれるんです。一度、思い切ってぶつかってみたら、『いや~、君とは良い話ができた。』なんて満足げに言われたりしました。とにかく議論のために議論をするような人たちですから!」
こうして、ものごとを余計な言い回しをすることなく、はっきり言うことによって、イスラエル人の共感を得ていた綱掛さんですが・・・
「日本に帰ってきてから、というよりも、既に家庭内でも、何でもはっきり言ってしまう性格になってしまったものですから大変です。妻からは相当反感を買ってます。たぶん周囲からも・・・。」
●戦後、日本が最初に国交を結んだ国
―日本では、イスラエルについてあまり良く知られていないと思うのですが、日本とはどのような関係があるのでしょうか?
「実は、占領後の日本が初めて国交を結んだ国は、何とイスラエルなんですよ。イスラエルは1948年に建国しましたが、当時の日本はまだGHQの占領下でした。そのような敗戦したばかりの日本にとって、周囲のアラブ大国に打ち勝って建国したイスラエルの姿は、精神的に大きな励ましになったんでしょうね。1951年にサンフランシスコ平和条約を締結した日本は、翌52年の同条約発効(主権回復)を待って初めて国交を結ぶ国としてイスラエルを選んだのです。」
●イスラエル人にとっての日本
「イスラエルにとっても、アジアで初めて国交を結んだ国が日本だったのです。ですから、その物珍しさと、同国内で圧倒的な人気を誇る日本車の影響などもあって、イスラエル人は従来から日本に対して強い関心を持っています。でも、1973年の石油ショック以降、日本はアラブ諸国との関係を重視せざるを得なかった時代があり、一般には『日本はイスラエルに対して冷たい』と思っているイスラエル人も多いかもしれませんね。残念ですが。」と綱掛さん。

ユダ砂漠のワジ(水無川)に造られた修道僧の村。
●日本独自の貢献:イスラエルとパレスチナの信頼醸成
綱掛さんは、ヘブライ語の専門家として、2005年から中東第一課でイスラエルと中東和平について四六時中考える・・・という生活を送っています。その綱掛さんが、日本政府は、イスラエルとパレスチナの間の信頼醸成や、中東和平に積極的に貢献している、という話もしてくれました。
「現在では、韓国や中国から多くの企業が進出したり、アジアからの出稼ぎ労働者が沢山流入したりして、日本の存在感が薄れているのではないかとの懸念もありますが、日本政府は、中東地域の政治的権益に関して下心がありませんから、中東和平に関してはその利権を度外視した独自の貢献ができると自負しています。例えば、日本は、太平洋戦争でアメリカと激戦を繰り広げたにもかかわらず、今や日米両国は、最も関係の深い同盟国となっています。このような日本の経験は、何らかの形で中東和平の為にも活かせると考えています。」
●ホームステイで始まるイスラエルとパレスチナのコミュニケーション
綱掛さんが手がけている中東和平の為のプログラムの1つが、イスラエルとパレスチナの青年を一緒に日本に招待するという「イスラエル・パレスチナ合同青年招聘」。将来、それぞれの社会でリーダーとなることが期待されている青年を日本に連れてきて、一緒に旅行させ、旅館の大部屋に寝泊まりさせたり、ホームステイを体験させたりします。例えば、ホームステイでは、わざと英語を話さない家庭を選び、そこにイスラエルとパレスチナの青年を1人ずつペアで預けるようなこともやっています。
「最初はつーんとして話もしない2人が、日本人のホストファミリーを前に、どうやって日本人とコミュニケーションを取ろうかと、一生懸命相談を始めるんです。」
●次世代を見据えたプログラム
この2つの民族の複雑な関係は、互いに対する優越感と劣等感から成る複雑なコンプレックスによって、単純な意思疎通さえできなくなっていることが原因だと考える綱掛さん。
「例えば、パレスチナ人の子どもに、イスラエル人の絵を描いて、と言うと、ほぼ全員が軍服の兵士を描くんです。即ち、パレスチナ人にとっては、“イスラエル人=兵士”なのです。逆に、イスラエル人の方は、パレスチナ人は自爆テロを繰り返す “悪魔”だと思っている。残念ながら現地ではお互いに話をできる状態ではないのです。」
そうしたお互いに先入観を持った青年たちが、日本で初めて出会い、一緒に旅をしながらコミュニケーションをとる。これが両者の信頼醸成につながり、話し合いのできる関係に発展するよう、長い目で見守るのがこのプログラム、というわけですね。
●「原爆を落としたアメリカが憎くないの?」
綱掛さんが、このプログラムの中で得た印象深い経験談をしてくれました。
「プログラムでは、必ず広島を訪れ、被爆者から被爆体験の話を聞きます。その中で両国の青年から必ず出てくる質問は、『原爆を落としたアメリカが憎くないのか?』。その質問に対して、被爆者の方々は一様に、『憎くない。原爆は憎いけれど、アメリカ人や、アメリカは悪くないんだ。』と答えます。これは、青年たちにとって相当のショックみたいです。」
地道な活動かもしれませんが、こうした青年たちが、いずれイスラエルとパレスチナの未来の関係を変えていくことを願って、綱掛さんは、今日も明日もイスラエルと中東和平のことを考えています。
綱掛さんのヘブライ語
●好きな言葉
![]() (サブラヌート) 「忍耐・我慢」(←これは、イスラエルのみならず、現行中東和平プロセスに携わる全ての人にとってのキー・ワードです。)
(サブラヌート) 「忍耐・我慢」(←これは、イスラエルのみならず、現行中東和平プロセスに携わる全ての人にとってのキー・ワードです。)
●便利なフレーズ
![]() (トダ・ラバ)(todah rabah)~ありがとう
(トダ・ラバ)(todah rabah)~ありがとう
![]() (ベヴァカシャ)(bevakashah)~どうぞ(=please)/どういたしまして(You are welcome.)
(ベヴァカシャ)(bevakashah)~どうぞ(=please)/どういたしまして(You are welcome.)
![]() (マ・ニシュマ?)(mah nishma'a)~(形式張らない形で)元気ですか?
(マ・ニシュマ?)(mah nishma'a)~(形式張らない形で)元気ですか?
![]() (トヴ)(tov)~良い(good)/元気です。
(トヴ)(tov)~良い(good)/元気です。
![]() (マ・イニヤニーム?)(mah innyanim)~(より親しい者に)儲かりますか/元気?
(マ・イニヤニーム?)(mah innyanim)~(より親しい者に)儲かりますか/元気?
![]() (カハ・カハ)(kach kach)~まあまあ(so-so)/ぼちぼちです。
(カハ・カハ)(kach kach)~まあまあ(so-so)/ぼちぼちです。
![]() (アニー・ミヤパン)(ani mi-yapan)~私は日本から来ました。(I am from Japan.)
(アニー・ミヤパン)(ani mi-yapan)~私は日本から来ました。(I am from Japan.)
![]() (レヒットラオット)(lehitraot)~再会(See you again)/さようなら。
(レヒットラオット)(lehitraot)~再会(See you again)/さようなら。
★ヘブライ語を主要言語とする国: イスラエル国

