チャレンジ41カ国語~外務省の外国語専門家インタビュー~
タイ語の専門家 長谷川さん
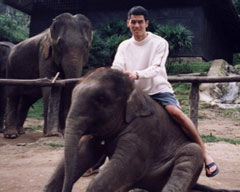
![]() (サワッディー)=こんにちは(昼夜を問わず一日中使用可)
(サワッディー)=こんにちは(昼夜を問わず一日中使用可)
国際関係法学科の学生だった長谷川さんは、国際的な仕事がしたいと考え、外務省に入省を決めました。バックパックを担いで旅行したことのあるタイが気に入ったこともあり、外務省での研修は東南アジアの言語を中心に希望し、見事、第2希望だったタイ語に決まりました。(←第2希望が適うことがどのくらい大変なことかは、「チャレンジ」リピーターの皆さんには、ご理解いただけることと思います。)
「旅行で訪れて感じたのは、発展のエネルギー。これから重要な地域になるだろうな、と。」
と言うとおり、長谷川さんが旅行で訪れた1993年の首都バンコクと、赴任した1997年のバンコクには、たった4年の間とはいえ、例えば1993年には数多くあったトゥクトゥクと呼ばれる三輪車タクシーが、1997年にはほとんどが普通自動車のタクシーにとって代わられていたなど、目に見えた発展の跡があったそうです。
●42×36の音がある?
旅行で訪れたことがあるので、タイ語の響きや文字などにはなんとなく親しみはあったとはいうものの、本格的に勉強を始めてみると、意外と難しい言葉。
何が難しいのかというと、タイ語には、子音が21あるのですが、それだけでなく、「二重子音」や「末子音」という組み合わせを取るため、結果として合計42の子音があることになります。また、母音も基本は9なのですが、これに長短の違いや、二重母音などが組み合わさり、結果、17文字で36通りの母音ができあがります。これにプラスして「5声調」といって、子音の声調の違いがあり...一体いくつの音があるのやら...。

●サンスクリット語が起源の言葉
その上、更に・・・
「タイ語の語源となっているサンスクリット語のスペルをタイ語のスペルに置き換えるので、全く同じ音でも、単語によって違う文字を使い分けなければならなかったりと・・・結構難しいんですよ。」
というわけで、文字を勉強せずに、耳で聞いた言葉をそのまま覚えても、日常会話程度までだったら、簡単に学習できる、と長谷川さん。
「本格的にやるとなると、課題はやはり文字と発音ですね。発音は声調の他にも、有機音と無機音があったりして、発音も聞き取りも複雑です。文法は、一応規則はありますが比較的単純なため、文脈によって意味がいくらでも変化するので、文脈を読み取ることが重要です。」
●大学ではすぐに友だちが
長谷川さんが、現地の研修で選んだのは、バンコクにある、タイ屈指の有名大学チェラロンコン大学の政治学部。聴講生として、興味のある授業に、なるべく多く出席しました。タイ人の学生たちは、人なつこい上に、日本から来た長谷川さんがめずらしく興味津々。友だちはすぐにできました。
―友だちとは、一緒に何をして過ごしたのですか?
「タイの学生たちは、仲良しグループみたいな感じで、よくグループ単位で行動します。授業後はショッピングモールに行ってアイスクリームを食べたり、他愛もない会話をして過ごしたり、といった感じです。3、4年生くらいになると、一緒に飲みに行ったりもします。カラオケも大好きなんですよ。」

●学生レベルと外交レベルはやっぱり違う!
タイ人の友人たちとの付き合いを通してグングンとタイ語を吸収した長谷川さんですが、研修後、いざ大使館で勤務が始まると、
「学生時代とは使っている言葉がまるで違う。一応、政治・経済用語も授業でも使って身につけたつもりではいたのですが、要求される言葉の精度が全く違うことに気がつき、まだ通訳レベルには程遠い自分のタイ語に焦りを感じて、2~3カ月必死で勉強しました。」
長谷川さんは、本省から送られてくる日本国政府の見解などをタイ語に訳して、ネイティブにチェックしてもらうという勉強方法で、外交レベルのタイ語を短期間で習得していきます。
●会談の潤滑油として

今では、天皇陛下を始めとして、総理や要人の通訳を数多く行っている長谷川さん。通訳として、思い出深い会談はあるのでしょうか。
「タクシン前首相と小泉前総理は、首相になった時期が近く、会談の機会も多かったので、非常に話がはずみましたね。ですから、二人の会談では、外交問題ばかりでなく、冗談も交えながら実に様々な話題に話が及びました。でも、そういうふうに出てくる話題は事前に分かりませんから、その場で咄嗟に対応しなければなりません。通訳泣かせです。一度、総理が冗談でおっしゃった言葉を、訳して良いものやら、判断つきかねて暫しフリーズしたところ、タイ側の通訳がうまい具合に訳してくれたことがありました。会談に同席されていたタイ側の方々は、一斉に爆笑。総理の冗談だけでなく、若い通訳が訳せずに困ってしまった理由もわかって受けたのかもしれません。」
ややもすれば通訳の失敗になってしまうかもしれないところが、逆にその場が和やかになったとか。日頃からタイ政府の人々と良い関係を築いている長谷川さんの裏技1本!というところでしょうか。
●王様には特別の言葉!
「それから、通訳で苦労したのは王語です。タイでは、国民の王室に対する敬愛が非常に強く、王族に対する言葉は、普通の言葉と全く違うんです。これは、タイの王室に対して使うだけでなく、タイ人が天皇陛下に謁見する時にも、陛下に対して最高の敬意を表す為、タイ人はこの王語を使います。」
長谷川さんは、この王語を、現地で毎日夜8時に流されているという王族ニュースを見て勉強したそうです。本当に王室が国民に支持されているのですね。
●入場無料のトリック!?
―タイ語を話すことで、なにか得したことってありますか?
「よく見かけるのですが、観光地の入場料などには、タイ人料金と旅行者用料金があるんですよ。これ、すごいトリックで、料金所みたいなところに、タイ語で『入場無料』、同時に英語で『Adult: 50B(大人:50バーツ)』って書いてあるだけなんです(笑)。タイ語がわかれば料金所は素通りです!」
●長谷川さんのお勧め料理
最近では、タイを訪れる日本人旅行者も多く、多くの方がタイの文化や料理についても詳しいとは思いますが、タイに5年間滞在した長谷川さんにお勧めのタイ料理を聞いてみました。
「タイ南部の特産で“サトー”という豆があり、独特の臭いがあるのですが、これがクセになる。豚肉や海老と一緒に炒めたサトー豆は、ビールと非常に良く合う!お勧めです!」
とのことでした。タイにお出かけの際は、是非みなさんも試してみて下さい。
●タイで気をつけること
ところで、タイに日本人旅行者が増え、二国間の交流が活発化するのは、タイをこよなく愛する長谷川さんとしては喜ばしいことですが、実は、世界中で、事件や事故に巻き込まれた日本人を援護した件数が最も多い在外公館(大使館や総領事館)は、タイなのです。平成17年の援護件数は、1,499件にも上り、2位の英国(919件)を大きく上回っています。海外旅行で事件や事故に巻き込まれる危険性は、どこの国でも同じですが、海外旅行に出かける際は、外務省の海外安全ホームページを事前にチェックし、安全対策を万全にしてご旅行ください。

沈没寸前…ではなく、こういう舟です。
タイから陸路でラオスを訪れたとき。
長谷川さんのタイ語
●挨拶の言葉
![]() (サバーイディー・マイ?):元気ですか?
(サバーイディー・マイ?):元気ですか?
![]() (サバーイ・ディー): 元気です。元気でないときは
(サバーイ・ディー): 元気です。元気でないときは![]() (マイ・サバーイ)
(マイ・サバーイ)
![]() (チョーク・ディー): 幸運を(旅立ち等、永い別れの際の、比較的カラッとした明るいお別れの言葉)
(チョーク・ディー): 幸運を(旅立ち等、永い別れの際の、比較的カラッとした明るいお別れの言葉)
●便利なフレーズ
![]() (マイペンライ): 基本的には何でもない、気にしない、どういたしまして等の意味。文脈によって多様な意味を持つ奥の深い、便利な言葉。ミスをした当人がマイペンライということもあり、日本人は当初憤慨するが、タイ生活が長くなるとそのうち自分でも言うようになります。
(マイペンライ): 基本的には何でもない、気にしない、どういたしまして等の意味。文脈によって多様な意味を持つ奥の深い、便利な言葉。ミスをした当人がマイペンライということもあり、日本人は当初憤慨するが、タイ生活が長くなるとそのうち自分でも言うようになります。
![]() (アローイ・マイ?):美味しい?
(アローイ・マイ?):美味しい?
![]() (アローイ・マーク):とても美味しい。美味しくないときは
(アローイ・マーク):とても美味しい。美味しくないときは![]() (マイ・アローイ)
(マイ・アローイ)
全て文末に、男性は![]() (クラップ)/女性は
(クラップ)/女性は![]() (カー)をつけると丁寧語になり、これを付けないといわゆる「ため口」になります。
(カー)をつけると丁寧語になり、これを付けないといわゆる「ため口」になります。
●お勧め料理の言葉
![]() (パッ(ト)・サトー):サトー豆(南部特産の強烈な匂いの豆)炒め
(パッ(ト)・サトー):サトー豆(南部特産の強烈な匂いの豆)炒め
★タイ語を主要言語とする国: タイ王国

