チャレンジ41カ国語~外務省の外国語専門家インタビュー~
ギリシャ語 専門家 根本さん
![]() (ヤー・サス・・・読み方)=こんにちは!
(ヤー・サス・・・読み方)=こんにちは!

語学学校のクラスメートと。左から3人目が根本さん。
「大学時代、国文学を専攻していたので、『古典つながり』でギリシャ語を選んだのかもしれない」という根本さんは、大学入学の頃から国際関係の仕事がしたいと考えていました。「まずは日本のことを知っておかないと。」ということで、大学では国文学(平安・鎌倉時代の和歌)を専攻。夢だった国際関係の仕事、そして公のためになる仕事がしたいと考え、外務省を目指すことを決めた根本さんは、卒業後に法学部に編入し直して必要な勉強を積み、平成9年に外務省の試験に合格しました。
●「すみませんが、ギリシャ語です」
「外務省から合格の連絡があったとき、『すみませんが、ギリシャ語に決まりました。』と言われました。外務省に入る前の僕を含め、ふつうの日本人はそうだと思いますが、ギリシャといえば、青い空に青い海、エーゲ海、ギリシャ神話など、良いイメージしかなかったので、その言葉には、『???・・・』。」
根本さんは、その言葉の意味を、約1年後、いよいよ、ギリシャに住んでから知ることになるのです・・・。
●病気にはなれない!?
―ではそんなギリシャに行ってみての印象は?
「常識というか、習慣というか、が日本と違う。例えば、窓口の応対は日本なら本当に丁寧ですが、ギリシャでは郵便局の窓口で、担当がたばこをふかしたり、お茶なんか飲みながらの対応がふつうですから。ビジネスマンや、学生さんたちから、1年間の外国人滞在許可証の更新に半年以上かかって苦労したという話を聞き、驚きました。」
窓口にとどまらず、公立病院の手術室の前を犬がウロウロしていたりするものだから、『ここでは決して病気になれないぞ!』と思ったそうです。
●長い間つきあえる、本当の友人
「でも、ギリシャ人は思ったことを素直に、ストレートに表現する人たちで、大声で言い合うこともあるけれど、言いたいことを言えるということは、長くつきあえる友だちもできやすいです。きれいな海もあるし、夏は長いし、いいところですよ。」
と、さすがに外務省のギリシャの専門家だけあって良いところもきちんと見ています。
●ギリシャ語は奥さんと競争
根本さんは、アテネから北へ500キロメートル程のテッサロニキという、新約聖書にも載っている古い街で2年間の研修生活を送ります。このとき既に結婚していたので、奥さんも一緒にギリシャに暮らし、同じテッサロニキ大学附属の語学学校でギリシャ語の勉強を始めます。
「良く言われますが、やはり女性は語学に向いているんでしょうか。家庭教師を雇ったり、二人で同じように勉強していると、なんだかどちらが研修生かわからないほど、妻の上達が早い。危機感を感じたりもしました。大使館の指導官からは、『研修後の語学試験は君と奥さんと両方並べて、成績の良かった方を採用するぞ!』なんて(笑)。」
●外交官にとっての「内助の功」?
もちろん奥さんの語学学習の費用は全部私費で賄います。しかし、外交官は、現地の人々を家に招いたり招かれたり、家族ぐるみの付き合いをしながら生活し、こうした関係を仕事にも役立てていくわけですが、自分のパートナーが同じ言語を話すことができるというのは、非常に助けになりますし、有利です。外交官版「内助の功」とでも言いましょうか・・・・。

語学学校の修了証明書

学校で知り合った友人とは家族ぐるみの付き合い
●ギリシャ語ってどんな言葉?
「あの独特の文字は、フェニキア文字(もともとは象形文字)をもとに作られたとも言われています。ラテン語よりもっと以前に印欧語族から枝分かれして、体系が整ったと言われています。名詞に男性名詞、女性名詞、中性名詞があって、英語と比較すると、文法的には複雑な言葉だと思いますが、発音の種類は少ないです。母音はほとんど日本語と一緒の「あ・い・う・え・お」。日本人には聞き分けにくいと言われている「L」と「R」の違いも、ギリシャ語だと「R」の音が強いので聞き分け易い。」
なるほど。では、そんなギリシャ語を、根本さんはどうやって「モノ」にしたのでしょうか。
●ギリシャ人の団体ツアーに参加してみる
「休みを利用して、何度かギリシャ人の団体ツアーに参加して、海外旅行をしました。周りはギリシャ人ばかり、ガイドの説明もギリシャ語。語学の勉強になるだけでなく、ずぅーっと一緒にいるわけですから生活スタイルも学べました」と、根本さん。面白かったのは、夕方4時頃になると観光は一旦終了、ホテルに戻って次の集合は夜8時だと告げられます。次の集合時間まで根本さん夫妻は何をするでもなくぼーっと過ごしてしまったそうですが、同行のギリシャ人たちは8時に集合したときには皆ドレスアップして顔色もよく、飲んで踊って・・・と深夜まですこぶる元気。根本さん夫妻は疲れ切ってしまうのに、彼らは次の日は朝早く起きてきてけろりとしています。実は、ギリシャ人は夕食前に一寝入りし、シャワーを浴びて、いざ、一日のお楽しみ=家族や、恋人、仲間との夕食に突入するのが一般的。旅行中でも彼らはギリシャ・スタイルを堅持していたというわけです。
●ギリシャ人ゆかりの地を訪ねる
そうしたツアーでトルコのイスタンブールを訪れた根本さん。ギリシャ人の手にかかると、聖ソフィア大聖堂はビザンツ帝国(=東ローマ帝国=ギリシア帝国→ギリシャ)の残した聖堂であるということでゆっくり一時間くらいかけてガイドが説明しながら回るのに対し、有名なオスマン・トルコ時代のブルーモスクはさぁっと通り抜けるだけ。同じくイタリアのヴェネチアでは、ヴェネチアがいかにビザンツ帝国の影響を受けたかをとうとうと語られたとか。
●愛国心の強いギリシャ人
―そうすると、ギリシャ人は愛国精神が強いのですね?
「ものすごーーーく強いんです!ただ、ギリシャは長い間オスマン・トルコに占領されていましたし、東ローマ帝国時代は、ローマ人として生きていましたから、ギリシャが独立する際に、ギリシャ人というアイデンティティを作り上げる必要があったという背景もあります。」
●古典に学ぶ語学上達の秘訣
古典を専攻された根本さんならではの語学学習の秘訣をお教えします。
「『これを知るものはこれを好む者に如かず、これを好む者はこれを楽しむ者に如かず』という言葉がありますが、楽しいと思ってやっていることが一番の上達の近道だと思っています。ですから、自分ではその域に達したと言えませんが、ギリシャ語も楽しんで勉強するようにこころがけました。」
やはり、何事も楽しむことが大切なのでしょうか。
●古代ギリシャ語の格言によれば・・・
古典専攻の根本さんは、さらに、
「古代ギリシャ語に、『善きものは努力しなければ得られない』といった言葉や、『継続は学習の母』というのがあります(*末尾の「根本さんのギリシャ語」を参照)。まったくそのとおりで、努力や継続は大事だと思います。もちろん今でも努力してギリシャ語に触れるようにしています。読んで、書いて、聞いて、話す。これに尽きると思います。」
と続けます。やはり、古今東西、語学学習に近道や特効薬はないようです・・・。
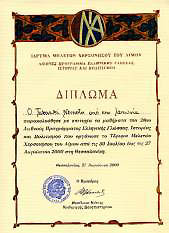
夏期講習の修了書
●今でも思い出す、大使の優しい一言
―研修を終わってすぐ、アテネの大使館に勤務されていますよね?
「ギリシャ語を話すのは、館員13名のうち僕を入れて3名だけでした。専門家とはいっても、働き始めて間もないですし、経験もないですから、はっきり言って、まだ『使い物にならない』。そんな自分を自分で良くわかっていて、自信も持てなかった時期に、当時の大使がある時、お客様に向かって『いや~、根本君に頼りっぱなしですよ。』とおっしゃられたのを聞いて、ある種のショックを受けました。
「こんな自分でも、大使は「頼りにしている」と言ってくれる。それに応えるためにも、専門家としての自覚と責任をもって、仕事に向かわなくてはいけない、と。・・・・その大使は、その後すぐに亡くなられたということもあって、『もっと、何かできることがあったのではないか』と後悔もしていますが、今でも失敗したり、辛いことがあったりするとこの言葉を思い出して、頑張っています。」
と、根本さんにとって忘れられない思い出の話をしてくれました。働き始めてすぐにいろいろな仕事や体験ができるというのも外務省の仕事の魅力ですよね。根本さん、これからも、こうして働き始めた当時の初心を忘れることなく頑張ってください。
根本さんのギリシャ語
●ギリシャ語名言集
![]() (イ エパナリプシス エスティ ミティル パシス マシセオス)~継続は学習の母(継続は力なり)
(イ エパナリプシス エスティ ミティル パシス マシセオス)~継続は学習の母(継続は力なり)
![]() (ヌス イギイス エン ソマティ イギイ)~健康な体に健康な精神は宿る
(ヌス イギイス エン ソマティ イギイ)~健康な体に健康な精神は宿る
![]() (タガサ コピス クトンデ)~善きものは努力しなければ得られない
(タガサ コピス クトンデ)~善きものは努力しなければ得られない
●便利なフレーズ
![]() (ゼン ピラージ)~何の問題もない(困った時によく使う。)
(ゼン ピラージ)~何の問題もない(困った時によく使う。)

