チャレンジ41か国語~外務省の外国語専門家インタビュー~
アラビア語 専門家 榎下さん

![]() (マルハバン・・・読み方)=こんにちは!
(マルハバン・・・読み方)=こんにちは!
榎下さんは、平成9年に外務公務員採用I種試験(当時)に合格しました。この試験枠から入省した職員は、41か国語ではなく、英語、フランス語、スペイン語、中国語、ロシア語、アラビア語、ドイツ語、朝鮮語の8言語の中から研修言語を選択します。「異文化間の理解を促進したい」という理由で外務省に入った榎下さんは、「自分にとっても、一般の日本人にとっても、最もなじみの薄い言語を選ぶべき」と考え、アラビア語を、迷うことなく研修言語として希望しました。
●アラビア語は神のことば
「アラブ人(のムスリム)にしてみれば、『神は、アラビア語を使って預言者ムハンマドにメッセージ(コーラン)を伝えた。つまりアラビア語は神の言語である。』ということ。だから、彼らはアラビア語に対して非常に誇りを持っています。」
と榎下さん。なるほど、誇りを持つのはよく分かります。そして神の言葉であるアラビア語はコーランに収められ・・・コーランに書かれたアラビア語は、当然のことながら、一言一句変わりません。神の言葉ですから。
●こうして口語と文語の乖離が始まった・・・
こうして7世紀のアラビア語にかなり近い形の書き言葉=文語が現在でも使われることになります。でも、当然、長い年月の間に、話し言葉=口語の方は変化します、ラテン語が口語として各地で変化して、フランス語やスペイン語となったように。1300年あまりの間に、アラビア語の口語はアラブ世界の各地で様々に変化し、コーランの文語とはかなり異なる言語になっていきました。その結果、
「演説やニュースは文語が使われていますから、テレビをつけると、極端に言えば、いきなり7世紀の人(日本なら平安時代の人)がタイムスリップしてきてしゃべっているような感じです。アラブの国はどこでも、人々が町中で文語で会話をすることはまずありません。が、外国人がアラビア語を基礎から勉強するとなると、やはりまず文語(≒ラテン語)を学び、その次に口語(≒フランス語やスペイン語)を覚えるということになります。」
●アラビア語は辞書が引ければ一人前?
―アラビア語は世界一難しい言語とも言われますが?
「う~ん、今となっては、そうでもないと思いますよ。ただ、学習していて、なかなか軌道に乗らない言語ではありますね。学習を始めて何カ月か経っても辞書が引けないといった難しさもありますし。」
辞書が引けないとは、なにゆえ?
簡単に説明すると――アラビア語は、ほとんどの言葉が、子音3文字を核として成り立っていて、その3文字から関連する言葉が派生します。例えば、k・t・bの3文字を核として、kataba(書く)、katib(書く人、作家)、maktab(書く場所=事務所)というように。派生した言葉の中には核の3文字にはない文字が加わったり、核の3文字そのものが変化したものもあるので、どれが核になる3文字か、一見して解らない単語が少なくないそうです。
問題は、こうして派生した単語を辞書で引く場合、核となる3文字から辞書を引かないと単語が出てこないのです。(例えば「統一する」という意味の"ittahada"という単語を調べるには、なぜかw・h・dの項目を見なければなりません。ちょっと説明するのがむずかしいのですが、興味のある人は是非調べてみて下さい。)ですから、榎下さんも、どうしても辞書で見つけることができなかった単語があるそうです。初心者には辞書を引くのも一苦労なコトバのようです。さすがは神の言葉・・・・・。
●本腰を入れるべし!
「ただ、最初は難しくても、ある時、急に理解することができて、ぐーんとレベルが上がります。僕は、インドネシア語も勉強したことがあるのですが、最初の1カ月で学べた量は、インドネシア語の方がはるかに多かった。だから、アラビア語を始めたときは、なかなか上達しなかったので、『僕は語学センスがないのかもしれない。』と落ち込みましたね。本腰を入れてやらなければほとんど上達しない言語だと思います。」
やはり、アラビア語は難しいのでは?!
●発音が一番大切
どの言語でも正しい発音を身につけることが一番大事だと考えている榎下さん。アラビア語はのどを使う音が多いので、アラビア語を習いたての頃は、発音練習のしすぎで、レッスンのあった次の日はのどが痛くてほとんどしゃべれなかったという経験もあったとか。
研修地であるシリアではコーランの音読にもかなり時間を割きました。イスラム諸国では、正しい・きれいな発音でコーランを音読する「読誦学」が盛んで、読誦が職業にもなるほど重要視されているそうです。
●どんな国? どんな人たち?
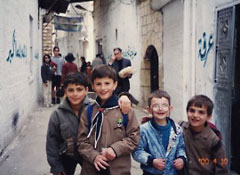
-シリアはどんな国でしたか?
「想像していたとおり、日本と全く異なる世界でした。首都ダマスカスは世界で最も古い町のひとつと言われていますが、今残っている家も古いのが多く、昔ながらの生活が営まれている感じ。僕がホームステイしていた家も築何百年なのか分からないほど古かったです。夏は50℃に迫ることもありましたが、その家では冷房がなく、僕は家の中にいて熱射病になりました。そんな暑さですが、ダマスカスの後、ボストン、アブダビと転勤して生活しましたが、僕も妻も、ダマスカスが一番良かったと言っています。」
シリアは地球温暖化防止にも貢献している地球に優しい国のようです。
ではシリアの人々は、どんな人たちなのでしょうか?
「シリア人は一般的にシャイです。人への敬意を大切にしますし、日本人と似ている部分があるな、と感じました。また、非常に親切です。道ばたで誰かに道を尋ねると、一緒にバスに乗ってくれて、おまけに気前がいいというか、最後にはバス代を払ってくれたりするくらいです。」
そんなアラブ人気質を良く表しているという言葉を紹介してくれました。
●人間らしさ
「![]() (ムルーア) : 『人間らしさ』といった意味です。イスラーム成立前からアラブ人が大切にしていた考えだそうです。その中には、今言ったような気前の良さなんかも含まれているんだと思います。アラブ世界では、人と人の関係を律するルールが生きている、と感じられることがあるのですが、宗教に加えて、こういう古くからの道徳観によるところがあるんだと思います。」
(ムルーア) : 『人間らしさ』といった意味です。イスラーム成立前からアラブ人が大切にしていた考えだそうです。その中には、今言ったような気前の良さなんかも含まれているんだと思います。アラブ世界では、人と人の関係を律するルールが生きている、と感じられることがあるのですが、宗教に加えて、こういう古くからの道徳観によるところがあるんだと思います。」
●アラブ世界への関心の高まり
「アラブ世界の人々は、日本に対して『戦後の焼け野原から短期間で復興した経済大国』といった、漠然とした憧れ・親近感を抱いています。アラブと日本の間には、欧米のような直接的な植民地支配の歴史がないことも原因でしょう。ただ、日本とアラブ諸国との交流は、まだまだ希薄で、例えば、アラブ諸国に住んでいる日本人は石油に関係した人の割合が高いです。
まだまだ課題が山積みだと思っていますが、実は、9・11以降、日本におけるアラブ諸国への関心が高まったという面があります。理由は兎も角、せっかく目が向いたのですから、今後は理解を深めるという方向に向いて欲しい。」とアラビスト(外務省では、アラビア語を研修した人のことをこう呼びます。)らしく、日本とアラブ諸国との友好関係に心を砕いている様子でした。
●無神論者がアラビア世界で生きる!?
最後に、榎下さんならではの、アラビア語に関するエピソード。「僕は無神論者なんです。そして、性格的に、自分を相手に同化させようとはしません。」ときっぱり言い切る榎下さん。シリア人に「宗教は?」と尋ねられたら正直に自分の考えを答えていた榎下さん。アラブ世界では、神が世界を造った・神が全てを決めているという考えが当たり前だそうですが、榎下さんが神はいないと言うのを聞いて怒るシリア人に遭遇したことはなく、むしろ憐れみにも見える反応を見せる人が多いのが興味深かったとのこと。
●便利な言い回し・・・
アラビア語には、「神:アッラー」にまつわる言い回しが沢山あり、実際そのような言い回しは、日常生活で非常に便利なフレーズであることが多いようです(下に紹介している「便利なフレーズ」をご覧ください)。しかし榎下さんは自身の信条に則り、このような神にまつわる言い回しを使用することさえ避けて、首脳レベルの会談の通訳までこなしているそうですが(これは結構大変なことなのですよ!)、一度、どうしても代わりの表現を思い出せず使ってしまったのが悔しいという榎下さんでした。
榎下さんのアラビア語
●好きな言葉
![]() (ムルーア) 「人間らしさ」
(ムルーア) 「人間らしさ」
●便利なフレーズ(全て文語の挨拶です。)
![]() (シュクラン・ジャズィーラン)(shukran jazilan)~ありがとう
(シュクラン・ジャズィーラン)(shukran jazilan)~ありがとう
![]() (カイファ・ハールカ?)(kaifa halka)(女性に対しては「カイファ・ハールキ?」と読む)~お元気ですか
(カイファ・ハールカ?)(kaifa halka)(女性に対しては「カイファ・ハールキ?」と読む)~お元気ですか
![]() (アナー・ミナル・ヤーバーン)(ana minal yaban)~私は日本から来ました。
(アナー・ミナル・ヤーバーン)(ana minal yaban)~私は日本から来ました。
![]() (マァッサラーマ)(maassalama)~さようなら
(マァッサラーマ)(maassalama)~さようなら
![]() (イン・シャー・アッラー)(in sha alla)~神が望めば→多分ね/了解しました
(イン・シャー・アッラー)(in sha alla)~神が望めば→多分ね/了解しました
![]() (アルハムドゥ・リッラー)(alhamdu lilla)~神に讃えあれ→ああ良かった
(アルハムドゥ・リッラー)(alhamdu lilla)~神に讃えあれ→ああ良かった
★アラビア語を主要言語とする国: アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イラク共和国、オマーン国、カタール国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、バーレーン王国、ヨルダン・ハシミテ王国、レバノン共和国、アルジェリア民主人民共和国、エジプト・アラブ共和国、エリトリア国、コモロ連合、ジブチ共和国、スーダン共和国、ソマリア民主共和国、大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国、チャド共和国、チュニジア共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モロッコ王国

