世界一周「何でもレポート」
チャレンジ!外国語 外務省の外国語専門家インタビュー
ヒンディー語の専門家 椿本さん
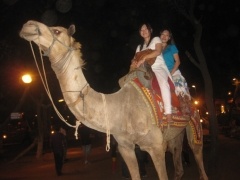

ヒンディー語の専門家 椿本(つばきもと)さん
नमस्ते! ナマステー!
椿本さんが外務省に入省したのは平成19年。研修言語として,第一に英語,第二にヒンディー語を希望しました。「大学を卒業した当時,報道などでBRICs(ブラジル,ロシア,インド,中国を表す略語)が盛んに話題になっていました。外務省への入省が決まり,これから仕事をしていく上でどの国を専門としていけばよいかと考えたときに,インドはこれから面白いかもしれないと思ったんです。」
この時,初めてインドという国を意識した椿本さん。研修語は希望通りのヒンディー語となりましたが,当初は「ナマステってヒンディー語だったんだ!?」というほど,ヒンディー語の知識はゼロ。初歩からの学習となりました。
椿本さんによれば,ヒンディー語の文法は規則的で難解さはなく,初習者にも学びやすいとか。サンスクリットの文字としても使われる独特の「デーヴァナーガリー文字」も,一見難解に見えますが,ルールは簡単で,「ローマ字のような感覚で子音字と母音字の組み合わせさえ覚えてしまえば,後は書いてあるとおりに読めばいいんです。」
とはいえ,もちろん日本語にはない発音もあります。ヒンディー語には無気音と,強く息を出して発音する有気音があるため,初習者はその区別から覚えます。最初のうちはその違いを習得するために,口の前に紙を立て,無気音のときは紙が動かないように,有気音のときはひらひら動くようにと発音の練習を繰り返したそうです。

ちなみに,はじめてヒンディー語を耳にしたときの印象は?
「『なんとかかんとか,フーン!』『なんとかかんとか,ヘー』と・・・語尾が面白いな,というのが最初の印象でしたね(笑)」
「フーン」というのは,「私は○○です」の「です」にあたる述語部分。学習するうちに,実はこの文末の部分にヒンディー語の面白さがあることに気づいたそうです。「ヒンディー語では主語や述語など,柔軟に語順を変えて文を組み立てることが可能なんです。単語を入れ替えて文末の語尾をそろえ,韻を踏ませることによって詩的なリズムを生んだり,ニュアンスを変えたりすることができます。日常会話に使われることはあまりないですが,政治家の演説などを聞いていると,その特徴をいかし,韻を合わせて美しい響きを持たせたり,主張したい点を強調したりと,自由度が高くてアレンジがきくところがとても面白い言葉だなと思います。」
単語の数の多さも特徴の一つ。「ヒンディー語は様々な地域の言語が一体となってできた言葉なので,インドではヒンディー語だけでなく,ウルドゥー語やサンスクリット語,英語などの単語を使うこともよくあります。例えば,『愛』を表す単語は4つもあります。これは極端な例ではありますが,一般的に一つの意味に対してヒンディー語の単語とウルドゥー語の単語が使用されることは多く,片方だけ覚えていても別の方の単語が使われるとわからなくなってしまうので,両方覚えるのが一苦労です。ウルドゥー語系の単語には少し詩的な響きがあり,歌や映画で使われることが多いなど,使用する単語によって文章のニュアンスも異なってきます。」

クジャクの声で目覚める
インドでは2年間,デリーにあるジャワハルラール・ネルー大学の寮で研修生活を送りました。「敷地内は広大な森に囲まれ,野生動物もたくさんいて,まるでジャングルみたいでした。朝はクジャクの鳴き声やバサバサっという羽根の音で目が覚めたり,歩いているとヤマアラシが目の前を横切っていったり・・・。」
優雅にも聞こえますが,やはりインドの夏の暑さは過酷。夏場,室内の温度は夜中でも40度以上になります。エアコンはなく,天井にはファンがついているだけ。
「暑くて眠れないので,パジャマを着たままシャワーを浴びて全身を濡らし,ファンの風にあたって気化熱で体を冷やして寝ていました。外国からの留学生はよくその方法で寝ていましたね。」しかし,夜中の12時頃からは「パワーカット」と称して頻繁に電気が停まってしまいます。「電気が停まった瞬間,室温が上がって目が覚める。眠れなくて外に出ると,みんな同じように外を徘徊していて,『また停まったよ』と愚痴を言い合って(笑)・・・とにかくずっとサウナにいるような状態で,どこにいっても暑さから逃れられないのが辛かったです。あまりの暑さに,これはもう危ないと思ってシャワーの蛇口をひねると,そんなときに限って水も止まっていたり(笑)何とか正気を保って,がんばれ,がんばれ,って自分に言っていました。」
ある時には大雨で水道管が壊れ,蛇口から下水が出てくるという事態に。修理に2週間もかかり,その間毎日給水車から水を運び,お湯を使うためにバケツの水に電熱コイルを直接さしこんで温めていたそうです。「コイルで感電しそうになったり,うっかりバケツを溶かしてしまったことも。まるでキャンプ生活のようでしたね(笑)。
一方で,こういった経験以上に,インド人の友達の寮を訪ねてお茶を飲みながらインドや日本のことについて話し合ったり,友達と色んな寮のご飯を食べに行ってインド料理について教えてもらったりと,楽しい経験もとても多かったです。」
大変な経験も楽しい経験も共有することで,インド人と心から信頼できる友達になれた気がしたそうです。

ボリウッド映画で語学力アップ
椿本さんの考える現地での語学力アップのコツは,何といっても趣味なども含め,好きな分野を見つけること。「私の場合は映画音楽でした。いわゆるボリウッド映画では,節目節目に音楽が流れて俳優が踊り出すんですが,そういう映画音楽を専門に歌うとても声のよい歌手がいてファンになり,その音楽に惹かれて映画をたくさん見るようになりました。好きになった作品は何度も見て,気になるフレーズは先生に意味を聞いて単語ノートを作り,繰り返し聞いて覚えました。映画では日常会話が使われるので役に立ちましたし,好きなものだから何度繰り返し見ても飽きずに楽しく,とても効果がありましたね。」
インドの人々から学んだこと
現地での研修中は語学力向上のため,なるべく日本人とは会わず,インド人とだけ過ごすようにしていました。最初は精神的に辛かったものの,次第に会話が上達すると,むしろインド人の中で過ごす方が心地よくなったとか。なぜなら,「彼らの中にいるととても楽。ゆったりしていて,細かいことは気にしないし,ミスをしても大らかに許してくれます」。もちろん相手のミスはこちらもスルーする度量が必要。昔は割と短気でイライラすることも多かったという椿本さんですが,気づけばほとんど怒ることがなくなっていたそうで,「インドの人から,大らかな気持ちを学んだかもしれません。」
寛容なインドの人々ですが,日本人として気をつけるべき点も。「よく,一部の混沌としたイメージだけにとらわれて,『何でもありの国だろう』というような考えでいくと,当然そうではなく,一見フレンドリーに見えて慎重なところがあったりもします。また,インドにはイスラム教徒,ヒンドゥー教徒,シーク教徒,キリスト教徒,仏教徒等,多くの宗教の信者が共存して,日本人には理解しにくい宗教観で自分たちの宗教を信じ,それぞれの宗教にあわせたカレンダーや戒律のもとで生活しています。たとえばベジタリアンというと,日本人的発想では少しくらいの肉は大丈夫だろうと考えがちですが,インドでは宗教的な信念に基づいた,生き方に関わる問題です。当然ではありますが,宗教を始め,私たちとは違う生き方や考え方に十分配慮し,尊重する姿勢が大事です。」
基本的にインドの人たちは親切で,日本人に対して何の偏見もなく好意的。先入観をもたずに個人を見て判断してくれるので,とても接しやすいそうです。ただし,インドは思ったことは遠慮なく主張する社会でもあります。「はっきり言葉に出して自分の考えを主張しないと,先手を打たれる感じはありますね。イヤなものはイヤ,欲しければ欲しい,とどんどん前に出ていかないと。」また,インドでは体面や形式を重視するあまり,問題があってもごまかされてしまったりと,悩まされることも多々・・・。

“Unity in Diversity” インドの多彩な魅力
インドは地方により文化や民族も様々。「北の山の方は中国に近く,日本人のような顔をしている人も見かけますし,食事も中華やチベット料理に似ています。北でもデリーなどのあたりは,日本でもよく食べるような,カレーとナンやチャパティといったパン食が多いです。コルカタなどの東では魚食文化も存在し,カレーにも魚を入れたりします。南は米食で,料理にもココナッツを入れたり,比較的東南アジアに近くなります。気質も南は暖かいせいか,のんびりと陽気な人が多いんですが,北の方では短気な人が多くて,道ばたでよくけんかする人を見かけましたね(笑)。
インドでは『Unity in Diversity』といって,色々な民族や文化が集まっているけれども,みんな,自分たちはインド人だという意識を心に持っているように感じます。多様でありつつ,インドというまとまりを感じさせるところが,とても魅力的な国だと思います。」
多様で奥深い魅力を備えるインド。他国と比べて日本との個人レベルでの交流はまだそれほど盛んとはいえませんが,「インドの魅力を皆さんに知ってもらって,インドから日本,日本からインドと,留学や観光などを通して個人レベルでの関係が強まるといいなと思っています。」
好きな言葉・便利なフレーズ
कोई बात नहीं|
(コーイー・バート・ナヒーン)= 大したことないよ,大丈夫
インドにいるとき,こちらが謝ったり,お願いを聞いてもらって御礼を言ったりすると,たいていこのフレーズを使って「全然大丈夫だから気にしないで」と答えてくれました。私にとってインド人のおおらかさを感じるフレーズです。

インドの楽しみ方
インド流オシャレ
インドでの生活は大変というイメージがありますが,日本からの駐在員や出張者に接していると,実は多くの場合,男性よりも女性の方が,より現地の生活を楽しんでいるように思えるそうです。「インドの人はとてもオシャレ好きなんです。道ばたで『メヘンディ』と呼ばれる伝統的なボディアートを楽しんだり,好きな布を選んで好みのデザインの服を仕立てたり,腕輪などのアクセサリーもいろんな種類があって,女性ならではの楽しみがいっぱい。それもすべてが安いんです。」

おすすめスナック
カレーに代表される豊かな食文化もインドの魅力の一つですが,椿本さんにとっての最も忘れられない味は,屋台で食べたスナック。「『ダヒー・プーリー』というんですが,初めて食べた瞬間,インド人は天才だ!と思いました。こんなにおいしいものがあるのか,よくぞこの味を思いついたと・・・」
形はピンポン球に似て,外側は春巻きの皮のようにかりっと揚げられたボール状のものに指で穴を開け,そこにジャガイモやスパイスの具を入れて甘辛い液体に漬けて食べるパーニー・プーリーというスナックが原型。こちらはソースが漏れないうちに急いで食べると,お店の人が一個,また一個とお皿に追加してきて,まるでわんこそばのように食べるのが楽しいスナックです。ダヒー・プーリーは,甘辛い液体につける前のパーニー・プーリーを皿に並べ,上からヨーグルト等のソースをかけてアレンジしたものです。なかなか想像し難い味ですが,椿本さんはこの「日本には絶対にない不思議な味」を求め,各地のダヒー・プーリーを食べ比べたそうです。

おすすめスポット
観光面では,バックパッカーによる苦労話はよく聞くところ。日本人の間では「遠い」「汚い」というイメージもありますが,椿本さんが声を大にして言いたいのは,「インドはそれだけではありません!」それなりの費用を出せば快適で,それなりにサービスの行き届いた滞在ももちろん可能。食事もおいしく,エステ等を楽しんだり,リゾート地として優れた面があることも知ってほしいと思っています。
特に椿本さんのおすすめはインド南方のケーララ地方。「バックウォーターという大きな湖があるのですが,そこにハウスボートを貸し切って美しい自然の中を遊覧したり,専属シェフもついて,ボートの中に宿泊することもできるんです。」それほど高額でなくても日本では味わえないリゾート気分が満喫できるのも,まだあまり知られないインドの楽しみ方かもしれません。

