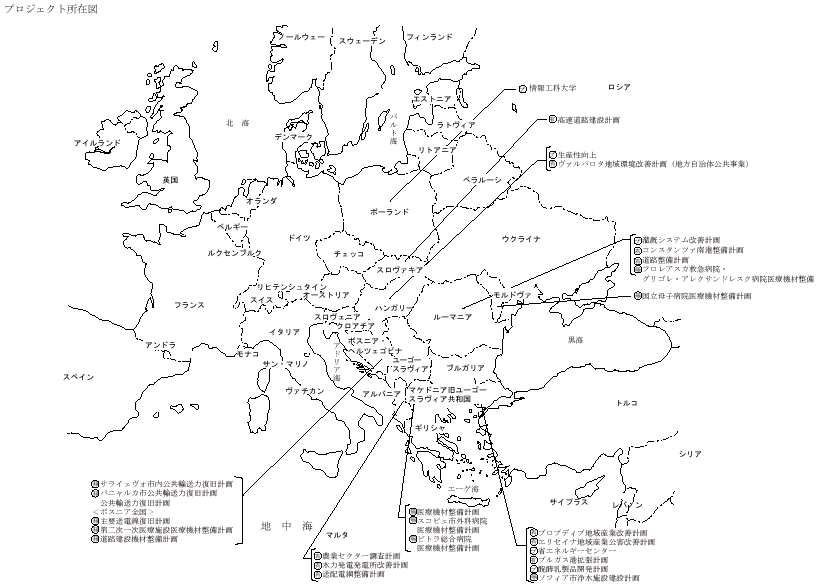国別援助実績
1991年~1998年の実績
[17] ラトヴィア
(1) ラトヴィアは、1991年9月、ソ連からの独立を達成した。98年10月成立した中道右派3党から成る少数連立政権のクリシュトパンス内閣は、99年7月には連立与党への不信感からクリシュトパンス首相が辞任し、シュチューレ前首相率いる中道右派政権が成立した。また同月、バルトで初めて女性のヴィーチェ-フレイベルガ大統領が誕生した。現政権は前政権同様、EU統合に向けての改革の促進を目標として掲げている。
(2) 経済面では、ラトヴィアは木材、輸送機器、軽工業製品、食品などの製造業を主要産業としている。独立後、IMFの勧告に沿って経済改革を進め、価格の自由化、農産物に対する補助金の撤廃等の措置が取られ、92年に960%に達していたインフレ率は93年には35%に下がり、94年にはGDP成長率が独立後初めてプラスに転じた。95年に入って銀行危機が顕在化し、国内最大のバルチヤ銀行を含む10行が破産宣告を受けたことから、経済全体に悪影響が及び、成長率は再びマイナスとなったが、95年12月に成立したシュチェーレ内閣は中央銀行とともに金融機関に対する引き締めを行い、経済は回復を見せ、96年のGDP成長率も2.8%となった。98年3月以降は、対ロ関係の悪化及びロシア経済危機の影響を受け、成長は鈍化の傾向が見られる。貿易は94年に入超に転じて以来、95年以降貿易収支の赤字を記録している。95年のEU諸国との自由貿易協定発効後、EU諸国との貿易が飛躍的に拡大しており、主要貿易国としてはEU諸国が輸出、輸入とも約5割を占めている。
(3) 外交面では、政治、経済、安全保障面での欧州への統合のため、EU加盟とNATO加盟を希望するとともに、バルト諸国をはじめとする近隣諸国との友好関係の維持に努めている。98年1月には、ワシントンで「米国、エストニア、ラトヴィア、リトアニア間のパートナーシップ憲章(いわゆる米・バルト憲章)」に調印している。この憲章は、米国
(参考1) 主要経済指標等
| - | 90年 | 95年 | 96年 | 97年 | |
| 人口(千人) | - | 2,516 | 2,490 | 2,465 | |
| 名目GNP | 総額(百万ドル) | - | 5,708 | 5,730 | 5,995 |
| 一人当たり(ドル) | - | 2,270 | 2,300 | 2,430 | |
| 経常収支(百万ドル) | - | -16 | -280 | -441 | |
| 財政収支(百万ラッツ) | - | - | -44.13 | 23.34 | |
| 消費者物価指数 | - | 160.4 | 186.9 | 199.1 | |
| DSR(%) | - | 1.6 | 2.4 | 4.4 | |
| 対外債務残高(百万ドル) | - | 462.6 | 474.9 | 503.3 | |
| 為替レート(年平均、1USドル=ラッツ) | - | 0.528 | 0.551 | 0.581 | |
| 分類(DAC/国連) | 移行国/- | ||||
| 面積(千㎞2) | 62.1 | ||||
(参考2) 主要社会開発指標
| - | 90年 | 最新年 | 90年 | 最新年 | ||
| 出生時の平均余命 (年) |
- | 68(97年) | 乳児死亡率 (1000人当たり人数) |
- | 15(97年) | |
| 所得が1ドル/日以下 の人口割合(%) |
- | <2(93年) | 5歳未満児死亡率 (1000人当たり人数) |
- | 19(97年) | |
| 下位20%の所得又は 消費割合(%) |
- | 8.3(95年) | 妊産婦死亡率 (10万人当たり人数) |
- | 15(90-97年平均 | |
| 成人非識字率(%) | - | 0(95年) | 避妊法普及率 (15-49歳女性/%) |
- | - | |
| 初等教育純就学率 (%) |
- | 90(96年) | 安全な水を享受しうる 人口割合(%) |
- | - | |
| 女子生徒比率 (%) |
初等教育 | - | 48(96年) | 森林面積(1000km2) | - | 29(95年) |
| 中等教育 | - | 51(96年) | ||||
がバルト三国の防衛に法的義務を負うことを保証するものではないが、バルト三国側のNATO加盟に対する熱意を歓迎するとしている。99年2月には、WTO(世界貿易機関)の加盟国となった。対ロシア関係で大きな課題は、住民の約3割を占めるロシア語系住民への国籍付与問題及び国境画定問題である。ロシア政府からのロシア語系住民に対する人権侵害の批判に対しては、98年10月にOSCEの勧告を基に国籍法改正を行い、社会統合に取り組んでいる。国境画定問題については、国境画定案は確定したが、署名に至っていない。
(4) 我が国との関係では、96年7月ビルカフス外相、98年2月サウスニーティス経済相、同年12月ウルマニス大統領が訪日している。
(1) ラトヴィアが、91年のソ連からの独立以来、民主化及び市場経済化に積極的に取り組んでいることや良好な二国間関係を踏まえ、これまで、輸銀による世銀及び欧州復興開発銀行(EBRD)との協調融資、種々の招へい等の非ODAスキームにより国際収支支援や社会資本整備支援等の援助を実施してきている。
(2) 96年度より我が国の有償資金協力、技術協力の供与対象国とし、96年10月には、経済協力政策協議を実施し、先方からは3主要港の再開発、電力開発、民活インフラ、環境等の分野への協力について期待表明があった。この結果を踏まえ、98年4月に環境分野のプロジェクト形成調査団を派遣し、関連情報収集及び案件形成支援を行った。技術協力では、96年度より研修員の受入れを開始し、98年度からは専門家派遣を実施している。
| 年度別・形態別実績 | (単位:億円) |
| 年度 | 有償資金協力 | 無償資金協力 | 技術協力 | ||||||||||
| 96 | なし | なし | 0.03億円
|
||||||||||
| 97 | なし | なし | 0.13億円
|
||||||||||
| 98 | なし | 0.42億円
|
0.35億円
|
||||||||||
| 98年度 までの 累計 |
なし | 0.42億円 |
0.52億円
|
(注)1.「年度」の区分は、有償資金協力は交換公文締結日、無償資金協力及び技術協力は予算年度による。(ただし、96年度以降の実績については、当年度に閣議決定を行い、翌年5月末日までにE/N署名を行ったもの。)
2.「金額」は、有償資金協力及び無償資金協力は交換公文ベース、技術協力はJICA経費実績ベースによる。
(参考) 98年度実施開発調査案件
案 件 名 |
| ルバナ湿地帯総合管理計画事前調査(S/W協議)(水文・水理) ルバナ湿地帯総合管理計画事前調査(S/W協議)(土地利用計画(GIS)) |