(2)債務問題への取組
公的金融による支援は、開発途上国の経済成長を促進するために活用されますが、マクロ経済環境の悪化等によって、受け入れた資金の返済が困難となった場合、途上国は過剰の債務を抱えることとなり、持続的成長を阻害する要因となり得ます。本来は、債務国自身が改革努力などを通じて、自ら解決しなければならない問題ですが、過大な債務が途上国の発展の足かせになっている場合、国際社会による対応が必要になります。
債務問題への国際的な取組については、これまでも重債務貧困国(HIPC)解説に対する拡大HIPCイニシアティブ注7やパリクラブ注8のエビアン・アプローチ注9などで債務救済が実施されています。しかし、近年、一部の低所得国においては、債務救済を受けたにもかかわらず、再び公的債務が累積し、債務持続可能性が懸念されています。この背景として、債務国側では、自国の債務データを収集・開示し、債務を適切に管理する能力が不足していること、債権者側では、資金供給の担い手が多様化しており、パリクラブによる貸付割合が減少する一方で、担保付貸付等の非伝統的かつ非譲許(じょうきょ)的な貸付を含む、新興債権国や民間債権者による貸付割合が増加していることが指摘されています。
2020年4月、新型コロナウイルス感染症の拡大による低所得国への影響に対処するため、G20およびパリクラブは、これら諸国の公的債務の支払いを一時的に猶予(ゆうよ)する「債務支払猶予イニシアティブ(DSSI)」に合意し、2020年11月には、「DSSI後の債務措置に係る共通枠組」注10(以下、「共通枠組」)に合意しました。2021年10月に開催されたG20ローマ・サミットで発表されたG20ローマ首脳宣言において、暫定的な推計によれば、DSSIの下で、2020年5月から2021年12月までに、50か国が恩恵を受け、少なくとも合計127億ドルの債務支払猶予が行われた旨が記載されています。DSSIは2021年12月末に失効したことから、今後は「共通枠組」の下での債務措置を迅速に実施する必要があります(関連する日本の対応については、「ア 危機に対応するための経済財政支援」を参照)。
低所得国をはじめとする各国の債務持続可能性に大きく影響を与え得る要素の一つとして、インフラ投資が挙げられます。港湾、鉄道といったインフラ案件は額が大きく、その借入金の返済は借りた国にとって大きな負担となることがあります。インフラ案件への融資を行う場合には、貸す側も借りる側も債務持続可能性について十分に考慮することが必要です。債務持続可能性を考慮しない融資は、「債務の罠」として国際社会から批判されています。
「質の高いインフラ投資に関するG20原則」注11には、個々のプロジェクトレベルでの財務面の持続可能性に加え、国レベルでの債務持続可能性を考慮することの重要性が盛り込まれているほか、開放性、透明性、ライフサイクルコストを考慮した経済性といった原則も盛り込まれています。G20各国は自らが行うインフラ投資においてこれらの原則を国際スタンダードとして実施すること、また融資を受ける国においてもこれらの原則が実施されるよう努めることが求められています。
キルギス
税務局人材育成システム向上プロジェクト
技術協力プロジェクト(2017年7月~2020年11月)
キルギスでは、2015年のユーラシア経済同盟加盟後、国内税制度が大きく変更されたこともあり、税務に携わる職員の税制に対する理解向上を図るため、職員の能力強化が不可欠となっていました。キルギス国内には本局と62の税務署などに約2,200名の職員が配属されています注1が、国土の98%が山間部で4,000m級の山脈が東西南北を分断しているため、地方の職員が首都ビシュケクでの研修に参加することが難しいケースがあり、また首都での研修の体制自体も十分に整備されていませんでした。
そこで、日本は、地方職員の能力向上を図るため、遠隔地教育(eラーニング)システムを活用して人材育成を支援しました。
日本人専門家は、キルギス税務局と共に人材育成計画を策定し、新入職員、中堅職員および納税者教育担当職員向けの3コースを対象に、キルギス語にも対応したデジタル教材を開発しました。パソコンで受講できない職員向けにスマートフォン用アプリケーションも導入するなど、現地の実情に合わせた開発を行い、新型コロナウイルス感染症の拡大後もプロジェクトを継続した結果、当初目標の300名を大幅に上回る585名が研修を受講した上、受講者の満足度も9割以上となりました。
さらに、プロジェクト期間中には、キルギス税務局も独自に2つの研修コースを開発し、研修担当職員が2名増員されるなど、キルギス自身が主体的に研修を展開できる体制を整えました。本プロジェクトの成果を踏まえて、今後もキルギス税務局が持続的な人材育成を行い、同国の税務行政が改善されることが期待されます。
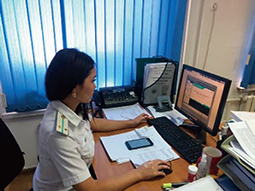
遠隔地教育システムを利用し、新入職員のための税務研修を受講するビシュケク市内の税務署職員

キルギス税務局ワーキング・グループのメンバーとJICA専門家が共同で研修教材を開発している様子(写真:(一社)金融財政事情研究会)
注1 2020年10月時点(事業完了報告書)。
●日本の取組
日本は、円借款の供与にあたって、被援助国の協力体制、債務返済能力および運営能力、ならびに債権保全策などを十分検討して判断を行っており、ほとんどの場合、被援助国から返済が行われていますが、例外的に、円借款を供与する時点では予想し得なかった事情によって、返済が著しく困難となる場合もあります。そのような場合、日本は、前述の拡大HIPCイニシアティブやパリクラブにおける合意等の国際的な合意に基づいて、必要最小限に限って、債務の繰延注12、免除、削減といった債務救済措置を講じています。2020年末時点で、日本は、2003年度以降、33か国に対して、総額で約1兆1,290億円の円借款債務を免除しています。なお、2020年に引き続き、2021年も円借款債務の免除実績はありませんでした。
日本は、「質の高いインフラ投資に関するG20原則」の重要な要素である債務持続可能性の確保の観点からも、JICAによる研修や専門家派遣、国際機関への拠出等を通じ、途上国の財務省幹部職員の公的債務・リスク管理に係る能力の向上に取り組んでいます。たとえば、ガーナ、ザンビア等21か国41名の行政官に対する偶発債務リスク管理に係る世界銀行との連携による研修、国際通貨基金(IMF)・世界銀行の各信託基金への新たな資金拠出など、債務国の能力構築に向けた支援を実施しています。
用語解説
- 重債務貧困国(Heavily Indebted Poor Countries:HIPC)
- 貧しく、かつ重い債務を負っているとして、包括的な債務救済枠組である「拡大HIPCイニシアティブ」の適用対象となっている、主にアフリカ地域を中心とする開発途上国。2021年6月末にスーダンが同イニシアティブの下での決定時点に到達し、同イニシアティブが適用される38番目の国となった。
- 注7 : 1999年のケルンサミット(ドイツ)において合意されたイニシアティブ。
- 注8 : 特定の国の公的債務の繰延に関して債権国が集まり協議する非公式グループ。フランスが議長国となり、債務累積国からの要請に基づき債権国をパリに招集して開催されてきたことから「パリクラブ」と呼ばれる。
- 注9 : 「パリクラブの債務リストラに関する新たなアプローチ(エビアン・アプローチ)」。重債務貧困国以外の低所得国や中所得国が適用対象となり、従来以上に債務国の持続性に焦点を当て、各債務国の状況に見合った措置を個別に実施する債務救済方式。
- 注10 : 「共通枠組」は、新興債権国をはじめとする非パリクラブ国を巻き込んだ形で、合同で債務措置の条件を確定することを初めて約束したもの。用語解説も参照。
- 注11 : 用語解説「質の高いインフラ」を参照。
- 注12 : 債務救済の手段の一つであり、債務国の債務支払の負担を軽減するために、一定期間債務の返済を延期する措置。
