第4節 平和で安全な社会の実現と地球規模課題への取組
●法の支配
開発途上国の「質の高い成長」による安定的な発展のためには、インフラ(経済社会基盤)の整備とともに、法の支配の確立、グッドガバナンス(良い統治)の促進、民主化の促進・定着、女性の権利を含む基本的人権の尊重等が鍵となります。特に、法の支配は、国内において公正で公平な社会を実現するための不可欠の基礎であると同時に、友好的で対等な国家間関係の基盤となっています。日本は、国際社会における法の支配の強化を外交政策の柱の一つとしており、法整備などを通じた各国国内における法の支配の強化にも貢献してきています。このような法制度整備支援は、開発途上国に対し、立法や制度整備およびその理解と定着に向けた取組に対する支援を通じて、グッドガバナンスに基づく開発途上国の自助努力を支援するとともに、持続的成長のために不可欠な基盤作りを支援するものです。
開発途上国において、その経済成長や人権の保障、貧困削減といった目標を達成し、人々が安心して豊かに暮らせるようにするためには、国民の意志を反映した合理的なルールが、公平かつ適正に執行・管理・運用されなければなりません。日本は、JICA、法務省、最高裁判所、日本弁護士連合会、大学関係者等、オールジャパン態勢で、各国のニーズや課題に合わせ、人材育成を中心に、それぞれの開発途上国の法制度・司法制度の整備・改善に向けた取組を支援しています。
日本が、政府開発援助(ODA)により最初に法制度整備支援を実施した国はベトナムです。ベトナム政府は、1986年にドイモイ(刷新)政策を導入し、市場経済に転換するために民商事法の整備・改正に着手しました。こうした流れの中、日本は、同国政府の要請を受け、1996年にODAによる法制度整備支援を本格的に開始し、市場経済の基盤となる民法・民事訴訟法の起草や、法令を実際に運用する人材の育成を、日本の法律専門家の派遣や日本での研修員受入れなどの方法により支援してきました。このような長年の支援が実を結んだ一例として、1999年から日本のODAによる研修員受入制度を通じて名古屋大学に留学し、2003年に博士号を取得したレー・タイン・ロン氏が、2016年4月にベトナムの司法大臣に就任し、活躍されています。

ネパール・カトマンズで行われた民法案含む主要5法案に関するパブリックコンサルテーションの様子(写真:長尾貴子)
ネパールでは、1990年代初頭、民主化を求める人民運動から端を発した政府と反政府勢力マオイスト間の内戦が、1996年から2006年の包括的和平合意締結までの10年間続き、その間多くのネパール人の命が失われました。日本は、内戦後のネパールの民主化を後押しするために、現代社会のニーズや新憲法と法律との乖離(かいり) 、宗教的要素の法的位置付けなど、ネパールの法整備の様々な問題について、支援の必要性を感じ、日本の有識者により構成されるアドバイザリーグループとネパールの法曹関係者との間で慎重に協議しながら、民法草案づくりを含む立法等を支援しました。(「国際協力の現場から」参照)
日本は、2013年5月に改訂された法制度整備支援に関する政府基本方針に基づき、アジアの8か国(インドネシア、ベトナム、ミャンマー、モンゴル、カンボジア、ラオス、ウズベキスタン、バングラデシュ)で重点的に法制度整備支援を展開してきました。一方で、アフリカ諸国に対しても、コートジボワールに司法アドバイザーを派遣し、市民へ法情報の提供を行うコールセンターの設置や、同国を含む西アフリカ周辺8か国の刑事司法関係者を対象に、同国および日本において刑事司法研修を実施したりするなどの支援を行っています。これらの支援は、相手国の自由な社会経済活動や社会の安定に資する法制度の確立に寄与するのみならず、日本企業をはじめとする各国企業が現地で事業を展開しやすくなるという国際社会全体のメリットもあります。
日本が法制度整備支援を含むガバナンスの分野において行ってきた支援の額は、2005年から2014年までの10年間で、約27億ドルに上ります。
法の支配の貫徹のためには、法執行の確保も重要です。日本は政府の不正腐敗対策、武器輸出入管理・取締り、人身取引を含む組織犯罪・テロ対策のため、税関・警察への能力構築支援を行っています。また、日本は海洋国家であり、海洋における法の支配の貫徹のため、ODA等のツールを活用して、船舶の供与や技術協力、人材育成を通じ、開発途上国の海上保安機関等の法執行能力の向上も支援しています。
●自由で開かれたインド太平洋戦略
安倍総理大臣は、2016年8月にケニアで開催されたTICAD(ティカッド) Ⅵにおける基調演説の機会に、「自由で開かれたインド太平洋戦略(Free and Open Indo-Pacific Strategy)」を発表しました。この戦略は、国際社会の安定と繁栄の鍵を握るのは、「2つの大陸」、すなわち成長著しい「アジア」および潜在力溢れる「アフリカ」と、「2つの大洋」、すなわち自由で開かれた「太平洋」および「インド洋」の交わりにより生まれるダイナミズムであるとの考えに基づき、これらを一体としてとらえた外交を進めていくものです。
既に東南アジアおよび南アジアでは民主主義・法の支配・市場経済が根付き、自信・責任・リーダーシップが醸成されています。こうしたアジアの成功を「自由で開かれたインド太平洋」を通じて中東・アフリカに広げてその潜在力を引き出す、すなわち、アジアと中東・アフリカの「連結性」を向上させることで、地域全体の安定と繁栄を促進していくことが重要です。具体的には、東アジアを起点として、南アジア~中東~アフリカへと至るまで、インフラ整備、貿易・投資、ビジネス環境整備、開発、人材育成等を面的に展開するとともに、アフリカ諸国に対し、開発面に加えて政治面・ガバナンス面でも、相手国のオーナーシップを尊重した国づくり支援を行っていきます。
こうした戦略の実施に当たっては、とりわけODAの役割が重要です。たとえば、地域の物流・人流を活性化させる「生きた連結性」を実現するため、日本はODAを活用して、インドにおけるムンバイ・アーメダバード間高速鉄道等、質の高いインフラ投資を通じた物理的連結性の強化のみならず、通関円滑化等の制度的連結性の強化のための支援も進めてきています。また、こうしたインフラや制度を使いこなす人材も不可欠であることから、産業人材・高度人材の育成を積極的に行うとともに、日本とアジア・アフリカの人材交流・ネットワーク構築を後押しし、人的連結性も強化しています。
さらに、地域の連結性を高め、点や線ではなく「面」としての経済圏を創出し、貿易・投資を活性化させ、地域のポテンシャル(可能性)を最大限に発揮させることが極めて重要です。これは日本と国際社会にとってWin-Winの関係をもたらします。日本は、「自由で開かれたインド太平洋戦略」の下、今後とも戦略的にODAも活用し、国際社会の平和、安定および繁栄に貢献していく考えです。
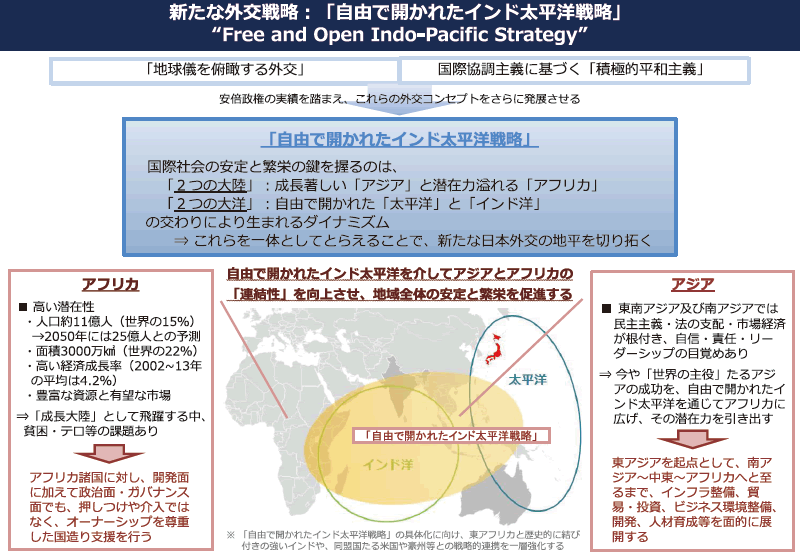
●中東安定化支援
中東地域において、シリア・イラクの難民・国内避難民数は依然として高い水準にあり、非人道的な状況が継続しています。また、難民受入国の負担も増大しているほか、北アフリカ諸国等においても、政治的混乱や若年層の高い失業率に伴い、暴力的過激主義の拡大が懸念されています。このような中東地域に対し、人道支援のみならず、中長期的な観点から、貧困や格差、若年層の雇用問題をはじめ、復興と開発を後押しすることで、中東不安定化の根本原因の解決を促していくことが不可欠です。
日本は、2016年5月に行われたG7伊勢志摩サミットの機会に、「中庸が最善」という考えの下、暴力的過激主義の拡大を阻止し「寛容で安定した社会」を中東に構築するため、今後3年間で約2万人の人材育成を含む総額約60億ドルの支援の実施を表明しました〈注1〉。また、テロとの闘い、財政面での課題や経済の強化に取り組むイラクに対して、日本による5億ドルの新規支援を含め、G7による36億ドル以上の支援を結集しました。加えて、JICA専門家等の人道支援チームである「シリア難民及びホストコミュニティ支援チーム(J-TRaC)」による難民キャンプ等への派遣やシリア人留学生の受入れ拡大を行うことを表明しました。
●気候変動・地球規模問題対策

モロッコ・マラケシュのCOP22の会場に設置された日本パビリオン。日本の低炭素技術を紹介するジオラマが展示されている。(写真:環境省)
地球規模の環境問題は、持続可能な開発に対して重大な影響を与え、一国の努力だけで解決できる水準を既に超えています。地球温暖化防止のためにはすべての国が温室効果ガス排出削減に取り組むことが不可欠である一方で、多くの開発途上国は、自国の経済開発にも取り組まねばならず、自国の資金と実施能力だけでは十分な対策を実施できないというのも現実です。そこで、国際社会は、地球規模での気候変動対策の推進に向け、開発途上国支援に積極的に取り組んできています。
気候変動対策には、省エネルギー、再生可能エネルギー等の低炭素エネルギーの利用推進による温室効果ガスの削減を指す「緩和」と、気候変動によって引き起こされる悪影響(例:海面上昇、干ばつ)の防止・軽減のための「適応」策に大別できますが、日本は、この「緩和」と「適応」の双方の面において、これまでも積極的に開発途上国支援を実施してきています。
2015年にそれまでの長年の交渉の末、京都議定書に代わる新たな枠組みであるパリ協定を採択したCOP21の首脳会合では、安倍総理大臣が2020年に官民合わせて年間1.3兆円の気候変動対策事業が開発途上国で実施されるようにすると表明しました。これは、先進国による「2020年までに官民合わせて1,000億ドルを動員する」との目標の実現(2010年のCOP16決定)に道筋をつけ、パリ協定の合意妥結を大きく後押ししました。また、2016年に入ってからも、10月、先進国側が「1,000億ドルに向けたロードマップ(Roadmap to $ 100 billion)」を発表し、これに対し、11月のCOP22において、開発途上国側から歓迎の意向が示されるなど関連の取組が着実に進展しています。
日本として、今後とも引き続き関係国と連携しつつ、2020年の目標の実現に向け、特に地熱発電や都市鉄道、防災インフラ、水の確保などの日本の得意分野を念頭に、この分野で積極的に開発途上国に手を差し伸べていきます。

2016年11月、高知県黒潮町において開催された「世界津波の日高校生サミットin黒潮」に参加した、日本を含む30か国の高校生たち(国内参加高校生約110名、海外参加高校生約250名)
また、日本は、防災をはじめ、その他の地球規模課題についても、積極的に取り組んできています。
日本は、2015年3月に、第3回国連防災世界会議を仙台で開催しました。2030年までの防災に関する国際的な枠組を規定する「仙台防災枠組2015-2030」の採択を主導し、日本独自の取組として「仙台防災協力イニシアティブ」を発表するなど、国際防災協力を積極的に行ってきています。
また、世界レベルで津波の脅威に対する認識を高め、津波による被害を最小化するため、「世界津波の日」を提案し、2015年12月に国連総会において、142か国の共同提案国を得て全会一致で採択されました。これを受け、2016年には世界各地で津波に関する啓発のための各種会議や避難訓練等を開催しました。さらに、11月には高知県黒潮町で「世界津波の日高校生サミット in 黒潮」を開催し、日本を含む30か国の高校生約360名が参加しました。参加した高校生は、日本の津波の歴史や防災・減災の取組を学ぶとともに、今後の課題や自国での取組等について発表し、サミット全体の成果文書として「黒潮宣言」を採択しました。
●テロ対策支援
世界中に拡がるテロの脅威は、経済社会発展の重大な阻害要因です。そのため、今日、国際社会は一層の連携・協力が求められるとともに、テロへの対処能力を向上させるのみならず、その根源にある暴力的過激主義への対策が喫緊の課題となっています。こうした問題意識の下、2016年5月のG7伊勢志摩サミットでは、日本は議長国として、①テロ対策、②暴力的過激主義に代わる他の意見を表明させる力と寛容の拡大、③能力構築支援を柱とし、国際社会が特に取り組むべき課題に的を絞った「テロ及び暴力的過激主義対策に関するG7行動計画」の発出に向けた議論をリードしました。また、7月には、アフリカにおけるテロ対処能力向上のため、日本が2016年から2018年までに、3万人への人材育成を含む1.2億ドルの支援を実施することを発表しました。さらに、9月の日ASEAN(アセアン)首脳会議では、アジア地域に対する総合的なテロ対策強化策として、①テロ対処能力向上、②テロの根本原因である暴力的過激主義対策、および③穏健な社会構築を下支えする社会経済開発のための取組を、今後3年間で450億円規模で実施するとともに、2,000人のテロ対策人材を育成する旨発表しました。
また、2016年7月のダッカ襲撃テロ事件を受けて同年8月に発表された「国際協力事業安全対策会議」の最終報告においても、開発途上国のテロ対策・治安能力の構築支援を積極的に行うこととしています。
日本は、これらの具体的な実現に向けて、技術協力、無償資金協力および有償資金協力といった二国間協力に加えて、国際機関を通じた協力も有機的に組み合わせながら、重層的かつ効果的な支援を行っています。
たとえば、テロリストや外国人テロ戦闘員の流出入を防ぐため、各国国境管理当局によるインターポールの盗難・紛失旅券等データベースの活用強化に向けた支援について、他のG7や関連国際機関との連携・協力を開始しました。生体認証や爆発物の検知等の分野における先端技術といった日本の持つ強みを活かした協力を通じて各国の水際対策の強化にも取り組んでいます。
また、日本は従来から穏健な社会の構築のための経済社会支援に取り組んでいるとともに、過激化防止に取り組む市民社会の活動支援等にも着手しています。
日本は、国際社会と連携しつつ、一層積極的にテロおよび暴力的過激主義の問題に取り組んでいく考えです。
- 注1 : G7直前の世界人道サミットにおいて、福田政府代表からも表明。
