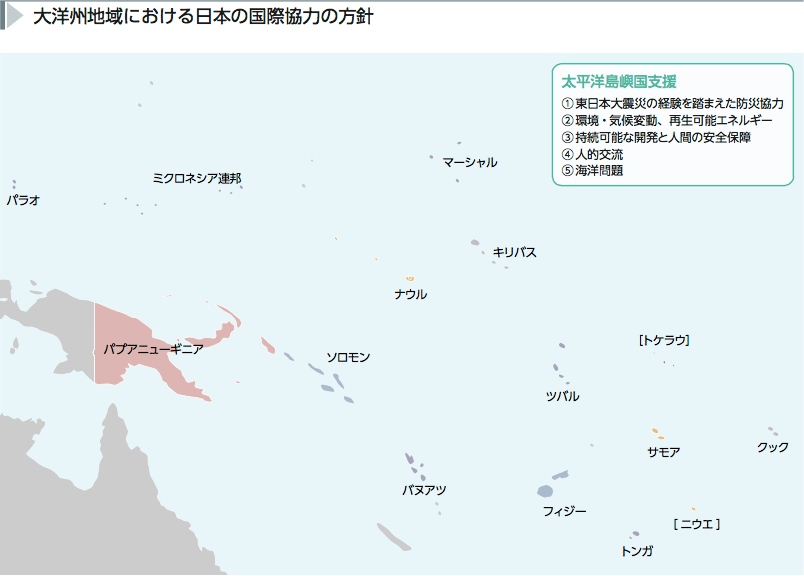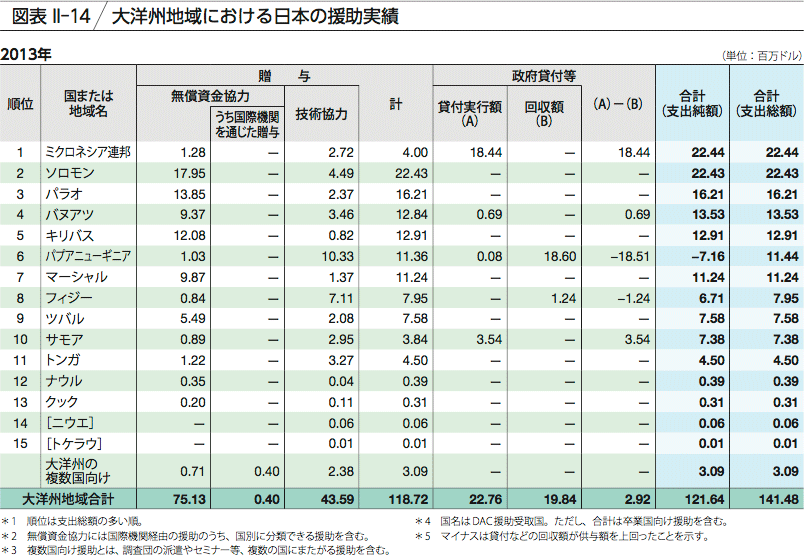7.大洋州地域
太平洋島嶼(とうしょ)国・地域は、日本にとって太平洋を共有する「隣人」であるばかりでなく、歴史的に深いつながりがあります。また、これらの国・地域は広大な排他的経済水域(経済的な権利が及ぶ水域、EEZ)を持ち、日本にとって海上輸送の要(かなめ)となる地域である上、遠洋漁業にとって大切な漁場を提供しています。太平洋島嶼国・地域の平和と繁栄は日本にとって極めて重要です。
一方、太平洋島嶼国・地域には比較的新しい独立国が多く、経済的に自立した国家を築くことが急務です。加えて経済が小規模で、第一次産業に依存していること、領土が広い海域に点在していること、国際市場への参入が困難なこと、自然災害の被害を受けやすいこと、海面上昇により国土を失ってしまう可能性があることなど、島嶼国・地域に特有の共通の問題があります。さらにフィジーでは、民主化に向けた取組を進めています。このような事情を踏まえ、日本は太平洋島嶼国・地域の良きパートナーとして、各国・地域の事情を考慮した援助を実施しています。
< 日本の取組 >

2014年9月、ソロモンを訪問し、ソアラオイ外務・貿易大臣と握手を交わす宇都隆史外務大臣政務官

トンガでそろばんを持ってポーズをとる子どもたち(「日本のそろばんと島国の子どもたち『国際協力の現場から』」をご覧ください)(写真:長岡由佳)
太平洋島嶼国・地域における政治的な安定と自立的経済発展のためには、社会・経済的な脆弱(ぜいじゃく)性の克服や地域全体への協力が不可欠です。日本は、太平洋島嶼国・地域で構成される地域協力の枠組みである太平洋諸島フォーラム(PIF)(注8)との協力を進めるとともに、1997年以降、3年ごとに日本と太平洋島嶼国・地域との首脳会議である太平洋・島サミットを開催しています。
2012年5月に沖縄県名護市で開催された第6回太平洋・島サミットでは、「We are Islanders:広げよう太平洋のキズナ」というキャッチフレーズの下、日本は、①自然災害への対応、②環境・気候変動、③持続可能な開発と人間の安全保障、④人的交流、⑤海洋問題という5本柱に沿って協力を進めるため、今後3年間で最大5億ドルの援助を行うべく最大限努力することを表明しました。この支援の5本柱の一つである「自然災害への対応」では、東日本大震災の教訓を共有しつつ、太平洋災害早期警報システムの整備などの協力を行っていくこととしています。
また、2013年10月には太平洋・島サミット第2回中間閣僚会合を開催し、第6回太平洋・島サミットのフォローアップ、次回のサミットに向けた準備、太平洋島嶼国共通の課題と協力についての意見交換を行いました。太平洋島嶼国・地域は、環境・気候変動、教育や保健などの分野においても課題を抱えており、これらの国々の持続的な発展のため、日本は、各国への協力のみならず、太平洋島嶼国・地域全体の利益を考慮した地域協力を実施しています。
たとえば、気候変動による影響が大きく、自然災害を受けやすい太平洋島嶼国・地域の防災能力を向上させるために、住民が適切に避難できる体制づくりなどを支援しています。また、サモアにある地域国際機関である太平洋地域環境計画(SPREP)と連携し、各国の国家廃棄物管理計画の策定や廃棄物管理に携わる人材の育成を支援しています。
- 注8 : PIF加盟国・地域:オーストラリア、ニュージーランド、パプアニューギニア、フィジー、サモア、ソロモン、バヌアツ、トンガ、ナウル、キリバス、ツバル、ミクロネシア連邦、マーシャル、パラオ、クック、ニウエ
●パプアニューギニア
道路補修機材整備計画・道路整備能力強化プロジェクト
無償資金協力・技術協力プロジェクト(2013年11月~実施中)

贈与された建機を用い、公共事業省職員に対して、実際に道路整備を行いながら技術移転を実施している(写真:中田康雄/株式会社アンジェロセック)

パイロット事業開始に当たっての住民説明会。地方の未舗装道路を対象として実施するパイロット事業に対する周辺住民の期待は大きい(写真:中田康雄/株式会社アンジェロセック)
パプアニューギニアには総延長約8,700kmの国道がありますが、その64%が舗装されていない砂利道です。道路の維持管理も不十分なため、特に地方ではその9割が悪路のまま残されています。また、地形が険しく、雨季には全国各地で地滑りや洪水などが発生し道路が寸断されてしまいます。
こうした状況を改善するため、日本は、道路整備機材の不足・老朽化の問題に対し、無償資金協力「道路補修機材整備計画」を通じ、モロベ州、西ハイランド州、東セピック州、西ニューブリテン州の4州に対して道路整備機材を供与しました。これとあわせてもう一つの課題であるパプアニューギニアの公共事業省の職員の能力向上のため、供与された機材の運転・整備などを含む、技術協力「道路整備能力強化プロジェクト」を実施しました。パプアニューギニアが舗装されていない道路の維持管理や災害対策を適切に行うことができるよう、総合的な支援を行っています。
今後、このプロジェクトによりパプアニューギニア公共事業省の道路維持管理能力が向上することで、地方においても人々が教育・保健などの社会サービスを利用しやすくなったり、農産物の消費地への輸送コストが低減するなど、隔絶された地域の住民の所得を向上させる機会の増加につながることが期待されます。(2014年8月時点)
●フィジー/ソロモン
大洋州地域コミュニティ防災能力強化プロジェクト
技術協力プロジェクト(2010年10月~2013年10月)

建設した避難所は120名の村人を収容可能で、2基の貯水タンクにより飲み水および生活用水が確保されている(ソロモン)(写真:JICA)

ナワンガルア村での避難訓練風景(フィジー)(写真:JICA)
太平洋地域の島嶼国は国土が拡散している国が多く、台風、地震、津波、火山噴火などの自然災害に対して脆弱な地域です。この地域では、島の都市・村落間はもちろんのこと本島・離島間の情報通信や輸送は必ずしも容易ではありません。そのため、災害情報が住民まで迅速かつ的確に伝達されず、災害時の緊急援助も届きにくい状態でした。フィジーやソロモンもその例外ではありませんでした。
このプロジェクトでは、フィジーとソロモンにおいて中央政府レベル、コミュニティレベルでの防災能力の強化を支援しました。両国の気象局や水公社(フィジー)ならびに水資源局(ソロモン)に対し、水位計や雨量計などを設置して、洪水予測に関する気象データの収集能力や、洪水が起こった場合のデータ解析などの洪水予測能力を強化しました。また、気象局や水公社・水資源局の出す災害・避難情報(警報)を国家災害管理局やコミュニティレベルへ速やかに伝達できる体制を強化しました。さらに、コミュニティでの防災計画体制を整備するため、簡易型雨量計の設置やハザードマップの作成、住民向け防災啓発活動や避難訓練の実施など、ハードとソフトの両面で支援を実施しました。
ほかにも、日本は太平洋島嶼地域に対して、自然災害に強い社会を構築するための支援として、気象観測能力、地震・津波観測能力の向上や、予警報伝達体制の強化に対する支援など、災害に強い社会づくりに向けて包括的な支援を実施しています。今後もこれらの支援を継続して、この地域の防災・減災に貢献していきます。