3 科学技術外交
2015年9月に岸田外務大臣によって任命された岸輝雄外務省参与(外務大臣科学技術顧問)は、外務大臣の活動を科学技術面でサポートし、各種外交政策の企画・立案における科学技術の活用について外務大臣及び関係部局に助言を行う役割を担っている。また、内外の科学技術分野の関係者との連携強化を図りながら、日本の科学技術外交についての対外発信にも取り組んでいる。
2016年には、外務大臣科学技術顧問を座長とする「科学技術外交推進会議」の会合を3回行った。また、同顧問の下で有識者及び政府関係部局を交えて開催された日米協力、海洋・北極、保健及び国際協力の4分野のスタディ・グループ会合では、科学的根拠に基づく政策決定の重要性が強調された。こうした取組の結果、G7伊勢志摩サミットの成果文書には、科学的知見に基づく海洋資源の管理等のための海洋観測強化の支持及び医療データ分野での国際協力の重要性が記載された。また、同顧問は、第6回アフリカ開発会議(TICAD VI)に向け、人材育成を通じたアフリカの科学技術水準の向上及び研究開発成果の社会全体への還元の2点を柱とする提言を外務大臣に提出し、同会議がケニアで開催された際、関連イベントに出席し、また現地の科学技術関連施設の視察や関係者との意見交換を行った。

また、同顧問は米国、英国、ニュージーランド等の各政府の科学技術顧問と共に各種国際会議に出席し、顧問の役割や科学的知見を外交政策に生かす方法等につき意見交換を行う等、ネットワーク構築に当たった。
さらに、同顧問は、日本の優れた科学技術力について発信を高めるべく、内閣府と外務省の連携による科学技術イノベーションの対外発信事業(5)を欧州諸国にて行った(6)。このほか、5月24日に都内で開催した科学技術外交シンポジウムを始め国内及び国外での各種フォーラム等で、日本の科学技術外交の取組について広く発信している。
日本は47の国・機関を対象とする32の科学技術協力協定を締結しており、これらの国々と定期的に、協定に基づく合同委員会を開催して政府間対話を行っている。2016年は、スウェーデン、フィンランド、カナダ、米国、インドネシア、英国及びドイツの7か国との間でそれぞれ合同委員会を開催し、関係省庁・機関も出席の下、多様な分野における協力の現状、今後の方向性などを協議した。また、関連内容のセミナー・フォーラムや施設見学等の関連行事への参加・実施を通じて、各国との科学技術交流の促進に寄与した。特に、インドネシアとは34年ぶりの委員会開催となった。またEUとの間で課長級のタスクフォース会合を開催して次回の合同委員会へ向けた意見交換を行った。

多国間では、旧ソ連の大量破壊兵器研究者の平和目的研究を支援する国際科学技術センター(ISTC)の理事国として、米国及びEUと協力し、中央アジア諸国を中心に支援を行っているほか、国際熱核融合実験炉(ITER)計画に参画している。
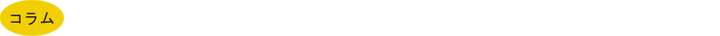
~外務大臣科学技術顧問の活動の展望~
岸輝雄 外務省参与(外務大臣科学技術顧問)
地球環境問題、感染症、自然災害への対応など、世界が直面する課題の中で、その解決のために科学技術の知見が求められるものは多くあります。
日本が持つ科学技術の強みをどう外交に生かすか。この点に関する助言が、外務省における科学の専門家としての、科学技術顧問の活動で期待されている点です。適切な提言や助言のために、これまで国内では17人の専門家から成る科学技術外交推進会議の委員の知見を総動員しています。同時に、科学界においては、こうした助言や提言が結果的に、日本の科学技術の成長にもつながることへの期待も高いのです。

科学技術の強みを外交に生かす上では、科学的な知見やデータを外交政策の策定に活用する、という考え方が重要です。日本の優れた技術を使って、データを精度良く収集し、科学的証拠に基づく解析を進め、政策に生かすという発想です。
日本と外国の共同研究や開発途上国での人材育成などを通じて、科学技術が日本外交において果たせる役割は多くあります。国連における持続可能な開発目標(SDGs)の達成に、日本の科学技術を生かしていければ、日本外交としての更なる成果となるでしょう。このため、SDGsに関する日本の科学技術イノベーションの取組を国内外で紹介し、国際連携の在り方を考えています。
科学技術顧問や各国の科学者とのネットワーク構築も、顧問としての活動の重要な一部です。科学技術顧問を設置している国は米国、英国、ニュージーランドなどで、その数はまだ比較的限られています。こうした状況もあって、各国の顧問が集まると、顧問の活動を通じて世界の科学技術外交を鼓舞していこうとの話になることも多くあります。各国の顧問が集まって議論をすることで、その時々の国際情勢や科学技術情勢を踏まえ、科学技術顧問として注視すべき課題が見いだされてくる、といった面もあります。こうした形での科学技術外交の展開は、外交における新たな興味深い動きとも言えるでしょう。
外務省内での科学的知見の集約と浸透も重要です。このため省内の科学リテラシー向上を目指した省内セミナーを実施したり、在外公館と本省を結ぶ科学技術外交ネットワークを活用し各国の科学技術情報の集約や戦略的イノベーション創出プログラム(SIP)キャラバンなど日本の科学技術の発信に関する取組を進めています。
科学の専門家として、自らにとって新たな世界である外交の分野に飛び込んだことで、自分自身にとっても新たな刺激を得られました。むろん、日本政府にとっても、科学技術顧問の活動は外交力に厚みを増す効果を生んでいると自負しています。日本の科学技術力が、これからも、日本外交への貢献につながっていくことを期待します。
5 将来の国際協力や日本の研究開発成果の国際展開の布石とするため、内閣府(総合科学技術・イノベーション会議)が司令塔機能を発揮し、省庁・分野横断的な11の課題において産学連携により基礎研究から実用化・事業化までを見据えて一気通貫で研究開発を推進する「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」について、外務省(在外公館)との連携により、諸外国に向けて紹介する事業(通称「SIPキャラバン」)
6 2016年6月にドイツ、同10月にオーストリア、フランス及び英国で実施
