6 地域協力・地域間協力
アジア太平洋地域の戦略環境が大きく変化している中、平和で繁栄した同地域の実現は日本にとって不可欠である。そのために積極的な役割を果たすべく、日米同盟を基軸とし、日・ASEAN、EAS、ASEAN+3、ARF、APECなどの地域協力の枠組みを活用し、国際法にのっとったルールを基盤とする社会、そして自由でオープンで密接な地域経済を地域の国々と共に作ることを重視している。
(1)東南アジア諸国連合(ASEAN)情勢全般
ASEANは、最大の課題である2015年の共同体構築に向け、2008年のASEAN憲章の発効やジャカルタに常駐するASEAN常駐代表委員会の発足、共同体構築の中核的施策である連結性マスタープランの実施や域内の格差是正を目的としたASEAN統合イニシアティブの推進など、着実に統合努力を重ねている。加えて、ASEANを中心として、東アジアの地域協力が進展しており、EAS、ASEAN+3、ARFといった地域協力の枠組みが多層的に発達している。さらに、ASEANは、ASEAN自由貿易圏(AFTA)を構築するとともに、日本、中国、韓国、インドなどと自由貿易協定を締結するなど、ASEANを中心としたFTA網作りを進めている。2013年5月には、ブルネイにおいて、RCEP交渉を開始した。
ASEANは、世界の人口の約8.6%を占めている。GDPは、現在では世界全体の約3.2%ではあるものの、過去10年間高い経済成長率を実現している。今後も中間層の増加による購買力の飛躍的向上が見込まれており、世界の成長センターとしての存在感を更に高めていくものと思われる。ASEANの政治的・経済的な重要性が高まるにつれ、各国は積極的にASEANとの関係強化に乗り出している。ASEANが地域の平和・安定維持の要とする東南アジア友好協力条約に、日本、中国、韓国、米国、ロシア、インドなどのアジア太平洋諸国のみならず、EU、英国、フランス、トルコといった欧州、中東諸国からの加入も相次いでおり、2013年にはノルウェーが同条約に署名した。
一方で、ASEANの一体性の維持に関しては、南シナ海における中国とフィリピン、ベトナム等の領有権をめぐる問題について、2012年にASEAN内での意見の相違が顕在化し、ASEANの一体性保持にも懸念が生まれる結果となったことを受け、同年7月のASEAN外相会議では、共同コミュニケが歴史上初めて発出されなかった。その後マルティ・インドネシア外相が東南アジア諸国を訪問した結果、7月にASEAN諸国は「南シナ海に関するASEANの6項目原則についてのASEAN外相声明」に合意し、2013年9月には、中国とASEANとの間で行動規範(COC)の策定に向けた協議が開始されるに至ったものの、統合を進め成長を続けるASEANが地域の安定と繁栄に与える影響を考えると、今後ASEAN一体性の維持・強化に向け、ASEAN自体の努力に加え、日本を始めとするASEAN域外国によるより一層の支援が重要となっている。
(2)日・ASEAN関係
東アジアにおいて進展する様々な地域協力の原動力であるASEANがより安定し繁栄することは、地域全体の安定と繁栄にとって極めて重要である。この認識の下、日本は2011年の日・ASEAN首脳会議で採択した「バリ宣言」と「行動計画」を着実に実施しつつ、2015年のASEAN共同体構築を積極的に後押しすることとしている。特に、共同体構築の鍵を握る連結性強化、災害管理、人材交流といった分野での協力を推し進めていく。
このような中、「日・ASEAN友好協力40周年」を迎えた2013年は、日・ASEAN関係を一層強化する絶好の機会となった。安倍総理大臣は、友好協力40周年がスタートした1月早々、ASEAN諸国を訪問し、訪問先のインドネシアにおいて「対ASEAN外交5原則」を発表した。その際、対等なパートナーとしてASEANと共に歩んでいくことを明確に打ち出すとともに、アジア太平洋地域における3万人規模の青少年交流計画である「JENESYS2.0」を発表した。その後も、安倍総理大臣は積極的な首脳外交を展開し、日本の総理大臣としては初めてASEAN10か国全てを訪問した。2013年12月には、日・ASEAN友好協力40周年を総括する日・ASEAN特別首脳会議が東京で開催された。同会議においては、日本から「積極的平和主義」に基づく安全保障政策について説明し、ASEAN側の理解を得た。また、国連海洋法条約を含む国際法の普遍的な原則に従った紛争の平和的解決の重要性、上空飛行の自由及び民間航空の安全を確保するための協力の強化で一致した。経済分野においては、日・ASEAN包括的経済連携協定の投資章及びサービス章の交渉が実質合意に至ったことを歓迎するとともに、日・ASEAN航空協定の締結可能性を検討していくことで一致した。さらに、日本は、新たな連結性主要案件リストを提示し、引き続きASEAN連結性強化に貢献していく姿勢を示すとともに、今後5年間で2兆円のODA供与のコミットメント及び1億米ドルの日・ASEAN統合基金(JAIF)2.0の設置を表明した(詳細については52ページの特集参照)。
また、日本は、経済発展の中でASEANが直面する環境、高齢化、保健といった新たな経済・社会問題や防災に対する協力を推進していくことを明らかにした。とりわけ防災分野では、5年間で3,000億円規模の支援と1,000人規模の人材育成を実施することを表明した。さらに、交流の分野において、日本は2020年までの7年間を目途に、「文化のWA(和・環・輪)プロジェクト~知り合うアジア~」を実施することを発表した。具体的には、芸術家・文化人の対話・交流事業や、3,000人以上の日本語学習パートナーを派遣して日本語学習者を支援する事業などを実施すること、JENESYS2.0の枠組みを活用し、青少年のサッカー交流を実施していくこととなる。
ASEAN加盟国各国市民同士や日本国民との間で相互理解を深めるとともに日本経済の再生に向け、日本に対する潜在的な関心の増進、日本の強みや魅力などの日本的な「価値」への国際理解の増進、訪日外国人数の増加のため、JENESYS2.0を実施し、日本とASEANとの間での交流を強化した。こうした取組に加え、テロ・感染症・環境など地域や国際社会が直面する諸課題への対処についても、日本とASEANとの間の協力が深化した。
メコン地域(カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナム)の経済発展は、ASEANの域内格差の是正や地域統合の促進に資するものであり、ASEAN全体、ひいては東アジア地域全体の安定と繁栄にとって重要である。この地域では、近年インフラ整備が進み、域内の経済活動も活発化し、著しい成長を遂げている一方、依然として域内格差などの課題を抱えている。日本は、このメコン地域を経済協力の重点地域としている。2013年6月には、ブルネイにおいて第6回日メコン外相会議が行われ、岸田外務大臣は、日本として今後ともメコン地域の発展に寄与していくと表明した。同会議では、日メコン協力の進展と今後の方向性などについて議論がなされた。
12月に東京で開催された第5回日メコン首脳会議では、2012年に策定された2015年までの日メコン協力の方針「東京戦略2012」と中間評価とその行動計画のフォローアップが行われた。安倍総理大臣は引き続きメコン地域の発展に寄与していきたいと述べ、メコン地域への支援の拡充と着実な支援の実施を表明した。ブルネイ(B)、インドネシア(I)、マレーシア(M)、フィリピン(P)が、開発の後れた島嶼部の発展のために進めている「ビンプ・東ASEAN成長地域(BIMP-EAGA)」の取組についても、日本はASEAN域内の格差是正に資するとの観点から支援している。

2013年12月14日、日・ASEAN特別首脳会議が開催されました。この会議は、2003年に続き、10年ぶりに東京において、ASEAN10か国の首脳の参加を得て開催されたものです。2013年は日本とASEANの友好協力関係40周年にも当たる年であったため、1年間を通じて、600件を超える政治、経済、文化、青少年交流、観光などの事業が行われました。その集大成ともなるこの会議においては、日本とASEAN諸国の打楽器奏者、AKB48やEXILEといったJポップのアーティストが参加するガラ・ディナーなどを含めて様々な行事が行われ、日本とASEANとの交流を一層深める機会になりました。また、同会議に際して、安倍総理大臣は10か国全ての首脳と個別に首脳会談も行い、ASEANとの関係強化のための個別の課題についても議論を深めました。
日本とASEANとの関係は、1973年の日・ASEAN合成ゴムフォーラムから始まりました。その後、1977年の福田赳夫総理大臣の東南アジア訪問の際に、日・ASEAN首脳会議が初めて開催され、日本の対ASEAN外交の原則を示した、いわゆる「福田ドクトリン」が発表されるなど、その後の日・ASEAN関係の発展の基礎が形作られました。その後、二度の経済・金融危機などの影響はありましたが、多くの日本企業がASEAN各国に進出し、また、双方の得意分野をいかした貿易も大幅に拡大してきました。特に、2000年代以降、日本とASEANとの間で二国間経済連携協定、投資協定及び日・ASEAN包括的経済連携協定が締結され、日本とASEAN域内全体の生産ネットワークの強化へとつながり、相互依存関係はますます深まっています。
10年前に開催された初めての日・ASEAN特別首脳会議では、「日・ASEAN東京宣言」が発出されました。ASEANが共同体構築に動きだし、かつ、ASEAN地域フォーラム、ASEAN+3、東アジア首脳会議(EAS)といった地域のフォーラム形成において主導的な役割を果たしています。そうした中、日・ASEAN関係を、東アジア全体の安定と繁栄にとって不可欠な役割を果たす「戦略的パートナーシップ」と位置付ける契機となりました。
今回の首脳会議では、「ビジョン・ステートメント」(1)と「地域・地球規模課題に関する共同声明」(2)に合意しました。2015年のASEAN共同体形成に向けたASEANの取組を引き続き支援し、2015年以降を見据えた日・ASEAN協力を実施していくことが表明されるとともに、日・ASEAN協力の範囲が地域のみならず地球規模の課題にまで広がってきていることが改めて確認されました。今後も、日本とASEANの関係は一層緊密な関係になることが期待されます。
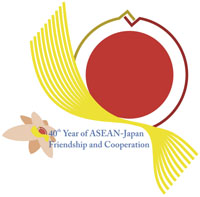


1 日本とASEANは、以下の4つのパートナーシップの分野において協力を強化することを確認。
①平和と安定のパートナー(政治・安全保障) ②繁栄のパートナー(経済・経済協力)
③より良い暮らしのためのパートナー(新たな経済・社会問題) ④心と心のパートナー(人と人との交流)
2 「世界の中の日・ASEAN関係」という観点から、日本とASEANが地域及び地球規模の課題に対する共通認識を示した共同宣言。
(3)東アジア首脳会議(EAS)(参加国:ASEAN 10か国+日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インド、米国、ロシア)
EASは、地域及び国際社会の重要な問題について首脳間で率直な対話を行うとともに、地域共通の課題に対し、首脳主導で具体的協力を進展させる目的で、2005年に発足した地域の重要なフォーラムである。EASには、現在、ASEAN10か国と日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インド、米国、ロシア8か国、合計18か国が参加している。パートナー国には多くの民主主義国が参加しており、域内における民主主義や「法の支配」などの基本的価値の共有や貿易・投資などに関する国際的な規範の強化に貢献することが期待されている。
7月にバンダルスリブガワン(ブルネイ)で開催されたEAS参加国外相会議では、EASにおける協力の見直しや将来の方向性、南シナ海や北朝鮮などの地域・国際情勢について議論が行われた。岸田外務大臣からは、海洋、低炭素成長、災害管理、不拡散の各分野における協力についての日本の取組や考え方について述べ、青少年交流、連結性、国境を越えるテロ・犯罪、保健・開発分野の取組の重要性を指摘した。南シナ海をめぐる問題については、地域の平和と安定に直結する国際社会共通の関心事項であり、いずれの当事者も力による一方的な行動を慎み、関係国際法を遵守することが地域における法の支配を確立するために重要であることなどを述べた。10月にバンダルスリブガワンで開催された第8回EASでは、安倍総理大臣から、EASは政治・安全保障分野を中心に首脳間で率直な議論を行う極めて重要なフォーラムであり、更に力強く発展させていきたいと述べた。海洋安全保障については、海洋は重要な国際公共財であり開かれ安定したものでなければならず、その秩序は「力」ではなく「法」により支配されなければならないこと、そのために各国間の信頼醸成を図り、具体的協力を促進することが不可欠である、その観点から、ASEAN海洋フォーラム拡大会合(EAMF)を今後も定期的に開催していくことが重要であると述べた。また、ブルネイ提案の漁業管理などを通じた食料安全保障の強化に関するスタディー・グループを強く支持しており、積極的に協力していきたいと述べた。地域・国際情勢については、まず、南シナ海をめぐる問題は地域・国際社会共通の関心事項であり、全ての関係国が関連国際法を遵守し、一方的な行動を慎むべき、紛争は国際法に基づき平和的に解決されなければならないとの日本の基本的立場につき述べた。これに加え、法的拘束力があり紛争解決にも資する実効性のある行動規範(COC)が早期に作成されることを期待すると述べた。これに対し、多くの国から同様の発言があった。北朝鮮については、安倍総理大臣から、北朝鮮が継続している核・ミサイル開発は、安保理決議及び六者会合共同声明に違反するのみならず、核物質や関連技術拡散の危険が増大する可能性をはらむ重大な脅威であると指摘した。その上で、国際社会が、北朝鮮に対し、国連安保理決議をきちんと履行するよう求め、核保有は認めないとの確固たる姿勢を明確に示すことが極めて重要であると述べた。また、まず北朝鮮が非核化等に向けた具体的行動をとる必要があると強調した。さらに、拉致問題を含む北朝鮮の人権問題全体に対する懸念について述べるとともに、3月の国連人権理事会において北朝鮮の人権状況に関する調査委員会(COI)設置が決定されたことを歓迎すると述べた。また、EAS協力に関しては、災害管理、低炭素成長の分野における日本の取組について述べた。
(4)ASEAN+3(参加国:ASEAN10か国+日本、中国、韓国)
ASEAN+3は、アジア通貨危機を直接の契機として発足し、1997年に第1回首脳会議が開催されて以来、金融を始め、農業、食料安全保障、教育、観光、保健、エネルギー、環境など、幅広い分野で実務的協力を推進している。現在、24の協力分野において、65の協議メカニズムが存在する。ASEAN+3協力は、ASEAN共同体の実現に向けたASEAN統合を支援する枠組みであるとともに、長期目標としての東アジア共同体の構築に貢献するものと位置付けられている。
2013年6月の第14回ASEAN+3外相会議(於:バンダルスリブガワン(ブルネイ))では、ASEAN+3協力の見直しや将来の方向性、北朝鮮などの地域・国際情勢について議論が行われた。また、進展の著しい金融協力、食料安全保障協力を始めとする実務協力、同年5月に開始されたRCEP交渉などについて議論が行われた。岸田外務大臣からは、ASEAN+3連結性パートナーシップとの関連で、教育や観光分野の協力促進の重要性を指摘するとともに、北朝鮮情勢に関連し、拉致問題について各国の協力を求めた。
10月に開催された第16回ASEAN+3首脳会議(於:同上)においては、2007年に採択された、ASEAN+3協力の具体的な指針である「ASEAN+3協力作業計画(2007-2017)」の改訂版(2013-2017)が採択された。その際、近年の新たなニーズを踏まえて、「連結性」が新たにASEAN+3協力の柱とされたほか、公務員制度、情報・メディアなどが新たな分野に加えられた。また、同首脳会議においては、金融協力に関して、危機的な状況が生じた国に対して短期の外貨資金を供給し、危機の連鎖の拡大を防ぐことを目的とするチェンマイ・イニシアティブ(CMIM)や、地域の経済・金融の監視・分析の役割を担うASEAN+3マクロ経済調査事務局(AMRO)の国際機関化を含む機能強化など、地域の金融協力の重要性について議論が行われた。さらに、食料安全保障分野の協力に関しては、ASEAN+3緊急米備蓄(APTERR)協定に基づく、域内の緊急事態に備えたコメの備蓄制度の成果と今後の発展などについて議論が行われた。
安倍総理大臣は、連結性協力の重要性に言及しつつ、ASEAN+3の枠組みにおいては、教育、観光といった「人と人との連結性」を特に重視していると述べた。その上で、2013年8月に観光協力の促進をテーマに京都で開催した第11回東アジア・フォーラム(EAF)や、9月末に東京で開催した高等教育の流動性や質保証に関する国際会議などについて紹介した。さらに、安倍総理大臣は、北朝鮮と外交関係を有するASEAN各国に対し、核・ミサイル問題に関する前向きな具体的行動をとるよう北朝鮮に働きかけるよう要請するとともに、拉致問題について北朝鮮による前向きな対応を促すべく各国の理解と協力を要請した。
(5)日中韓協力
日中韓3か国は、地理的な近接性と歴史的な深いつながりを有し、世界経済の約20%、東アジアのGDPの約71.7%を占めている。これら3か国が協力を深めるとともに、国際社会の課題解決に向けて一層協力を促進していくことは、たとえそれぞれ二国間において問題が生じている場合でも、東アジア地域、ひいては世界の平和と繁栄にとって大きな意義がある。2013年は、韓国が議長国を務め、高級事務レベルでの協議やアジア政策対話が行われたが、日中韓外相会議及びサミットは開催に至らなかったにもかかわらず、引き続き、環境、文化、防災や保健分野での閣僚会議などが開催され、幅広い分野で日中韓の間の実務協力の進展があった。
また、2011年に韓国・ソウルにおいて活動を開始した日中韓協力事務局は、2013年9月に設立2周年を迎え、岩谷前駐オーストリア大使が新しく事務局長に就任した。新しい体制の下での日中韓協力事務局の様々な活動を通じて日中韓協力が一層促進することが期待される。
(6)アジア太平洋経済協力(APEC:Asia-Pacific Economic Cooperation)
APECは、各エコノミー(43)の自発的な意思によって、アジア太平洋の持続可能な発展を目指し、地域経済統合と域内協力の推進を図る枠組みである。APECは、アジア太平洋地域の21か国・地域から構成されており、世界の人口の約4割、GDPの約5.5割及び貿易量の約4.5割を占める「世界の成長センター」である。APECはその貿易の約6.5割が域内貿易であるなどEU並みの密接な域内経済を構成している。APEC地域の経済面における協力と信頼関係を強化していくことは、日本の更なる発展を目指す上で極めて重要である。また、APEC首脳・閣僚会議は、経済問題を中心に、国際社会の主要な関心事項について、首脳・閣僚間で率直な意見交換を行う有意義な場となっている。
インドネシアが議長を務めた2013年、APECでは、「多角的貿易体制」、「連結性の促進」及び「衡平性を伴う持続可能な成長」を優先課題に掲げ、APEC首脳宣言「強靱なアジア太平洋、世界成長のエンジン」及び「多角的貿易体制への支持及び第9回WTO閣僚会議(MC9)に関する独立文書」が発出された。
特に、連結性の促進については、アジア太平洋地域の連結性を強化し、地域統合へ向けた動きを促進すべきとの認識が共有され、「インフラ開発・投資に関する複数年計画」の策定に合意した。また、多角的貿易体制の重要性について改めて認識し、第9回WTO閣僚会議(MC9)の成功に向けたコミットメントを再認識し、新たな保護主義措置の不導入の2016年末までの延長を含む保護主義の抑止に取り組むとした独立文書が採択された。
(7)アジア欧州会合(ASEM:Asia-Europe Meeting)
ASEMは、アジアと欧州との対話と協力を深める唯一のフォーラムとして1996年に設立されて以降、首脳会合や各種閣僚会合などを通じ、政治、経済、文化・社会等を3本柱として活動を行っている。ASEMには、アジア・欧州の49か国・2機関が参加しており、その人口、GDP、貿易額の合計は、世界全体の約6~7割を占めている。ASEMは、地球規模の課題や地域の課題に対し、両地域の共通認識を形成し、協力を促進するとの重要な意義を有している。
2013年11月には第11回外相会合(於:インド)が開催され、参加国・機関の外相などが一堂に会し、「成長と開発のためのパートナーシップの架け橋」とのテーマの下、経済成長と持続可能な開発、非伝統的安全保障上の課題、国際・地域情勢について議論が行われた。
岸田外務大臣は、「アベノミクス」による日本経済の再生とその成長戦略の重要な柱である貿易・投資の自由化・円滑化、経済連携などを通じ、地域・世界経済の成長に貢献していく決意、そして、「積極的平和主義」の立場から、地域と国際社会の平和と安定に積極的な貢献を行う決意を表明した。そのほか、防災、北朝鮮情勢、海洋の安全保障について日本の考え方、立場を示し、理解と協力を求めた。また、5月には第4回教育大臣会合(於:マレーシア)が開催され、教育の質保証と相互認証や職業教育・訓練を含む生涯学習などに関し、意見交換や知見の共有が行われた。
なお、ASEMの枠組みでは、11月に、日本などが共催国となり、第2回原子力安全セミナー(於:リトアニア)が開催された。また、アジア欧州間の相互理解促進のための活動を行う(アジア・欧州財団(ASEF))が、ポスト2015年開発目標策定に向けた議論におけるメディアの役割をテーマとして円卓会議(於:インド)を開催するなど様々な分野で具体的協力が行われている。

(8)南アジア地域協力連合(SAARC)
SAARC(44)は南アジア諸国による比較的緩やかな地域協力の枠組みであり、SAARC憲章において南アジア諸国民の福祉の増進、経済社会開発及び文化面での協力・協調などを目的としている。
日本は2007年からSAARCにオブザーバーとして参加している。民主化・平和構築、エネルギー、防災、児童福祉など多岐にわたる分野で南アジアの域内協力事業を実施しており、駐ネパール大使をSAARC担当大使に任命するなど関係強化に努めている。また、日・SAARC間の青少年交流の一環として、2007年から5年間で、「21世紀東アジア青少年大交流計画(JENESYS)」を通じて高校生、理工系学生、日本語学習者など約900人を招へいした。また、これに続いて、2012には、「キズナ強化プロジェクト」を通じて約440人、2013年には、「JENESYS2.0」を通じて約730人の青少年をSAARC各国から招へいした。
43 中国香港、チャイニーズ・タイペイを含めたAPEC参加単位
44 事務局はカトマンズ(ネパール)に所在。域内人口16億人、域内GDP約2兆円を有する。加盟国は、インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、ブータン、モルディブ、アフガニスタンの8か国。また、日本、中国、米国、韓国、イラン、モーリシャス、EU、オーストラリア、ミャンマーがオブザーバーとして参加している。
