3 東南アジア
(1)ブルネイ
ブルネイは、豊富な天然資源を背景に、高い経済水準と充実した社会福祉を実現している国である。外交面でも2013年にはASEAN議長国を務め、その存在感を世界に示した。
日本とブルネイは、長年の液化天然ガス(LNG)の安定供給を基盤とした良好な関係にある。2013年は、1月の岸田外務大臣のブルネイ訪問を皮切りに、2月のボルキア外務貿易相の訪日、5月のボルキア国王同妃両陛下の訪日、10月のASEAN関連首脳会議の際の安倍総理大臣のブルネイ訪問、そして12月の日・ASEAN特別首脳会議のためのボルキア国王訪日など、要人往来が極めて活発に行われた。一連の会談では、LNGの安定供給の重要性を確認しつつ、経済多角化、再生可能エネルギー及び省エネルギーの分野でも協力を一層強化していくことや、2014年の両国外交関係樹立30周年に向けて様々なレベルで交流を進めていくことで一致した。12月に東京で行われた日・ASEAN特別首脳会議では、ボルキア国王が安倍総理大臣と共同議長を務め、会議を成功に導いた。
(2)インドネシア
インドネシアは、第2期ユドヨノ政権での政治的安定の下、堅調な成長を維持し、新興経済大国としての存在感を示している。外交面でも、11月に第6回バリ民主主義フォーラム(BDF)を開催し、地域における民主主義の定着に取り組むなど、国際社会の課題に積極的に関与している。
日本との関係では、2013年は日・インドネシア外交関係樹立55周年の記念の年として、戦略的パートナーとしての良好な両国関係を一層強化する1年となった。安倍総理大臣は、就任後最初の訪問国の1つとして、1月にインドネシアを訪問し、対ASEAN外交5原則を発表したのに続き、10月にはインドネシアが主催したAPEC首脳会議に出席するためにバリを訪問した。これらの機会における日・インドネシア首脳会談において、両首脳は、経済、政治、安全保障、交流、それぞれの分野において協力を強化していくことで一致した。12月には、日・ASEAN特別首脳会議出席のためにユドヨノ大統領が訪日した。都内で行われたユドヨノ大統領による特別講演では、日本が安全保障上より大きな役割を果たすことについて、理解が示された。また、2013年で3度目となる日・インドネシア首脳会談を実施し、両首脳は、両国の安全保障や経済分野における協力を促進し、良好な二国間関係を更なる高みに引き上げていくことで一致した。経済面でも両国の協力関係は進展しており、10月にはバリにおいて、日・インドネシア経済合同フォーラムが行われた。また、12月には、東京において、ジャカルタ首都圏投資促進特別地域(MPA)第4回運営委員会が実施され、MPA戦略プランの実施の一層の加速化に向けた協力を進めていくことで一致した。文化面においても、8月に東南アジア地域及びイスラム圏で初となる大相撲ジャカルタ巡業が行われるなど、様々な行事が開催された。
また、2月にマルティ外相がパレスチナ開発のための東アジア協定促進会合(CEAPAD)の機会に訪日、10月のAPECの機会に岸田外務大臣がバリを訪問し、いずれの機会にも外相間で閣僚級戦略対話を実施した。
(3)マレーシア
マレーシアは、ASEANにおいても工業化が進んでいる国である。2020年までの先進国入りを目指し、国際競争力強化のため規制緩和・自由化を進めており、国内経済は投資と国内消費に支えられて安定した成長を維持している。
ナジブ政権は、「ワンマレーシア(国民第一、即実行)」のスローガンの下、2010年に発表した「政府変革プログラム」、「新経済モデル」、「第10次マレーシア計画」及び「経済変革プログラム」を着実に実施し、民族融和、行政改革や国民福祉の充実を図っている。内政面では、2013年5月に連邦下院選挙が行われ、ナジブ首相の再任が確定し、第2次ナジブ政権が発足した。
日本との関係では、2013年7月に、安倍総理大臣が日本の総理大臣として6年ぶりにマレーシアを訪問したほか、12月には日・ASEAN特別首脳会議に出席するために、ナジブ首相が訪日したことで、首脳レベルでの相互訪問が実現した。一連の首脳会談では、両首脳は、東方政策に基づく層の厚い絆(きずな)を基に時代に即した新たな二国間関係を構築することで一致した。
経済面では、日本はマレーシアに対する最大の投資国であるほか、マレーシアへの進出日系企業数は1,400社にも上るなど、引き続き緊密な協力関係にある。また、良好な二国間関係の基盤である東方政策は2012年に30周年を迎え、これまでに1万5,000人が日本に留学・研修を行っており、両首脳間では、マレーシアが進めている東方政策「セカンドウェーブ」(37)への協力も確認された。また、2011年に発足したマレーシア日本国際工科院(MJIIT)をASEANにおける日本型工学教育の拠点とすべく、協力が進められている。
(4)フィリピン
フィリピンは、大統領制を採用する民主主義国家であり、近年は、英語を話す若い労働力をいかして高い経済成長を遂げている。任期4年目となるアキノ大統領は、引き続き高い支持率を維持し、2013年5月の中間選挙で勝利するなど安定した政権運営を行っている。また、高い経済成長が達成された。中国との南シナ海領有権問題については、フィリピン政府は、2013年1月に国連海洋法条約に基づく仲裁裁判手続を開始した。
2013年には、日・フィリピン間で首脳及び外相レベルの要人往来が活発化した。1月に岸田外務大臣がフィリピンを公式訪問し、5月にもデル・ロサリオ外相が訪日し、外相会談が行われた。7月にフィリピンを日本の総理大臣として約6年半ぶりに公式訪問した安倍総理大臣は、対フィリピン外交「4つのイニシアティブ」(①活力ある経済を共に育む、②海洋分野での協力、③ミンダナオ和平プロセス支援の強化、④人的交流の促進)を表明した。その際、アキノ大統領との間で、同イニシアティブに基づいて両国間の「戦略的パートナーシップ」を更に深化させることで一致した。その後、10月にはASEAN関連首脳会議の際にブルネイで、また12月には、日・ASEAN特別首脳会議で訪日した際に首脳会談が実施され、フィリピンによる地上デジタル放送日本方式の採用、両国間の航空関係を拡大するための航空協定の付表の改正、フィリピン沿岸警備隊の能力向上を目指し、巡視艇供与を行うための円借款案件への署名などの具体的な進展がみられた。また、2013年11月にフィリピン中部を襲った台風30号による甚大な被害に対して、日本政府は、過去最大規模となる1,180人の自衛隊員や医療チームなどの国際緊急援助隊の派遣や緊急に必要な物資や資金として約56億円の支援を行った。今後の復旧・復興の段階でも、500億円に増額した「災害復旧スタンドバイ借款」などを通じて引き続き支援を行っていくこととしている(詳細については38ページのコラム参照)。
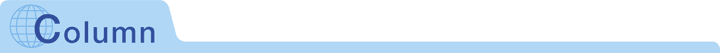
2013年11月8日にフィリピン中部を横断した台風30号(フィリピン名:ヨランダ)は、「スーパー台風」とも形容されるほど勢力が大きく、高潮や暴風によってレイテ島北部やサマール島南部を中心に甚大な被害をもたらしました。この災害については、日本でも大きく報道されたことから、ご記憶の方も多いことでしょう。
日本とフィリピンとは長年にわたって友好関係を築いてきており、近年では、「戦略的パートナーシップ」と呼び合うほど関係が緊密化しています。こうした関係も踏まえて、日本は、フィリピンの救援活動を最大限支援するため、過去最大となる約1,200人規模の自衛隊部隊を含む国際緊急援助隊の派遣、緊急援助物資の送付、また緊急無償資金協力の実施を行いました。日本は、東日本大震災の際に、救援物資の提供や医療チームの派遣などフィリピンからの支援を受けており、今回のフィリピンへの支援はその「恩返し」ともいえるものです。
ここでは、国際緊急援助隊として、現地に派遣された医療チームの診療活動について、紹介します。医療チームは、被害の大きかったレイテ島タクロバン市を中心に、11月15日から12月9日まで活動し、約3,300人の診療を実施しました。私は、医療チームの第1次隊に同行しましたが、災害発生直後で交通は寸断され、治安状況も確認しながらの現地入りとなりました。各国の支援チームの中でも先駆けて到着したこともあり、外傷を負った患者を中心に、多くの人々が市内の広場に設営された診療所に列をなしました。医療チームは、レントゲンのような高度な医療機材も持ち込んでおり、女性の足に刺さっていた異物を発見するなどその効果がいかされました。また、サマール島南部のバサイ町の地域病院にも日帰りで人員を派遣し、町民の診療に当たりました。被災直後からこの地域病院を支えていた医師から感謝状が送られるなど、その活動は現地で高く評価されています。フィリピン国内の関心も高く、私も専門としている現地語(タガログ語)でインタビューに応じることもありました。今後の中・長期的な復旧・復興についても、日本はフィリピンへの支援を続けていきます。
南部アジア部南東アジア第二課 松田茂浩
(国際緊急援助隊・医療チーム一次隊副団長)


(5)シンガポール
シンガポールは、ハブ機能の強化を目指した国家戦略によりASEANの中で最も経済が発展し、ASEANのオピニオンリーダーとしての地位を確立している。また、1965年の独立以降、人民行動党(PAP)による安定した政治体制が続いている。一方、近年では国民の政治意識に変化も見られ、シンガポール政府もこれまでの積極的な外国人受入れ政策の一部見直しを始めるなど、国民の関心が高い問題への対応を進めている。また、いわゆる「第4世代」といわれる次世代の指導者候補の起用を進めるなど、世代交代にも着手している。
日本との関係では、2013年は極めて活発な要人往来が行われ、良好な二国間関係を再確認する1年となった。1月には、岸田外務大臣が就任直後にシンガポールを訪問した。5月には、リー・シェンロン首相が訪日し、7月には、安倍総理大臣が日本の総理大臣として11年半ぶりにシンガポールを訪問し、伝統ある「シンガポール・レクチャー」(38)において、日本の成長戦略に関するスピーチを行った。また、12月には、日・ASEAN特別首脳会議出席のためにリー首相が再び訪日し、2013年で3度目となる首脳会談で、地域・国際社会における両国の更なる協力について忌憚(きたん)のない意見交換が行われた。経済面では、多くの日系企業がシンガポールに地域統括拠点を設置しており、インフラなどの分野でも両国企業の連携が進んでいる。また、「21世紀のための日本・シンガポール・パートナーシップ・プログラム(JSPP21)」を通じて、開発途上国に対して共同で技術協力を行っている。
(6)カンボジア
現在、カンボジアは、2030年の高中所得国(39)入りを目指し、ガバナンス(統治)の強化を中心とする開発政策を推進している。日本は、1980年代後半のカンボジアの和平プロセス及びその後の復興に積極的に協力しており、その過程で培われた信頼を背景に、両国間には緊密な関係が構築されている。また、近年日本の民間投資の増加に伴い、両国関係は経済面でも緊密化している。
2013年は両国外交関係樹立60周年に当たり、11月には13年ぶりの二国間公式訪問として安倍総理大臣がカンボジアを訪れた。その際の首脳会談において、両首脳は、地域・国際社会の平和と繁栄に向けた協力や、政治・安全保障、民主主義と法の支配などの分野における関係の強化で一致し、共同声明が発出された。また、12月にフン・セン首相が東京での日・ASEAN特別首脳会議への参加に引き続き日本を公式訪問した際には、両国関係を「戦略的パートナーシップ」に格上げすることで一致し、二国間航空協定の締結に向けた交渉入りが表明された。
カンボジアにおいては、2013年7月に国民議会(下院)選挙が行われた。インフラ整備を中心としたこれまでの開発政策の成果を訴える現職のフン・セン首相率いる与党人民党は、野党の躍進で大幅に議席を減らしながらも、過半数の議席を獲得した。これに対し、貧富の格差是正、賃金上昇を公約に掲げた野党救国党は、選挙に不正があったと主張して国会をボイコットし、デモ集会などの抗議活動を行っている。
なお、カンボジアは2015年までASEAN対日調整国を務めており、2013年を通じ、日・ASEAN間の各種会議開催や成果文書などの調整を行った。
(7)ラオス
ラオスは、中国、ミャンマー、タイ、カンボジア及びベトナムの5か国と国境を接する内陸国であり、その地理的制約と過去の内戦等の影響から経済発展が遅れていたが、近年、インドシナ半島の中央に位置する地理上の優位性に着目した域内物流の拠点化等、連結性向上による経済発展を目指している。
日・ラオス関係は伝統的に良好であるが、特に最近では、日系企業のラオスに対する関心が高まっており、日本が依然としてトップドナーである開発協力のみならず、民間投資を含む経済面での交流が活発化している。
2013年11月、安倍総理大臣が13年ぶりの二国間公式訪問としてラオスを訪れた。その際の首脳会談において、両首脳は、両国の「包括的パートナーシップ」を更に具現化させるべく共同声明を発出し、政治・安全保障分野において外務・防衛当局間協議を早期実施することで一致した。このほか、日本貿易振興機構(JETRO)による現地事務所開設の決定を歓迎した。また、12月にはトンシン首相が日・ASEAN特別首脳会議に出席するために訪日し、二国間航空協定の締結に向けた交渉入りが表明され、人的・文化交流を含む種々の分野で前向きな進展が見られた。
(8)ミャンマー
ミャンマーにおいては、2011年の民政移管以降、テイン・セイン大統領主導の下、民主化、国民和解、「法の支配」の強化などの改革が進められてきた。2013年も、政治犯釈放の調整を行う政治犯審査委員会の設置、政府と少数民族勢力との停戦に向けた対話の実施など、国内の改革に係る取組が見られた。ミャンマーは、中国とインドの間の地理的な要衝に位置し、発展への潜在性が高く、また、ミャンマー国民は概ね親日的である。こうした点を踏まえ、日本はミャンマーの改革努力を後押しすることにより、同国が地域の繁栄と安定に貢献する国として変貌を遂げていくことを期待している。
2013年5月、安倍総理大臣は日本の総理大臣として36年ぶりにミャンマーを訪問し、ミャンマー政府による改革努力に対し、日本として官民をあげて支援していくことを表明した。これにより、これまでの両国間の信頼関係を基に、日・ミャンマー関係を更に強化し新たな次元に高めるための礎が築かれることとなった。また、12月には、日・ASEAN特別首脳会議に出席するために訪日したテイン・セイン大統領との間で再度首脳会談が行われ、ミャンマーにとって初の本格的な自由化型の投資協定が署名された。2013年1月に長年の懸案であった延滞債務問題が解決されたことを踏まえて、安倍総理大臣訪問の際に、ディラワ経済特区への支援を含む510億円の円借款と総額400億円の無償資金協力・技術協力を行うことについて合意したほか、12月の首脳会議に際しても総額632億円の円借款供与についてプレッジを行った。また、2014年が日・ミャンマー外交関係樹立60周年、ミャンマーのASEAN議長国就任という重要な年となることを踏まえ、日本としてミャンマーを支援していくことを表明している。さらに12月にミャンマーが初めて東南アジア諸国のスポーツの祭典であるSEAゲームを主催するに際して、日本の民間企業がユニフォームのデザイン・供与等の支援を行った。このほか、日本は、ミャンマーの発展のためには独立以来の懸案である少数民族との和解が不可欠との観点から、2月に笹川日本財団会長を少数民族和解政府特使に任命しているが、この会談を受け、政府と少数民族勢力との和平プロセスを後押しするための日本の具体的な支援が2014年1月に発表された。
なお、ミャンマーからは、2013年4月には、長年自宅軟禁におかれていたアウン・サン・スーチー女史が日本政府の招待で訪日した。同女史は日本に留学経験もあり、また、民主化の象徴として注目を集めた。そのほか、シュエマン下院議長、多くの閣僚が訪日した一方で、日本からは1月初めの麻生副総理兼財務大臣を皮切りに、多くの閣僚がミャンマーを訪問した。
(9)タイ
タイは、東南アジア地域の中心にあって、日本を含む海外からの投資の受け皿として経済成長を遂げつつあり、地域の発展をけん引している。
日・タイ両国間では、皇室・王室の緊密な関係を礎に、政治面、経済面を含む国民レベルで活発な交流が行われている。また、基本的人権の尊重、「法の支配」、資本主義などの基本的価値観や市場経済の共有を背景に、両国政府は二国間関係を「戦略的パートナー」と定義している。2013年1月の安倍総理大臣就任後初の外国訪問としてのタイ訪問の機会や、5月のインラック首相の訪日の機会に行った首脳会談を通じ、経済、安全保障、人的交流を含む様々な分野で「戦略的パートナーシップ」を更に発展させることが合意されている。さらに、7月、日本がタイ人短期旅行者に対する査証免除措置を開始して以来、タイ人訪日者数は前年同月比でほぼ倍増する形で推移しており、双方向での更なる交流が期待される。
現在のタイ社会は、2006年のクーデターによって政権の座を追われたタクシン元首相を支持する世論と同元首相を糾弾する世論に分断されている。タクシン派の支持を背景に、2011年の下院総選挙に勝利して政権に就いたインラック首相は、約2年間にわたり安定的な政権運営を行ってきた。しかし、与党議員が国会に提出した恩赦法案を契機に、2013年11月半ばからバンコク都内での反政府デモの規模が拡大し、12月初め、インラック首相は下院解散を発表するに至った。そのため同月の東京における日・ASEAN特別首脳会議にはインラック首相が出席できず、ニワットタムロン副首相が代理として出席した。反政府・反タクシン勢力は、政治改革の実施や下院総選挙の延期を引き続き主張してデモ集会を継続しており、国内情勢は流動的な要素が多い。
(10)ベトナム
ベトナムは2020年までの工業国化を目指し、2000年代後半以降の国内経済の停滞からの脱却を図るべく、インフラ整備や投資環境の改善を通じた外資誘致、また、不良債権処理や国営企業改革といった経済の非効率の改善を進めている。
日本との関係では、あらゆる分野で協力を拡大する「戦略的パートナー」であり、特に経済面では、日本はベトナムにとって最大の政府開発援助(ODA)供与国であり、かつ最大の投資国となっている。
2013年は、日・ベトナム外交関係樹立40周年を記念する友好年として、両国において様々な文化交流行事が行われ、両国国民の間の友好関係が深まった。また、首脳や閣僚の相互訪問が実施され、政治レベルでの信頼関係も深まりを見せた。1月には、安倍総理大臣が就任後初の外遊先の1つとしてベトナムを訪問し、ズン首相との間で、「戦略的パートナーシップ」を更に発展させ、協力関係を強化していくことで一致した。また、12月に日・ASEAN特別首脳会議のためにズン首相が訪日した際には、海洋の平和と安定の維持や、経済関係・開発協力、政治・安全保障などの分野で協力していくことで一致した。
内政面では5月の国会において、閣僚などに対する信任投票が初めて実施され、信任された。また、11月の国会において憲法改正案が採択され、ベトナム共産党が人民の監査を受け、人民に対して責任を負うとの規定が新設された。こうした動きは、共産党が国民からの支持を得ることの重要性を意識しつつあることを示していると見られる。
(11)東ティモール
東ティモールは21世紀初の独立国家として、国際社会の支援の下で平和と安定を実現し、ルアク大統領及びグスマン首相の下、民主主義に基づく国造りを実践してきている。
日本は、紛争後の復興から本格的な開発という新たな段階に移行した東ティモールの努力を引き続き全面的に後押しすることとしているほか、国際場裏でも緊密な協力を続けている。また、東ティモールはASEAN加盟を希望しており、日本としても、東ティモールの加盟努力を後押ししていくこととしている。日・東ティモール外交関係樹立10周年に当たる2012年に引き続き、2013年も、4月に城内外務大臣政務官が東ティモールを訪問したほか、6月にはASEAN関連外相会合の機会に両国外相が会談を行った。9月には、立法府の長であるグテレス国民議会議長が訪日するなど、引き続き活発な要人往来や意見交換が行われている。
37 時代に即した形で東方政策の質の転換を図ること。マレーシア側が検討中。
38 1980年からシンガポール国立大学東南アジア研究所(ISEAS)が主催する講演会で、シンガポールで最も権威の高い講演会とされる。日本の総理大臣としては、これまで橋本総理大臣(1997年)、小泉総理大臣(2002年)が講演を実施。
39 高中所得国(UMICs:Upper Middle Income Countries)。2013年現在、2012年の一人当たり国民総所得(GNI)が4,086米ドル超12,615米ドル以下の国・地域(世界銀行アトラスベース)。
