4 南アジア
(1)インド
ア インド情勢
与党コングレス党を中心に2009年に発足した第2次シン政権は、社会開発と経済成長の両立を目指した包括的成長を目標に掲げ、社会的弱者対策を積極的に進めるとともに、インフラ整備などを通じた経済開発を推進している。
内政面では、7月にインド北西部で発生した大規模停電、8月の石炭鉱区の採掘権割当汚職疑惑、9月のマルチブランド小売業の海外直接投資(FDI)規制緩和をめぐり、野党などが反発するなど、政権が守勢に立たされる場面も見られた。経済面では、インドは主要新興国として2005年から2007年度には3年連続で9%台のGDP成長を達成したものの、2011年度は6.5%、2012年7月から9月までについては対前年度同期比5.3%と減速傾向にある。外交面では、伝統的な非同盟外交を堅持しつつ、引き続き米国、中国、ロシアなどの主要国や周辺国との関係強化に取り組んでいる。また、カシミール問題など困難な問題も存在する。パキスタンとの間では、8月の非同盟諸国(NAM)首脳会議の機会に首脳会談を実施し、9月にイスラマバード(パキスタン)において外相会談、12月に内相会談を実施するなど、対話を継続している。
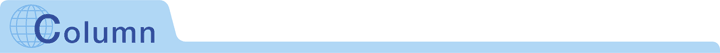
~「日本・ラオス親善ゾウ」と被災地の子供たちとの触れ合い~
東日本大震災に際し、ラオスからも多くの心温まる支援が寄せられました。その中の一つ、ラオスから被災地にはるばるゾウが来たことについて御紹介します。
ラオスは、かつてランサン(「百万頭のゾウ」の意味)王国という名前の国であったほど、ゾウはラオス人の生活に近い特別な動物です。今でも、ラオス国内の最大の生息地であるサイニャブリー県では、毎年ゾウ祭りが行われ、国内外からの多くの観光客でにぎわいます。
以前から、岩手県一関市、福島県二本松市、栃木県那須市の3県のサファリパークは、ラオスからのゾウの借入れを検討していました。そうした中、2011年3月11日、東日本大震災が発生しました。震災直後、サファリパークは、ゾウをラオスから連れてくるべきか、悩んだそうです。しかし、園内での話合いでは、震災があったからこそ、被災地の子供たちに、ゾウとの触れ合いを通じて、自然の素晴らしさを知ってほしい、希望と元気を与えたい、との前向きな意見が多数を占めたそうです。そして、多くの職員自身も被災しているにもかかわらず、被災地の子供たちに笑顔になってほしいとの思いから、ラオスからゾウを連れてくる努力を再開しました。
サファリパークの関係者は、幾度となくラオスに足を運び、関係者一人一人に計画を説明し、慣れない国での手続を進めました。その熱意とゾウを大切にする気持ちが伝わり、ラオス政府は、被災地の支援の一環として、ゾウの貸し出しを許可することとなりました。
この過程で、以前から大使館などで相談を受けて支援を行ってきていた外務省は、このような被災地の皆様の取組を広く知っていただくため、また、ラオスからのゾウたちが被災地の子供たちに元気と夢を与え、日本とラオスとの関係が一層深まる契機となることを期待して、ゾウたちに「日本・ラオス親善ゾウ」の名称を付与することを決めました。人間の「親善大使」ならぬ動物にこうした肩書きを政府が付与するというのは、極めて異例なことですが、日・ラオス関係を担当する職員の熱い思いが実った結果といえるでしょう。
その後必要な許可などの全ての手続がそろいましたが、関係者の不安は消えませんでした。というのは日本とラオスとの間で直接ゾウを空輸した実績はなく、ゾウの輸送は、全くの手探り状態だったからです。しかし、輸送関係者やラオス政府の尽力により、2012年9月27日、ゾウは無事成田空港に到着したのでした。
2012年10月19日、福島県二本松市のサファリパークで、ゾウたちのお披露目式と「日本・ラオス親善ゾウ」の名称付与式が行われました。今回、ラオスから来たゾウは全部で6頭。今回のお披露目式典では6頭が勢ぞろいしました。このゾウたちは、岩手県、栃木県那須市、福島県の各サファリパークに2頭ずつ配置され、ラオスから来たゾウ使いたちと一緒に生活することになります。
このゾウのお披露目式には、地元二本松市の関係者のほか、多くの地元幼稚園生や小学生が招待されました。その子供たち全員が、順番に、ゾウにエサのバナナをあげたり、実際にゾウに乗ってみたりしました。どの子供も、満面の笑みを浮かべて大はしゃぎ。周りで見守る大人たちからも笑みがこぼれ、会場は、明るく楽しい雰囲気に包まれました。
これからも、日本とラオスの友好と親善の象徴であるゾウたちが、被災地の子供たちに笑顔を与え、被災地に元気を与えてくれることを願っています。
南東アジア第一課長 佐々山拓也


イ 日・インド関係
日本にとって、インドは、シーレーン(海上交通路)上の要衝に位置するため、地政学的に重要性である。また、経済面でも、高い経済成長を通じて中間所得層が増加しており、日本企業にとっての投資先や市場としての重要性も年々増している。民主主義などの普遍的価値や多くの戦略的利益を共有し、経済的な相互補完性を有するパートナーである日本とインドとの関係は、2006年の「戦略的グローバル・パートナーシップ」構築以降、更に緊密になっている。両国間では、ほぼ毎年交互に首脳や外相が相手国を訪問し、年次首脳会談、外相間戦略対話を行っており、政治、安全保障、経済などの二国間関係から地域や地球規模の課題に至るまで幅広い分野で関係を強化している。安全保障分野では、6月に海上自衛隊とインド海軍との間で初の二国間海上訓練を実施するなど、海賊対策を含む海上安全保障における協力を強化している。経済面では、4月に初の閣僚級経済対話を実施したほか、11月に社会保障協定に署名するなどビジネス環境整備のための取組が進んでいる。また、貨物専用鉄道建設計画(DFC)、デリー・ムンバイ間産業大動脈構想(DMIC)、インド南部開発などのインフラ整備についても協力を強化している。2012年は国交樹立60周年に当たり、両国において1年を通じ様々な文化行事などが開催された。

(2)パキスタン
内政面では、2011年秋以降政府と軍部の対立が深まり、1月には一時軍部によるクーデターが現実味を帯びるなど緊迫した状況を迎えた。さらに、ザルダリ大統領の汚職裁判に関する命令(2009年12月)の執行をめぐる政府と最高裁との対立の中で4月にギラーニ首相が法廷侮辱罪で有罪となり、6月には議員辞職に追い込まれた。その後8月、後任のアシュラフ首相は、従来の政府方針を転換して最高裁の命令に従う意向を示し、11月には大統領に対する裁判の再開手続を行ったことから、政府と最高裁が対立する事態は収拾した。
経済成長も全体的に低迷しているが、その主な原因としては、2012年2月からIMF融資の返済が始まったこと、治安情勢の悪化による海外直接投資の減少傾向が進んだこと、さらに、深刻な電力不足によって経済活動全般に悪影響が及んだことが挙げられる。また、喫緊の課題である経済改革にも目立った成果は見られなかった。
駐アフガニスタン北大西洋条約機構(NATO)軍による誤爆事件(2011年11月)などによって米国との関係は停滞したが、米国とパキスタンの双方が7月の電話外相会談を契機に歩み寄り、地域の安定に向けた協力の強化に再び取り組んでいる。アフガニスタンとの間でも、2008年3月に民主的改革を経て成立した政府がパキスタンにおいて発足した後は、関係改善が進んでおり、11月にはアフガニスタンの和平高等評議会(HPC)がパキスタンを訪問し、同国で拘束されていた元タリバーン政権の一部メンバーが釈放されるなど、パキスタン・アフガニスタン間の対話は具体的な成果を見せ始めた。パキスタンはインドとの間で領土問題など課題を抱えているが、2011年以来本格的に開始されたインドとの対話プロセスは2012年も継続され、貿易関係の正常化を中心にいくつかの進捗が見られた。
2012年は、日本とパキスタンが国交樹立60周年を迎えた節目の年でもあった。双方で様々な文化事業などが開催されたほか、カル外相が2度の訪日を果たし、玄葉外務大臣との間で外相会談を行った。10月には、二国間投資・貿易関係の強化に向けて、日本からビジネス・ミッションがパキスタンを訪問した。

(3)スリランカ、バングラデシュ、ネパール、ブータン、モルディブ
ア スリランカ
スリランカでは、ラージャパクサ大統領の下、安定した政権運営が行われており、9月に実施された東部州を含む3州の州議会選挙でも、同大統領が率いる統一人民自由連合が勝利した。また、経済面でも2009年の内戦終結以降、順調な経済成長を維持しており、治安情勢の改善によって観光客数が顕著に増加している。
内戦(1)後の国民和解の面では、国内避難民(IDP)の再定住や「タミル・イーラム解散の虎」(LTTE)元兵士の社会復帰に加え、スリランカ政府は、7月に、2011年12月に公表された「過去の教訓・和解委員会(LLRC)」報告書の勧告実施に向けたLLRC国家行動計画を公表した。一方、国民和解のための重要要素である少数民族問題の政治解決、すなわち少数民族の政治的権利の向上の在り方については、地方への権利委譲などが話し合われたものの、政府と最大のタミル政党であるタミル国民連合(TNA)との直接協議に進展は見られなかった。
日本との関係では、2012年は国交樹立60周年に当たり、様々な記念事業が実施された。要人往来の面では、5月に岡田克也副総理大臣がスリランカを訪問し、ラージャパクサ大統領と会談し、内戦の被害から復興途上にある北部地域を視察した。また、7月に、ピーリス外相が訪日し、外相会談において経済関係強化や海上安全保障分野での協力について意見交換を行った。玄葉外務大臣からは、日本としてスリランカの国民和解に向けた取組を引き続き支援することを表明した。
イ バングラデシュ
人口約1億5,000万人を抱えるバングラデシュは、後発開発途上国ではあるものの、経済は堅調に成長し、安価で質の高い労働力が豊富な生産拠点として、また、インフラ整備などの需要や潜在購買力の大きい市場として、注目を集めている。2009年に発足したハシナ政権は、物価対策や外交などで一定の成果を上げているものの、厳しい与野党対立の下で政権を運営しており、2013年末から2014年初頭にかけて実施が見込まれている次期総選挙に向けて、与野党間の対立が高まりつつある。
経済面では、近年6%以上の経済成長率を維持しており、縫製品を中心とした輸出も好調を維持しているが、電力・天然ガスの安定した供給が引き続き課題となっている。また、海外移住者や出稼ぎ労働者からの海外送金が多いのが特徴で、名目GDPの1割弱を占めている。進出日系企業数は61社(2005年)から135社(2012年)に増加しており、バングラデシュの対日輸出も繊維品を中心に大幅に増加している。
日本との関係では、2012年は国交樹立40周年に当たり、5月には岡田副総理大臣が、3月には日バングラデシュ友好議員連盟メンバーが、それぞれバングラデシュを訪問した。

ウ ネパール
ネパールでは、2006年11月の包括的和平合意(2)を受けて、2008年に制憲議会が招集されて以来、憲法制定の取組が行われている。主要政党間の対立により、当初2年間の制憲議会任期が計2年間延長されたが、2012年5月、憲法制定に至らないまま制憲議会が任期満了のため解散された。現在、マオイスト暫定政府の下で、憲法制定プロセスを軌道に戻すための合意形成の努力が主要政党間で続けられている。日本もこれまで、国連ネパール政治ミッション(UNMIN)への要員派遣、選挙支援、法制度整備などネパールの民主主義の定着を支援してきた。日本との関係では、2012年1月にシュレスタ副首相兼外相が訪日し、5年ぶりの外相会談を行ったほか、4月には玄葉外務大臣が日本の外務大臣としては35年ぶりにネパールを訪問し、同年2度目の外相会談を行った。
エ ブータン
ブータンでは、2008年に王制から立憲君主制に平和裏に移行し、ティンレイ政権の下で民主化定着のための取組が行われている。政府は、国民総幸福量(GNH)を国家運営の指針とし、第10次5か年計画の課題である貧困削減、基礎インフラの整備、農業生産性の向上に取り組むとともに、GNHの国際社会における普及・発展にも力を入れ、第65回国連総会において、ブータンや日本を含む多数の国が共同提案国となり、「幸福」に関する決議がコンセンサスで採決された。この決議に基づき、2012年4月には、ブータンの提唱により、国連本部にて「幸福に関するハイレベル会合」が開催された。2011年の外交関係樹立25周年の際のジグミ・ケサル国王及びジツェン・ペマ王妃両陛下の国賓としての訪日は、ブータンに対する親近感を高める契機となり、2012年上半期には、ブータンを訪れる外国人観光客のうち、日本人観光客の数が最多を記録するなど、両国の交流が様々な分野・レベルで一層活発化している。
オ モルディブ
モルディブでは、与野党対立により政情が不安定化し、2012年2月、野党による反政府デモを契機として、ナシード大統領が辞意を表明し、ワヒード副大統領が新大統領に就任した。なお、この政権交代については、8月に国家調査委員会が、合法かつ合憲であると結論付ける報告書を公表している。
日本との関係では、1月に、ナシーム外相が訪日し、外相会談において国際場裏での協力や二国間協力関係についての意見交換が行われた。
(4)南アジア地域協力連合(SAARC(3))
日本は2007年からSAARCにオブザーバーとして参加し、民主化・平和構築、域内連携促進、人的交流促進などへの支援を通じて南アジアの域内協力を支援しており、4月には駐ネパール大使をSAARC担当大使に任命するなど関係強化に努めている。日本はこれまでSAARCへの拠出金などを通じて、域内共通の課題であるエネルギー、防災などの分野での域内協力事業を実施しており、また、日・SAARC間の青少年交流の一環として「21世紀東アジア青少年大交流計画」に基づき、2007年から2011年までの5年間で、高校生、理工系大学生、日本語学習者・教師など約900人の青少年をSAARC各国から招へいした。2012年には、日本再生に関する外国の理解増進や風評被害に対する効果的な情報発信など東日本大震災の被災地支援を目的とした「アジア大洋州及び北米地域との青少年交流」の一環で、約440人の青少年を招へいした。

1 スリランカでは1983年から25年以上にわたり、スリランカ北部・東部を中心に居住する少数派タミル人の反政府武装勢力であるLTTEが、北部・東部の分離独立を目指し、政府側との間で内戦状態にあった。政府軍は、LTTEを徐々に追いつめ、2009年5月、戦闘終結を宣言した。
2 ネパールは、1990年の民主化運動を経て国王親政から立憲君主制に移行したが、マオイスト(共産党毛沢東派)が武装闘争を開始した。ネパールの政党はマオイストと連携し、2006年5月、国王の政治・軍事に関する諸権限の廃止を決めた。同年11月、ネパール政府とマオイストは、約10年に及んだ紛争の終結を含む包括的な和平合意に署名した。
3 南アジア諸国による比較的緩やかな地域協力の枠組み。域内人口16億人、域内GDP約2兆円を有する。加盟国は、インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、ブータン、モルディブ、アフガニスタンの8か国。また、日本、中国、米国、韓国、イラン、モーリシャス、EU、オーストラリア、ミャンマーがオブザーバーとして参加している。SAARC憲章は、SAARCの目的として、南アジア諸国民の福祉の増進、経済社会開発及び文化面での協力・協調などを規定している。事務局はカトマンズ(ネパール)に所在。