1 米国
(1)日米政治関係
日米両国間では、首脳・外相レベルを始め、あらゆるレベルで相互の信頼関係の強化と緊密な政策協調が行われている。
2010年1月、岡田外務大臣はハワイを訪問し、クリントン国務長官と日米外相会談を行った。両大臣は、普天間飛行場の移設についてお互いの立場を確認した上で、現行の日米安全保障条約締結50周年に当たる2010年に、今後30年、50年と、日米同盟を持続可能なものに深化させていくための協議プロセスを開始した。また、両大臣は、対アフガニスタン支援、イランの核問題、北朝鮮問題、ミャンマー情勢、気候変動、核軍縮・不拡散などについて積極的かつ建設的な議論を行った。また、現行日米安保条約署名から50年に当たる1月19日には、日米両国の首脳がそれぞれ談話を発表するとともに、日米安全保障協議委員会(「2+2」)の閣僚が共同発表を行い、日米両政府は、二国間関係はもとより、アジア太平洋地域や地球規模の課題における日米協力を強化し、日米同盟を21世紀にふさわしい形で深化させていくことを確認した。
また、3月のG8外相会合に際して行われた日米外相会談においても、岡田外務大臣とクリントン国務長官は、普天間飛行場の移設について、日米間で引き続き協議していくことを確認した上で、北朝鮮、ミャンマー、イランといった幅広い課題について充実した議論を行った。
4月にワシントンにおける核セキュリティ・サミットに際して、鳩山総理大臣は、オバマ大統領との間で意見交換を行った。日米関係については、鳩山総理大臣から日米同盟を一層深化・発展させたい、また、普天間飛行場の移設につき、5月までに決着させたい旨を述べ、この方向で努力していくこととなった。また、オバマ大統領から、イランの核問題に関して提起があり、同問題についても意見交換が行われた。
5月には、クリントン国務長官が、国務長官として2度目となる日本への訪問を行い、日米外相会談及び鳩山総理大臣への表敬を行った。外相会談では、3月に起きた韓国哨(しょう)戒艦沈没事件など、アジア太平洋地域情勢及びイランの核問題への対応を中心に幅広い議題について議論が行われた。中でも、韓国哨戒艦沈没事件について、岡田外務大臣から、今後北朝鮮による更なる挑発行為の可能性も念頭に、日米間で警戒態勢を高めるとともに、外交、防衛、インテリジェンス(情報)の面での協力を一層強化していきたい旨を述べた。これに対し、クリントン国務長官からは、本件を非常に懸念しており、韓国の46名の水兵の命を奪った北朝鮮の行為は休戦協定に違反するものであり、強く非難する旨の発言があり、両大臣は日米韓が緊密に連携していくことで一致した。また、鳩山総理大臣への表敬においても、日米関係の他、韓国哨戒艦沈没事件への対応について意見交換が行われた。
5月28日、日米両政府は、「2+2」共同発表において、普天間飛行場の移設についての方向性を示すとともに、日米同盟を21世紀の新たな課題にふさわしいものにすることができるよう幅広い分野における安全保障協力を推進し、深化させていくことを確認した(第3章第1節1「日米安全保障体制」参照)。
6月に就任した菅総理大臣は、第174回国会における所信表明演説において、日米同盟を外交の基軸とする旨を述べ、日米同盟は日本の防衛のみならず、アジア太平洋の安定と繁栄を支える国際的な共有財産であり、今後も同盟関係を着実に深化させることを明らかにした。そして、同6月、G8・G20サミット出席のためカナダを訪問した際、オバマ大統領と首脳会談を行い、同会談において、両首脳は、日米同盟が日本のみならずアジア太平洋地域の平和と繁栄の礎であることを確認し、引き続き日米で緊密に連携していくことで一致した。また、両首脳は、北朝鮮、イラン、アフガニスタン・パキスタンや、地球規模の課題についても建設的な意見交換を行った。
7月、東南アジア諸国連合(ASEAN)関連外相会議出席のため、ベトナムを訪問していた岡田外務大臣は、ハノイにおいてクリントン国務長官と外相会談を行った。両大臣は、同盟の深化について引き続き日米間で議論を継続し、11月の横浜でのAPEC首脳会議の際のオバマ大統領訪日の成功に向けて、緊密に意思疎通をすることで一致した。また、同会談では、朝鮮半島情勢、中国、イランの核問題、国連安保理改革についても積極的な意見交換が行われた。
9月の国連総会に際しては、菅総理大臣とオバマ大統領との間で、また前原外務大臣とクリントン国務長官との間で、それぞれ日米首脳・外相会談が行われた。首脳会談では、菅総理大臣が、日米同盟を安全保障、経済、文化・知的・人的交流の三本柱で深化させていきたい旨を述べたのに対し、オバマ大統領は、その3つの分野の重要性について完全に同意する旨を述べた。日米首脳・外相両会談において、中国、北朝鮮などアジア太平洋地域についても議論が行われ、両首脳・大臣は、最近の海洋を巡る問題について関心を持って注視するとともに、今後、日米で緊密に連絡をとっていくことで一致した。外相会談においては、クリントン国務長官から、日米安保条約第5条が尖閣(せんかく)諸島に適用されることが改めて確認された。また、日米首脳・外相両会談において、イランに関し、日本が安保理決議第1929号の履行に付随する措置を決定したことについて、オバマ大統領及びクリントン国務長官がそれぞれ謝意を表明した(第2章第6節3「イラン」参照)。
上記日米首脳会談及び外相会談を踏まえ、10月に前原外務大臣がハワイを訪問した際に行われた日米外相会談では、両大臣は、安全保障、経済、文化・人材交流を三本柱として、日米同盟を21世紀にふさわしい形で深化させることで一致した。具体的には、前原外務大臣から、日米安保協力の着実な強化、二国間の経済対話の強化、クリーン・エネルギー及び高速鉄道などでのパートナーシップの推進、日米両国の様々な層における相互理解・交流の促進に向けて緊密に連携していきたい旨を述べた。また、同会談の翌日、クリントン国務長官は「米国のアジア太平洋への関与」と題する講演の中で、日米同盟がアジア太平洋地域における米国の関与の礎である旨を改めて述べ、過去50年間と同様に、日米同盟が今後50年間も効果的なものとなるよう、戦略的環境の変化に合わせて日米の協力関係を拡大していく旨を表明した。
11月、菅総理大臣は、横浜で開催されたAPEC首脳会議出席のため来日したオバマ大統領との間で3回目となる日米首脳会談を行った。同会談で両首脳は、日米同盟の深化・発展について一致し、また、オバマ大統領から菅総理大臣に対し、2011年前半の米国訪問に向けた招待があり、菅総理大臣が訪米した際に、21世紀の日米同盟のビジョンを共同声明のような形で示すことで両首脳は一致した。さらに、中国、北朝鮮を始めとするアジア太平洋地域、国連安保理改革、アフガニスタン・パキスタン、核セキュリティ・核軍縮といった地球規模の課題についても積極的な意見交換が行われた。そして、会談終了後、日米双方で「新たなイニシアティブに関するファクトシート」及び「核リスク低減に関する日米協力」の文書を発表し、また、日本側から、ファクトシート「日米同盟深化のための日米交流強化」を発表した。
11月下旬、北朝鮮によるウラン濃縮計画が発覚し、また、延坪島(ヨンピョンド)(韓国)に対する砲撃事件が発生したが、これについて日米は迅速に対応し、かつ緊密な意見交換を行った。同事件後直ちに日米外相電話会談が実施され、両大臣は、今後の対応に当たっても日米及び日米韓で引き続き緊密に連携していくことを確認し、12月6日には、クリントン国務長官主導の下、日米外相会談及び日米韓外相会合がワシントンにおいて実施された。日米外相会談では、六者会合議長国である中国が北朝鮮との関係でより一層大きな役割を果たすことを期待し、中国及びロシアとの連携を一層強化していくことを確認した。続く日米韓外相会談においては、北朝鮮の挑発行動に対して、北東アジアの平和と安定のため、日米韓の3か国が引き続き緊密に連携して取り組むという強い決意を持って臨むことが確認された(第2章第1節1(1)「北朝鮮」参照)。
2011年1月、前原外務大臣は、ワシントン及びフロリダ州訪問のため訪米し、外相就任後4回目となる日米外相会談を始め、バイデン副大統領への表敬、連邦議員や有識者との意見交換、米国のシンクタンクである戦略国際問題研究所(CSIS)での「アジア太平洋に新しい地平線を拓(ひら)く」と題する講演、スコット・フロリダ州知事との会談などを実施した。CSISにおける講演で、前原外務大臣は、日米両国に課せられた最優先の課題が、変革期のアジア大洋州地域における新しい秩序形成に取り組むことであり、具体的な分野として東アジア首脳会議(EAS)の役割の拡充・強化や、APECにおける連携、成熟した民主主義や市場経済を共有する国々との連携を強化することによる安全保障・経済の両面における協力システムの構築などを挙げた。また、日米外相会談では、2011年前半の菅総理大臣訪米に向け、日米同盟の深化の中身を詰めていくことを再確認し、安全保障協力、高速鉄道、文化・人材交流といった個別案件について外相間でしっかりとした議論を行い、21世紀の日米同盟のビジョンを示す文書を作成すべく、日米間で今後とも緊密に協議を行うことで一致した。また、強固な日米同盟に基づき、アジア太平洋の平和と安定、繁栄の観点から東アジア情勢及びこの地域の諸課題について共に取り組んでいくことについて議論した。

(2)日米経済関係
世界経済情勢が変化する中で、日米が両国経済のみならず、アジア太平洋地域経済、世界経済の新たな成長を実現し、地球規模の課題に対処するため、経済分野における協力を更に強化していくことが重要となっており、これは日米両首脳が目指す日米同盟深化の三本柱の一つを成している。
日本がAPEC議長を務めた2010年は、2011年の議長である米国と、アジア太平洋地域の更なる成長、統合に向けた連携が進んだ1年であった。3月に行われた日米外相会談の際には、「日米APEC協力に関するプレス・ステートメント」が発表され、両国が地域経済統合の推進、地域の新たな成長パラダイム(枠組み)の構想などについて協力して指導力を発揮し、さらに、食料安全保障、女性起業家支援、気候変動、防災といった分野で具体的イニシアティブに共同で取り組んでいくことが確認された。この後、両国は横浜APECの成功に向け緊密に連携し、10月の日米外相会談では、APEC協力の進展を確認した。さらに、11月の前原外務大臣とカーク通商代表の会談では、2011年の米国APECの成功のために引き続き協力していくことで一致した。
11月の横浜APECの際の日米首脳会談では、この直前に日本で閣議決定された「包括的経済連携に関する基本方針」も踏まえ、日米二国間や環太平洋パートナーシップ(TPP)を含むアジア太平洋における貿易・投資などの自由化について、協議を行っていくことで一致した。2011年1月にはワシントンで両国間の貿易・投資などに関する問題を幅広く議論する「日米貿易フォーラム」が開催され、日本による情報収集の一環としてTPPも取上げられた。
幅広い分野での二国間の対話・協力も進み、11月の日米首脳会談では、「新たなイニシアティブに関するファクトシート」が発表された。その中で、日米間の経済関係を更に強化するために、日米経済調和対話、イノベーション・起業・雇用創出促進のための日米対話及びインターネットエコノミーに関する日米政策協力対話が立ち上げられた。日米経済調和対話は、貿易円滑化、ビジネス環境の整備、個別の問題への対応、共通の関心を有する地域の課題などについて、日米両国が協力をして取り組んでいくために開催するものである。また、この首脳会談前に、日米の航空会社が両国間の路線や便数を決定することを可能にする日米のオープンスカイ合意が発効し、日米間の往来の促進が図られた。さらに、2009年11月の首脳会談で協力推進につき一致したクリーン・エネルギー分野では、日米共同のスマートグリッド実証実験、沖縄-ハワイ協力のためのタスクフォースの設置など、協力体制が築かれ、先述のファクトシートにおいて、日米クリーン・エネルギー政策対話が立ち上げられた他、アジア太平洋地域の持続可能な成長及び長期的な雇用の創出を下支えする、エネルギー・スマートコミュニティ・イニシアティブも開始された。また、10月の日米外相会談では、レアアースなど戦略資源の安定供給確保について協力していくことで一致し、実務者間の連携が進んでいる。一方で、11月の前原外務大臣とカーク通商代表との会談では、カーク代表から米国産牛肉輸入問題及び保険についての提起があった。米国産牛肉輸入問題に関しては、2011年1月の日米外相会談では、この問題に関し、引き続き議論していくことが確認された。
この他、オバマ政権が推進している高速鉄道計画への日本の技術の導入を図るため、菅総理大臣、前原外務大臣などのハイレベルから積極的な働きかけを実施した他、米国での高速鉄道セミナーの開催なども行った。5月のラフード運輸長官、9月のシュワルツネッガー・カリフォルニア州知事などの訪日の際には、新幹線への試乗などを通じて、日本の高速鉄道技術に対する理解促進を図った。さらに、超電導リニアに関する日米協力の推進にも取り組んでいる。
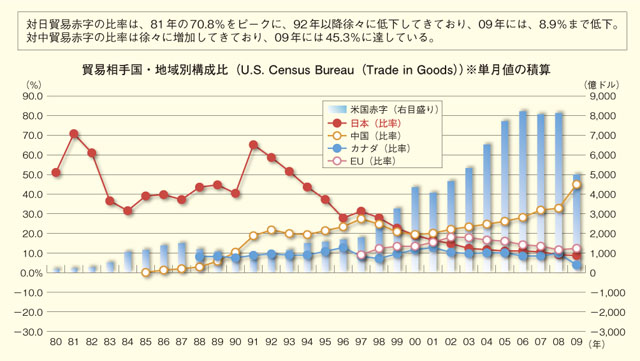
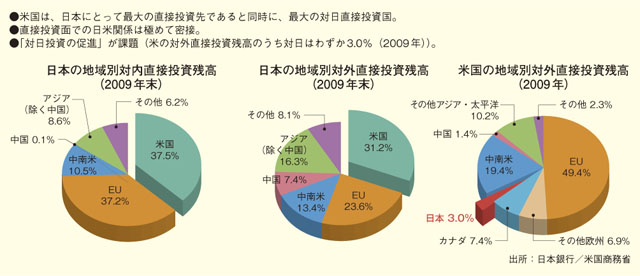
(3)米国情勢
ア 政治
発足2年目を迎えたオバマ政権にとって、2010年の最重要課題は、回復の遅れている経済・雇用情勢への対処であった。オバマ大統領は、1月27日、就任後初となる一般教書演説を行い、政権2年目の最優先課題は雇用対策であることを明確にするとともに、医療保険制度改革、金融規制改革、教育改革などに引き続き取り組む決意を表明した。
米国議会では引き続き党派対立が厳しい状況にあったが、オバマ大統領は共和党議員の切り崩しに成功し、3月には歴史的業績とも言える医療保険制度改革法の成立を実現させた。また、7月には金融規制改革法を成立させるという大きな成果を上げた。
一方、経済・雇用情勢の回復は思わしくなく、失業率は引き続き10%近くにとどまった。大規模な財政出動を伴う雇用対策には共和党のみならず民主党内保守派からも反対の声が上がる中で、オバマ政権は有効な対策を打ち出せない状態が続いた。さらに、メキシコ湾原油流出事故など不測の事態の影響で、これまでの実績を効果的に広報することもできなかった。この結果、大統領の支持率は40%台半ばを前後するようになり、夏以降不支持率が支持率を上回る状況が続いた。
このような中、11月2日に中間選挙が実施された。4年に1度行われる大統領選挙の中間の年に行われる中間選挙は時の大統領の業績に対する評価との側面があり、大統領の所属政党は議席を減らす傾向にある。特に11月の選挙では、景気・雇用回復の遅れに伴う国民の経済面・生活面での不安感、ワシントン政治における党派対立の激しさといった状況への責任が問われ、政権党である民主党にとって非常に厳しい結果となった。同党は、上院では多数を維持したものの、下院では、第二次世界大戦後最多となる63議席を失い、2011年1月からの新議会期において共和党に多数党の地位を奪われることとなった。
この結果を受け、翌3日オバマ大統領は記者会見を行い、選挙結果は政府の経済運営や景気・雇用回復のペースに対する国民の不満の表れとの見方を示し、責任が大統領自身にあることを率直に認めた。同時に、今後は経済再生に向け党派を超えた協力が必要と呼びかけた。
選挙後から会期末までの間に改選前の議員構成で開催されるいわゆるレームダック・セッションで、オバマ大統領は、ブッシュ前政権時代に法制化された大型減税(ブッシュ減税)の延長問題を巡り共和党との間で妥協を成立させるとともに、新戦略兵器削減条約(START)締結の上院による承認や、同性愛者がその事実を公表して軍務に就くことを禁ずる政策(「見ざる、言わざる政策」)の撤廃などの成果を上げた。今後、小さな政府を志向し、オバマ政権のこれまでの経済運営に反発するティー・パーティー系議員を含む共和党議員が増加した新議会期において、オバマ大統領が前会期末と同様に共和党との妥協を成立させ、成果を上げることができるかが注目される。
イ 経済
(ア)総論
2008年のいわゆるリーマン・ショック以降、米国政府は、総額7,000億米ドルの不良債権買取プログラム(TARP)による公的資本注入など、金融機関支援を実施するとともに、悪化する実体経済に対し、2009年2月に成立した米国・再生再投資法(ARRA)などに基づき、景気刺激策を進めた。それらの政策効果もあり、2009年第3四半期以降、国内総生産(GDP)成長率はプラスに転じ、2010年を通じて景気は緩やかに回復した。しかし、失業率が10%近い水準で高止まりするなど景気回復が停滞するリスクは残るとともに、財政赤字が拡大しており、経済回復と財政再建の両立が政府の優先課題となっている。
2011年1月の一般教書演説においてオバマ大統領は、雇用創出と米国企業の競争力強化のため、クリーンエネルギーを始めとするイノベーション、教育及び高速鉄道を含むインフラへの投資を促進する方針を示すとともに、2014年までの輸出倍増に改めて言及した他、国内雇用に資する貿易協定の追求、国内の制度・規制の見直しなどにも言及した。また、今後5年間の国内支出の凍結など、財政再建、税制改革、医療保険制度改革を始め、主要な国内課題に対処する強い意思を示した。
(イ)各論
米国連邦準備制度理事会(FRB)は、11月に開催された米国連邦公開市場委員会(FOMC)定例会合において、8月のFOMC時に公表した保有証券の償還元本の再投資を維持する他、長期の米国債を2011年第2四半期末までに更に6,000億米ドル購入する旨を発表した。この追加的金融緩和は、経済回復を支え、インフレ率低下のリスクを減少させることが目的とされている。
12月には、2010年末に期限を迎えるいわゆる「ブッシュ減税」の全国民に対する2年間延長を含む共和党との枠組み合意が発表された。これを受け、同月、遺産税減税、失業保険給付延長、研究開発減税、設備投資減税なども含む包括的な減税法が成立した。
また、過去2年間の深刻な不況を招いた主な要因が金融システムの崩壊にあるとして、7月には、銀行などの自己勘定取引禁止を盛り込んだいわゆる「ボルカールール」を含む金融規制改革法が成立した。3月には、将来的に米国民の約95%が医療保険に加入(無保険者3,200万人を解消)することを可能にする、医療保険改革法が成立したが、本改革の議論は国民世論を二分し、有権者の賛否は拮(きっ)抗している。
通商面では、2010年の一般教書演説でオバマ大統領が提案した「国家輸出イニシアティブ」に基づき、向こう5年間での輸出倍増を目指し、様々な輸出促進策がとられた。例えば、12月には米韓FTAの補足合意が発表された他、2011年11月のホノルルでのAPEC首脳会合に向け、TPP協定交渉が精力的に進められている。

