気候変動
小島嶼開発途上国向け緑の気候基金レディネス支援ワークショップ
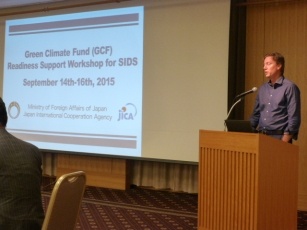


9月14日(月曜日)から16日(水曜日)の3日間,外務省と国際協力機構(JICA)との共催により,大洋州地域を中心とする島嶼国16カ国及びGCFと協働する7つの国際機関等の担当者等を招待して,東京において「小島嶼開発途上国(SIDS)向け緑の気候基金(GCF)レディネス支援ワークショップ」が開催された。
本件ワークショップは,本年5月に我が国が15億米ドルの拠出を決定した,GCFを活用した気候変動対策のための案件実施に必要な要件や,準備の進め方などに関する実践的な理解を深めることにより,それぞれの国における案件形成の促進を図ることを目的に開催したもの。
ワークショップでは,GCF事務局による案件形成までのプロセスに関する説明や,参加国・機関による取り組み事例の発表が行われ,GCFの活用に向けた課題やその解決策などについて活発な議論が行われた。また,SIDSで実施されている日本企業による気候変動対策事業に関するプレゼンテーションや展示施設の視察も行われ,参加者は我が国の先端環境技術について理解を深めた。
各セッションの概要は以下のとおり。
9月14日(月曜日)
1 気候変動分野における日本のSIDS支援
外務省から,我が国の適応分野における途上国支援体制である「適応イニシアチブ」や,GCFへの拠出,本年5月に開催された第7回太平洋・島サミットで発表された日本の支援策等について説明した。JICAからは,太平洋地域の島嶼国等で実施してきた支援例を紹介した。これに対し,島嶼国側からは我が国からの支援に対する感謝の意が表明された。また,我が国企業3社から護岸保護,マイクログリッド及び無収入水量削減に関する島嶼国での事業実施事例に関するプレゼンテーションが行われ,出席者は熱心に耳を傾けるとともに,各事業の効果やコストなどに関する活発な質疑応答が行われた。
2 GCFとの協働に必要な戦略的枠組み策定
GCF事務局からGCFとの協働のための要件や,各国のGCF窓口機関(NDA/FP)に期待される役割,レディネス活動の概要等について説明。続いて,GCFによるレディネス支援の供与が決定したクック諸島及びミクロネシアが,申請準備から供与決定までの過程で得た経験に基づき,案件の内容や実施場所等を考慮しつつ,GCFが示す要件を満たす機関をデリバリー・パートナーに指名することが重要である旨指摘。なお,ミクロネシアのプレゼンテーションに先立ち,ローレンス同国財務・管理大臣が気候変動分野における日本のSIDSへの支援に対し謝意を述べるとともに,11月のGCF理事会におけるSIDS向け案件の採択への期待を表明した。
午後のセッションでは,サモア及びドミニカ共和国がそれぞれの戦略的枠組み策定作業について発表。関係機関との連絡調整と情報共有の徹底,取り組むべき事項の優先順位付け,市民社会や民間企業の参画促進,GCF事務局との連携強化等の重要性を指摘した。
9月15日(火曜日)
1 GCF案件形成
GCF事務局からの案件形成プロセスに関する説明に続き,現在案件の形成が進められているフィジーおける上下水道管理事業(認証機関:ADB)及びツバルにおける護岸事業(認証機関:UNDP)について,事業実施国と認証機関がそれぞれの立場から,事業の概要や案件形成作業の進捗状況や,これまでの成果,今後の課題等について発表した。発表者からは,困難であった点として,11月のGCF理事会において審査を受けるための時間が限られていたことや,案件形成に当たってGCF事務局から求められる情報が膨大であったことを挙げた上で,認証機関や関連部署との役割分担を明確にし,緊密に連携していくことの重要性等が指摘された。
2 気候変動関連技術に関する日本企業展示施設の視察
ワークショップ参加者は,都内にある総合電機メーカーの環境技術に関する展示施設を訪問。同社による島嶼部での水やスマート・エネルギー関連事業などに関するプレゼンテーションに真剣に聞き入っていた。参加者からは,日本の先進的な技術・取組の島嶼国への展開に関する実例を知る貴重な機会となったとの感想が述べられた。
9月16日(水曜日)
1 GCF案件形成(15日からの続き)
GCF事務局より,GCFの資金供与手段に関する説明が行われ,プロジェクトに最適な資金供与手段の種類を事例毎に相談しながら決めていくことの重要性が示された。世界銀行からは,プロジェクトに民間資金を呼び込む必要性が指摘され,世銀グループが民間機関と共同で行っているプロジェクトの事例(太平洋リスク保険,地熱開発計画など)が紹介された。パラオ開発銀行からは,2020年までに再生可能エネルギーをエネルギー源の20~30%にするという国家目標と,そのためにパラオ開発銀行が行っている省エネルギーの家屋を建設するためのローンや補助金の紹介がおこなわれた。最後にJICAから,インドとエチオピアで民間企業と共同で行っている融資や保険のプロジェクトを紹介した。
2 機関認証プロセス
GCF事務局より,実施機関として認証されるためのプロセスや必要要件,認証の種類などの説明が行われ,各国が案件ごとに最適な実施機関とパートナーシップを組んでプロジェクトを形成することの重要性が指摘された。太平洋地域環境計画(SPREP)からは,GCFの実施機関プロセスは,大量の資料が求められ,時間を要する非常に大変な作業であると述べた上で,GCF事務局と話し合いながら進めていくことや認証のための専属チームを作ることが望ましいなどのアドバイスが示された。また,フィジー開発銀行(FDB)より,同行が実施している環境配慮型プロジェクトに関する説明の後,GCF実施機関として承認されるまでの課題等について説明があった。最後にモルディブからは,国で行われている数々のプロジェクトをコーディネートする機関の必要性を指摘した上で,モルディブ・グリーンファンド・プロジェクトについて説明した。
3 グループディスカッション
2つのグループに分かれてディスカッションを行い,最後にそれぞれの議論の内容を共有した。グループAからは,各国のGCF窓口機関をその国の事情に応じた最も適切な場所に設置することの重要性と,プロジェクト形成の際は,最適な技術的な解決策について地域コミュニティーと十分に対話を重ねることの重要性が指摘された。グループBからは,GCFが実施機関の認証やレディネス支援,案件承認に柔軟性を持つ必要性や,承認プロセスを簡略化する必要性が指摘されると共に,案件承認プロセスにおける透明性と一貫性の必要性が指摘された。参加者からの声により,本会合で話し合われた要点をまとめて小島嶼国やGCF内で共有することとなった。

