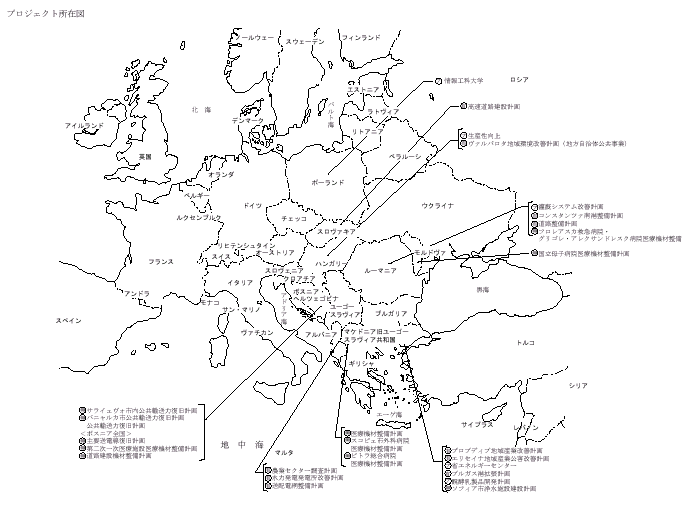国別援助実績
1991年~1998年の実績
[20] 旧ユーゴースラヴィア地域
(1) 旧ユーゴースラヴィアは、第一次大戦を契機に成立し、6共和国と2自治州からなる多民族連邦国家であった。第二次大戦時にパルチザンを率いて対独レジスタンスを戦い抜き国土を解放したチトー大統領の下、各民族に配慮した連邦制を採用し、自主管理に基づく社会主義の建設を目指す一方、対外的には非同盟主義のリーダーとして独自の道を歩んだ。しかし、もともと言語・宗教が複雑に混在する中で、1980年にチトー大統領が死去した後は、石油危機以降の経済不振もあり、民族対立が次第に表面化し拡大した。89年の東欧における民主化の波の影響により、各共和国で民族主義が高揚し、対立は一層深刻化した。
91年夏からは分離独立派の共和国・民族と連邦維持派の共和国・民族との間で武力衝突に発展し、クロアチアには国連平和維持部隊が投入され、92年春にはボスニア・ヘルツェゴヴィナで大規模な武力紛争に入り、同共和国にも国連平和維持部隊が派遣された。
(2) これら構成共和国間の対立・紛争を経て、スロヴェニア、クロアチア及びマケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国が91年に独立を宣言、ボスニア・ヘルツェゴヴィナも92年春にセルビア系住民がボイコットした中で実施された住民投票で圧倒的多数で独立に賛成する等、旧ユーゴースラヴィアが事実上解体し、残るセルビア及びモンテネグロも92年4月ユーゴースラヴィア連邦共和国(新ユーゴー)を樹立し、旧ユーゴースラヴィアは5か国に分裂した。
92年5月、国連安保理は新ユーゴーに対し、ボスニア・ヘルツェゴヴィナにおける内戦を理由に包括的な制裁を決議した。そのため、新ユーゴーは内戦の惨禍を受けないまでも、経済活動は壊滅的な打撃を受けるに至った。国連制裁で打撃を受けた新ユーゴーは、ボスニアのセルビア人勢力に対し、国際社会による和平案を受入れるよう説得を続け、また、米国は95年11月オハイオ州デイトンにて紛争三当事者を集め、包括和平協議を開始し、同21日仮署名にこぎつけた(正式署名は12月14日パリにおいて行われた)。この仮署名を受けて翌22日、国連安保理は新ユーゴーに対する包括的制裁措置を全面的に停止させた。更に、96年9月14日に実施されたボスニアにおける選挙の後、10月1日の国連安保理決議で新ユーゴーに対する制裁は全面的に解除された。しかしその後も、国内の民主化、少数民族の扱い(特にコソヴォ地方のアルバニア系住民)、デイトン合意の履行状況等が問題とされていた。
また、新ユーゴーは、旧ユーゴーとの継続性を有する国家であるとの主張を撤回していないため、国連等国際機関への新たな正式加盟を求めておらず、さらにIMF、世銀等の国際金融機関へのアクセスが認められていない。
(3) 98年2月から3月にかけ、コソヴォ自治州でアルバニア系住民の武装組織コソヴォ解放軍(KLA)とセルビア治安部隊の衝突が発生したことに端を発し、コソヴォ問題が拡大、アルバニア系住民対ユーゴー当局のコソヴォでの戦闘が激化した。こうした事態に対し国際社会は政治的解決のために努力し、99年2~3月、3年間を暫定期間とするコ[20]旧ユーゴースラヴィア地域ソヴォ自治のための和平合意案を両者に提示したところ、アルバニア系住民側は合意案に署名したが、ユーゴー側は合意案受入れを拒否した。和平調停決裂後の3月24日、NATOはユーゴーに対する空爆を開始、和平案への合意を迫った。また、国際社会の政治解決に向けての動きが重ねられ、5月6日ボンにおけるG8外相会議を経て、米ロ間の調整が続けられアハティサーリ・フィンランド大統領が調整に加わった上、6月3日に和平案が提示され、ユーゴーのミロシェヴィッチ大統領は受諾を表明した。その後、空爆の一時停止、国連安全保障理事会決議の採択、国際安全保障部隊のコソヴォ展開といった段階を踏んで、6月20日、ユーゴー部隊のコソヴォからの撤退とNATOの空爆が終了した。この対立により発生したコソヴォからのアルバニア系難民の数は95万人にのぼっている。
(4) 我が国は、92年3月にスロヴェニア及びクロアチアを、93年12月にマケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国を、また、96年1月にはボスニア・ヘルツェゴヴィナを国家として承認し、新ユーゴーについては97年5月に外交関係を開設した。(新ユーゴーを除く4か国についての概要及び我が国政府開発援助の実績とあり方の詳細については当該国の記述参照。)
(1) 我が国は、旧ユーゴースラヴィアに対して当初は商品借款等を行っていたが、同国が鉱山資源を豊富に産出し、また工業化も進んでおり、所得が比較的高かったことから、文化無償等若干の資金協力以外はプロジェクト方式技術協力、行政、運輸・交通、工業部門を中心とした研修員受入れや専門家派遣等の技術協力を行っていた。
(2) 90年7月、G24は旧ユーゴースラヴィアを支援対象国と決定したが、その後のユーゴー情勢に鑑み、91年11月、G24は経済協力の停止を決定した。我が国もユーゴーに対し、人道的観点からの国際機関を通じた支援や草の根無償資金協力を除き、援助を停止している。
(3) コソヴォ問題に関連して、我が国はG8の一員として問題の解決に貢献するため、99年4月、総額約2億ドルの支援を行うことを表明した。具体的には、第1に、UNHCR等国際機関への拠出を含めた難民への緊急人道支援として約4,000万ドル、第2に、多数の難民受入れの影響を受けているマケドニア旧ユーゴースラヴィア及びアルバニアに対する支援として2年間で約6,000万ドル(詳細については当該国の記述参照)、第3に、コソヴォの復興と難民帰還等を支援するために今後約1億ドルを拠出することを表明した。さらに、同年7月、コソヴォ難民等に対する追加支援として、総額約2,000万ドルをUNHCR及びWFPへ拠出することを表明した。
| (1) 我が国のODA実績 | (支出純額、単位:百万ドル) |
| 暦年 | 贈 与 | 政府貸付 | 合 計 | |||
| 無償資金協力 | 技術協力 | 計 | 支出総額 | 支出純額 | ||
| 94 95 96 97 98 |
-(-) -(-) 5.32(79) 29.81(92) -(-) |
0.33(100) 0.35(100) 1.42(21) 2.68(8) -(-) |
0.33(100) 0.35(100) 6.73(100) 32.49(100) -(-) |
- - - - - |
-(-) -(-) -(-) -(-) -(-) |
0.33(100) 0.35(100) 6.73(100) 32.49(100) -(-) |
| 累計 | 36.03(60) | 17.05(28) | 53.07(88) | 56.57 | 7.06(12) | 60.12(100) |
(注)( )内は、ODA合計に占める各形態の割合(%)
(2) DAC諸国・国際機関のODA実績
| DAC諸国、ODA NET | (支出純額、単位:百万ドル) |
| 暦年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | うち日本 | 合 計 | ||||||||||
| 95 96 97 |
|
|
|
|
|
6.7 32.5 44.5 |
1,049.3 851.8 715.9 |
| 国際機関、ODANET | (支出純額、単位:百万ドル) |
| 暦年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | その他 | 合 計 | ||||||||||
95 |
|
|
|
|
|
11.3 23.9 42.5 |
561.8 945.2 822.9 |
| (3) 年度別・形態別実績 | (単位:億円) |
| 年度 | 有償資金協力 | 無償資金協力 | 技術協力 | ||||
| 90年度 までの 累計 |
152.27億円 (内訳は、1997年版のODA白書参照、もしくはホームページ参照(http://www.mofa.go.jp/mofaj/b_v/odawp/ |
1.29億円 (内訳は、1997年版のODA白書参照、もしくはホームページ参照(http://www.mofa.go.jp/mofaj/b_v/odawp/ |
7.03億円
|
||||
| 91 | なし |
なし |
0.70億円
|
||||
| 92 | なし |
28.00億円 災害援助 (28.00) |
なし |
||||
| 93 | なし |
42.28億円
|
なし |
||||
| 94 | なし |
22.12億円
|
なし |
||||
| 95 | なし |
63.91億円
|
なし |
||||
| 96 | なし |
33.11億円
|
なし |
||||
| 97 | なし |
26.97億円
|
なし |
||||
| 98 | なし |
33.49億円
|
なし |
||||
| 98年度までの累計 | 152.27億円 |
251.17億円 |
7.72億円
|
(注)1.「年度」の区分は、有償資金協力は交換公文締結日、無償資金協力及び技術協力は予算年度による。(ただし、96年度以降の実績については、当年度に閣議決定を行い、翌年5月末日までにE/N署名を行ったもの。)
2.「金額」は、有償資金協力及び無償資金協力は交換公文ベース、技術協力はJICA経費実績ベースによる。
3.66年度から90年度までの有償資金協力及び無償資金協力実績の内訳は、1997年版のODA白書参照、もしくはホームページ参照(http://www.mofa.go.jp/mofaj/b_v/odawp/index.htm)
| 案 件 名 | 協力期間 |
|
PHC生涯教育 |
84.11~90.11 |
| 案 件 名 |
|
ウルツィニ診療所医療機材整備計画 |