第4章 プロジェクト・ケーススタディ2
フエ市児童福祉総合支援プロジェクトJASS
(ベトナムの「子どもの家」を支える会)
4.1 プロジェクトの背景
4.1.1 ベトナムでの活動の背景
ドイモイ政策がとられ資本主義経済が浸透するなか、南部のホーチミン、それに続き北部のハノイが発展する一方で、それ以外の都市は発展に取り残されている。特に中部の都市は発展が遅れ、また、都市と農村の格差も広がっている。ベトナムにおける貧困問題解決への道のりは未だ遠い状況にあり、その中で社会的弱者である子どもは大きな影響を受けている。
このような状況にあるベトナムを訪れた一人の旅行者であった小山氏が、1993年に再び単身ベトナムに渡り、中部の町フエ市において個人的にストリートチルドレンの支援を始めたのが、JASSの活動の始まりである。
4.1.2 ベトナム「子どもの家」を支える会(JASS)の概要
当初、小山氏はフランスのNGOが建てた子どもの家を通じて、個人資金を使って10人のストリートチルドレンの支援をしていたが、1994年に独自の「子どもの家」を開設するに伴いJASSという組織を設立し、その後も賛同者を増やし活動内容・範囲を広げている。
現在、JASSは日本とベトナムに事務所を持ち、日本には「子どもの家」の子どもの里親として、毎年寄付をしている会員がいる。(2001年5月現在、93名)JASS代表の小山氏自身は、1年の内、9ヶ月をベトナムで過ごし、3ヶ月は日本にて講演活動をしてJASSの活動を広く知らしめながら活動資金を集めている。
4.1.3 開発福祉支援事業に至る経緯、全活動の中での位置付け
開発福祉支援事業が入るまでの活動は大きく分けると、「子どもの家」における活動、と障害児医療センターにおける活動である。ベトナム、フエ市における活動開始後しばらくすると、フエ市より敷地を提供され、JASS独自の「子どもの家」を小山氏の個人資金にて建設し、1994年11月に開設した。それ以降、日本から送られる寄付金、助成金、日本政府の草の根無償資金協力などにより「子どもの家」増築、併設職業訓練センター設立、同児童文化センター設立、奨学金支給等を運営実施している。
さらに、別途1997年より、フエ市キムロン病院の一角に障害児センターを建設し、機材や人件費、運営資金を支援してきた。障害児センターの建設費は国際ソロプチミスト東京あずまからの寄付金による。開発福祉支援事業の前年にパイロット・プロジェクトとして、市内1地区を対象として障害児を見つけ出し、10人程度の手術等の治療、リハビリ、車椅子の提供を小さな規模で行った。
開発福祉支援事業は1999年1月28日~2002年1月27日の3年間の事業として開始された。これにより、「子どもの家」並びにその併設関連施設の一部分が増築され、障害児支援に関しては、パイロット・プロジェクトで行った結果を基に規模が拡大されて実施された。また、従来実施してきたこれらの活動を続けるための財政的基盤を作り、さらに子どもが自立するために上級職業訓練センターが設立された。
4.2 当該プロジェクトの概要
4.2.1 目的・地域・対象
報告書等の書類によれば、当プロジェクトは、トウア・ティエン・フエ省において障害児のリハビリが進むと共に、フエ市のストリート・チルドレン等の福祉が向上することを目的としている。対象は、トウア・ティエン・フエ省における障害児およびフエ市のストリート・チルドレン、その他生活困難な状況にある児童である。具体的な人数等は、以下の主な活動の項に記した通りである。
4.2.2 主な活動
現在までにJASSよってベトナム・フエにて実施された活動は大きく5つに分けられる。
| (1) | 「子どもの家」における子どもの衣食住の確保:孤児や事情により家族と暮らせない子ども達に家を提供する。2001年2月現在において67名の子どもが住んでおり、内61名が幼稚園児~高校生、6名が子どもの家から独立した18歳以上の職業訓練生である。またその他に、在宅支援児童6が26名いる。
|
| (2) | 児童文化活動:「子どもの家」併設で、児童文化センターとして、図書室、音楽室を設置し、また夜間には絵画教室、日本語教室、英語教室を毎日開いている。これらの活動は、情操教育として、希望者に対して提供されており、「子どもの家」の外部からの地域の子ども達も対象としている。
|
| (3) | 職業訓練:「子どもの家」併設の職業訓練センターにおいて「子どもの家」及び地域の子どもを対象として、木工彫刻、刺繍、ミシン、コンピューター教室を開講している。1997年以降の修了者も含む受講者数は、上記の順にそれぞれ11名、42名、46名、208名であり、いずれ家を出て自活して行かなければならない子ども達に技術訓練を提供するのが目的である。
|
| (4) | 職業訓練:上級職業訓練センターにおいて「子どもの家」及び地域の子どもを対象とし、職業技能に直結するようなオートバイ修理等のより高度な職業訓練を実施する。この活動は2001年1月に建設完了し、2月の本調査時点では5名の訓練生が決まりこれからスタートする段階であった。上記4の職業訓練を発展させた技術訓練という目的に加えて、3年程度のちには修理工場として収益を上げ上記1、2の「子どもの家」の運営資金を捻出できる様になることも開設の大きな目的の1つとなっている。
|
| (5) | 障害児支援:トア・ティエン・フエ省内の障害児の実態調査(各地域人民委員会と協力し地元調査員の募集、研修後の調査)、総合健康診断(フエ医科大学診療チーム)、手術の実施(協力医療機関)、リハビリテーション、車椅子贈呈などを通じて、障害児の日常生活の向上を図る。 |
上記の活動の内、(1) (2) (3) は「子どもの家」で、(4)は「上級職業訓練センター」で、(5)はキムロン病院障害児センターで、実施されている。
4.2.3 開発福祉支援事業に関わる部分の活動
前項のうち、開発福祉支援事業によって実施されている活動は、(2)、(3)、(4)、(5)の一部である。それぞれの活動について、開発福祉支援事業によって今までに実施された内容の詳細を以下に記す。
| (2) | 図書室、音楽室、絵画教室の機材・備品・椅子机等を整備し、また、日本語教室、英語教室のAV機器やテープ教材等の整備と教師の給与の一部を支給した。 |
| (3) | 日本語教室、英語教室、コンピューター教室、刺繍教室、ミシン教室の機材・備品を整備した。 |
| (4) | 上級職業訓練センターの建設を実施した。 |
| (5) | トア・ティエン・フエ省内2157名の子どもに対して健康診断を行い、内、701名に手術を実施、535名にリハビリテーションを実施、65名にベビーカーを贈呈、121名に歩行用等補助道具を贈呈、91名に眼鏡を贈呈、キムロン病院にリハビリ器具を贈呈した。 |
さらに表4.1に、JASSによるそれぞれの施設建設の資金源を示し、開発福祉支援事業によって実施された部分を明らかにする。
表4.1 JASS各施設の建設資金源
| 建物 | 用途 | 資金源 | |
| 子 ど も の 家 |
A棟1階 | 子どもの部屋 | 小山氏個人資金、友人らによる寄付 |
| A棟2階 | 子どもの部屋 | 草の根無償資金協力 | |
| B棟1階 (職業訓練センター) |
縫製教室 | 草の根無償資金協力 (ミシンを含む) |
|
| B棟2階 (児童文化センター) |
音楽室、図書室 | 静岡中央ライオンズクラブ (パソコン12台、プリンター2台、TV、ビデオの備品を含む。) |
|
| C棟1階 (職業訓練センター) |
縫製教室 | 国際ソロプロチミスト京都西山寄付金 | |
| C棟2階 (児童文化センター) (職業訓練センター) |
絵画教室、コンピューター教室、語学教室(日本語、英語) | 開発福祉支援事業 (家具類、パソコン、テレビ、テープレコーダー、などの備品を含む) |
|
| キムロン病院障害児医療センター | 障害児治療のための事務局 | 国際ソロプロチミスト東京あずま 開発福祉支援事業(リハビリ器具) |
|
| 上級職業訓練センター (「子どもの家」から離れた敷地にある施設) |
バイク修理訓練施設(将来は他の職業訓練にも活動を広げる予定) | 開発福祉支援事業(建物) 訓練機材はバイク生産企業寄付 |
|
なお、表4.1に記載の建設資金のほか、開発福祉支援事業より、日本語教室、英語教室、絵画教室の講師料の支援を受けた。尚、「子どもの家」のスタッフの給料はJASSより出ているが、開発福祉支援事業からは出ていない。
4.2.4 実施体制
開発福祉支援事業による部分の実施体制のみを説明するのは不可能であるので、JASSによる活動全体の実施体制をここでは説明する。
JASSベトナム事務所には、事務所長である小山氏を筆頭に、日本人副事務所長、その他3人のベトナム人所員(含むボランティア1名)が勤務している。ベトナム人所員は、3人共、フエ師範大学の日本語学科の卒業生であり、小山氏が同大学で日本語を教えていた頃の、生徒である。
JASSはフエ市人民委員会外務部と良好な関係を保ち、活動の方針や方向性を、JASSが外務部と相談し合いながら、プロジェクトを実施している。フエ市人民委員会外務部では、1993年来、小山氏との窓口となってきたニャン氏がキーパーソンである。
今回の共同評価での訪問時に、JASS並びにフエ市人民委員会より明確な組織構造の説明は受けなかったが、実施体制の概念図は、図4.1の通りである(調査団作成)。形式上は、「子どもの家(含む文化センターや職業訓練センター)、及び併設上級職業訓練センターの最高責任者は、小山氏とフエ市長となっており、いずれの施設の土地もフエ市より無償提供を受けている。障害児医療センターも所長、副所長はフエ市立キムロン病院院長、副院長が兼務している。いずれの施設に関しても、フエ市人民委員会職員の1ないし数名が出向の形で事務担当、寮長、顧問などの立場で勤務しているが、出向元の機関は、活動の運営に関して関係を持ってはおらず、最終的な運営責任はJASSにある。また、人件費その他運営に関わる経費は、一部を除いて7ほとんど全額JASSが負担している。
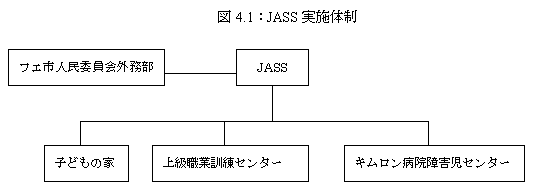
それぞれの施設で勤務するスタッフの種類および人数を以下に示す。
<子どもの家>
人民委員会派遣の委員長、寮長(各1名)
寮母4名、後は各1名―副委員長、会計係、医師、図書館管理者、裁縫教師、コンピューター教師、調理員、警備員。いずれも8時間フルタイム勤務。寮母は交代で1名の夜勤。
<上級職業訓練センター>
人民委員会外務部派遣の顧問1名、バイク修理の技術者1名、その他事務員2名
<キムロン病院障害児センター>
人民委員会外務部派遣の顧問1名、所長1名(キムロン病院長を兼務))、副所長1名(キムロン病院副院長を兼務)、事務局長1名(医師)、事務所員
4.3 現地調査結果
4.3.1 プロジェクト目標の達成度・効果
障害児に関しては、病気も含め障害を持った子どもに対して、治療・リハビリテーションが行われ、支援対象となった子どもに直接効果が現れている。ストリートチルドレン等に関しては、「子どもの家」併設の児童文化センターと職業訓練センターが増築され、備品が整い子ども達に利用されていること、上級職業訓練センターが建設され、まもなくバイク修理教室が開講されることを確認した。
しかしながら、児童文化センター、職業訓練センター、上級職業訓練センターによる効果はまだ時を待たなくてはならない。またこれら3つの活動に関して、事業としての具体的達成目標を明確に設定し取り組んではいないようである。福祉的側面の強い日常生活支援のような活動において「達成目標」を設定するのは難しいと思われるが、例えば職業訓練においては必要であろう。上級職業訓練センターは、子どもへの職業訓練ばかりでなく、「子どもの家」の経済自立策として実施されているのであるので、経済面での達成目標やその実現可能性の検討などが不可欠である。
4.3.2 プロジェクト効果や活動の持続性
本プロジェクトは実施パートナーであるフエ市人民委員会にも高く評価されており、人民委員会はこの活動を継続して行きたいと考えている。しかしながら、フエ市当局自身未だ手がけていない福祉事業をJASSが財政的に事実上丸抱えしているため、地元当局に予算的、組織的にも受け皿体制が整っているとは言えない。JASSは当初計画通り事業開始後10年すなわちこれから3年後に手を引く予定であるが、事業の自立、継続性をいかに確保するかが今後の大きな課題である。
JASSは、「子どもの家(児童文化センター、職業訓練センターもその一部)」の維持費創出のため、上級職業訓練センターで子どもに対してバイク修理の職業訓練を行い、卒業生によるバイク修理による収入の一部を維持費に回すことを考えている。上級職業訓練センターは、プロジェクト活動の持続のためばかりでなく、子ども自身の自立のためでもあるが、このセンターが期待された成果を出せるかどうかについては、センターが始まったばかりの現時点では、まだ何とも言えない状況である。また病気・障害児の治療をさらに続けていくための資金目処もまだ立っていない。
JASSは今後もある程度の資金援助を行っていくことが必要であると考えられ、実際JASSが引き上げる3年後以降も、少なくとも、子どもの家の各児童が日本の里親から受ける寄付の部分は続行される見通しである。その一方で、フエ市も、電気・水道代等の公共料金の免除、派遣している市職員の給与支払い等8より一層の負担を引き受けていくよう努力することが望ましい。障害児童支援についても受益者負担等の工夫の余地があるであろう。今後の活動には事業計画(活動計画)と予算案と、どう終了させていくのかの計画案が欠かせないと思われる。
以上のように今までのJASSの活動を持続させるために不可欠である財政基盤は、まだ整っていないが、人材という側面で見ると、小山氏の教え子の何人かが、事業推進の中核に育っていることは具体的成果であると言え、今後の事業の持続に向けて彼らに期待したいところである。
4.3.3 開発福祉支援事業としての妥当性
SCJプロジェクトの場合同様、このプロジェクトが開発福祉支援事業対象案件として妥当であったかどうかを、「住民への直接裨益」「住民参加」「ソフト支援」の3要件を満たしているかどうかで、開発福祉支援事業としての妥当性を評価する。JASSプロジェクトでは、次に示すように、3要件のうち「住民への直接裨益」を満たすに留まっている。
(1) 住民への直接裨益
受益対象となった病気または障害を持った子どもは、治療・リハビリの結果、目に見える形で改善している。また、「子どもの家」併設の児童文化センター施設は、「子どもの家」に住む子ども達を始め、地域の子ども達によって活用されており、上級職業訓センターは活動を開始されたばかりであるが、地域の青年に対してバイク修理訓練を行っている。従って、フエ市児童福祉総合支援プロジェクトは、ストリートチルドレン等の住民に直接裨益していると判断される。
(2)住民参加
本プロジェクトは、JASSとフエ市人民委員会が中心となって推し進められているが、住民参加によるプロジェクト実施という側面では十分とは言い難く、受益者である子どもは、文字通り援助の対象であり客体となっている。今後、子どもの依存心を生み出さないように配慮することや、成長した子ども、あるいは保護者などが事業運営活動に参加できるような仕組み9を整備することが望まれる。
また、子どもが保護の対象としてのみ捉えられていることは、子どもの成長過程の障害になる可能性もある。今後、子ども達が精神的に自由で自立した存在へ脱皮していくための教育的配慮を進めていくことが不可欠であろう。
(3)ソフト支援
本プロジェクトは、施設の建設、機材購入などのハード部分、または障害児の治療といった直接的な問題解決をする支援が多く、人材育成、制度作りなどのソフト面での活動は弱いので、今後より強化することが望まれる。
4.3.4 開発福祉支援事業によるインパクト
開発福祉支援事業が入ることによって、ベトナムの「子どもの家」を支える会による活動の規模が大きくなり、それ以前に出来なかった事業も手がけることができるようになった。また副次的なインパクトとして副院長が挙げていたのは、開発福祉支援事業により事業規模が拡大することで治療事例が大幅に増え、それが関連病院の医師らの技術を磨く機会ともなり自信と技術向上に役立ったとのことであった。
一つ懸念されることが、対象地域内での子ども間の不均衡である。JASSが直接実施することで、病気あるいは障害の子どもに直接裨益した効果は大きいが、一方、財政基盤が整っていない為、治療対象となっているにも関わらず、未だ手術を受けていない子どもが、今度この便益を受ける可能性は不確実である。NGOの活動によって、地域に一時的な不均衡がもたらされるのはやむを得ない時もあるが、できるだけ、社会的な公平が保たれるよう目指していく必要がある。
また、調査中気になったことは、フエ市外務部やキムロン病院副院長らが一様に「小山氏、あるいは日本人だから出来たことだ」と強調していた点である。病院では以前にも他の外国援助を受けているが、副院長はそれらとJASSとの違いとして、規模の大きさやカバーする疾病が全範囲に及ぶことを挙げ、今後もそのような大きな規模のことに取り組みたいと述べた。日本政府のミッションであることで更なる支援を期待しての発言であることも割り引いて考えねばならないにせよ、現実にはごく小さな規模でもフエ市の自己資金で継続する予算措置がまだないなかで、外部からの支援に対する期待が大きく膨らんでいる。
4.4 本プロジェクトに対する提言
4.4.1 ソフト面の重視
JASSの支援活動は直接的であり、効果も目に見える形で表れている。しかしながら、限られた資金で同じような活動を広い地域で実施していくことは困難である。今後JASSの活動による効果が他地域へ波及するようになるには、現地社会の制度への働きかけが重要となってくる。例えば、外務部での聞き取りによればフエ市はストリートチルドレンに対する政策はまだ持っていないとのことであるが、具体的で実現可能な制度などを持つよう働きかけるなど、実現可能と思われる制度を提案していけるのではないかと考える。
4.4.2 フエ市による一部資金負担への移行
後3年でハンドオーバーという目標を持っていることは評価するが、現実にはまだ行政による財政負担はごく一部しか行われていない。3年後に残り全てを一気に受け渡すのは困難であるので、可能なものから徐々に負担を移行していく必要があると考える。
4.4.3 小さくても続けて行ける活動に
3年後の自立に向けて、JASSでは上級職業訓練センターでの収益による運営資金確保を期待しているようであるが、これも楽観できる状態ではないと予想される。今の時期からハンドオーバーした段階でまかなえる予算規模を試算し、それに見合った事業規模に縮小するなりの対策を同時に取っていく必要があると考える。さもないとフエ市当局では引き受けられないこととなろう。
4.4.4 評価の実施
より良い活動を実施するには、第三者による定期的な評価を行い、その結果を基に、新たに計画、実施していく過程が必要である。JASSは個人的活動から出発したが、活動の発展と共にニーズも変わり、NGOとして取り組むべき問題も変わってくる。外部者による今までの活動の評価は、今度取り組む問題へのより良いアプローチ方法を見つける契機にもなるであろう。
4.4.5 他のNGOの経験に学ぶ
職業訓練やストリートチルドレンの活動に関し、将来的に行政へのハンドオーバーを想定しているのであれば、運営方法やハンドオーバー実績などに関して、他団体のノウハウから学ぶことも必要だろうと考える。特にフェーズアウトの戦略は重要である。直接実施でうまくいく例は多いが、ハンドオーバー自体がスムースに出来るか、ハンドオーバー後継続できるか、などは課題を抱えるところが多い。うまくいっている事例もあるので、ぜひ参考にして欲しい。
6 家族と生活しているが、毎月20ドルの支援金を受けている子ども。この様な子ども達の一部は以前「子どもの家」にいた子ども達であり、現在は親元にいるが、経済的に困難な状況にいる。JASSは、親が仕事をし、子どもを学校へ通わせることを条件として、資金援助をしている。
7 障害児医療センターの所長、副所長はそれぞれフエ人民委員会厚生部長、副部長でもあるので、人民委員会から一定の月給が支給されている。JASSは、この点を考慮に入れて、この二名には補助金程度を支給している。また、上級職業訓練センターのバイク修理技術者の給料は、1年間に限りホンダベトナムが支援している。子どもの家のスタッフ人件費、その他運営費は、国際ボランティア貯金からの寄付で過去3年間賄っている。
8 キムロン病院障害児医療センターの所長、副所長は、それぞれフエ市立病院長、副病院長でもあるので、基本的に給与はフエ市人民委員会より受け取っているが、JASSはそうした点を考慮にいれて多少の補助金程度を出している。また、障害児センターのその他のスタッフ、「子どもの家」スタッフ、上級職業訓練センターのスタッフの給与は、人民委員会から派遣されている職員のものも含めて、JASSを始めとする外部資金に頼っている。
9 例えば、障害児支援であれば、障害児またはその保護者が、自ら車椅子などを作成するための訓練を行った上で、彼ら自身が車椅子を作る、など。

