第3章プロジェクト・ケーススタディ1:
子どもの栄養改善事業:SCJ
(セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン)
3.1 プロジェクトの背景
3.1.1 ベトナムでの活動の背景
ベトナムでは1980年代後半の市場システム導入以来、経済は成長過程にあるものの、従来国家から提供されていた社会福祉予算が大幅に削減されたこともあり、多くの社会的弱者、特に女性と子どもの保護体制が弱体化した。その結果、農村部でも子どもの栄養不良は深刻化している。ベトナムの5歳児の40%が栄養不良とされており、東南アジアの近隣諸国と比較しても著しく高い数字である。ベトナム政府は、これを重大な問題と受け止め、栄養不良児の割合を30%に引き下げるという目標を掲げ、国家栄養改善事業(NPN:National Program of Nutrition)を進めているが、効果はあまりあがっていない。このような状況のもと、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン(SCJ)は米国SCが91年から行っていた子どもの栄養改善事業に学び、95年から独自に事業を開始した。SCJは現地での資源を有効に活用して児童の栄養改善を図る手法をもって、地元の組織と連携し、それまで手の届かなかった地域を含めて活動対象範囲を拡大している。
3.1.2 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン(SCJ)の概要
SCJは、1986年に主旨に賛同した青年商工会議所および国際婦人福祉協会の有志が中心になり大阪に設立された団体で、セーブ・ザ・チルドレン・世界連盟(SCA)の第22番目のメンバー組織である。SC世界連盟の各団体は財政・運営上独立しており、連盟のもとに緊密に連絡をとりながら、それぞれの特徴を生かした活動を各地で展開している。SCJは設立以来アジア5カ国(ネパール、フィリピン、タイ、ベトナム、ミャンマー)に日本人職員を派遣して様々な活動を実施し、1995年3月に社団法人の認可を、さらに2001年4月に特定公益増進法人の認可を外務省より受けた。SCJは発展途上国の子どもの生存、発育、保護、参加における基本的人権の実現を使命とし、そのために途上国に駐在員を長期派遣し、現地スタッフとの協力のもとに現地住民社会の社会・経済的自立をサポートすることを通じて、子どもの権利実現を阻む問題を効果的・持続的に解決することを目指している。
3.1.3 開発福祉支援事業に至る経緯、全活動の中での位置付け
SCJは1995年にベトナムで活動を開始して以来、これまでタイン・ホア省、ゲアン省、イェン・バイ省の計41村にて、子どもの栄養改善のための活動を実施してきた。1998年にSCJへの支援が開始された開発福祉支援事業によって、新たな事業対象村を選び、活動範囲を拡大することが可能となったが、基本的にはそれまで実施してきた活動が、そのまま他地域へ適用された。しかしながら、開発福祉支援事業が入った地域では、それまでの活動では実施していなかった事業も加えて実施されることになり、(「家庭菜園事業」)子どもの栄養改善のためのより総合的な活動を行えるようになった。
3.2 当該プロジェクトの概要
3.2.1 目的・地域・対象
当プロジェクトは、対象地域での3歳以下の子どもと妊産婦の栄養状態改善状況を数値化できる指標を用いて持続的に向上させることを、目標としている。開発福祉支援事業による支援対象となった地域は、タン・ホア省ビンロック地区5村(ビンクアン村、ビンフン村、ビンミン村、ビンホア村、ビンカン村)、タン・ホア省トゥオングスワン地区5村(トタイン村、ゴクフ村、スワンカム村、スワンズオン村、スワンカオ村)、及び、イエンバイ省5村(バオアイ村、ブウリン村、イエンビン村、ホプミン村、クイモン村)である。開発福祉支援事業によるプロジェクト実施期間は、1998年12月26日~2001年12月28日で、まず、ビンロック地区5村にて活動が実施され、その後トゥオングスワン地区5村、イエンバイ省5村で実施された。それぞれの地区での実施期間は以下の通りである。1
ビンロック地区5村:1998.12~2000.11(1998.12.26~1999.9.30)
トウオングスワン地区5村:1999.10.1~2001.9.30 (1999.10.1~2000.3.31)
イエンバイ省5村:2000.4.1~2002.3.31 (2000.4.1~2001.3.31)
SCJでは、一定地域での活動期間は2年以内とし、その後は地域住民の自主的な活動に委ねている。例えば、今回調査団が視察したビンロック地区の場合では、1998年の12月に事業開始し、翌年9月30日まで開発福祉支援事業による活動が行われ、事業開始から2年経った2000年11月に事業最終評価を行い、その結果、事実上撤退した。
裨益者は3歳以下の子どもとしているが、結果として、子どもの母親、妊産婦、その他地域の住民へも間接的に裨益する。表3.1に直接対象者数を示す。
表3.1 子どもの栄養改善プロジェクト:対象地域の人口及び対象者数
|
3.2.2 主な活動
SCJは以下4つの事業を実施することによって、子どもの栄養改善に総合的に取り組んでいる。それぞれの事業は、プロジェクト管理上複雑化することを避けるため、それぞれ次の事業が始まる前に十分消化されるように間隔を置いて段階的に開始される。
(1)子どもの栄養事業::Child Nutrition Program(CNP)
中・重度栄養不良児を持続的に削減するために、幼児検診と13日間の子どもの栄養回復教育活動(NERP)2を毎月実施する。具体的には、村の3歳児以下の子どもを全員検診し、「正の逸脱」家庭(貧しいが子どもが健康で栄養状態が良好な家庭)3を見つける。草の根保健婦4は、「正の逸脱」家庭を訪問し、そこから学んだ内容5を基に子どもの栄養回復教育活動(NERP)を行う。各村内の保育所などの既存施設を活用して10~12箇所のNERPセンターを設け、各センターを一人の草の根保健婦が受け持って、子どもの母親達を対象に研修を実施する。NERPは一回13日間であり、「正の逸脱」家庭から学んだ食材や育児法を使った栄養回復食メニュー、栄養教育用のポスターの作製と使用法などを中心に教える。参加する母親達は、「地域に比較的豊富にあり、かつ栄養価が高い食材」を持ち寄り、母親と草の根保健婦が一緒に調理することから始める。栄養教育に使われるポスターは6枚であり、1日1主題、6日で一巡してから、2週間目にもう一度繰り返す。
(2)産前検診事業:Ante-Natal Care Program(ANC)
すべての妊産婦が質の高い産前検診を受けられ、コミュニティー全体に妊婦に関する健康管理法を普及するために、医療スタッフによる毎月1度の産前検診と草の根保健婦による妊産婦および新生児を持つ母親の家庭訪問を行う。また、産前検診を行うためには、村の保健所に最低限必要な医療機材を提供する。
(3)家庭菜園事業: Household Food Security Program (HFSP)
栄養不良児と妊産婦が各家庭で栄養状態を改善できるようにするために、家庭菜園普及によって日々の家庭での食料の供給を改善する。栄養不良児または妊婦のいる家庭に、野菜の種を配布し菜園作りを教える。訓練を受けた草の根保健婦と菜園普及員が各家庭を定期訪問し、菜園作りについて助言、また子どもの栄養教育についてのフォローアップを行う。
(4)小規模貸付事業:Saving and Credit Program(S/C)
家庭菜園事業の対象者を中心に、小人数グループを作り、預金活動を行う。その後、預金率の高いグループから小規模回転資金貸付を行う。この事業の目的は家庭菜園の普及、貧窮家庭の経済向上、子どもの栄養改善、草の根保健婦の活動を継続するための継続的資金の自己捻出である。
3.2.3 実施体制
ベトナムにおけるSCJスタッフは、日本人1人、ベトナム人6人であり、内、日本人1人及びベトナム人4人はハノイのプロジェクト・オフィスに、2人のベトナム人スタッフはタイン・ホア省のフィールド・オフィスに駐在している。ベトナム側は、プロジェクト実施地域の人民委員会を基盤として組織された地区事業管理委員会、村事業管理委員会がパートナーとなって、プロジェクトを実施している。
地区事業管理委員会の委員長は、地区人民委員会議長が務め、その他のメンバーは地区児童ケア委員会から1名、地区保健局から1名、地区農業農村開発局から1名、地区女性同盟から1名選ばれる。そして、それぞれ栄養改善地区管理者、産前検診地区管理者、家庭菜園地区管理者、小規模貸付地区管理者を務めている。
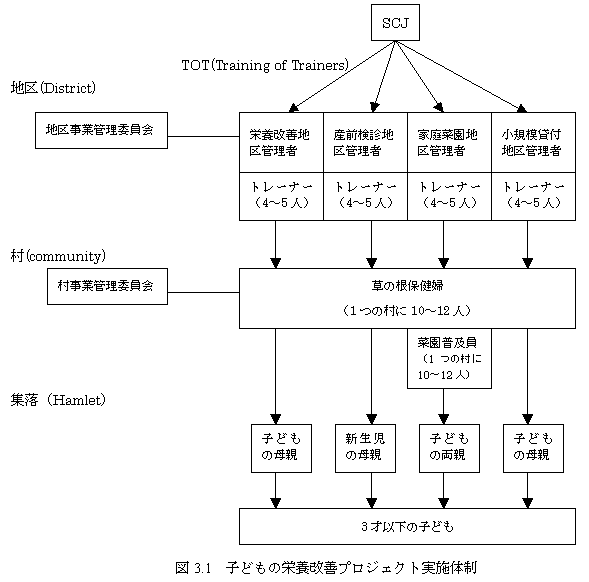
実施にあたっては、SCJスタッフが地区事業管理委員会メンバーおよび、村からのトレーナーに、7~10日間ほどのTOT(トレーナーのための研修)を実施し、さらにトレーナーがそれぞれの村において、草の根保健婦、および菜園普及員へ研修を実施する。草の根保健婦、菜園普及員は、1村につきそれぞれ10~12人程おり、1村には5~10程の集落があるので、1集落を1~3名程の、草の根保健婦、または菜園普及員が担当している。
村での研修と活動は常に研修-実施-評価の3段階方式が繰り返される。事業活動を実施する前にはその活動を実施する方法、技能、意味を理解するための研修が行われる。研修で学んだ事はすぐその翌日には実施される。実施後は直ちにその活動結果をまとめ、実施上の問題点について解決策を話し合い、次回の実施時に反映させるための自己評価が行われる。
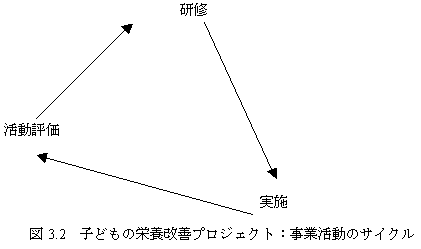
3.3 現地調査結果
3.3.1 プロジェクト目標の達成度、その効果
プロジェクトの主要目標である中・重度の低体重栄養不良については、大幅な改善が見られた。また急性の栄養不良についても、明確なプロジェクト効果が測定された。但し、長期的なスパンで効果が発現する軽度の低体重栄養不良及び慢性の栄養不良については、一部の地域を除いて、まだ十分な効果が現れるには至っていない。
その他の活動毎における達成度及びその効果を見ると、産前検診事業では、産前検診の機会が増え、妊産婦の意識を改善したことで、出生児の栄養不良改善、危険出産数が減少する等改善が見られる。
家庭菜園事業では、家庭菜園の知識、技術を普及させることにより、栄養不良児、妊産婦の食事の改善が図られた。さらに、収入の増加も認められ、家庭菜園を行う習慣を育成する等、住民の意識の改善が認められる。
小規模貸付事業は、対象家庭の収入を増やし、食生活の改善、生活の向上を目指し、最終的にはSCJ撤退後全事業活動を持続、向上させる目的を持っているが、現在展開中であり、結果が出るまでは、しばらく時間が必要である。
3.3.2 プロジェクト効果や活動の持続性
アプローチや運営体制において、自立発展性に留意して計画実施されており、効果や活動に持続性が見られる。まず、栄養改善の対策として新たな食物を推奨するのではなく、貧困家庭でも栄養状態が優れた子どものいる家庭で食べている地元で手に入る食物を再評価することで、誰でも入手可能な範囲から改善できるというモデルを提示しており、すでに母親達の行動変化が見られるなど、協力効果がかなり浸透、定着していることが確認された。一方、実施体制は将来的に地方行政が担っていけるよう、初めから行政担当者らを中心とした地区事業管理委員会を組織し、彼らによるチームづくり、計画立案などを共に行ってきている。さらに、集落レベルでは母親らを中心とした草の根保健婦を育成し、地元の人々が中心的に担っていける仕組みを作っている。加えて、これら草の根保健婦の育成は、同管理委員会がトレーナーとなって行っており、行政官らはプロジェクト終了後もトレーニングを企画実施するノウハウを身に付けている。以上の点からみて、プロジェクト終了後も一定の活動は継続される可能性が非常に高いものと判断される。
地区事業管理委員会は、地区人民委員会(ベトナムの行政上、地区政府に該当する)に設置されているが、栄養改善事業として単に保健部内だけではなく、家庭菜園担当としての農林部、女性達の生活改善のための小規模貸付事業を担当する女性同盟担当者、など複数部局にまたがってチームとして組織されている。このことが活動に幅を与え、保健以外の要因への対処を可能にしていると思われる。このような複合チームの効果を、人民委員会も肯定的に受け止めており、ベトナム政府がWHO・UNICEFなどと共同で取り組んでいる国家栄養改善計画との違いとして明確に認識されていた。各分野が共通の目標のために連携して活動することにより、既存の組織の専門知識も効率的に活用されて、保健医療部門だけの活動と比較して効果的な事業を展開できる可能性が高まると考えられるため、このようなアプローチが波及することが期待される。
また、活動に参加することで、母親達が自分の子どもの健康管理に関心を持つようになったり、母親同士が集まる楽しさ、情報交換の場としての有意義さなどを実感しているようであり、これらの点からも活動が継続される可能性が高いと判断された。
今後の課題としては、草の根保健婦の人件費を捻出することなどを目的とした小規模貸付事業が定着するかどうかがポイントである。しかし、既に記した通り、母親の行動変化(食事、育児、健康管理等の適切な方法の実践)はかなり進んでおり、草の根保健婦の活動(育児・栄養改善知識の普及、産前検診等の活動)が停滞した場合でも、母親達の自発的な活動による効果の持続は期待される。
3.3.3 開発福祉支援事業としての妥当性
開発福祉支援事業は、住民が直接裨益するような開発プロジェクトを住民の参加を得て実施するものを支援するとし、さらに資機材や施設の供与よりも技能の訓練や組織化の支援に重点を置いている。そこで、前章で述べた通り、このプロジェクトが開発福祉支援事業対象案件として妥当であったかどうかを、「住民への直接裨益」「住民参加」「ソフト支援」の3要件を満たしているかどうかで、開発福祉支援事業としての妥当性を評価する。SCJプロジェクトでは、3要件のすべてを満たしており、妥当性は非常に高いものと判断される。また、投入資金の規模もそれほど大きくなく、活動対象を絞って、短期間で集中的に援助を実施することにより効率的に事業を推進している。
(1)住民への直接裨益
最終裨益者である3歳以下の子どもの栄養状態が改善していることを始めとして、その母親達の健康管理に対する意識も改善され行動変化として表れており、住民に直接裨益している。
(2)住民参加
草の根保健婦を対象地域村民が務めており、既に彼女たちだけで、体重測定、記録、良い食習慣、健康管理方法の説明などを行っている。また、母子が参加しての子どもの体重測定が習慣として確立していると見受けられ、これは住民にとって自分の子どもの栄養改善という非常に身近で強いニーズのある活動であったことから、参加の意欲が高かったことが理由であると考えられる。
(3)ソフト支援
本プロジェクトでは、対象地域で入手可能な食材を活用するなど持続可能性に特に配慮が行われており、外部から導入されたのは体重計、身長計、野菜種子など限定されており、また地域コミュニティーの中に一定の組織・仕組み作りと意識改革を指導していくというソフト面を重視したアプローチをとっている。
3.3.4 開発福祉支援事業によるインパクト
開発福祉支援事業により、SCJの独自資金での活動と比較した場合、活動地域の拡大やプログラムの規模の増大(家庭菜園事業の実施など)がもたらされ、SCJとして総合的な栄養支援を組めるようになった。活動アプローチ・方法面では、開発福祉支援事業が入ったことにによる変化は特になく、SCJは独自で活動を実施していた時から、「住民への直接裨益」、「住民参加」、「ソフト支援重視」などの開発福祉支援事業が目指す形態での活動を実施していた。ネガティブなインパクトは、特に確認されなかった。
3.4 本プロジェクトに対する提言
3.4.1 経験の拡大
国家栄養計画に比較して成果や持続性が高いことを地方行政官も認めている点から見て、本事業での経験を類似の他事業へ波及させるようにすることが望ましい。本ミッション期間中に、SCJ主催で本事業の評価結果を他団体に報告するワークショップを開催していたが、このような機会を出来るだけ増やし、より多くの人々、団体に知らしめることが望まれる。
3.4.2 小規模貸付事業のフォローアップ
草の根保健婦の活動の継続性を保証するため、回転資金による小規模貸付事業が実施されている、資金源確保や運営上の困難さがあるようである。ベトナムにおいては同種の活動が広く行われており、担当する女性同盟などには経験の蓄積があると思われるが、さらなるフォローアップ、モニタリングが必要と考える。
1 括弧内の期間は、開発福祉支援事業によるプロジェクトの実施期間として便宜上区別したものである。
2 Nutrition Education rehabilitation Program
3 経済的に豊かな家庭の子どもは、栄養状態が良く、貧しい家の子どもは栄養不良であるのが一般的な傾向ではあるが、貧しい家庭であっても、子どもの健康状態が良好な場合もある。そのようなケースを「正の逸脱」と呼んでいる。
4 3.2.3実施体制参照
5 例えば、ある「正の逸脱」家庭では、近所の田んぼで獲ってきたザリガニを食べるなどしている。

