(3)教育分野に対する日本の貢献度合と目的の達成度合の評価
1)援助によって実現した成果
「ベトナム情報研修所」(プロ技、96年度 5年間)、「ハノイ工科短期大学機械技術者養成計画」(プロ技、2001年度)は、人材育成分野の案件として、本報告書では評価を実施している。同様に、「ハノイ農業大学強化計画」(プロ技、2000年度)、「カントー大学農学部改善計画」(無償、93~95年度)は、農業・農村開発分野の案件として評価している。また、関連情報としては、「日越人材協力センター」(プロ技+無償、2000年度 )が、2002年2月(ハノイ校)、3月(ホーチミン校)にそれぞれ開所している。したがって、本項3.2.4では、教育分野における日本の最大の援助案件である「初等教育施設整備計画」を教育分野の主な評価対象としつつ、それに加えて草の根無償資金協力として実施したストリート・チルドレンを対象とした小学校整備(正式名称「6月1日学校建設計画」、ホーチミン市)を視察案件として加える。
日本の初等教育施設整備計画(第一次~第四次)によって整備された小学校は以下のとおりである。なお、整備の具体的な内容は、校舎の新築、増設及び付帯設備の供与である。
初等教育施設整備計画(無償、94年~97年)とりまとめ表(PDF)
上記の表によると、「初等教育施設整備計画」として、計17県において、合計195校の小学校整備支援が行われたことになる。なお、これらの小学校は、海岸部に立地し、台風の被害を受けやすい小学校である。援助を開始して以来、現在まで対象の195校のうち、61校で引き渡し式が終了している。
なお、ベトナムの教育制度に関して注意を要する点がある。ベトナムでは、以前、第1学年から第9学年までを同一の校舎で教えていた。年齢でいうと6才から15才までである。これは日本で言うと、ほぼ小学校と中学校を合わせた学年にあたる。これを「基礎学校」(Basic Schools)と呼んでいたが、現在は、第1~5学年までを「小学校」(Primary Schools)、第6~9学年を「中学校」(Lower Secondary SchoolsあるいはMiddle Schools )として分割する政策が取られている(下図参照)。この移行課程にあるため、統計にあらわれる定義が統計書によりばらばらで混乱しており、日本からの援助効果を事前と事後の比較で評価することを難しくしているが、調査団では可能な限り統一的な指標を用いて評価することに努めた。
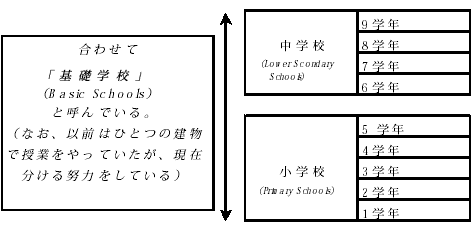
2)ベトナム側が目指した目的の達成度合
初等教育に関し、第5次5カ年計画(1991 - 1995)において、「識字化の徹底と初等教育の完全普及」が掲げられている。そして、続く第6次5カ年計画(1996 - 2000)では、初等教育について特に言及されてはいないものの、「研修の実施による工業化・近代化の要求を満たす人材資源の質的向上」、「中等教育修了者および研修修了者などの労働可能人口の増加」を目標として掲げており、初等教育の完全普及と識字化はそのための必須の基盤となると言える。また、第7次5カ年計画では、再び「全国的な初等教育の実施と非識字率の改善(とくに山岳地帯と遠隔地において)」と明示的に目標が掲げられるに到っており、国家開発計画上、常に高いプライオリティを与えられてきたと言える。ベトナム政府は、こうした高いプライオリティづけを踏まえて、1990年に、基礎教育(初等教育のほか、中等教育、成人識字教育も含む)に特化した「万人のための教育-2000」('Education for All -2000')という教育開発計画を策定した。ここに掲げられた目標と、目標年度の2000年の実績を次のページにまとめた。なお、表の右端に、「達成状度合」を調査団が評価して付記した。総じて述べると、1990年に掲げられた数値目標はおおむね達成されたと言える。達成されなかったのは、「小学生の数を1,100万に増加させる」(2000年の実績値975.1万人)であるが、これは就学率が向上していることから未就学児童の増加が原因ではなく、単に予想より出生率が下がったためであると教育訓練省では分析している。また、「中学校の児童数を350万人に増加させる」としていたが、実績は598万人で、中学校の進学率が予想を越えて上昇したとしている。総じて、ベトナム政府が掲げていた初等教育の改善計画は、計画どおりに達成されたと言えるであろう。
上記‘万人のための教育-2000’の達成の過程で、ベトナム政府が日本の援助に期待したものは、老朽化した校舎の立替え、教室数の絶対数の増加、設備の近代化などと、それらを通じた就学率、卒業率の改善と、交代制17の回数の軽減、そして最終的には識字率と学力の向上であった(JICA Basic Design Study各回による)。これらの目的に関し、教育訓練省からのヒアリングによると、日本が建設した校舎は「質がいい」と学校関係者は高く評価しているとのことである。また、本件援助のインパクトは大きく、台風がよく来る時期にも勉強することができるようになったほか、現地の人たちが避難するためにも利用されている、と評価している。総じて、ベトナム側では、‘万人のための教育-2000’で掲げられた目標の達成に、日本の初等教育施設整備は貢献したと評価していると言える。
また、テレビや新聞でも日本の援助によって完成した小学校が紹介され、現地の人たちは日本の援助で建設されたことをよく知っているとのことである。
‘万人のための教育’(2000を目標年次とした教育開発計画)で掲げられた目標とその達成度合の評価(PDF)
3)日本側が目指した目的の達成度合
日本の外務省が作成した国別援助方針(94年度、95年度に記載あり)では、「高い進学率や識字率が社会指標に表れているが、教育環境は改善の余地が極めて大きい」として、「初等・高等教育機関の施設・設備の整備等を図る」ことを日本が目指すべき援助の目的として掲げていたわけであるが、実際の初等教育機関の施設・整備への貢献は、以下の表のとおりにまとめることができる。
既に述べたように、ベトナムでは第1学年から第9学年までを同一の校舎で教える「基礎学校」(Basic Schools)で教えられる課程を初等教育と呼んでいたが、現在は、第1~5学年までを「小学校」、第6~9学年を「中学校」として分割する政策が取られている。したがって、日本の援助の実施前と実施後のそれぞれでどこまでを「小学校」に含めて計算するかで日本の援助の貢献度合の評価も変わってくるし、またベトナム側の統計も、どこまでを含めているか不明な場合もある。このような事情のもと、今回入手できた限られた資料をもとに計算した。
表中の「初等学校」(Elementary Schools)とは、従来の「基礎学校」と新しい定義での「小学校」とを合計したものである。日本の援助が実施される前の年(ベースライン年)と、日本の援助が実施された後の年(評価年)のあいだに増加した「初等学校」の数は、第1次援助の3省では182校(92/93 2000/01年)、第2次援助の3省では1,417校(92/93 2000/01年)、第3次の3県では129校(95/96 2000/01年)、第4次の8県では337校だった(95/96 2000/01年)。したがって、第1次、第2次と、第3次、第4次でベースライン年が違うことはあるが、合計すると2,065校と計算された。これに対して、日本の援助で整備された小学校は195校だったので、総増加数の9.4%が日本の援助によって実現したことになる。
なお、今回得られた教育訓練省からの資料によると、日本が援助を実施した17県における新しい定義での「小学校」(第1~5学年)は、合計7,390校とされており、これに対して日本の援助で整備された小学校数は195校であるので、総数のうちの4.1%が日本の援助によって実現したことになる。
冒頭に述べた、「初等・高等教育機関の施設・設備の整備等を図る」という日本側の目的は、初等教育に関しては上記の表に示した程度に達成され、すでに解説した ‘万人のための教育-2000’の高い実現度合に貢献したと評価できる。
現地視察1:第1次援助によって整備されたナム・ハ省のタイン・ギ小学校(Thanh Nghi Primary School)
調査団は、定量的な評価に加えて質の面からの評価を実施すべく、日本の第一次援助で整備(新しく建設)されたタイン・ギ小学校を視察した。ハノイ市から車で2時間の距離に立地する同小学校の建設着工は94年で、完成して使い始めたのは96年からである。なお、第1~9学年までを教えていた古い校舎が近くにあり、それは中学校専用の校舎として使用されていた。
生徒数は以下のとおりである。なお、2000年から2001年に生徒数が減っているのは、全国的な傾向である出生率の低下もあり、地域全体の人口が減ったからである。
| 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 2001 | |
| 学生数 | 654 | 650 | 661 | 630 | 638 | 640 | 623 | 585 |

授業風景:元気に学ぶ子供たち。中央が校長先生。
新しい校舎が出来る前と出来た後で何がもっとも大きく変わったか、という質問に対し、「教室がきれいで明るくなり、学習する環境が改善された。また、生徒達があまり休まなくなった」との回答があった。また、台風の影響は軽減したのかと聞いたところ、「前の学校では、台風の影響で勉強できない日が2~3日あったがそれがなくなった」とのことであった。
一方、就学率・卒業率については、「以前も現在もほぼ100%である。卒業率は現在は100%だが、以前は中退する子もいた。中退していた理由は、家庭の理由による。なお、この新しい学校ができて、近くの別の学校に子供を通わせていた人たちもこちらの学校へ子供を通わせるようになっている。その比率は全生徒数の5%程度である」とのことである。
なお、以前は第1学年から第9学年までを同一の校舎で教えていた。現在は、第1~5学年までを「小学校」、第6~9学年を「中学校」として分離する政策が取られている。これに従い、日本の援助でできた小学校で第1~5学年が学び、以前の校舎で第6~9学年が学んでいる。こうした状況のなかで、小学校レベルでの2交代制は改善したのか、という問いに対し、「新しい校舎で学ぶ小学生(第1~5学年)は、以前と同じ2交代制(午前か午後どちらかの授業のみ)が中心で以前と変わらないが、旧校舎で学ぶ中学生(第6~9学年)が、以前の2交代制から、現在は交代なし(全日教育)へ移行できた」との回答があった。

日本の援助で建設された小学校校舎

小・中で共用していた以前の校舎
(現在は中学校専用として使用)
以上の現地視察から明らかになったことは、同小学校において日本の無償援助はたしかに台風の影響を減少させたし、就学率や卒業率の向上にもある程度貢献したと言えるが、もっとも大きなインパクトは、中学生の学習環境の改善であったということである。つまり、中学生の授業時間が2倍に伸びた、と考えられる。
現地視察2:6月1日学校(孤児学校)
6月1日学校は、家庭の事情等で小学校へ通うことができない子供たちに対する教育を行なっている。この学校に通う子供たちの多くは、非常に貧しい家庭で、なおかつ片親あるいは親戚に預けられている子供たちで、その中には住む場所がなくストリート・チルドレンとなっている子供たちもいる。
6月1日学校は、以前70名の子供たちが通っていたが、現在は300名以上となっている。また、そのうちの15名の子供たちは、帰る家がないので、学校に住まわせて扶養している。
午前6クラス、午後6クラス。普通の授業以外に、縫製、刺繍、オートバイの修理、室内電気の技術などの職業技術を教えている。この学校には8才~15才までの子供たちが学んでいる。1999年の開校以来、卒業生は30名~40名となったが、多くは中学校へ通うほか、学んだ職業技術を活かす卒業生もいる。
調査団としては、子供たちの顔がたいへんに明るかったのが印象的であった。また、校長先生はじめ先生方もたいへんに熱心である。日本の援助で校舎や施設が整備されたことは先生も生徒もよく知っているようだった。このように草の根無償で、若いベトナム人を育てているのは高く評価できる。

6月1日学校での授業風景

家庭の事情により、同学校にて扶養されている
子供たち(15名)の部屋。(左端は校長先生)
17 一つの教室を一日いくつの学級が使うかという回数。例えば「2交代制」とは、ひとつの教室を、午前中だけ授業を行なう学級と午後だけ授業を行なう学級が使用しているということを示している。

