(3)農業分野における日本の貢献度合と目的の達成度合の評価
1) 農業セクターの現状
a) 農業生産の構造と動向
米の生産に強く依存しているのがベトナム農業の1つの特徴である。作物と畜産を含めた農業生産額における米のシェアは、コーヒーなど、工芸作物がこの10数年間で大きく増大したため、やや減少する傾向にあるものの、現在もまだ5割強という高い比率を維持している。1999年の時点で米以外の主な種目の比重を見ると、畜産17%、工芸作物・果物・野菜28%であった。
表1は、1986―99年の期間における農業セクターと、食糧(その9割以上が米)、畜産、永年作物15の生産額を示している。農業セクターの全体で見ると、この13年間に生産が1.9倍となり、年平均で5.1%という高い率で拡大しつづけた。農業セクターに含まれる食糧、畜産、永年作物を見ると、食糧4.8%、畜産5.2%、永年作物8.1%と、畜産と永年作物がより高い伸び率を記録している。特に南部の工業地帯(ホーチミン市およびその周辺)と高原地域を主産地とする永年作物の生産額が、この期間に2.8倍に拡大し、農業セクターに占めるそのシエアを11%から16%に伸ばした。
ドイモイによって1989年輸入から輸出に転じた米は、現在も重要な輸出品目の地位を保っている。永年作物において、コーヒーとゴムは生産量と輸出量の両方を飛躍的に伸ばしており、特にコーヒーはブラジルに次いで、コロンビアと並ぶ水準までその輸出量を拡大している。
| 表1. 農業生産の推移(1994年価格、100億VN$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出所:Statistical Data for Vietnam: Agriculture, Forestry, Fishery, 1975-2000(Hanoi: Statistical Publishing House, 2001) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2. 主要永年作物の生産量の推移(1000トン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出所:表1と同じ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上で見たように、作物と畜産を含めた農業セクターは、1986-99年の期間に順調に拡大しており、全期間にわたって年平均で5.1%の高成長率を記録している。この成長はどのような要因によってもたらされたかを見るために、農業生産(Y)が農地面積(A)、農業労働人口(L)、農業生産の資本ストック(K)と技術(D)農業の生産関数を推計した(カッコ内はパラメーターの標準偏差)16。
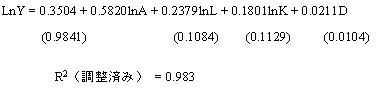
1986―99年の期間のデーターにあてた回帰分析の結果として得られた各生産要素のパラメーターと同期間に記録した各変数の増加率から要因別の貢献度を算出した(表3)。固定価格で表示される農業生産額は、この13年間で約90%の増加を記録したが、その約3分の1は土地面積の拡大と労働力の増大によって説明され、残る3分の2は基礎インフラへの投資と制度・技術の変革によって貢献されたことが確認されている。
すなわち、ドイモイ下の農業生産の上昇は大きく灌漑や農村道路など、基礎インフラへの投資と、組織・制度の改革と技術の研究・普及に起因しているもので、インフラ投資の高い収益性と制度・技術変革の重要性を裏付けている。このように生産額を大きく上昇させた農業セクターは、より多くの労働力(42%増)の吸収と労働生産性の上昇を可能にしている(生産性に14%増)。
| 表3. 生産増加の要因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:要素変化は、農地、労働とインフラはΔln、技術はΔD。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) 地域間の格差
細長い国土をもっているベトナムの農業は、中国の国境に接する北部から南部の最先端まで並ぶ8つの地域の間に、作付の形態と生産性にかなりの格差を見せている。以下、主な作物について地域間の生産量と生産性の格差を見てみよう。
表4は、1998年における8つの地域の農業生産額、米の生産量と永年作物の面積を示している。作物と畜産を含めた総生産額11.3兆VN$の3分の1はメコンデルタ地域によって占められている。さらに、国内の食糧としても輸出品目としても最も重要な地位を占めている米は、北部のホン河デルタと南部のメコン・デルタを主産地としているが、この2つの地域を比べると、総生産量に占める割合としてホン河デルタの18.4%に対してメコン・デルタは50%を越えている。このように、農業全体から見ても、食糧の生産から見ても、南部のメコン・デルタ地域が重要性である。
輸出作物として現在も米が第1位を占めているが、近年、コーヒーやゴムなど、永年作物はその生産量と輸出量を急激に拡大している。永年作物の作付面積を地域別で見ると、南部の工業地帯(ホーチミン市およびその周辺)と高原の2地域だけで全体の3分の2を占め、永年作物の生産も南部へ傾斜している傾向を物語っている。
| 表4. 地域間農業生産量の比較(1998年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出所:Statistical Data of Vietnam: Agriculture, Forestry, Fishery (1975-2000.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域間の格差は、農家がもっている土地面積の規模と作物種類にも鮮明に現れている。1戸当たりの農地面積で表される農家の規模は、南部に大きく、北部と中部に小さい。また、同じく広い農地面積を有している南部の3地域の中でも、メコン地域が米の生産に集中しているのに対して、工業地帯地域と高原地域は永年作物に傾斜していることが観察される。
表5は、8つの地域における農家戸数、農地面積、米作面積、永年作物の面積とそれぞれの地域における1戸当たりの面積規模を示している。ベトナムの総農家戸数は約1千万戸と推計され、その半部以上がホン河デルタとメコン・デルタに集中しており、山岳地帯の北西部と南部高原には農家戸数が少ない。1戸当たりの経営面積は、全国平均で0.736ヘクタールとなっているが、南部の3つの地域が1.2-1.8ヘクタールの水準にあるのに比べて、その他の地域は0.5ヘクタール未満で、特に人口密度が高いホン河デルタの地域の平均規模は0.25ヘクタールに過ぎない。同じ米作地帯であっても、ホン河デルタとメコン・デルタとの間に経営面積と所得水準において大きな格差があることを裏付けている。
1戸当たりの農地面積をさらに米作と永年作物に分けると、それぞれの地域がもつ作付体系の特徴を読み取ることができる。図1に見られるように、メコン・デルタの地域には、米作の面積が他の地域を大きく上回っており、米の生産における同地域の絶対的な優位を示している。逆に、南部の高原と工業地帯には永年作物の面積が大きい。それぞれの地域の農業形態はこれらのデーターから推測することができる。すなわち、ホン河地域には、小規模な稲作経営が主体であるのに対して、メコン・デルタ地域は、同じく米作中心であっても、経営規模が大きいこと、南部の高原と工業地帯には小規模な米作と永年作物の農園が並存していることなどがそれである。
| 表5. 農家規模の地域間比較(1998年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) 農業開発の制約要因
以上で見たように、ベトナムの農業生産は、配給制・管理価格の縮小・廃止や個人農家の導入などの改革により1986-2000年の期間に大きな飛躍を記録している。
しかし、ドイモイという制度上の改革によるこの飛躍があったものの、同国の農業・農村が今後も引き続き成長するには、以下に要約される制約要因を打破しなければならない。
| (1) | 水利・道路などの管理組織の脆弱さ
農業合作社(合弁会社)は、現在、多額の債務やメンバーの脱退などでほとんど活動停止の状態にある。これらの合作社は、1986年以前の期間には農業の生産に限らず、農産物の流通、農業生産に必要な投入財の購入、灌漑や道路の維持・管理などの機能も果たしていた。ドイモイの下で合作社が活動停止に追い込まれた現在は、農業インフラの維持・管理が重要な課題となりつつあるが、協同組合法の制定により農業協同組合がその担い手として着実に育成されつつある。 |
| (2) | 酸性土壌の問題
低地の南部では、メコン(Cuu Long)やドンナイ(Dong Nai)、ヴァムコ(Vam Co)など、主要な河の下流に、塩分の多い海水の逆流で土壌が酸性となり、作物の成長を妨げ、米やその他の穀物の単収と品質を悪化させる大きな要因となっている。 |
| (3) | 水利施設など 農業インフラへの投資が不足している。(灌漑面積は農業用地の約7割を占めるに至っているが、水利施設は十分な維持・管理を受けていない。農業投資は政府予算の1.6%に過ぎない。) |
| (4) | 栽培技術の向上(農家レベル)、新しい農業技術の研究・普及(中央官庁・地方政府レベル)、計画立案の能力(中央官庁・地方政府)などを含めた技術・制度・組織はまだ脆弱。 |
2)ベトナムの農業・農村開発と日本の援助
a) ベトナム農業・農村開発に対する日本の援助
ベトナムの内戦で同国に対してほぼ停止の状態になった日本の援助は、ドイモイの実施をきっかけに本格的に再開するようになった。農業・農村開発の分野についての日本の援助は無償、プロジェクト方式技術協力及び開発調査を行なっている。無償の形態には、-農学部改善計画、草の根無償(ダンフォン村貯水池・農道整備計画など)の灌漑施設整備計画)などが含まれる。プロ技協には、メコン・デルタ酸性硫酸塩土壌造林技術開発計画とハノイ農業大学強化計画がある。開発調査には、ゲアン省ナムダン県農業総合開発計画、同県におけるモデル農村開発計画調査、ドンタップモイ農業開発計画調査などが含まれている。このように、農業分野における日本の援助は、小規模な灌漑設備を除いて、技術訓練・研究の強化、農村開発の計画・立案と土壌の改善を行なっている。
b) 日本の援助の効果
すでに述べた制約要因に照らして見ると、日本援助はベトナム農業の開発ニーズに合致しているものと言える。特に、日本援助は技術の研究・普及と小規模灌漑に集中したが、1986―2000年に記録した農業生産の飛躍についての要因分析で(1-1を参照)この2つの要素はベトナム農業の成長に大きく貢献したことことが確認されている。それぞれの協力形態についての評価は以下に要約される。なお、「援助実績とりまとめ表」に掲げたように農業セクターにはこの他の援助案件もあるが、今回調査では時間的な制約から、全件を評価することはせず、代表的な援助案件をサンプル的に評価せざるを得なかった。この点による制約があることに注意を要する。
プロ技協
この形態の援助は、総じてベトナム農業がおかれている組織や技術の現状に非常によく機能していると見受けられる。以下、実施の現状、効果と問題点を要約する。
| 〇 | 構成と手順が基準化されたこの協力形態は、まだ援助の受け入れになれていないベトナム側にとっては受け入れられやすい。 |
| 〇 | デスクワークに傾斜しがちなベトナム人教員に対して実験・研究計画の立案と実施に関する技術移転は非常に高く評価されている(大学の強化プログラム)。 |
| 〇 | ハノイ農大への協力の実施をきっかけにして、同大学がいくつかの大学に対して独自の協力プログラムを進めたほど、大きな波及効果を生み出している。 |
| 〇 | 受け入れるベトナム側のカウンターパーツ(特に大学教員の場合)が十分に対応できないケースがしばしば生じる(兼務で時間的余裕がない)。 |
開発調査
調査の計画と実施に人材と資金が不足している現状では、開発調査は非常に歓迎されている。以下、実施の現状、効果と課題を要約する。
| 〇 | 調査の過程でベトナム側(農業農村開発省、大学、研究機関、地方行政)への技術移転の効果が少なからずあったと指摘されている。 |
| 〇 | 農業・農村開発について行なわれた調査の結果はまだ具体化されていないが、今後の計画実施に大きく貢献するものと推量される。 |
| 〇 | 開発調査については、調査期間が2~3年かかるため、ベトナムの農業のように成長の速い分野については、常に最新情報に基づいて実施していくことに留意する必要がある。 |
無償資金協力
無償資金協力の分野では、「カントー大学農学部改善計画」(無償、93~95年度)がある。同学部は、我が国の援助によって設立された学部であり、南部地域の省庁的な案件のひとつとなっている。戦前には学部が建設時点から日本は協力を実施しており、戦後には無償資金協力によって学部校舎建設(1993~1995年度)および教育機材供与を実施してきた。ただし、今回評価調査においては、時間的制約から現地視察は実施しなかった。
草の根無償(灌漑施設整備計画など)
村落レベルでの灌漑の整備を主とするこの形態の援助は、対象地域の灌漑の改善だけでなく組織・管理の面での技術移転にも役立っているものと指摘されている。以下、実施の現状、効果と問題点を要約する。
| 〇 | 農業インフラの維持管理の重要性への地方政府や農家の認識の向上に役立っている。 |
| 〇 | 実際に農業生産の増大に貢献している。 |
15 本報告書における「永年作物」には、茶、コーヒー、ゴム等が含まれる。なお、ベトナムの輸出に占めるこれらの作物の比率等を議論する場合には、文脈上「輸出作物」という用語も用いている。
16 分析の期間における技術変化を反映するようにDに(0,0,0.5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)の値を仮定した。

