(3)インフラ分野の開発に対する日本の貢献度合と目的の達成度合の評価
ここでは、インフラ分野に対する日本の援助に関して、運輸、電力、通信、都市開発/地方開発という4つの分野に分けて、日本の貢献度合と目的の達成度合に関する分析を行い、インフラ分野に対する日本の援助の評価を行うこととする。
1)運輸
運輸分野では、ベトナム側は、第6次5カ年計画(1996~2000年)において、基幹ルートにおける円滑な交通をはじめ、各地域における需要に見合った運輸サービスの供給、山間部、農村部における道路整備、山間部ならびにメコン・デルタ地域における道路の整備等、インフラ整備の中でも特に運輸インフラの整備を重視してきた。
また、日本側は、対越援助方針(1994年~1999年)において各交通形態の特性に応じた運輸分野での協力を重要な課題として挙げるとともに、対越国別援助計画(2000年)では、越国内の都市間及び都市と農村を結ぶ基幹輸送網や地方道路や都市公共交通基盤の整備を図りつつ、また域内や国内の物流の増加に貢献する港湾・空港・鉄道等の物流基盤施設、及び東西回廊等の広域プロジェクトにも配慮し、効率的な運輸インフラ整備を検討することを盛り込んでいる。
運輸分野は、日本が対越援助の中で、電力分野と並んで最も重点を置いている分野の1つである。有償資金協力だけで見た場合に、1992~2000年度における有償資金協力の貸付承認額の総額に占める運輸分野の割合は37%である。案件数も道路、橋梁、港湾を中心に、有償資金協力案件が2001年7月までに14件、無償資金協力が2件承認されている。世銀の推定によれば、1992年から1997年までの間に承認された運輸分野に対するODAの承認額は総額で約15億ドルであるが、そのうち日本が33%(4.92億ドル)、世銀が32%(4.82億ドル)、ADBが21%(3.2億ドル)、他ドナーが13%(2億ドル)を占めている(図1を参照)。また、ベトナム交通運輸省によれば、ベトナムが2001年から2005年までの間に実施を計画している運輸分野の案件に対するODAにおいて、日本が実に全体の52%を占めている。世銀が24%、ADBが9%、他ドナーが15%となっている(図2を参照)。
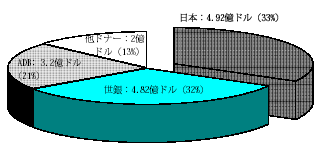
図1.ベトナムの運輸分野における ODA
に対する各ドナーの貢献度(1992-1997 の承認額)
出所:世銀推定値
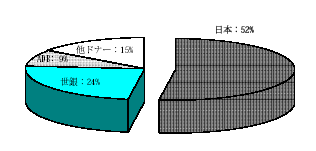
図2.ベトナムの運輸分野における ODAに
対する各ドナーの割合 (2001-2005の計画)
出所:ベトナム交通運輸省
日本の有償資金協力の案件の実施状況については、ベトナム交通運輸省及び日本側の情報によれば、日本の案件14件のうち、ハイフォン港復旧計画は終了、国道5号線改善計画、南北統一鉄道橋梁復旧計画、国道1号線橋梁復旧計画は現在も一部事業中、それ以外は現在建設中あるいはこれから建設開始である。
また、運輸分野に対する日本の援助の評価について、ベトナム交通運輸省は、日本の援助によって行われている案件は、いずれもベトナムの運輸分野の重要な案件であり、日本の援助はベトナムの運輸インフラの整備に大きく貢献し、その結果として経済社会発展や貧困の削減にも役立っている、と評価している。
具体的には、首都ハノイを中心に北部地域の主要な運輸インフラについて、国道5号線(ハノイ~ハイフォン港)、国道10号線(ハイフォン港~ニンビン省)、国道18号線(ハノイ~カイラン港)、国道1号線橋梁(ハノイ~中国との国境)、ビン橋(ハイフォン市)、タインチ橋(ハノイ市)等、主要都市間や主要港湾、工業団地、観光地を結ぶ道路・橋梁の整備と、ハイフォン港とカイラン港という北部地域の2大港湾の整備、等トータルな運輸インフラの整備を支援することにより、北部地域の経済・社会活動に貢献することが予想される(図3を参照)。

日本の援助で整備された国道5号線(首都ハノイ~ハイフォン港)
(片道2車線(一部片道3車線)、歩行者専用道路及び街灯あり)

日本の援助で整備された国道10号線
(片道2車線、街灯あり)

完成した案件では、例えば国道5号線は首都ハノイと北部地域の最重要港であるハイフォンを結ぶ全長106kmの道路であるが、有償資金協力プロジェクトでは、このうち91kmについてリハビリと車線の拡幅を行なった。以前はハノイからハイフォンまでの所要時間が5時間以上であったが、有償資金協力プロジェクトにより、現在は所要時間が半分以下に短縮され、物流が大幅に改善された。これは近年のハノイ周辺地域への我が国企業による投資増加にも結びついている。
また、ハイフォン港はベトナム北部地域最大の港であり、有償資金協力による「ハイフォン港復旧計画」によりコンテナ取扱能力が格段に向上した。ハイフォン港湾局によれば、ハイフォン港の貨物取扱量は、1993年には240万トンであったのが、2000年には750万トンにまで伸びた。有償資金協力案件が実施される前の1993年におけるコンテナ取扱能力は年間30,000~50,000TEUであったが、有償資金協力案件の実施により、2000年には220,000TEUにまで拡大した14。現在、有償資金協力によるフェーズ2が開始されており、フェーズ2が完成するとハイフォン港のコンテナ取扱能力は年間500,000TEUにまで拡大する見込みである(フェーズ2の完成予定は2004年末である)。
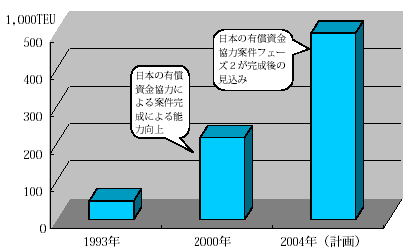
図4.ハイフォン港の年間コンテナ取扱能力の推移
出所:ハイフォン港湾局

ハイフォン港の様子1

ハイフォン港の様子2
ホーチミン市を中心とする南部地域については、サイゴン東西ハイウェイ(ホーチミン市)やカントー橋(メコン・デルタに位置するカントー市)、国道1号線橋梁(ホーチミン市~メコン・デルタ、ホーチミン市~中部地域)等により、南部地域の交通改善に貢献することが見込まれる。これらの案件は南部地域の経済発展にとって大変重要であるという認識をベトナム交通運輸省側も示していた(図3を参照)。
また、開発の遅れている中部地域については、中部地域の主要港であるダナン港の改良と、国道1号線の難所であるハイヴァン峠にトンネルを建設することによって、中部地域の交通改善にも貢献する(図3を参照)。さらに、山岳地域や地方についても、無償援助によって北部に29本の橋が建設された。なお、今回評価の対象ではないが、関連情報としては、南部のメコン・デルタに37本の橋を建設中であり、今後中部地域で45本の橋を建設する予定である。これらは地方住民の交通を改善するものであり、貧困削減にも効果的であるとベトナム交通運輸省側は評価している。
日本の技術協力・開発調査に関しても、「運輸交通開発戦略調査」や「北部地域交通システム開発計画」、「全国沿岸海上輸送整備開発計画」等の開発計画は、ベトナムの交通セクター開発戦略を策定する上でとても重要な調査であると運輸省側は評価している。
2)電力
電力分野では、ベトナム側は、第6次5カ年計画(1996~2000年)において各地域における需要に見合った電力の供給と山間部、農村部における電力インフラの整備を目標として掲げていた。また、日本側は、対越援助方針(1994年度~1999年度)において将来的な需要の増加に対応するための電力分野での協力を重要な課題として挙げるとともに、対越国別援助計画(2000年度)では、発電・送配電・地方電化等ハード面の整備に加えて、効率的な事業計画、運営能力向上等ソフト面への支援を検討することを盛り込んでいる。
電力分野は、日本が対越援助の中で、運輸分野と並んで最も重点を置いている分野の1つである。有償資金協力だけで見た場合に、1992~2000年度における有償資金協力の貸付承認額の総額に占める電力分野の割合は35%である。
ベトナム工業省によれば、ベトナム政府はエネルギー関連に年間約10億ドルの投資を行っており、そのうち、日本のODAが年間約3億ドル、世銀が約1.5億ドル、ADBが約1億ドル程度である。世銀やADBと比べて、日本は援助の金額が大きく、条件が有利であるため、日本の有償資金協力援助は主に大きな投資が必要となる発電所の建設に充てており、他方、世銀やADBからの援助は主に送電システムの整備や政策の策定に充てているとのことである。世銀などと比べて、日本は融資する際に厳しい条件をつけないことをベトナム側は高く評価している。ベトナムにおいて現在電力料金は安く抑えられており、それが産業の発展には好条件となっているが、電力料金を急激に引き上げずにすむのは日本の援助のおかげであると電力公社は評価している。
有償資金協力案件の実施状況に関して、電力公社からの報告によれば、ベトナム最大規模の発電所であるフーミー火力発電所の3基(総出力1,090MW、ガス・コンバインドサイクル型)は完成して順調に発電を行なっている。また、ファーライ火力発電所の1基(出力300MW、石炭火力)、ハムトアン・ダーミー水力発電所(総出力475MW)は引き渡し前であり、現在試運転を行っている。また、ファーライ火力発電所の2基目(出力300MW)、ダイニン水力発電所(総出力300MW)、オモン火力発電所(出力300MW)の建設と、ダニム電力システム(40MW x 4基のダニム発電所およびサイゴン変電所と230kV送電線257kmの改修)、フーミー~ホーチミン送電線(500kVの送電線および変電設備の整備)は、現在建設中あるいは準備中である(各案件の位置に関しては図7を参照)。
したがって、援助を実質的に再開した1992年度以降、日本の援助はすでに完成した発電所だけで1,865MWの発電能力に対して支援を行なったことになる。これはベトナムにおける現時点での発電総能力8,038MWの約23%にあたる(図5)。また、1992年から2001年までの10年間におけるベトナムの発電総能力の伸びが4,861MWであるので、日本はその38%に対して援助を行ってきたことになる(図6)。
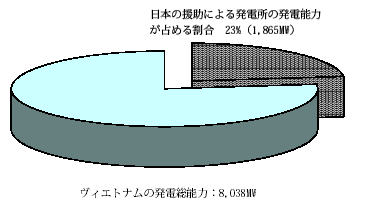
図5.ベトナムの発電総能力に対する日本の
援助の貢献度(2001年時点における稼働分のみ)
出所:ベトナム電力公社
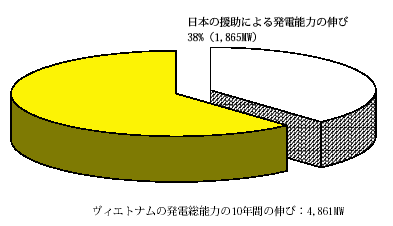
図6.ベトナムの発電総能力の伸びに占める
日本の援助の貢献度(1992-2001年の 10年間)
出所:ベトナム電力公社

フーミー火力発電所の外観1

フーミー火力発電所の外観2

ファーライ火力発電所の外観
3)通信
通信分野では、ベトナム側は、第6次5カ年計画(1996~2000年)において各地域における需要に見合った情報の供給と山間部、農村部における通信インフラの整備を目標として掲げていた。また、第5次5カ年計画(1991~1995年)でも、電話網の整備が主要課題として掲げられていた。一方、日本側は、対越援助方針(1994年度~1999年度)では通信分野について具体的には言及しなかったが、対越国別援助計画(2000年度)において、民間活力の活用をも視野に入れつつ、情報格差の是正に向けた協力の可能性を検討することが盛り込まれている。
通信分野におけるこれまでの日本の援助の主要案件は、有償資金協力による「中部地域地方通信網整備計画」をはじめ、「全国電気通信整備計画調査」(1998~1999年度実施、開発調査)や、現在実施中のプロジェクト方式技術協力「電気通信訓練向上計画」(1999~2004年度実施)による技術協力などが挙げられる。
「中部ベトナム地方通信網整備計画」は、電話普及率の低い中部10省における通信設備の整備であるが、56のパッケージから成っており、そのうち日本の援助が4パッケージに使われ、残りの52パッケージはベトナムの国内予算によって実施される。日本の援助によって行われる4パッケージは現在手続き中である。
「電気通信訓練向上計画」はまだ実施中であり、評価を行うには時期尚早であるが、ベトナム郵電公社側の話によれば、本案件は順調に進んでおり、本案件によりインターネットなどの新しい通信技術に関する郵電公社の幹部の知識レベルが向上している。
ベトナム郵電公社は、日本以外にもEU諸国(フランス、スウェーデン、イタリア等)からもODAを受けており、全ODAに占める日本の割合は20~25%程度である。また、郵電公社が行っている投資全体から見れば、日本のODAの占める割合はあまり大きくない。郵電公社は年間に約3億ドルの投資を行っており、これには自己資金とODA資金が含まれる。民間資本は地方インフラには投資できないので、ODAは非常に重要である。地方の通信インフラ整備は貧困削減にも役立つ、と郵電公社はコメントしている。
郵電公社側の評価では、通信分野に対するこれまでの日本からのODAの案件数は少ないが、実施された案件は効果的なものであった。
4)都市開発/地方開発
都市開発および地方開発について、ベトナム側は、上述の内容と重複するが、第6次5カ年計画(1996~2000年)で山間部、農村部におけるインフラ整備を目標の1つとして掲げていた。また、第7次5カ年計画(2001~2005年)では、ハノイ市、ホーチミン市等主要都市の都市インフラの近代化を目標の1つとして掲げている。これに対して、日本側は、都市開発あるいは地方開発を独立した目標として特に掲げてはいないが、対越援助方針(1994年度~1999年度)における「輸出志向型経済成長のための外国投資導入に資するインフラ整備」や、対越国別援助計画(2000年度)における「工業開発の促進に資する支援や投資の効率性向上に繋がる基礎インフラ整備に対する支援」には主要都市における都市インフラの整備も含まれるものと考えられる。
都市開発/地方開発に関するこれまでの日本の援助の主な実績としては、ハノイ市の都市インフラ整備に対して、有償資金協力案件1件(「ハノイ市インフラ整備計画」)と開発調査1件(「ハノイ市都市交通計画」(1994~1996年度実施))を実施してきた。また、地方における基礎インフラ設備のために、有償資金協力1件(「地方開発・生活環境改善計画」)を行ってきた。
「ハノイ市インフラ整備計画」はハノイ市の北部に位置するタンロン地区における工業団地・居住地域・物流センター・商業地域等の総合地域開発に必要なインフラ整備を行うプロジェクトである。なお、同開発調査に基づいて実施された「ハノイ市交通網整備計画」は、運輸インフラとして見ることもできるが、ハノイ市内の交通のボトルネックとなっている道路数ヶ所と交差点数ヶ所の整備・改良(地下道と橋の建設を含む)を行うプロジェクトである。ハノイ市人民委員会計画投資局によれば、どちらの案件も住民移転等のベトナム国内の問題により、案件の実施が計画よりも遅れている。
「地方開発・生活環境改善計画」は、地方における基礎インフラ設備(地方道路、地方電化)を目的としたプロジェクトであり、具体的には地方道路約2,970kmの整備、未電化村約470カ所の電化、地方水道37ヶ所の整備を目指している。本案件の事業実施者である計画投資省によれば、本案件はいくつかのフェーズに分けて実施されており、現在実施中である。計画投資省は、本案件について地方の人々を直接的にサポートする、とてもよい案件だと評価している。本案件は、ベトナムの第6次5カ年計画(1996~2000年)で目標の1つに掲げられている山間部、農村部におけるインフラ整備に合致したものであり、その実現の一部を担っている。
5)インフラ分野に対する日本の援助の評価
これまで日本の援助はベトナムのインフラ整備、特に運輸インフラと電力インフラの整備に大きく貢献してきた。劣化が激しい既存の運輸インフラの改修と、急速に拡大する運輸需要に対応するために新規の運輸インフラ整備を必要とするベトナムにおいて、運輸インフラに対する巨額の投資を日本は支援してきた。また、電力インフラについても、急速に拡大する電力需要に対応し、産業の発展にとって電力の供給不足がボトルネックとならないためには、電力インフラに対して巨額の投資を必要としてきているが、日本はこれを支援してきた。運輸、電力等のインフラ整備はこれまでベトナム側の国家開発計画においてもプライオリティの高い目標であったし、日本の援助方針においても重点分野のひとつであった。したがって、運輸・電力の2セクターだけで有償資金協力全体の70%以上を占めるというのは、ベトナム側、日本側双方の目的・目標に合致したものであったと考えられる。ベトナム政府側も、日本がこれまで行ってきた、このようなインフラ分野に対する重点的な援助を大変高く評価している。かつ、国道5号線、ハイフォン港、一部の電力案件等については、既に完成し、定量的な効果も確認されている。
その一方で問題点として指摘すべきは、種々の原因による遅れにより、承認された有償資金協力案件のうちですでに完成したものがまだ多くないということである。案件の実施が遅れる原因には、ベトナム国内の原因も含まれるが、日本側の手続きは、案件の提案から承認までに時間を要するということが、ベトナム政府の複数の省庁から共通して指摘された。一方で、日本から承認を受けてから案件の実施に到るまでのベトナム側の手続きにも時間を要していることが指摘されねばならない。
インフラは完成しないとその経済的効果は限定的なものに留まってしまうので、完成された案件が多くないということは、現時点でインフラ分野に対する日本の援助がベトナムの経済に与えた効果が限定的である可能性がある。現在実施中の案件が完成するにしたがって、日本の援助が今後ベトナム経済に大きな効果をもたらすことが予想される。
14 TEUとはTwenty-footer Equivalent Unitの略で、20フィート長のコンテナ換算でコンテナの個数が幾つかを数える基準となる単位である。20フィートのコンテナ1個は1TEU、40フィートのコンテナ1個は2TEUと計算される。

