(3)人造り・制度作りにおける日本の貢献度合と目的の達成度合
1)ベトナム政府側の評価
a) 経済改革支援借款
本件のカウンターパートである計画投資省は、経済改革支援借款(新宮沢構想)は、日本の初めての構造調整への取組みを条件としたローンであり、民間企業の育成、国営企業の改革、貿易・関税制度の改革に関し直接的、間接的にベトナム政府の改革を促すものであり高く評価している。
直接的という意味では、政府予算に繰り入れ、金融、関税システムの改革となって実行されつつある。また、間接的には、政府担当者の意識改革、さらには世銀その他ドナーの支援につなげる契機となった。このローンの条件となっていた項目のうちかなりは既に実現されている。
b) 市場経済化支援開発政策調査
同じく本件のカウンターパートである計画投資省からは、市場経済化支援開発政策調査(石川プロジェクト)は、日本初めてのベトナムの市場経済化支援のための政策提言型プロジェクトであり高く評価されてている。ベトナムの第6次国家開発5ヵ年計画(1996-2000年)策定にあたり、日本・ベトナムの数多くの経済専門家が協力、その成果は同開発計画に反映されている。マクロ経済政策、財政金融改革、産業育成、金融改革、国営企業改革、農業・農村開発など幅広い分野に研究分野はおよんでいる。
ベトナムへのインパクトとしては、1)参加したベトナムの政策担当者の能力向上、 2)政策担当者から、政府上層部、共産党上層部までの波及効果、 3)セミナー、報告書による広く一般への波及効果があげられる。また両国の交流の活発化と関係改善にも大きく貢献した。
さらに、本プロジェクトは、「石川プロジェクト」の名で広くベトナム政府関係者の間では知られており、石川滋・一橋大学教授もベトナム国家主席から友誼勲章を授与されている事実からもベトナム側の高い評価は理解される。同プロジェクトは、将来のベトナム経済に関する研究課題や協力の方向性なども示唆しているものであり、この点に重要性が認められる。また、移行経済の改革モデルとしてラオス、カンボディア、ミャンマー等が参加する国際セミナーでも報告されている。石川プロジェクトは経済開発の基本的方向や選択肢を示したもので、具体的法制度改革の提示までは到っていない。
しかしながら、同計画を策定したベトナムの政策担当者達が石川プロジェクトに参加したのであり、その担当者達への知的支援になっていることは疑う余地もない。
今後の開発計画もそれらの担当者が策定していくわけであり、そういった意味でも、ベトナムの経済政策の基本方向を定めるためのベースになった協力といえる。
c) 法制度整備支援
本件カウンターパートである法務省は、1996年、他のドナーに先がけ、初めて法制度関連の研修をスタートさせてくれたのが日本である。ベトナム側も、この点を高く評価している。
ベトナム側は、人的資源の改善と組織的改善が重要と考えてきたが、こうしたニーズを日本側が良く理解し、ベトナムの要請に沿ったトレーニングコースの設定と、提案を行ってくれたと評価している。日本で研修をうけたスタッフもほとんどが帰国後も関連の部署に在席しており技術移転や普及の効果もあるとしている。
他12に及ぶ国、国際機関等からの研修協力はあるが研修生受入れ等の面で規模的に日本が最大、また専門家派遣期間も長い。他のドナーの研修、専門家派遣は短期的なものがほとんどである。
日本側の法制度改革に対する提言は、ベトナムにおいて評価され、それに基づき法改正が一部実現し、その後共同で今後の民法改正についても調査研究中である。
d) 人材育成
工業省が本件の主なカウンターパートであるが、市場経済化、グローバル経済化が進む中で、ベトナム産業にとっては、製造業、機械工業で働く、ワーカーのレベルアップが重要な課題である。WTO加盟を控えて数年内に設備の近代化と人材育成を実現していく方針である。日本のODAによるハノイ工科短大の機械工業分野でのトレーニング・プロジェクトは、スタートしたばかりであるが、ベトナムのニーズにマッチしたものとして高く評価している。人材教育の面でも日本は他のドナーに比べ最大量を提供してくれており、また技術やその移転方法も文化的類似性があり、受入れ、理解しやすいという点で評価している。
e) 中小企業育成
中小企業育成は極めて重要な課題であり、現在はJICAのマスタープラン策定を投資計画省がカウンターパートとなって実施し、基本的政策方向を検討している段階にある。
政策の方向性を位置付けた後、工業省も加って具体的振興策を打ち出していくことになり、この分野で豊かな経験を持つ日本の協力に期待している。
2)日本側の評価
a)「市場経済化支援開発政策調査」
「市場経済化支援開発政策調査」に関しては、石川滋総括主査をはじめとする調査参加者によって「日越共同研究の自己評価」中間報告(2001年11月)という自己評価がとりまとめられている。この中間報告によると、日越共同研究が日本のODAとしてはじめての本格的な「知的協力」という性質を持つ援助であったことにより、評価をする上でも形式的意味での評価を超える特殊な重要性があるとしている。「知的協力」とは、経済開発の包括的な局面を対象とする経済政策、経済計画の立案・実施のための調査研究のあと、それにもとづく政策オプションの提案を含む支援であり、このような形態の援助は事実上すでにベトナムに続いてアジア地域のラオス、モンゴル、ミャンマーなどから、中南米、旧ソ連構成自治共和国、東欧諸国に拡がっていることが評価できるとしている。
また、このプロジェクトの意義深い特徴として2点が指摘されている。一つは日越の研究者により共同研究という新しいユニークな形式で市場経済化支援が実施されたことである。石川プロジェクトの最大の特徴はベトナム側のオーナーシップを最大限尊重しつつ、日越共同研究形式により政策提言のオプションを提示するといった、世銀/IMFとは異なる日本独自の援助スタイルで実施されてきた点である。具体的には、ベトナム側の問題意識を丁寧に確認しつつ日越双方が知恵を出し合いながらベトナムの現状に最も適していると思われる政策提言のオプションを形成した点である。一方的な日本側からの提言によらない方式を採用したことで日越間に信頼関係が醸成され、結果として提言内容が尊重されることに繋がったと考えられている。
二つ目は、冷戦終結後の世界における市場経済化、民主化の大きな流れの中でこれまで、ベトナムに対する市場経済化支援はその先駆的な役割を果たしたことである。ラオス、ミャンマーなどのインドシナ諸国に対する市場経済化支援の実施に際しては、ベトナムの市場経済化支援の成功例としての経験がその後の協力のモデルとなっていることは、たいへん意義深いと評価されている。
b)「ベトナム情報処理研修計画」
「ベトナム情報処理研修計画」に関する日越共同での終了時評価結果(2001年10月実施)では以下のように評価5項目に沿って高い評価がなされている。
実施の効率性:プロジェクト実施にあたっての機械、施設、人員等の投入は、計画通り適切であり、その成果も十分得られた。
目標達成度:マスタープランに含まれていた、5つの目標はほぼ達成された。具体的には運営体制の確立、必要な施設・機械の整備と維持、カウンターパートのITインストラクター及びプランナーとしての育成、産業界への新技術紹介である。研修は当初計画通り7分野にわたり、3,216人が参加して実施されている。また、個別組織に対する特別研修コースも601人の参加が得られた。
インパクト:カウンターパート組織ベトナム情報処理研修所の役割と存在意義は今回のプロジェクトにより大きく高まった。研修参加者からの評価を得て、人材育成機関としての同研修所の評価も高まり、それを通じた社会に果たすIT分野での波及効果も大きい。
妥当性:ベトナム政府の開発戦略であるIT2000が目指す生産性向上、品質管理、各種サービス向上が可能となる情報社会の実現に向けて、当プロジェクトの妥当性は高い。
自己発展性:自立発展に向けて、政府機関、大学、企業とのネットワークが今後も不可欠である。さらに技術面や財政面でも、2001年の首相令によって、当プロジェクト終了後VITTIはベトナム国家大学ハノイ校の情報技術研究所として改組され、組織的ステータスと業務遂行責任が格段に高まることになっており、自立発展性は期待できる。
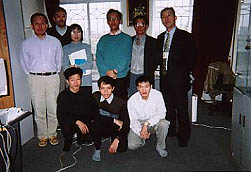
情報処理研修センター JICA専門家と研修生たち
(右端が木内JICA専門家(チームリーダー))
c)国別特設研修
JICAが2001年度に実施した「特定テーマ評価(国別特設研修)」のうち、ベトナム研修アンケート調査結果から、同事業団の研修に対する評価や研修のインパクトを人材育成の観点からレビューしてみたい。同アンケート調査の対象となったのは、1993年から2001年までの研修生約500人で、そのうち120人が回答を寄せている。回答者が受講した研修コースは中小企業振興25人、法整備支援17人、税務及金融14人、日本の経験11人、マクロ経済及び地方振興各8人などとなっている。
以下に研修生の具体的評価を主要項目別にみていく。
研修目的:特にすぐれているが50.8%、すぐれているが48.3%と研修受講者のほぼ全員が高い評価をしている。
研修テーマ:各研修コースがカバーしたテーマについては、特にすぐれているが35%、すぐれているが、61.67%となっており、この点でも評価は高い。
研修レベル、講師、教材:研修レベルについても、特にすぐれているが、28.33%、すぐれているが65.83%をしめている。また、講師及び教材に関しても、特にすぐれているが、それぞれ54.15%、37.5%、すぐれているが同じく45%、54.17%となっている。このほか、あまり高い評価はできないとする回答が残り数%を占めており、いずれの評価項目においても完全に否定的な回答は皆無である。
研修の理解度、効果:研修内容が十分に理解できたとするのが28.33%、ほぼ十分に理解できたとする回答が65.83%を占めている。なお、一部に理解できなかったと回答した理由として、コミュニケーションの問題及び内容レベルが高すぎたの2つがあげられている。研修の効果に関しても、非常に適切かつ役立つ内容であったと評価する者が57.5%、かなり適切かつ役立つ内容であったとする者42.50%を占めている。
研修の波及効果:回答者のほぼ全員96.67%が、研修で修得した知識や技術を何らかの形で同僚や友人に伝えたいとしており、研修の波及効果は認められる。伝える具体的方法としては、上司や職場への報告書(60%)、研修教材の回覧(41.67%)、雑誌や論文(39.17%)、教室やワークショップでの講師(33.33%)、セミナーやワークショップ(27.50%)となっている。
研修修了者の定着:回答者の大多数である76.4%が研修終了後も、転職せずに、研修終了前と同じ職場に定着していることがわかった。
調査団の評価
市場経済化に資する人材育成・制度構築に関する援助が、日本の対ベトナム援助の大きな特徴であると言える。これまで一般に日本が途上国向けに実施してきたのと同様の個別の人材育成案件に加え、ベトナムにおいては、経済改革支援借款(「新宮沢構想」)や市場経済化支援開発政策調査(「石川プロジェクト」)という政策支援を実施してきた点が極めて新しく特徴的であった。
経済改革支援借款は、日本の初めての構造調整への取組みを条件としたローンであり、民間企業の育成、国営企業の改革、貿易・関税制度の改革に関し直接的、間接的にベトナム政府の改革を促すものであり実現率も高く日越双方から高く評価されている。市場経済化支援開発政策調査も同様に、日本初めてのベトナムの市場経済化支援のための政策提言型プロジェクトであり高く評価されている。ベトナムの第6次国家開発5ヵ年計画(1996-2000年)策定にあたり、日本・ベトナムの数多くの経済専門家が協力、その成果は同開発計画に反映されている。調査研究対象も、マクロ経済政策、財政金融改革、産業育成、金融改革、国営企業改革、農業・農村開発など幅広い分野に研究分野はおよんでいる。
ベトナム側の各省庁もこれらの新たなスキームでの協力があったこと、またその波及効果についても明確に認識し評価している。一方、他ドナーからのヒアリングによると、同様の協力は他ドナーも実施してきたわけであり、石川プロジェクトのみが現在の国家開発計画に反映されているわけではない、とのコメントが出された。
このほか、法制度整備支援においても、他のドナーに先がけ、初めて法制度関連の研修をスタートさせたのが日本であり、この点は高く評価されている。日本で研修をうけたスタッフもほとんどが帰国後も関連の部署に在席しており技術移転や普及の効果もあるとしておりこの点も評価できる。
ベトナム側は、人的資源の改善と組織的改善が重要と考えてきたが、こうしたニーズを日本側が良く理解し、ベトナムの要請に沿ったトレーニングコースの設定と、提案をおこなってくれたとコメントしている。日本のかつての援助の受け入れの経験を活かしベトナムの発展段階や技術受け入れ環境に十分な配慮した人造り・制度造りの支援をおこなっている。

