3.2 ベトナム開発の重点分野へのインパクト
3.2.1 人造り・制度作り(市場経済化移行支援)
(1)日本の援助実績
人造り・制度造り(特に市場経済化移行支援)に関連してこれまで実施されてきた主要協力プロジェクトには協力形態別に見ると次のようなものがある。
| 1)無償資金協力 | |
| 日越人材協力センター (2000~2005年度)
経済構造改革支援 25億円 (1997年度) |
|
| 2)有償資金協力 | |
| 中小企業支援事業 40億円 (1998年度)
経済改革支援借款 200億円 (1999年度) |
|
| 3)プロジェクト方式技術協力 | |
| 情報処理研修計画 (1997~2002年度)
日越人材協力センター (2000~2005年度) ハノイ工科短期大学機械技術者養成計画 (2000~2005年度) 工業所有権業務近代化 (2000~2004年度) |
|
| 4)開発調査 | |
| 市場経済化支援開発政策調査(フェーズ1・2フォローアップ)(1995~1999年度)
市場経済化支援計画策定調査(フェーズ 3) (1999~2001年度) 中小企業振興計画 (1998~1999年度) ハイテクパーク建設計画 (1996~1997年度) 工業標準化計量・検査・品質管理計画 (1996~1997年度) (専門家派遣、研修員受入) 法整備支援 (フェーズ1) (1996~1999年度) 証券取引センター (2000年度) |
|
| 現在のベトナム側、日本側双方の開発目標、開発戦略、重点項目等 |
(日本側) ベトナム側第7次5カ年計画に記載された開発目標、開発戦略、重点項目等
|
(日本側)国別援助計画(2000年)に記載された開発目標、開発戦略、重点項目等
|
・ 上記の表にあげられた7つの主要プロジェクトの概要と協力目標は以下の通りである。
1)経済改革支援借款
本件借款は、ベトナム政府の経済改革努力を支援するため、新宮沢構想と同様の考えの下、その延長としての支援として供与されたものであり、日・ベトナム両国政府間の政策協議を受け、1)民間セクター育成プログラムの策定・公表、2)大規模国営企業の監査実施、3)非関税障壁の関税化の3点につき実施を約束したことを踏まえ、支援を行うことが決定されている。
両国政府間の協議において、ベトナム政府側は、関税化スケジュールを提示するなどの、具体的な改革へのコミットメントを示している。また、民間セクター育成についても、これまで、国有企業を優遇してきた金融部門や許認可等の諸制度を改め、民間企業が金融、技術、許認可等で適切な支援や便宜を受けられるような制度をつくるなどのコミットメントを示している。なお、本借款でベトナムがコミットメントした改革の進捗ぶりについては、日本政府、JICA、JBICでモニタリングを行なっている。
2)市場経済化支援開発政策調査
社会主義計画経済から市場経済への転換を指向するベトナムに対して、経済体制の移行に伴う諸問題への対応と、それに続く経済開発計画策定のための、より具体的、戦略的な提言をおこなったもので、日本の学者とベトナム政策当局者の共同同研究の枠組みのもとで実施されている。
第1フェーズでは、当時ベトナム共産党第8回党大会での審議をめざして作成中であった「ベトナム社会経済開発5カ年計画」の草案に対する日本側からの意見の提出を重点目標としてきた。第2フェーズでは同5カ年計画の実行とその過程で生じてきた新たな諸問題についての分析および政策提案を目的としてきた。具体的調査研究分野としては、農業・農村開発、産業政策および貿易政策、財政金融政策、国営企業政策等をとりあげている。
3)法整備支援
ベトナム政府は、ドイモイ路線採用以降、市場経済化と対外開放政策を推進している。そのためには旧ソ連の法制度を基礎として構築した法体系を見直し、市場経済化を支援する新たな法的枠組みを構築することが急務となっており、ベトナム司法省は各国政府及び国際機関の協力により法律の整備を進め、1992年に新憲法、また1993年に民法を制定した。ベトナム政府は、引き続き、商法や民事訴訟法等の法律や民法典の付属法令を早急に整備する必要がある。
(参考)日越共同研究の(「石川プロジェクト」)概要(PDF)
かかる背景を踏まえ、同国政府は、同国が急速な経済・社会改革に対応するために取り組んでいる各種法律(特に市場経済の導入に対応した民法、商法等)の整備及び人材育成等についての協力を我が国政府に要請した。
ベトナムの市場経済化に適合した行政体制の整備を図るため、民法・商法等の市場経済化に必要な法的枠組みの整備に対する支援を行っている。協力に当たっては、以下を3本柱としている。
(1)個別立法作業への助言
(2)法体系の整備への助言(現行法令の鳥瞰図作成、民法改正共同研究)
(3)人材育成(司法官僚、裁判官、検察官)
4)日越人材協力センター
1986年に採択されたドイモイ政策は、最新の国家開発戦略「2000年までの経済・社会発展戦略」の中でも明確に反映されており、経済活動自由化のための人材の育成が最重要課題の一つとして位置づけられている。
一方、我が国においては、アジアの市場経済移行国に対する人材育成支援の一環として、「日越人材協力センター」を設立することが構想され、1998年7月には同国及びラオスにプロジェクト形成調査団が派遣された。
この結果ベトナム政府は、以前から要望していた外国貿易大学に対する人材育成の為の技術協力要請を本案件に振り替えることに合意し、外国貿易大学のハノイ本校、及びホーチミン校それぞれに日越人材協力センターを設立することになった。
この協力により、ベトナム国において市場経済化を進めるために必要な人材の能力が向上する。また、ハノイ、ホーチミンの両市に設立する日越人材センターによりベトナム国の市場経済化のために必要な人材が継続的に育成され、日越の社会や文化についての相互理解の向上、日越間の人的関係が強化される。
具体的協力活動内容としては、
| 1) | ビジネスコース(会計、企業財務、マーケティング、ビジネスにかかる国際法、人材管理、統計、コンピュータ利用、経営・貿易実務、市場情報、生産管理、日本の経験等)の教材の開発とコースの実施 |
| 2) | ビジネスのための日本語コース教材の開発と、コースの実施 |
| 3) | 各種交流事業及びインフォメーションサービス |
5)ハノイ工科短期大学機械技術者養成計画
ベトナム国においてはドイモイ政策後の市場経済化促進により、機械分野における技能労働者が著しく不足しており(1998年270万人、2003年520万人)、これら技能労働者を養成する人材の確保が求められている。ベトナム北部において機械部門の技術者養成の拠点校と位置づけられているハノイ工科短期大学(HIC)の機械技術者養成能力を向上させることを計画し、日本側に技術協力を要請してきた。
ハノイ工科短期大学の機械技術者養成能力が向上し、ベトナムにおける機械工業分野の発展に対応した訓練コース(機械加工、機械板金加工、電気制御)が開発され、かつ、適正に実施される。
具体的協力活動内容としては、
| (1) | 訓練コースのための施設、機材を設置 |
| (2) | 機械工業分野のニーズに基づいてカリキュラム開発を行い、教材等を作成 |
| (3) | 指導員の訓練 |
| (4) | 入学志望者の応募資格、条件を規定し、募集選考の実施 |
| (5) | 自立発展に必要な組織・体制づくり |
| (6) | 現行の機械工業分野の訓練体系見直し |
6)情報処理研修計画
ベトナム政府はドイモイ政策の一環として、1993年8月に2000年までの情報工学分野整備計画を含む「IT2000」を発表し、生産性向上、品質管理推進及び各種サービス向上が可能となる「情報社会」を目指すことを明らかにした。
この計画に基づき、ベトナム政府は、1994年2月、わが国に対し、ベトナム国家大学の一組織であるハノイ科学大学にベトナム情報処理研修所( VITTI )を設立し、情報処理技術者の育成・質的向上を図ることにより、同国の産業、科学技術研究、サービス等の向上に資することを目的とするプロジェクト方式技術協力を要請してきた。
ベトナム情報処理研修所(VITTI)が、産業界のニーズに応じた情報処理関連の研修コース、セミナーを持続的に開催・運営できるようになる。
具体的協力活動内容としては、
| (1) | 養成計画の作成 |
| (2) | C/Pに対する講義指導及び教材作成に関する指導 |
| (3) | 研修コース運営のための指導 |
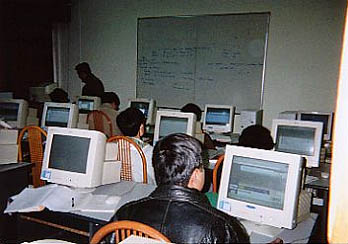
ベトナム情報処理研修所(VITTI)での研修の模様
7)工業所有権業務近代化
ベトナムにおいては、特許と商標の出願が急増しており、出願書類を現状の配置人員により処理することはますます困難になりつつある。ベトナム工業所有権庁(NOIP)にとって、国内外のユーザーのために工業所有権保護システムの利便性を向上させ、NOIP内の行政手続きを高めるコンピュータシステムを導入することが緊急の課題となっている。ベトナム政府は工業所有権制度運用の自動化、情報提供機能の充実を目的としたプロジェクト方式技術協力を我が国に要請してきた。
この協力の実施により、ベトナム工業所有権庁が効率的に工業所有権事務処理を実施できるようになる。
具体的協力活動内容としては、事務処理業務の効率化に必要なコンピュータシステムの導入と、そのシステムの運用並びに維持管理ができる人材を育成。また、このシステムを利用した、工業所有権事務処理を行う実務者も育成が、あげられる。
8)中小企業振興計画
雇用の創出に寄与する中小企業は、経済発展のために不可欠であり、特に、高付加価値の創出が期待される製造業の中小企業の果たす役割は大きい。
ベトナムにおける中小企業振興の重要性については、JICAが1995年度から2フェーズにわたって実施した「ベトナム国市場経済化支援開発政策調査」においても指摘されており、同国政府においても、中小企業振興の意識は芽生えつつある。しかしながら、政府としての振興のための資金不足、中小企業振興政策立案の組織体制の未整備、振興政策の不在という問題を抱えている。
1998年5月、ベトナム側はこれらの問題解決のためのマスタープラン策定のための開発調査の実施を日本側に要請した。
この協力では、ベトナムの中小企業振興のために、中小企業振興基本計画(組織、法律・制度、税制、金融政策を含む)及び実行計画を策定している。
具体的調査の内容としては、
| (1) | 中小企業政策に関する現状調査・分析 |
| (2) | 中小企業・重点サブセクターに関する現状調査 |
| (3) | 中小企業支援基本計画及び実行計画の策定 |

