3.1.2 定量分析によるマクロ経済へのインパクト推計:試算
(1)モデルの推計結果
まず最初に、シミュレーションを行うためのモデルの推計を行なった。ベトナムのGDPに対する日本の援助の効果を計測するためには、いわゆるGDP関数を推計する必要がある。GDP関数は、Ytをt年における実質GDP、Ktをt年における資本ストック(民間資本、政府資本の両方を含む)、Ltをt年における労働人口、Dtをt年における技術水準(生産性)を測るためのダミー変数とすると、次のような関数によって表される。
このGDP関数について、通常の分析でよく行われるようにコブ・ダグラス型の関数を仮定し、さらに規模に関して収穫不変(constant returns to scale)の仮定を置き、それを対数線形に変換して推計を行なった結果が以下の通りである。なお、係数の下のカッコ内の数字は標準誤差を表す。また、![]() は自由度修正済決定係数を表す。
は自由度修正済決定係数を表す。
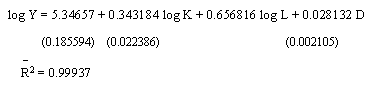
推計の結果、各係数は統計的に有効であり、また係数の符号や値の大きさは理論的に妥当な範囲内である。
次に、ベトナムの輸入関数について推計を行なった。輸入関数については、GDPと為替レートの関数として表されると考えられる。これに基づいて推計を行なった結果が以下の通りである。
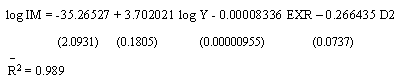
ただし、IMは輸入額、EXRは米ドルとベトナム・ドンとの為替レート、D2は1997年のアジア通貨危機の影響を考慮するためのダミー変数である。この推計の結果、log Yの項の係数が3.702021であることから、ベトナムの輸入のGDP弾力性が3.70であるということが分かる。すなわち、ベトナムのGDPが1%増加することにより、ベトナムの輸入は3.70%増加するということである。
また、ベトナムの輸出関数についても推計を行なった。輸出関数についても、GDPと為替レートの関数として表されると考えられる。これに基づいて推計を行なった結果が以下の通りである。
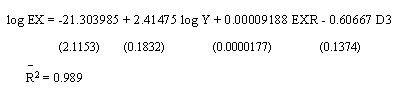
ただし、EXは輸出額、D3は1991年にソ連(当時)向け輸出が大幅に減少したことを考慮するためのダミー変数である12。この推計の結果、log Yの項の係数が2.41475であることから、ベトナムの輸出のGDP弾力性が2.41であるということが分かる。すなわち、ベトナムのGDPが1%増加することにより、ベトナムからの輸出は2.41%増加するということである。
(2)マクロ経済効果の試算結果
さて、上記の推計したモデルを用いて、日本の対ベトナム援助のマクロ経済効果について、日本の援助がベトナムのGDP(国内総生産)、資本ストック、輸入、輸出をどの程度押し上げる効果があったのかを分析した。資本ストックに対する押し上げ効果については、1991年から2000年までに供与された日本の援助によって形成された資本ストックを計算し、仮に援助がなかった場合にはその分だけベトナムの資本ストックが少なくなると仮定して、資本ストックの総量から日本の援助によって形成された分の資本ストック量を引いたものを「仮に日本の援助がなかったと仮定したときの資本ストック」として計算し、両者を比較した。また、GDPと輸入、輸出に関しては、上記の推計したモデルをそれぞれ用いて、日本からの援助があった場合となかった場合のGDP値および輸入値、輸出値をそれぞれ計算し、その2つの数値を比較した。
各マクロ経済指標の押し上げ効果を、上述の援助効果指標を用いて計測した結果をまとめたのが図1である。この図は、1991年から2000年の各時点において、GDP、資本ストック、輸入、輸出が、仮に日本からの援助がなかった場合と比べて、援助があったことによって何%くらい押し上げられたかを示している。例えば、分析対象の最終年である2000年時点でみた場合に、日本からの援助によってベトナムのGDPは1.57%、資本ストックは4.65%、輸入は5.94%、輸出は3.84%、それぞれ押し上げられた(図2を参照)。
また、1991年度から2000年度までに供与された日本の対越援助のマクロ経済的内部収益率を計算したところ、約19%という結果が得られた。したがって、援助によって押し上げられたGDPの増分を「便益」と考えた場合の、この間の日本の対越援助の「収益性」は19%程度の高さであったと試算される。
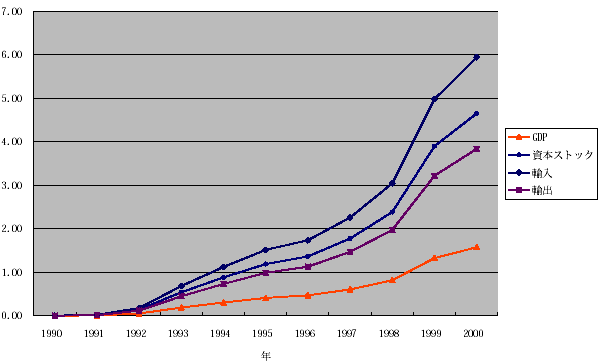
図1 日本の対ベトナム援助のマクロ経済指標押上げ効果(時系列変化)
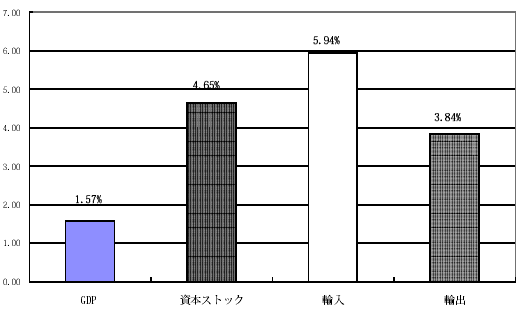
図2 日本の対ベトナム援助のマクロ経済指標押上げ効果(2000年時点)
(3)試算結果の考察
日本の対ベトナム援助のマクロ経済効果について試算を行なった結果は上述の通りである。この結果をもとに、マクロ経済的な観点から見た日本の対ベトナム援助の評価について若干の考察を行いたい。
まず、援助の効率性という観点から見た場合に、今回の試算で1991年度から2000年度までの日本の対ベトナム援助のマクロ的内部収益率が約19%と算出された。これは、十分に高い数字であると考えられる。この試算は様々な前提に基づいたものであるので、単純に議論することはできないが、約19%というマクロ的内部収益率の数字が意味するのは次のようなものであると考えられる。すなわち、1991年度から2000年度までの間に日本からベトナムに供与された援助額を、仮にベトナム政府が全額有利子の借入金で賄ったとして、19%までの利子であれば、その利子を払ってでも資金を借り入れて投資を行うことによって、それに見合っただけの効果がGDPを押し上げる効果としてベトナム経済にもたらされたということである13。もちろん実際には日本からの援助は、一部は無償であるし、また有償資金協力も、金利は現在の対ベトナムの場合通常の案件で1.8%、特別円借款や環境案件であればさらに低い金利が設定されており、ベトナム政府にとっては非常に有利な条件で投資に必要な資金を調達することができたのである。したがって、ベトナム側から見て、日本からの援助の「収益性」は非常に高いと言える。このことから、マクロ経済的な観点から見た場合に、これまでの日本の対ベトナム援助は効率的に行われてきており、投入に見合った十分な効果を上げてきていると評価することができる。
このように、日本のこれまでの対ベトナム援助は、投入に見合った十分な効果を上げてきていると考えられる。また、日本の援助がこれまでにベトナムのマクロ経済に与えてきたインパクトという意味では、今回の試算で日本の援助は2000年時点でベトナムのGDPを1.57%押し上げる効果があったという結果が得られた。
ここで、前ページの図1に戻ってマクロ経済効果の時系列変化をもう1度見てみると、GDP、資本ストック、輸入のいずれの押し上げ効果も、1998年までは比較的なだらかに上昇した後、1999年から急激に上昇しているのが分かる。これは、表1(21ページ)から分かるように、有償資金協力の実行額が1999年度から急速に拡大していることが主な理由と考えられる。日本の対ベトナム援助全体において、有償資金協力の規模が無償資金協力や技術協力と比べて相対的に非常に大きいので、有償資金協力の実行額が拡大することによって、日本の対ベトナム援助全体の金額も1999年度から急速に拡大した。援助のマクロ経済効果のメカニズムにおいて説明したように、援助は投資の一部としてベトナム経済における資本ストックを形成することによって経済効果を発揮する。資本ストックは年々蓄積されることによって効果を発揮するものであるから、援助のマクロ経済効果も累積的な効果として現れるものである。したがって、長期間にわたって継続的に援助を行うことによって、その経済効果は累積され、より大きなマクロ経済効果を発揮するのである。これに対して、日本の対ベトナム援助については、その支出総額の規模が急激に拡大したのが1999年度からであり、そのためまだ累積的な経済効果を発揮するに至っていないと考えられる。それが、2000年時点におけるGDP押し上げ効果が限定的となっている主な原因であると考えられる。
ベトナムに対して日本が援助を本格的に再開してからまだ10年しか経っていない。しかも、支出総額で見た場合の援助の規模が拡大したのはごく最近の2~3年のことである。したがって、対ベトナム援助のマクロ経済効果がまだ限定的であるのは、ある意味で当然のことと言える。今後については、1999年度以降急速に拡大した援助の効果が徐々に累積され、今後も予想される継続的な援助の支出総額が増加すればより大きなマクロ経済効果をベトナム経済に与えると予想される。
参考までに、分析手法等が同一ではないので、単純に比較することはできないものの、この結果を既存の直接投資がもたらすGDP押し上げ効果の研究結果と比較してみると、森永氏が計算したベトナムに対する外国直接投資のGDP押し上げ効果は、1994年時点で3.8%であった。外国直接投資によるGDP押し上げ効果のほうが高く試算される要因は、援助と直接投資の効率性の違いというよりは、単に援助と直接投資の規模の違いによるものと考えられる。すなわち、ベトナムが海外から受入れている直接投資の規模は、日本のODAの規模よりもかなり大きい。この規模の違いがGDP押し上げ効果の違いとなって現れていると考えられる。
12 かつて旧ソ連はベトナムにとって最大の貿易相手国であったが、1991年には政情不安と経済混乱により、対ベトナムを含め、輸入が大幅に落ち込んだ。1991年末にはソ連邦が崩壊した。
13 これは飽くまでも1つの解釈の仕方であって、実際にそれだけの利子で資金を借入することができるということではない。なぜなら、「便益」であるGDPの増分はベトナム経済全体にもたらされるものであって、その分が政府収入として回収できるわけではないからである。財務的な観点から計算する内部収益率とは異なっている点に注意が必要である。

