第3章 対ベトナム援助の評価
3.1 ベトナムの開発全体に与えたインパクト~定量的分析による試算~3.1.1 日本の対ベトナム援助のマクロ経済効果:分析の枠組み
(1)分析の目的と基本的考え方
日本の対ベトナム援助を評価する1つの視点として、援助が総体としてベトナムのマクロ経済にどのような効果を与えてきているのかを定量的に計測する方法を挙げることができる。つまり、日本の援助がベトナムのGDP(国内総生産)等のマクロ経済指標の数値をどの程度押し上げる効果があったかを計算することによって、日本の援助の貢献度を測るのである。従来の国別評価調査において、このような方法を用いて援助の評価を行うことはあまり行なわれてきていないが、ここでは1つの試みとして、このような方法による評価を行なうこととしたい。
援助のマクロ経済効果を試算するにあたって、その基本的な考え方となるのは次の通りである。日本の援助は基本的にベトナム政府の政府支出の一部を担っていると考えられる。すなわち、ベトナム政府が行なう道路や電力等のインフラに対する公共投資や、教育・保健医療等の公共サービスに対する支出、あるいは農業や工業等の生産部門に対する支援の一部が日本の援助によって行われているのである。厳密に言えば、有償および無償の資金協力の役割と、人材育成や技術移転、マスタープラン策定の支援等を目的とした技術協力の役割は異なっており、両者の効果も異なっていると考えられる。しかし、どちらもベトナム政府および公共部門の活動の一部を支えているという点では一致している。したがって、日本の援助がベトナムのマクロ経済に与える効果は、ベトナム政府および公共部門の投資あるいは支出がマクロ経済に与える効果の一部として捉えることができる。その中でも、マクロ経済効果という意味で中心となるのは、インフラや生産部門等の経済・社会基盤に対する投資である。そのような投資によって経済・社会基盤(資本)が形成されることで、ベトナム経済の生産部門を直接あるいは間接的に担うこととなり、その結果マクロ経済に対して様々な効果を発揮することとなる。日本の援助の効果はその一部として現れていると考えられる。
以上のような考え方に基づき、ここでは次のような方法によって、日本の対ベトナム援助のマクロ経済効果を試算する。まず、ベトナムのマクロ経済を捉えるモデル(計量経済学的な手法による方程式)を構築する。次に、そのモデルを用いて、仮に日本がベトナムに対して援助を全く行わなかった場合にベトナムのマクロ経済がどのようになっていたであろうかを計算する(シミュレーション)。その結果、仮に日本の援助が全く行われなかったという想定のもとで計算されたマクロ経済指標の計算結果(シミュレーション値)を、実際通りに援助が行われた場合のマクロ経済指標の値と比較することによって、その2つの数値の差が、日本の援助によってもたらされた効果と見ることができる。このようにして、日本の援助のマクロ経済効果を試算することができるわけである。なお、分析手法の詳細については後述する。
(2)ベトナムの経済と日本の対ベトナム援助実績
日本の対ベトナム援助のマクロ経済効果を試算するにあたって、まずベトナムのマクロ経済の状況と日本の対ベトナム援助の実績について概括しておく。
ベトナムは1986年にドイモイ(刷新)政策を導入し、市場経済化を推進してから急速に経済が拡大した。1989年に7.6%のGDP成長率を記録し、1990年~1991年は旧ソ連邦の崩壊等による援助の減少等により経済成長率がやや下がったものの、1992年以降、1997年のアジア通貨危機までは8~10%の高いGDP成長率を記録してきた。1997年のアジア通貨危機以降は、外国投資の減少等の原因により、急速な経済の拡大に陰りが見られ、経済の伸び悩みにやや苦しんでいた。1999年のGDP成長率は4.8%にまで落ち込んだが、2000年には復調の兆しが見え、GDP成長率も6.7%にまで回復した。
日本の対ベトナム援助の実績は、2000年度までの累計で有償資金協力が6,924.19億円、無償資金協力が863.82億円、技術協力が371.10億円となっている7。日本の対ベトナム援助は古く1950年代末から開始されたが、その後1960年代にはほとんど援助の実績はなく、1970年代の前半になって電力等のインフラ整備や保健・医療分野に対する有償・無償資金協力等が一時期実施された。しかし、その後ベトナム戦争と南北ベトナムの統一を挟み、1970年代後半から1980年代の間は災害緊急援助等が細々と行われただけであった。1990年度までの日本の対ベトナム援助の実績(累計)は、有償資金協力が404.30億円、無償資金協力が312.92億円、技術協力が24.49億円となっている。1992年度に対ベトナム援助が本格的に再開され、特に1995年度以降援助の規模が急速に拡大した。1995年度以降、日本はベトナムが受け入れている二国間援助のトップ・ドナーとなっている。日本の対ベトナム援助は、経済インフラの整備を中心に、農業・農村開発、保健医療、教育、市場経済化支援、環境等、幅広い分野にわたって援助を行なってきている。
有償資金協力に関しては、案件の承諾後、契約締結までには通常1年半程度を要すること等から、承諾額と実行額の乖離が生じているという点を指摘しておく必要がある。特にベトナムにおいては、有償資金協力の案件として承諾されても、有償資金協力手続に関する不慣れ等の原因により、その案件の実施が遅れており、実際にはベトナムに対する資金の貸付がまだ行われていないものが少なからずあるということである。1991年度から2000年度までの有償資金協力の承諾額と実行額を示したのが表1であるが、この間の承諾額の合計が6,519.9億円であるのに対して、実行額の合計は1,967.8億円に留まっている。日本の援助がベトナム経済に与えるマクロ経済効果という観点から言えば、案件が承諾されても実行されない限り、経済効果は発生しない。したがって、国道5号線、ハイフォン港、電力等の案件についてはミクロ的に定量的な効果が確認されてはいるが、有償資金協力の実行金額がまだあまり多くないということは、日本の援助のベトナム経済に対するマクロ経済効果が現時点では限定的なものとならざるを得ない。しかしながら、表に見られるように、承諾額に対する実行額の比率は、99年度以降大幅に改善しており、今後、更なるマクロ経済効果が期待できる。
| 表1 日本の対ベトナム有償資金協力実績(1991-2000年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:百万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出所:JBIC (2001) "Report on the 2001 ODA Portfolio Review." ただし表中の1999年の数字には、「経済改革支援借款」200億円を含めている。 |
(3)過去の試算の紹介とその評価
援助が途上国のマクロ経済に与える効果に関しては、これまでにいくつか試算が行なわれてきている。その中で、当センターが外務省の委託調査として1994~1995年度に行なった「東アジアの経済開発における日本のODAの定量的評価」では、タイ、インドネシア、マレイシアの3ヶ国を対象に、計量経済学的な手法を用いて日本のODAのマクロ経済効果を推計した。基本的な考え方は、「実際に援助を行なった場合のマクロ経済指標(実測値)」と「仮に援助が行なわれなかったと想定した場合のマクロ経済指標(シミュレーション値)」を比較することによって援助のマクロ経済効果を測定するというものである。その結果、日本が1972年度~1992年度の間に各国に対して供与したODAは、タイ、インドネシア、マレイシアの1991年の国内総生産(GDP)をそれぞれ5.4%、2.8%、1.8%押し上げる効果があったという結果が得られた。GDP以外のマクロ経済指標として、雇用、民間消費、民間投資、輸出、輸入等への効果も推計し、例えばタイの場合、日本が1972年度~1992年度の間に供与したODAはタイの雇用を2.1%、民間消費を4.4%、民間投資を7.4%、輸出を9.5%、輸入を5.9%、それぞれ押し上げる効果があったという結果が得られた(いずれも1992年度の数値)。
ベトナムに関しては、日本の援助のマクロ経済効果について分析した例はこれまでにない。関連した分析としては、栗木レタンギェップ・城西国際大学教授がドイモイ政策の経済効果について行なった分析がある(Nghiep and Quy, 2000)8。この分析で栗木教授はベトナム経済のGDP関数を推計し、それに基づいてドイモイ政策がベトナム経済に与えたインパクトをシミュレーションによって試算した。その結果、仮にドイモイ政策が実施されなかったと想定した場合のGDPと比較して、実際にドイモイ政策が実施されたことによって、GDPは1989年時点では3%高い程度であるが、1998年時点では42%も高くなっていると推定された。また、森永卓郎氏がベトナムに対する海外からの直接投資のマクロ経済効果について分析を行なっている(森永, 1996)9。森永氏の分析によれば、1994年時点で、直接投資はベトナムのGDPを3.8%押し上げる効果があった。部門別では、農業部門のGDPを2.0%、製造業部門のGDPを13.8%、それぞれ押し上げる効果があった。また、資本ストックに対する効果として、同じく1994年時点で、直接投資は農業部門の資本ストックを8.0%、製造業部門の資本ストックを21.3%、それぞれ押し上げる効果があった。
さらにベトナム政府の計画投資省(Ministry of Planning and Investment: MPI)に属する中央経済管理研究所(Central Institute for Economic Management: CIEM)がベトナム経済のマクロ計量モデルを構築し、政策効果に関する分析等を行っている10。
このように、計量経済学的なモデルを使ったシミュレーションを行なうことによって、援助やその他の政策がマクロ経済に与える効果を推計することができる。
(4)今回用いる試算の方法と特徴
日本の援助がベトナム経済に与えたマクロ経済効果を測定するために、ベトナム国のマクロ経済を計量経済学的な手法を用いてシミュレートするモデルを構築し、日本の援助のマクロ経済効果をシミュレーションにより試行的に推計する。なお、以下で構築されるモデルが絶対的に正しいというものではなく、構築できるモデルのひとつに過ぎないこと、理論的にはスキームあるいは分野によって効果が違うことが予想されること、そして国によって用いられるべきモデルの考え方あるいは手法が違うことがありえることを、あらかじめお断りしておく。
1)分析対象
援助のマクロ経済効果を測定するにあたって、上述の通り、技術移転や人材育成といった技術協力の経済的効果と資金協力(無償・有償)の経済的効果のメカニズムは異なっており、本来は両者をモデル上区別して計算するのが望ましいと考えられる。しかし、今回はデータの制約等により、その違いをモデルに反映させて計算することが困難であるため、今回の試算においては、資金協力(無償・有償)と技術協力を合わせた日本の対ベトナム援助全体を対象として分析を行なうこととする。ただし、援助がマクロ経済効果を発揮するためには、各案件が実施される必要がある。したがって、有償資金協力に関しては、承諾額ではなく実行額を分析の対象とする。
また、分析の対象期間については、日本の対ベトナム援助は1950年代末から始まっており、1970年代においては相当規模の援助の実績があるが、ベトナム戦争を経て、1980年代には災害緊急援助(無償資金協力)等の限定的な援助が行なわれたにとどまる。本格的な援助が再開されたのは1992年度からである。したがって、分析の対象期間は1991年度~2000年度とする。
今回の試算において、日本の対ベトナム援助のマクロ経済効果を計測する指標として、ベトナムのGDP(国内総生産)、資本ストック、輸入、および輸出を取り上げ、日本の援助がこれらのマクロ経済指標をどの程度押し上げる効果があったのかについて分析を行なうこととする。また、援助の効率性の観点からの評価として、日本の援助が投入に見合っただけの成果を上げてきているのかについても分析を行なう。
2)分析手法
今回の分析では、栗木教授や森永氏の論文と当センターが過去に行なった調査等の既存研究を参考にした上で、データ制約等を考慮して、以下の手法を用いて分析を行なう。計量経済学的なマクロ計量モデルを用いて分析を行なっているという点で既存研究はいずれも共通しており、今回の分析手法も同様である。分析に用いるモデルについては、基本的に栗木教授のモデルに若干修正を加えたモデルを用いることとする。これは、データの制約上、当センターが過去に行なった調査における分析のように、複数の方程式によって一国経済全体を表すモデルを構築したり、森永氏の分析のように部門を農業と製造業に分けて分析を行なったりすることが困難だからである。最もシンプルな栗木教授のアプローチが今回の分析には適していると考えられる。
上述の通り、援助のマクロ経済効果は、ベトナム政府の投資の経済効果の一部として捉えることができる。厳密には、民間部門の投資によって形成される民間資本ストックと政府部門の投資によって形成される政府資本ストックが果たす役割は異なっており、この両者をモデル上区別することが望ましい。しかし、社会主義国であるベトナムにおいては、国営企業が経済の中で大きな割合を占めているという現実と共に、民間資本ストックと政府資本ストックを区別したデータが入手困難であるというデータ上の制約から、今回の分析では民間部門と政府部門を区別せず、投資および資本ストックは経済全体として扱うことにする。したがって、日本の援助もこの経済全体の投資に含まれていると仮定する。
また、前出の栗木教授の研究により(Nghiep and Quy, 2000)、ドイモイ政策による技術・制度の変化がベトナムのマクロ経済に大きな影響を与えたことが指摘されている。したがって、分析に用いるマクロ計量モデルにおいては、この点を考慮することが重要であると考えられる。森永氏のモデルや当センターの過去の調査におけるモデル等では、この点が考慮されておらず、今回の分析で用いるモデルはこの点においてそれらのモデルよりも優れていると考えられる。ドイモイ政策の影響をモデル上考慮するという点については、後述のようにベトナムのGDP関数において、技術水準を測る変数を投入することによって対応する。
分析の手順としては、まずモデルが実際のベトナム経済に適合していることを確認した上で、仮に援助が行われなかったと想定した場合のマクロ経済指標をシミュレーションによって計算する。このシミュレーション値と実際通りに援助を行なった場合のマクロ経済指標の数値を比較することによって、日本の援助のマクロ経済効果を算出する。すなわち、日本の援助のマクロ経済効果の測定は、「実際に援助を行なった場合のマクロ経済指標」と「仮に援助が行われなかったと想定した場合のマクロ経済指標」を比較することで、例えば次のような指標で測定することができる。
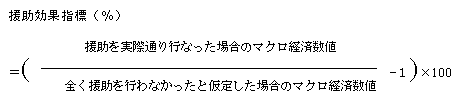
この指標は、援助が行われなかった場合に比べて、援助が実際通りに行われた場合のマクロ経済数値がどれだけ大きくなるか、その比率を計算したものである。これを「援助のマクロ経済指標押上げ効果」と呼ぶことにする。
しかし、このマクロ経済指標押し上げ効果を測る援助効果指標だけでは、日本の対ベトナム援助がその投入に見合っただけの効果を上げているのかどうかということを判断することは難しい。なぜならば、一般的には、援助額が多ければ多いほど、マクロ経済数値を押し上げる効果は大きくなると考えられ、効果の高さが援助の絶対額に大きく依存してしまうからである。つまり、援助のマクロ経済指標押上げ効果では、援助がどれだけ効率的に使われているのか(すなわち、援助1単位あたりの効果)という観点からの評価が行われないのである。そこで、プロジェクト評価において一般的に用いられる内部収益率(Internal Rate of Return: IRR)の考え方を応用して、これまでの日本の対ベトナム援助の効率性を計算することも試みたい。この試算は以下の手順によって行われる。
内部収益率の基本的な考え方は、あるプロジェクトにかかる費用と、そのプロジェクトから生みだされる便益をすべて現在価値に直し、費用の現在価値の総和と便益の現在価値の総和を等しくするような利子率を計算し、その利子率を内部収益率と呼ぶ。言い換えれば、内部収益率は仮にそのプロジェクトに投資する資金をすべて借入金で賄うとしたときに、いくらくらいの利子までであれば、有利子で資金を借り入れたとしても、そのプロジェクトを実施したほうがよいのかを表している。したがって、内部収益率はそのプロジェクトの収益性を測っているのである。
この考え方を援助に応用すると、日本の対ベトナム援助全体を1つのプロジェクトと考えたとすると、「費用」は実際に投入した援助額になる。それに対して、その「援助プロジェクト」から生みだされた「便益」を何と考えるかについては、必ずしも一般に合意された考え方があるわけではないが、ここでは援助によって押し上げられたGDPの増加分を便益として考えることとしたい。そうすると、日本の対ベトナム援助という「プロジェクト」の「収益性」は、内部収益率を計算するのと同じように、これまでの援助額(=費用)の現在価値の総和と、援助によって押し上げられたベトナムのGDPの増加分(=便益)の現在価値の総和を等しくするような利子率を計算することによって算出されることになる。ただし、ここで1つ注意する必要があるのは、「日本の対ベトナム援助プロジェクト」はまだ現在進行中であり、終了したプロジェクトではないが、それをある時点(2001年時点)で切って評価を行おうとしているという点である。上述の通り、日本の援助はベトナム国内における投資の一部となって資本形成に使われることによって経済効果を生みだすものである。したがって、現在進行中のプロジェクトである以上、これまでに行ってきた援助によって形成された資本の「残存価値」が存在すると考えられるが、その残存価値が生みだす効果(便益)はまだ実現されていない。したがって、これまでの「日本の対ベトナム援助プロジェクト」にかかった「費用」という意味では、これまでの援助の投入額から、この「残存価値」を差し引く必要があると考えられる。さもなければ、「便益」を生みだすために投入された「費用」を過大に計算してしまうことになる11。
この考え方に基づいて、援助の「収益性」(あるいは効率性)を測る指標として次のような「援助のマクロ的内部収益率」を定義する。評価時点をT年とし、評価の対象年の最初の年をt=1、最終年をt=T-1とすると、費用の現在価値の総和と便益の現在価値の総和を等しくする、すなわち
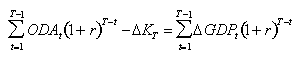
となるようなrが「援助のマクロ的内部収益率」である。ここで、ODAtはt年における援助額、ΔKTは評価時点(T年)における資本の増分の残存価値、ΔGDPtはt年における援助によって押し上げられたGDPの増分である。
7 有償資金協力の金額は承諾額である。
8 Nghiep, Le Thanh and Quy, Le Huu. 2000. "Measuring the impact of Doi Moi on Vietnam's Gross Domestic Product." Asian Economic Journal 14 (3): 317-332.
9 森永卓郎. 1996. 「マクロ経済モデルを用いたベトナム経済の計量分析」(竹内郁雄・村野勉(編)『ベトナムの市場経済化と経済開発』アジア経済研究所に所収).
10 Central Institute for Economic Management (CIEM). 2000. National Accounting Framework and A Macroeconometric Model for Vietnam. Youth Publishing House.
11 評価時点における資本の残存価値を「費用」ではなく、「便益」に算入するという方法も考えられるが、ここでは「費用」に算入する考え方を採用する。

