2.1.2 傾向分析
有償資金協力は1992年度に再開されて以来、幹線道路、電力、港湾といった基本インフラを重点的な対象分野としてきたが、1997年度以降、環境、上水道など社会インフラ案件への融資が増加している。また、アジア通貨危機を受けて経済再活性化のための特別円借款や、民間セクター育成プログラム策定などの経済改革を条件として200億円の円借款を実施するなど、プロジェクト単体の融資に留まらない融資が増えている。ただし、プレッジ額と実際の融資実行額の違いにも十分に留意する必要がある。
無償資金協力も1992年度に本格的に再開され、病院施設整備、小学校施設整備、橋梁や道路整備などを重点的な対象分野としてきた。近年は、経済構造改革努力を支援するための「ノン・プロジェクト無償」(25億円)や、日越人材協力センター建設計画、留学生無償などの人材育成を目的とした案件も実施している。
技術協力も1992年度から本格的に再開されているが、日本が実施している様々な途上国への援助の中でも、たいへん特徴のある協力が行なわれている。まず、1995年度から日越首脳会議での合意を受けて、ベトナム政府による市場経済化に関する政策策定を支援するために「市場経済化支援開発政策調査」(通称「石川プロジェクト」)が実施されている。特にフェーズI(1995-1996)及びフェーズIII(1999-2001)においては、それぞれベトナムの第6次5カ年計画(1996-2000)、第7次5カ年計画(2001 - 2006)および次期10カ年計画(2001 - 2010)の策定を支援するために、各分野に関する提言を行なった。その他、法制度整備支援、研修員受入れ、毎年100人以上の留学生受入れ、同じく100人以上の専門家派遣を実施している。
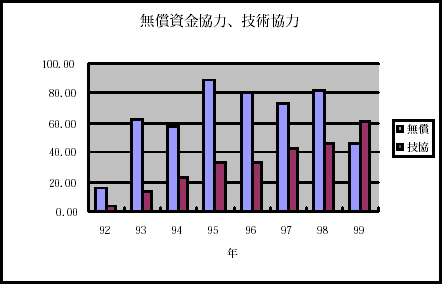
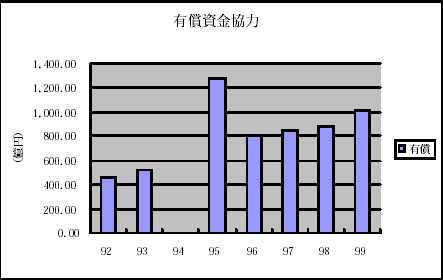
総じて、援助再開の初期には、戦争と社会主義経済のもとで疲弊したインフラストラクチャーのリハビリや新規建設案件への援助が中心であったが、1995年頃からそれらに加えて市場経済化を支援するための人材育成や政策策定の支援を目的とした新しいタイプの案件が増加してきたと言える。
なお、本件評価調査では、有償、無償、技協など各スキームがどう連携していたかについても可能な限り検証した。

