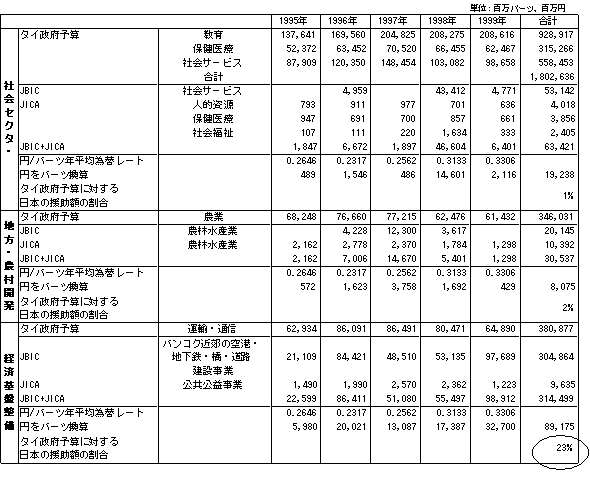第5章 対タイ援助政策の効果に関する評価
本章では、我が国対タイ援助政策の効果の評価を、対タイ国別援助計画の重点分野を軸に多面的に試みた。また指標の設定による今後の対タイ援助政策の有効性の向上についても考察を行った。
5.1 効果を評価する方法と前提とした考え方
JICA・JBICの個別実施案件は、事後評価報告書等で述べられている通り、タイ社会に対して有効な効果があったと評価されているものが多い。しかし複数の個別事業の評価結果を集計しても、それら案件が属する重点分野の評価とは必ずしも一致しない59。従って、我が国の対タイ援助政策の効果を把握するには、個別案件だけに注目するのではなく、各重点分野の推移を表す総体的な集計量に注目して分析を進める必要があると考える。
第2章で述べた通り、「タイの国家支出に対する日本の対タイ援助総額の割合は1.6~4.0%(1995~99年)」である。従って、タイにおける開発の成果において我が国援助の貢献度を抽出することは大変に難しい。後述するように、この点については他ドナーも悩んでいるところであり、そのため自らの援助効果を評価する上での指標の設定に本格的に取り組めない状態にある。
以上を踏まえ、本評価においては、図3-1の対タイ国別援助計画の目標の体系図における「重点分野」毎の効果を総体的に把握する方法を取ることにする。各重点分野において効果の総体的な把握が可能と思われる指標を設定し、数値の推移をみる60 61。しかし重点分野の効果を総体的に示す指標は、何十、何百通りもの指標が考えられる。そこで設定する指標については、主として対タイ国別援助計画の「重点的に取り上げる事項」の効果を測定する上で有効と考えられる指標62 63を取り上げることにした64。
評価手順としては、先ず「重点分野」毎の援助投入量とタイ政府予算の比較を行った。この比較を基に先述の“タイの開発成果における我が国援助の貢献度”の検証を試みた。次に、「重点的に取り上げる事項」毎の指標におけるデータを基にタイの開発の推移を見た。尚、我が国援助の具体例を理解するために訪問したJICA、JBIC、大使館担当の10案件については、現地調査の際に現場を視察して関係者から聴き取り調査を行っている。またそれら10案件の終了時評価報告書または事前評価報告書等も一読した65。これら作業の目的は、本章にて政策効果の指標設定に資する情報の収集にあった。視察結果は添付資料2として添付しており、本章における重点分野毎の効果評価に際しての参考情報として適宜活用した。
以上を踏まえ、重点分野毎の我が国対タイ援助政策の効果を多面的に評価する。
5.2 重点分野毎の援助政策の効果の評価
5.2.1 重点分野毎の我が国援助のタイ政府予算に対する割合
「タイの国家支出に対する日本の対タイ援助総額の割合は1.6~4.0%(1995~99年)」である。しかし表5-1のように重点分野毎にその割合を見た場合、経済基盤整備に関しては、タイ政府予算の「運輸・通信」部門に対する我が国援助額66の割合が、20%以上と極端に高いことが分かる。
第2章で触れたように、タイは産業構造を農林水産業から工業へと転換する方向で成長を続けてきた。工業化は電力、道路、港湾、橋梁等のハードインフラ整備を必要とするが、我が国援助がタイのハードインフラ整備に大きな貢献を果たしたものと推定される。例えば「東部臨海地域開発67
」において、レムチャバン商業港、マプタプット工業港、バンコク~チョンブリ間道路等、多くのインフラ事業が有償資金協力案件として建設されたが、これら産業基盤インフラ整備は日本等の海外直接投資をタイに促進させる主因の一つとなったとも考えられる。このように、我が国援助政策は重点分野として経済基盤整備を設定したことを通し、タイにおける経済・社会の開発に大きく寄与してきたものと評価できよう。
| 出所:調査団作成 |
尚、表5-1では3つの重点分野についてのみ、我が国援助のタイ政府予算に対する割合の検証を行った。「環境保全」及び「地域協力支援」については、タイ政府予算を特定することが困難であったため、ここでの検証を省いた69 。
5.2.2 社会セクター支援
重点的に取り上げる事項レベルでの開発の推移
対タイ国別援助計画の目標体系図より、社会セクター支援は8つの重点的に取り上げる事項に分類されるが、そのうちの4つに対応する指標の推移を見ることにより、重点的に取り上げる事項レベルでの開発の推移を確認した。
NGOとの連携等都市内貧困対策への支援
一般に、所得が増えれば子供を学校に通わせる可能性が高まる等、貧困率の低下と識字率の向上の間には一定の相関関係があると考えられる。都市部においては、表5-2のように、識字率は1992~98年の間で上昇した。また、所得の増大と病弱者率の減少の間にもある程度の相関関係が想定されるが、都市部における病弱者率は、通貨危機後こそ若干上昇してはいるものの、長期的には減少傾向にあることが分かる(表5-3)。これらから、タイ政府等により、都市部における貧困層など社会的弱者救済を企図した地道な努力がなされたものと推測される。
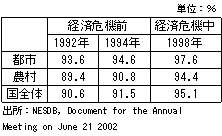
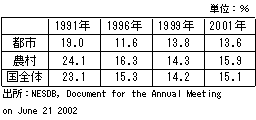
社会福祉対策における中・長期的課題としての継続的な取組み
タイ政府の社会開発予算は、主として社会サービスの農村振興予算の半減により減少傾向にある。しかし社会福祉政策関連予算は漸増傾向にある。具体的には、「社会/公共福祉」予算が1997年と2000年とでは倍増している(表5-4)。また通貨危機のあった1997年以後においても急激な貧困削減予算の減少は見られなかった(表5-5)。タイ政府が社会福祉政策を中長期的課題として重視し、木目細かに対応している姿勢が伺われる。
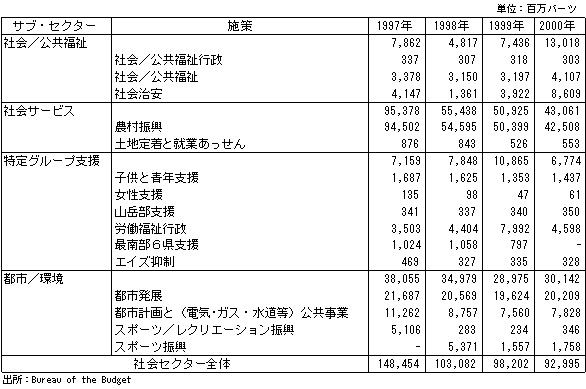
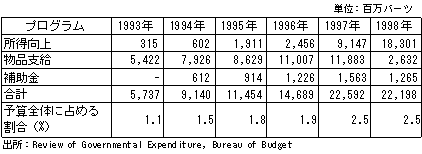
国際機関との連携を視野に入れた、地方における保健衛生サービス体制整備への継続支援、特にエイズ予防等への継続支援
表5-6の通り、エイズ感染者数及びエイズを原因とした死亡者数は着実に減少している。1990-91年のタイ政府のエイズ対策キャンペーン等により、エイズ感染者増加数は90年代始めをピークとして、その後減少した。このように、タイ政府はエイズ対策を政策的に重視している。更にタイは、日本政府が1994年に開始した「人口・エイズに関する地球規模問題イニシアチブ」の重点国であることからも、我が国を含め、国際社会からの支援がエイズ感染者減少に寄与しているものと考えられる。
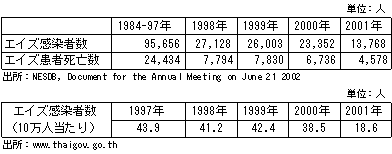
薬物鑑定・取締能力向上のための支援
タイでは薬物使用による犯罪自体も増えている一方で、表5-7のように逮捕数も上昇していることから、逮捕率維持の努力が伺われる。
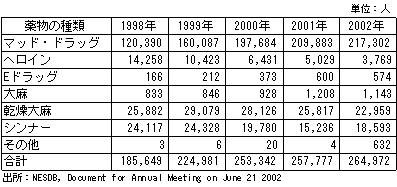
重点分野レベルでの効果の評価
前述より、タイ政府が自国開発において社会セクターの開発を着実に進めている様子が伺われる。1999年、タイはUNDPの 人間開発指数(Human Development Index: HDI70 )において174ヶ国中67位に位置付けられ、この順位は1990年の78位であった頃より向上している。この点からも、タイでの社会セクターの開発が着実に進んでいる様子が伺える。
1995~99年度の間に当該重点分野の範疇で実施された我が国援助案件は、
- 草の根無償資金協力案件: 94件
- プロジェクト方式技術協力案件: 5件
表5-1からも分かるように、社会セクターにおけるタイ政府予算に対する我が国援助額の割合は1%と他の重点分野と比べて小さく、タイの経済開発への直接的な影響は小さいものと考えられる。しかし1997年の経済危機後の経済回復過程を支えるなど、金額的にはタイ政府予算に対して小さいながらも、我が国援助は大切な貢献を行ってきたものと推定される。特に、草の根無償資金協力はタイ政府からの直接要請により案件が採択・実施されるのではなく、NGO等タイの社会問題に直接取り組む団体等からの要請を受けて実施されるため、他の協力形態と比べ、社会セクターの開発に直接的に寄与することが可能であり、更に社会問題の先取りが行える、という点で大変有効な援助形態であると考えられる。従って、我が国援助が社会セクター支援を重点分野とし、その中で草の根無償資金協力を集中的に実施可能な体制を政策的に確立してきた点は、高い意義があったものと評価したい。
5.2.3 環境保全
重点的に取り上げる事項レベルでの開発の推移
環境保全においては、重点的に取り上げる事項における開発の推移を見るための適当な指標が確定できなかった。その理由の一つは、環境保全対策の効果を見るには長期の時間がかかることが挙げられる。しかし、対タイ国別援助計画では「廃棄物の不適切な処理による環境汚染等の公害、森林の減少等の問題が顕在化している」との記載があり、このような我が国の懸念に連関する指標として活用が適当と考えられる、ゴミの量の推移及び森林面積の推移に関するデータを収集した。表5-8を見ると、タイ全体におけるゴミの量は漸増傾向にあるが、産業廃棄物を主体とする危険ゴミの量は減少傾向にあり、廃棄物処理に関して何らかの努力が伺える。しかし、表5-9のように森林面積は漸減傾向にあり、特に北部及び南部での減少速度が他地域と比べて著しく、十分な成果が見られない。
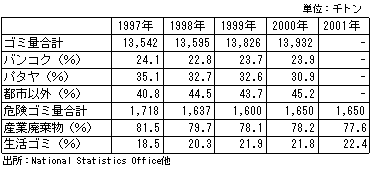
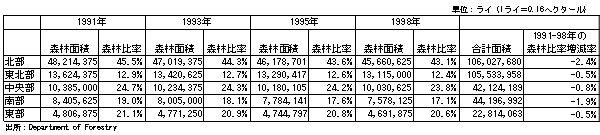
重点分野レベルでの効果の評価
前述の森林面積の減少化傾向より、環境保全においてタイ政府の政策は未だ十分な成果を挙げていないと言える。また1997年の経済危機の影響により、当該分野への予算的配慮をタイ政府が漸減する傾向を有していた可能性は否定できない。
1995~99年度の間に当該重点分野の範疇で実施された我が国援助案件は、
- 草の根無償資金協力案件: 1件
- プロジェクト方式技術協力案件: 3件
- 開発調査: 12件
- 有償資金協力案件: 1件
当該重点分野の範疇にある実施案件として、「環境保全基金支援事業(有償資金協力案件)」及び「東北タイ造林普及計画(プロジェクト方式技術協力案件)」を視察した(添付資料2)。前者は、地方自治体におけるゴミ処理能力の向上支援を眼目としている。生活ゴミ処理機械等の導入を有償資金協力にて実現しているだけでなく、地方自治体職員のゴミ処理及び環境保持に関わる人材育成にも寄与していることが視察を通し確認され、重点的に取り上げる事項の“環境対策を担う人材育成”という点に符合していると考える。但し現地調査での面談では、効果を計るための対応は本格的には取られていないことが確認された。今後も我が国が当該分野を重点的に援助していくのならば、このように効果発現が比較的明らかな案件では、定量的評価が可能となる指標の設定及びデータ収集をタイ政府と協議の上、進めていくことが望ましい。指標を設定することで援助効果が明瞭になることが、便益として挙げられる。指標の例としては、“環境保持に関わる研修を受けた行政官の数”というアウトプット・レベルの定量的な指標から、“同自治体のゴミ処理方法がモデルになり、環境保護関連法案が改訂または制定された”という政策レベルでの定性的な指標が考えられる。
後者は、東北タイでの森林面積保持を上位のプロジェクト目標とする援助案件である。表5-9のように、プロジェクト対象地域である東北部の森林率の低下速度が他地域と比べ緩やかであることから、間接的な援助効果が発現していると見ることも可能である。その理由はプロジェクトを通して植林推進の基盤が形成されていった訳だが、この活動は同地域における違法な森林伐採に対する抑止力という効果をもたらした可能性があるからである。案件関係者からは、プロジェクトの実施による地域住民の意識変革の他、タイ政府予算の増額による林野局の森林率保持に関わる活動の活性化が挙げられている。一方、案件関係者及び国際機関との面談を通し、指標にて森林率の保持・向上という点での援助効果を見るには、プロジェクト終了後15~20年のデータが必要という見解を得た。ユーカリのように短期間で成長する木を除き、多くの木が森林の一部となるまでには長い月日がかかるというのが理由である。従って同じ重点分野であるにも関わらず、重点的に取り上げる事項の種類によっては評価が困難である点が確認された。尚、当該プロジェクトは既に第二フェーズに移っているが、タイ側カウンターパートへの技術移転は順調に進んでいることが推察され、重点的に取り上げる事項の“環境対策を担う人材育成”が的確に反映されていると評価したい。
以上より、我が国援助はタイにおける環境保全にある程度寄与していると推察される。但し、開発の成果が定量的に明示されるまでにはまだ時間がかかるという点には留意したい。長期的視点で政策を進め且つ評価する体制が必要な当該重点分野では、先の経済危機のような局面に遭遇する度に、タイ政府による予算措置的配慮が減少することも考えられる。そのような事態にあっても、我が国が対タイ援助政策の中で重視する姿勢を堅持することでタイ政府の困窮への支援が可能だと考え、評価対象期間中に当該分野を重点分野として維持し続けた点は高い意義があったものと評価したい。
5.2.4 地方・農村開発
重点的に取り上げる事項レベルでの開発の推移
地方・農村開発は3つの重点的に取り上げる事項に分類されるが、そのうちの1つに対応する指標の推移を見ることにより、重点的に取り上げる事項レベルでの開発の推移を確認した。
開発が遅れている地域を中心とした農業振興・農業開発
タイにおける貧困農民の割合は通貨危機までは減少していたものの、通貨危機後一時増加し、その傾向は1999年まで続いたことが分かる(表5-10)。地方から都市への建設現場等の出稼ぎ労働者が、通貨危機後の経済停滞の影響を受けて故郷に戻ったことが主因と考えられる。
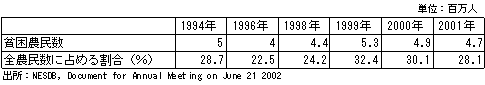
表5-11のように、農業組合振興、農村金融の共同組合を通した発展も通貨危機の影響を受け一時減退しているものの、長期的には拡大傾向にあり、地方・農村開発が将来を通じ安定的に進行する可能性は否定できない。貧困対策という観点から、このような制度面の整備推進は、所得の低い農民の所得向上へと繋がっていくものと期待される。
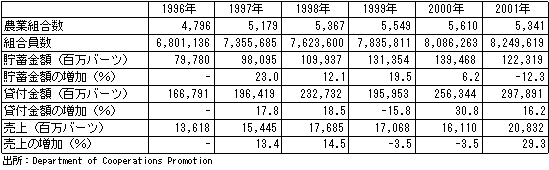
重点分野レベルでの効果の評価
通貨危機直後を除けば、貧困農民数が漸減傾向を示していることより、地方・農村開発においてタイ政府の開発政策が多少の成果を挙げた可能性が示唆される。
1995~99年度の間に当該重点分野の範疇で実施された我が国援助案件は、
- 草の根無償資金協力案件: 8件
- プロジェクト方式技術協力案件: 2件
- 開発調査: 18件
- 有償資金協力案件: 1件
有償資金協力案件においても農業共同組合銀行を継続的に支援するなど、制度面への支援や重点的に取り上げる事項である“開発が遅れた地域を中心とした農業振興・農村開発”に符合した貢献を実施してきたものと評価できる。
以上より、我が国援助はタイにおける地方・農村開発にある程度寄与していると推察される。
5.2.5 経済基盤整備
重点的に取り上げる事項レベルでの開発の推移
経済基盤整備は7つの重点的に取り上げる事項に分類されるが、そのうちの1つに対応する指標の推移を見ることにより、重点的に取り上げる事項レベルでの開発の推移を確認した。
道路・鉄道・航空などの運輸整備や排水整備等基礎的インフラへの支援
3つの指標より(表5-12、表5-13、表5-14)、整備されてきた経済インフラが順調に効果を生み出していると見ることができる。車輌台数登録(残高ベース)においては1997年の通貨危機にもかかわらず、1994~99年まで順調に増加した。港湾での貨物取扱量は連続的な増大傾向を示しており、特に円借款の活用によって整備されたレムチャバン港のコンテナ取扱量は順調に伸びている。鉄道は経済危機の落ち込みから回復後、僅かであるが漸増傾向を示している。このように、当該重点的に取り上げる事項レベルでのタイの開発は順調に推移しているものと推察される。
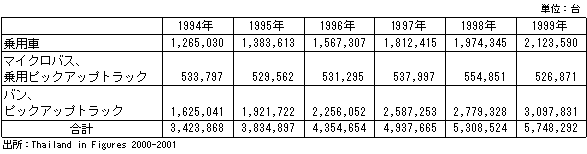
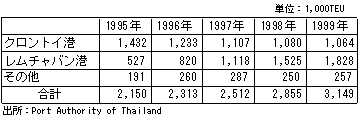
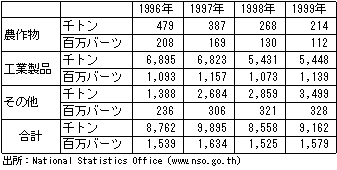
重点分野レベルでの効果の評価
前述の分析より、経済基盤整備の面でタイ政府の開発政策は大きな成果を挙げて来たものと推察される。1995~99年度の間に当該重点分野の範疇で実施された我が国援助案件は、
- 草の根無償資金協力案件: 3件
- プロジェクト方式技術協力案件: 5件
- 開発調査: 19件
- 有償資金協力案件: 6件
当該重点分野の範疇にある実施案件として、「新クルンテープ(ラマ三世)橋建設事業(有償資金協力案件)」及び「ハイウェイ・セクタープロジェクト(II)(有償資金協力案件)」を視察している(添付資料2)。両案件ともインフラ整備を眼目としており、プロジェクト・レベルでの効果発現の徴候も確認している。
当該重点分野は、案件数及び金額的に我が国の対タイ援助において主要な役割を果たしていると考えられるので、当該重点分野に関してはその効果の確認を別な角度から評価した。表5-15では、タイ南部にて有償資金協力により道路が整備された地域と全国における車輌登録台数の伸び率を比較した71。道路が整備された地域における乗用車、自動二輪車の伸び率は全国と比べ遥かに高い数値を示しており、個人による自動車等の保有が進んでいることを示している。しかし、マイクロバスと乗用ピックアップトラックは全国平均とほぼ同じ伸び率、バンとピックアップトラックは全国平均より低い伸び率である。この現象から、我が国援助によるタイ南部の道路整備が地域経済の活性化を促し、地域住民の所得向上へと繋がり、個人による自動車等の購入が進んだ、という推測が可能と考える。対タイ国別援助計画の中でも記載されている“地方経済基盤整備”を実施した成果であるとも言える。
以上より、我が国援助はタイにおける経済インフラ整備への支援に大きく寄与していると推察され、重点分野として経済基盤整備を設定したことの意義は十分に認められ、援助効果も発現されたものと評価したい。
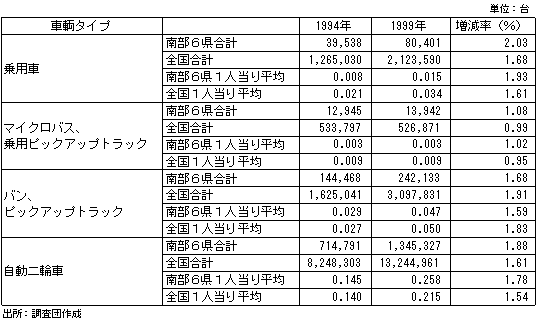
5.2.6 地域協力支援
重点的に取り上げる事項レベルでの開発の推移
地方協力支援は3つの重点的に取り上げる事項に分類されるが、そのうちの1つに対応する指標の推移を見ることにより、開発の推移を確認した。
南南協力(日・タイパートナーシッププログラム事業の維持・発展を含む)の促進支援
タイは我が国との間で1994年に「日・タイパートナーシッププログラム」を締結し、第三国研修の拡大、第三国専門家の派遣、日タイ共同プロジェクト(広域技術協力)等、南南協力を積極的に推進している(表5-16)。
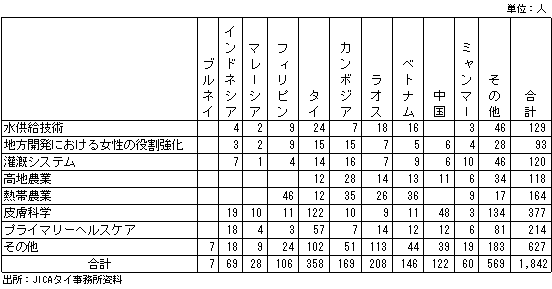
重点分野レベルでの効果の評価
1995~99年度の間に当該重点分野の範疇で実施された我が国援助案件は、
- プロジェクト方式技術協力案件: 1件
- 開発調査: 2件
である。視察を行った「ラオス国立大学工学部ディプロマ教師学士取得プログラム(JICAによる南南協力支援事業)」での面談においては、タイ・ラオス両国の大学間の協力関係の強化に結び付いたという発言もあった(添付資料2)。日・タイパートナーシッププログラムによる第三国研修の受講生数は9年間で1800人を超えており、1995年以後の受講生数割合が高い。このように近隣諸国の人材育成においてタイ国内の資源を有効活用してきたことは、我が国がこれまで援助してきた施設やそこで育成された人材、被援助国としてのタイの経験を有効に活用してきたものと評価できる。尚、開発調査はいずれも国境開発を意識した内容のものであり、重点的に取り上げる事項の一つである“国境を超えた広域開発協力案件の発掘・形成と具体的成果の早期実現”に結び付いていると考えられる。但し開発調査という性格上、具体的効果が出るまでには時間はかかると見られる。
5.3 他ドナーにおける効果測定のあり方
本評価の現地調査において訪問した世界銀行、ADB、UNDP、FAOの国際機関いずれにおいても、それぞれタイに対して行ってきた援助の効果を定量的に測ることは行っていない。世界銀行及びUNDPは、タイ予算中のタイ独自の予算が占める割合が相当程度高いことから、自らの援助がタイ全体の開発効果における寄与度を断定できないことを主な根拠として、定量的な指標を基にした効果評価には踏み切れないでいる。
特にUNDPは、日本や世界銀行のように大量の資金を事業予算として有してはいない。従って、定量的な指標を用いて自らの援助政策(プログラム)の効果の評価を行うことには意義を見出していない。但し、UNDPは効果の評価それ自体を否定しているのではない。タイの開発における媒体のような役割を果たすことに組織の存在意義を見出すべく、様々な手段を講じているところであり、定性的に自らの役割を評価できる指標の開発には努力中である。例えば、UNDPは産業公害をテーマとしたセミナーをタイで開催して問題提起を行ったが、UNDPによれば、その影響は工学系大学に産業公害を研究するための学科を設置するという法案の可決にまで至った、ということである。UNDPはこれを一例として、セミナーという投入がもたらした効果の指標として、「産業公害を研究するための学科設置」や「法案の可決」が有用であるという見解を示している。
他方で、ADBとUNDPがプログラム・レベルの効果を測るための指標設置調査を進めている点は特筆に値する。この指標は定性的指標と定量的指標を含む。ADBとUNDPは、タイ政府の進める地方分権化支援を評価するための指標の探索調査を進めている。例えば、中央政府が地方自治体にどの程度の行政能力の技術移転を行ったのかを客観的に測るための指標の開発を進めている。
5.4 結論と考察
5.4.1 結論
本章では主として、対タイ国別援助計画の「重点的に取り上げる事項」レベルでのタイの開発推移を通し、我が国援助政策レベルの効果の検証を試みた。しかし既述のように、我が国援助額がタイ政府の予算に占める割合が小さいことなどから、定量的に我が国援助の貢献度や効果を計ることには限界があることが当初より予想された。
このような制約がある中で検証作業を行った結果、評価対象期間のタイの開発は、少なくとも我が国援助が政策的に支援実行を決断した分野等に関しては、比較的良好な推移を示していることが分かった。また本文中に記載していない指標はデザイン・マトリックス(DM、添付資料1参照)にまとめているが、指標の多くが概ね良好な開発推移を示している。これらから、我が国のタイに対する援助政策がタイの開発において相応の貢献を行った可能性があると考えられる。尚、「経済基盤整備」に限っては、我が国援助がタイの開発において相当程度寄与した可能性が高いものと見られる。以上より、対タイ援助政策は有効に機能し、相応の効果を挙げたものと評価する。
現在入手可能なデータにより、定量的な分析による効果を論じることができるのは経済基盤整備のみだと考える。環境保護については、より確実性の高い評価を行うには、個別案件の成果が成熟するまで暫くの期間待つ必要のあることが分かった。社会セクター、地方農村開発、地域協力における我が国援助政策の効果を評価する場合には、定量的な検証の他に、個別案件レベルでの意見聴取等の定性的分析を組み合わせる方がより現実的に把握できるのではないか、ということが本調査での案件視察を通し理解された。
重点的に取り上げる事項レベルにて定量的指標を設置することが困難であったものについては、DM(添付資料1)にも参考指標として定性的な指標を例示した。定量的な指標の設置が困難であった主な理由は、そもそも定量的な指標の設定が難しい目標であること、適当と考えた指標のデータが継続的にタイ関係機関において収集されていないこと72 等が挙げられる73。前述のように国際機関等もタイに対する自らの協力の効果をどのように測るのか、という点では悩んでおり、解決策としては定量・定性それぞれの指標を組み合わせることで効果測定を検討していることが確認されている。
5.4.2 考察
本章の冒頭でも述べたように、対タイ国別援助計画にはその効果を測定するための指標が設定されていない。本調査では便宜的に目標体系図を基に指標を収集し、DMとして整理し、全指標とデータを総合的に検討することにより我が国援助政策の効果を評価する、という方法をとった。仮に、既定の指標が対タイ国別援助計画の中に存在し、数値の収集等のモニタリングが外務省や大使館において継続的に行われていたのであれば、本章における分析は更に深いものとなったと考えられる。例えば、我が国の対タイ援助に関わる関係者及びタイ政府関係者との面談の際、重点分野毎に指標と収集された数値が議論の俎上にあったのならば、数値の推移を軸に援助政策の効果に関わるより一層客観的な評価情報の収集が可能であったと考えられるからである74。従って、今後も我が国援助政策の効果を評価するのであれば、重点的に取り上げる事項分野レベルでの指標の設定を策定時に行い、データ収集のためのモニタリング体制の確立も行うことで、我が国援助政策の効果をより客観的に把握することが可能となるものと考えられ、その実施を提案したい75。
仮に重点的に取り上げる事項レベルでの指標の設定を正式に行うのであれば、プロジェクト・レベルでの効果評価にて相当の蓄積を行っているJICA及びJBICから設置すべき指標の提案を行うとすることも一案である。また外務本省にて設置された指標に沿ったモニタリング及びデータ収集は在タイ日本大使館が行うことが最も効率的であろう。
大使館から重点的に取り上げる事項毎の指標に基づいたデータが定期的に外務本省に送られ、それらを本調査で行ったように総合的に検証することから、対タイ国別援助計画にて設定した重点分野毎のタイの開発の推移を把握することが容易となり、タイの政治的変動に伴う国別援助計画内容の確認作業も迅速に行えると考える。このような体制、サイクルを確立することにより、現在よりも一層タイの開発の実情を示す情報が外務本省に集まり易くなると見られる。このような仕組みは対タイ援助案件採択においても迅速な意思決定に有効であるだけでなく、タイ政府との政策レベルでの対話や交渉においても有用と考えられる。我が国として重要と考える指標があれば、その収集に関しタイ政府に協力を求める必要も出てこよう。タイ政府に当該データ収集の予算や術がなければ我が国がその指標設置とデータ収集自体の支援を行う場合も考えられる。
59 大阪市立経済研究所「経済学辞典第3版、集計の問題」(1992年)657頁
60 当該重点分野が仮に良好な開発推移を示したとしても、我が国援助政策がどの程度効果発現に貢献したのか、その寄与度を定量的に把握する事は困難である。但し、寄与したか否かの可能性や寄与の意義に関する考察は可能と考える。また指標の推移を追う事によりタイの開発動向の多角的把握が可能になるという点からも国別評価における有用な作業の一つであると認識する。
61 本評価における指標の推移による効果の読み取り方は調査団の私見であり、絶対的なものではないことに留意されたい。
62 国内作業及びタイでの現地作業を通じて収集された指標の全ては、「添付資料1:対タイ援助政策デザイン・マトリックス(DM)」として掲載している。DMは委託元の外務省の指示により、表1-1にあるように、援助政策の効果を計るための手段として調査団が作成したものである。
63 大部分の指標はタイ政府諸機関が作成しているものだが、一部国際機関が用いる指標、我が国関連省庁が自らの政策効果を測る上で適用を検討している指標を活用している。
64 重点課題は2つの重点分野にて設置されているだけなので、重点課題毎の指標の収集は割愛した。
65 第1章で既述のように、終了していない案件も視察対象案件の中には含まれている。
66 表5-1の通り、1995~99年度に実施されたJICAの「公共公益事業」関連の案件及びJBICの「バンコク近郊における空港・地下鉄・橋・道路建設事業」関連の案件の合計金額を表す。
67 東部臨海開発の背景と概要:1973 年にシャム湾で天然ガスが発見されたことにより、それまで石油資源のなかったタイにエネルギーの自給に基づく工業化の道が開かれた。また、チャチェンサオ、チョンブリ、ラヨンの各県にまたがる東部臨海地域は、首都バンコクに近接していること、地形的に深海港の建設が可能であることなど、工業開発における恵まれた環境を有していると以前から考えられてきた。このような背景のもと、タイ政府は同地域の開発を第五次経済社会開発五か年計画(1982~1986年)の最優先課題の1つと位置づけ、首相を委員長とする東部臨海開発委員会を設置して積極的に推進した。東部臨海開発計画の主な内容は、重化学工業開発を中心とするマプタプット工業団地の建設、輸出型・非公害産業立地のためのラムチャバン工業団地の建設及び関連インフラストラクチャー(港湾、道路、鉄道)の整備であった。この計画に対し、日本政府は積極的な支援を表明し、1980年代からJICAやOECF(当時)を通じて協力が行われた。
68 経常予算・投資予算を含む。
69 タイ政府内において環境に関わる事業等を一元的に所管する機関は、昨年設立されたばかりである。
70 国の開発の度合いを測定する尺度として、1人当たりのGDP、平均寿命、就学率、識字率を基本要素として、これらをUNDP独自の数式に基づいて指数化したもの(UNDP東京オフィスホームページ)
71 ここで活用している有償資金協力事業の中には本調査の評価対象前に開始されているものも含まれているが、原則評価対象期間中に終了している。
72 タイ政府がデータを収集していない、収集を中断している、収集を近年始めたばかり、というのが主たる原因。
73 政策効果を測るには必ずしも定量的な指標でなければならないという訳ではない、というのが政策レベルに関わらず、プロジェクト・レベルでの評価における考え方としてもある。
74 大切なことは、「当初合意された指標」に基づき議論することである。本評価においても指標を示した上で面談を試みたことも時折あったが、調査中に調査団の判断で選んだ指標であったため、面談先と指標の妥当性について合意を得ることが難しい場面があった。また議論の俎上に載せることが適当であっても評価対象期間の数値が収集できない、という事情等から、数値の推移を基に援助政策の効果等の議論を深めることは困難であった。
75 指標は必ずしも定量的なものである必要はない。例えば援助開始時には存在しなかった行政機関や法律や規則が、数年後に当該重点分野に新たに出現した、という現象も定性的な指標として考えられる。