第3章 評価内容
1.3 援助政策の基本的な理念の妥当性の検証
ここで、上記1.2で把握したわが国の対スリランカ「国別援助方針」を妥当性という評価項目から検証する。ここでは、妥当性を計るために、わが国ODAの中で「国別援助方針」の基礎となる政策(ODA大綱やODA中期政策)と整合性が取れているか、スリランカの主要政策に見られるようなスリランカ側のニーズと整合性が取れているかについて検証した。
(1)日本のODA政策との整合性
1) ODA大綱と対スリランカ「国別援助方針」との整合性
ODA大綱の基本理念は日本が援助を行なう理由として、「国際社会は、多数の人が飢餓と貧困に苦しんでいることを人道的見地から見過ごすことはできない」とし、「国際社会の相互依存関係、すなわち、開発途上国の安定と発展が世界全体の平和と繁栄にとって不可欠であると認識しなければならない」としている。このことから、日本の援助の究極の目的は、「世界全体の平和と繁栄」への貢献と考えられる。また、「開発途上国の離陸へ向けての自助努力を支援することを基本とし、広範な人造り、国内の諸制度を含むインフラストラクチャー(経済社会基盤)及び基礎生活分野の整備等を通じて、これらの国における資源配分の効率と公正や「良い統治」の確保を図り、その上に健全な経済発展を実現することを目的として、政府開発援助を実施する。その際、環境保全の達成を目指しつつ、地球的規模での持続可能な開発が進められるよう努める。」と述べており、開発途上国の健全な経済発展のために「資源配分の効率と公正」及び「良い統治」が必要であり、これらの実現のためには「経済社会基盤及び基礎生活分野の整備」が必要であると述べている。
「国別援助方針」は経済発展をその援助政策目標として掲げ、その重点分野として経済基盤の整備、人的資源開発、基礎生活分野の整備を挙げており、これらの点で、ODA大綱や大綱に示される重点項目2に整合している。また、ODA大綱の「原則」3には、「軍事支出への動向」や「基本的人権」への注意が含まれる。これに対し、「国別援助方針」の「ODA大綱の運用状況」では、「戦時体制移行に伴う人権状況および開発支出の一時停止に注視する」と明記されており、この点もODA大綱に整合しており、妥当性が高い。
2)ODA中期政策と対スリランカ「国別援助方針」との整合性4
ODA中期政策はODA大綱の下、より具体的な5ヵ年政策として公表されたものであり、経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会(DAC)が1996年に策定した「新開発戦略」5を考慮すること、「良い統治」が重要であり、「各国との協調・連携を強化」すること、「開発途上国の経済成長と社会開発をバランスよく支援していく」こと、「国ごとの事情に適合した効果的・効率的な支援に努める」こと、「開発途上国、先進国、国際機関、民間部門、民間援助団体(NGO)など、あらゆる主体の持つ利用可能な資源との役割分担と連帯を図る包括的取組みが必要である」こと、「顔の見える援助」、「国民参加型の協力の推進に努める」ことなどを基本的考え方としている。また、「重点課題」としては「貧困対策や社会開発分野への支援」、「経済・社会インフラへの支援」、「人材育成・知的支援」、「民主化支援」、「アジア通貨・経済危機の克服等経済構造改革支援」、「紛争・災害と開発」、「債務問題への取り組み」を挙げ、それぞれにアプローチを提示している。さらに、スリランカが属する南西アジア地域への「地域別援助のあり方」については、「貧困削減と貧困層の生存の確保のための支援(保健医療、初等教育、農業・農村開発等の基礎生活分野)」、「民間活動の活発化及び海外からの投資促進に資する環境整備のための人材育成、経済・社会インフラ整備等への支援」、「人口増加や経済成長と関連した環境負荷増大に対応した、環境保全対策のための支援」を重視している。
「国別援助方針」の援助政策目標と重点セクター別目標及びサブセクター目標はほぼODA中期政策の「基本的考え方」、「重点課題」、「地域別援助のあり方」に記載されている内容と整合している。対スリランカ「国別援助方針」では、人的資源開発として「高等教育」と「中間管理職の育成」を重要視しているが、ODA中期政策でも「自助努力への支援を援助の基本理念とする」とし、「開発途上国自らが国造りのために人材育成を行なえる」ためにも、「高等教育を含む教育部門」を重視することが明記されている。
但し、鉱工業開発はODA中期政策からは重点分野であるとは読み取れない。また、対スリランカ「国別援助方針」の「保健・医療体制の改善」で重視しているのは、「州・地域機関病院の整備」、「検査/医療機器整備」、「検査技師・看護婦等の訓練」である。一方、ODA中期政策では、保健分野は「貧困対策・社会開発への支援」の中で「プライマリ・ヘルス・ケアの強化により、可能な限り多くの人に基礎的保健サービスを提供する」こと、「地球規模問題の取組み」の中では「人口・エイズ」と「薬物」への取り組みを明示している。保健人材の育成に関しては整合性に問題はないが、病院での治療サービスの強化を重視する「国別援助方針」と、予防と基礎的保健サービスへのアクセスを重視するODA中期政策とは、必ずしも一致していないことから改善の余地はあると考えられる。
(2) スリランカの開発計画にあるニーズ、優先度との整合性
1) 国家政策との整合性
ここでは、日本の援助基本方針の体系図と、スリランカ政府の開発政策の体系図を示し比較する。
当時のスリランカ政府の開発は、下図3.1-bにあるとおり、「経済成長の加速」と「成長の公平な配分」を上位目標に掲げ、その下に重点政策、さらにその下に重点分野が設定されている。
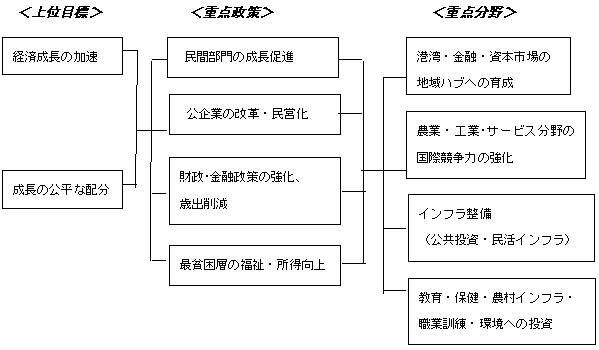
日本の6つの重点分野は、当時のスリランカ政府の開発重点分野(港湾の地域ハブへの育成・農業・工業・インフラ整備・教育・保健・環境)と合致している。重点分野における優先順位は、援助方針では明らかでないが、援助額の配分で見ると、日本の援助の56%を経済インフラが占める7。当時、スリランカの公共投資予算の32~45%を経済・運輸インフラが占めており、当時の政策協議でも、スリランカ政府から、「日本の支援は、特にインフラ整備や人材育成等に活用され、スリランカにとり不可欠である」と高く評価されていたことから8、この点の妥当性は高いと判断される。
2) スリランカ公共投資計画との整合性
ここでは、第2章2.2.1で述べた1995年から1999年までの公共投資計画(PIP)で、ほぼ共通して挙げられている政策・分野を分野別にこの体系図にまとめ、これらとわが国の対スリランカ「国別援助方針」に掲げられている重点サブセクターとの整合性を検証した。
(1) 経済基盤の整備・改善
日本のこの分野での体系図(下図3.1-c)を、スリランカの当該分野政策の体系図(下図3.1-d)と比較すると、以下のことが分かり、整合性が高い9。
- 経済基盤においても、日本の援助方針は、電力・通信・運輸(港湾を含む)と、全てのサブ分野の基盤整備をカバーしている。
- 「全国的なネットワーク形成への考慮」は、スリランカの各分野の地方を含めた全国的拡大のニーズに呼応するものである。
- 「南部地域開発」は、特にスリランカのインフラ部門の重点目標には挙げられていないが、1997年のPIPで、大統領の作業委員会が設置した重点分野に入っており、これに対応するものと考えられる。
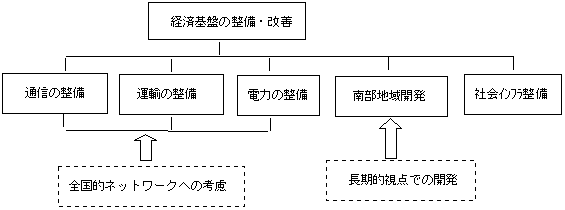
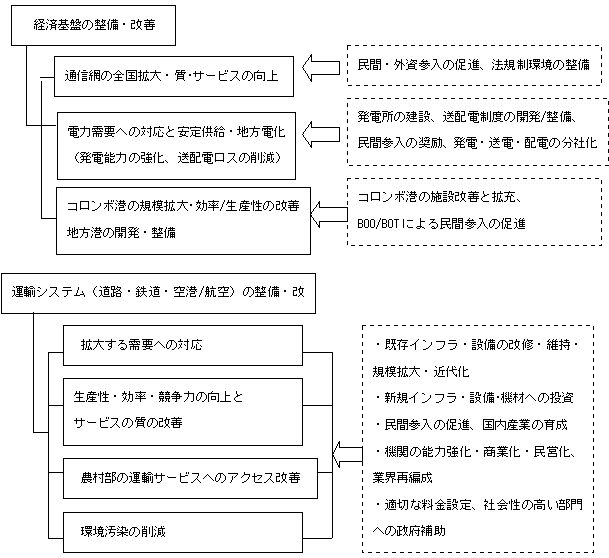
鉱工業分野における日本の援助政策の体系図(下図3.1-e)とスリランカの開発体系図(下図3.1-f)を比較すると、この分野でも、スリランカの重点政策とほとんど合致している。産業開発計画への協力も、民間投資促進や輸出振興などを目的として実施されており、1997年より示された「輸出・雇用創出型の産業育成」という目標も、スリランカの当分野の分野目標と重なることから、整合性が高いと判断できる。
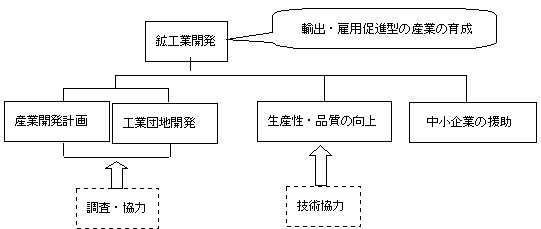
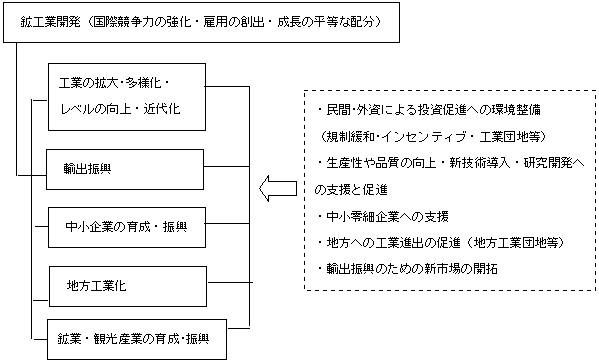
(3) 農林水産業開発
日本の援助政策は、農業生産基盤の整備、アグロ・インダストリーの振興、市場・流通の整備、農業研究・普及、(沿岸)漁業の振興という5つのサブ重点分野を設定している。1997年に重点項目として「基本食料生産の自給の向上」、「農村部への雇用・所得の増大」が追加された。この分野における日本の援助政策の体系図(図3.1-g)と、スリランカの開発体系図(図3.1-h)を比較すると、下記の点が理解できる。
- 日本の援助政策は、加工・市場・流通の改善、既存農業インフラの改修、農業研究・普及(作物の多様化と総合農業への支援も含む)といった、農業分野におけるスリランカの主要な開発目標・政策に合致している。
- 日本が重点項目として挙げた「基本食料の自給向上」については、最も主要な食料である米は1980年代中期にほぼ自給を達成していた。その他、牛乳・砂糖・野菜・果物など自給率の向上が望まれる食料は多いが、スリランカ側は、特に米を含めた食料の低価格での供給を重視していた10。従って、この重点項目がスリランカ側のニーズと整合していたかについては、今回の評価調査でスリランカ政府から疑問が呈された11。
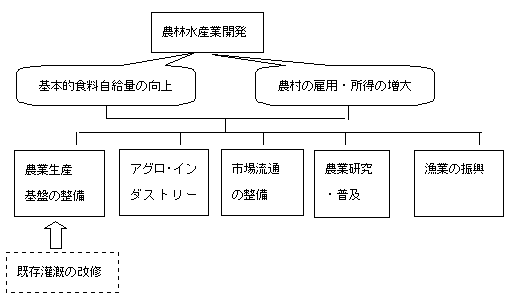
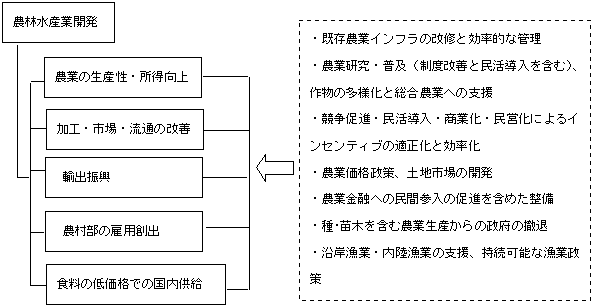
(4) 人的資源開発
わが国の「国別援助方針」において、この分野では、高等教育(後に技術・職業教育が追加)と行政中間管理層の育成に、重点サブセクターを絞り、特に当初は、技術協力を重視していた。高等教育は、スリランカの1995年からの重点政策に挙げられており、質のみならず、教育機会の拡大という量の改善も必要とされていた。そのためには、大学の設備拡張も課題であり、日本の援助方針に、高等教育の「質的・量的」改善という目標が掲げられたこと、後に教育環境整備が援助手法に加えられたことは適切であった。技術・職業教育の向上も、スリランカでは特に1997年から強調されていた。
人的資源開発分野での日本援助の開発体系図とスリランカの体系図を比較すると、わが国の「国別援助方針」に記載されている事項は、ほぼスリランカ側のニーズと合致している。しかしながら、「行政中間管理職の育成」は、スリランカのこの分野での重点目標・政策には特に挙げられていない。これはセクターを横断したスリランカ政府の行政能力の向上を目指すものだと想定される12が、この部分は必ずしも妥当性が高くない。
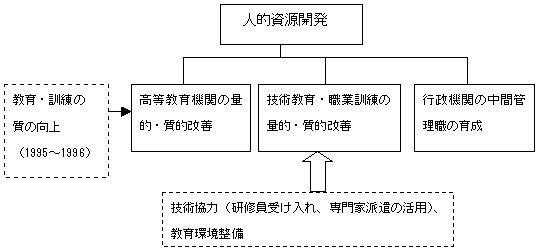
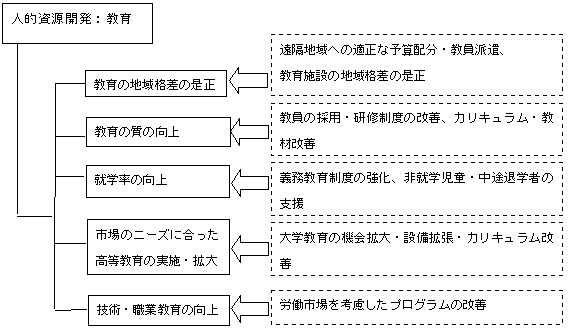
(5) 保健・医療体制の改善
この分野での日本の援助政策の開発体系図(下図3.1-k)とスリランカの開発政策の体系図(下図3.1-l)を比較すると、下記の点が理解できる。
- 日本の援助政策は、州病院施設の改善、医療従事者の技術向上や教育、感染症予防という点で、スリランカの重点開発政策に合致している。特に、1997年に病院整備で地域病院に重点を置いたのは、スリランカの「保健・医療サービスの地域格差の改善」という目標に対応するものであった。
- 1999年に、疾病構造への対応や、受益者負担原則の導入への配慮を打ち出したことは、高齢化などに伴うニーズの変化や、医療行政の改善が必要なスリランカの政策課題に対応するものと考えられる。
- 病院施設整備については、スリランカ政府のPIPには1996年に病院施設の「設備拡張」が示されたものの、1999年以降は、州病院施設の「改善」に留まっており、むしろ医療機関の効率改善や資源の効率的活用が重点政策に入れられるようになった。わが国の「国別援助方針」にある「病院・保健所の整備」が質的拡充なのか量的拡充かは明らかではないが、質的拡充を意味するものであれば妥当性は高いものと考えられる。
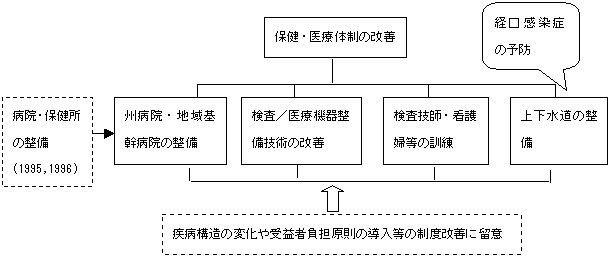
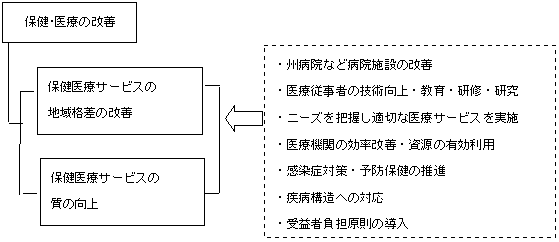
(6) 環境
環境については、わが国の「国別援助方針」では、1994年より「上記5分野以外では、近年環境分野を重視しており」として、重点分野に準ずる扱いで示されている。サブ分野としては、1995年は「居住環境」が挙げられるのみであったが、1997年からは廃棄物処理が加わっている13。この期間に実施された援助を下図3.1-mのスリランカの開発政策と比較すると、最も資金ニーズが高い居住環境インフラの整備を日本が支援しており、妥当性が高いと判断される。
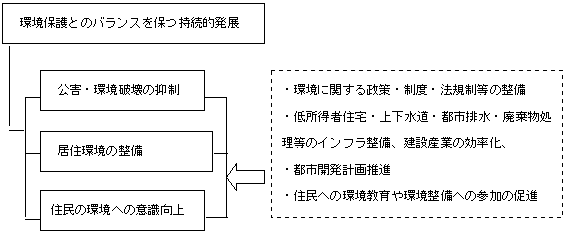
3) 他ドナーが把握していたスリランカの開発ニーズ・優先度との整合性
下表3.1-2は、他ドナーが優先度が高いと把握していた、スリランカの開発ニーズを示している14。わが方の「国別援助方針」の内容は、全体として、各分野で、ドナーが重要だと考えている基本的な開発ニーズと、共通点が多い。
(参考情報)
各ドナーの援助政策は、それぞれの比較優位や経験を基に分野や内容を決定している。各国の重点分野が一致する必要はないが、各国が何を優先事項として捉えていたかは、今後の国別援助計画を策定する上で参考になると思われるので、ここに記載する。
| 世銀(CAS 1998年) | ADB (COS 1998年) | 他のドナー | |
|---|---|---|---|
| 平和構築 | ・紛争解決が第一優先 | ・地方への権限委譲による早期解決 | ・紛争の政治的解決
・紛争地域の復興(UNDP、SIDA) |
| 構造調整・ 経済改革・ |
・財政赤字削減
・民間投資への政策環境改善(労働法) ・金融改革の実施 |
・財政赤字削減
・金融セクター改革(金融機関の能力強化、資本市場の育成) ・民間セクター開発への障壁(貿易・金融・税・労働法)の除去 ・公企業の民営化(可能な所では電力・水道・運輸も) |
・政府機関・公的サービスを、開放された競争的経済の需要に応じ調整すべき(UNDP)
・公セクターの改善と地方への権限委譲(UNDP) ・雇用を創出する裾野の広い経済成長(UNDP, DFID, USAID) ・財政赤字の削減と行政改革(DFID) |
| インフラ | ・鉄道・道路・都市交通・電力・水道・衛生分野の民活を含めた改善 | ・通信・電気・運輸インフラの改善・充実 | ・インフラ整備は経済成長の前提(SIDA) |
| 工業 | ・技術・付加価値指向の工業の多様化 と高度化(UNDP、UNIDO) | ||
| 農業 | ・市場への政府介入、土地法による土地販売の制限、灌漑での低いコスト回収の改善 | ・農業生産性の向上 | ・農業生産性の向上 (UNDP) |
| 人的資源開発 | ・過去に投資された人的資源の活用
・教育格差の是正 |
・コスト回収・受益者負担導入
・高齢化に向けた、年金など社会セクターへの民活 ・市場ニーズに合致した技術・職業訓練や高等教育の改善 ・サービスの悪化、マラリア・幼児栄養不良への対応 |
・教育・保健の質の向上と地域格差の是正(DFID)
・教育改革(教師雇用・配備、学校の合理化、高等教育への補助金の削減やコスト回収、教育の民間への開放)(DFID) |
| 貧困削減 | ・ターゲットの絞りこみ | ・ターゲットの絞りこみ
・農村インフラ整備 ・伝統農業・零細事業への支援 |
・民間での雇用創出(UNDP)
・ターゲットの絞込み(DFID) ・農村での雇用創出と所得格差の是正(SIDA) |
| 統治 | ・人員削減も含めた適切な政府雇用政策の実施
・透明な調達・民営化手続 |
・地方分権化・人員削減による行政改革、中央の権限委譲 | ・政府人事政策の改善(DFID)
(モラル向上、配置・昇進の透明化など) |
| 女性の地位 | ・女性の経済機会の向上 | ・女性の低所得の改善、経済・政治の意思決定への参加(UNDP) | |
| 環境 | ・環境保護(法整備等) | ・水質汚染の防止
・汚染防止・自然資源管理の制度枠組みの確固たる実施 |
・農村貧困に関連する、土壌悪化の防止(UNDP)
・環境法整備(DFID) |
| 人権保護・民主化 | ・人権保護意識の浸透(DFID)
・人権保護・裁判制度等の改善による民主的社会の確立(USAID) |
| 分野 | 日本の援助政策との相違点 |
|---|---|
| 経済インフラ | 日本が公共部門と民活の可能性のある部門とを満遍なく行い、民活導入に対してそれほど明確なメッセージを出さなかったのに対し、世銀・ADBは、膨大な投資をスリランカ政府が負担することは財政赤字を抱える状況から困難であるため、民活導入の促進を要求していた。SIDAも民活導入の動きを評価したが、運輸・道路等の収益の見込みにくい分野での民間投資は困難だろうとしていた。 |
| 農業 | 日本は農業研究と農業開発プロジェクトの実施を重視したのに対し、世銀は、政府による市場への過剰介入の削減・土地法の改正・灌漑コスト回収などの農業政策面を重視。 |
| 工業 | 日本が「産業開発計画」「工業団地開発」「中小企業支援」などの行政主導型の開発を掲げるのに対し、世銀・ADBは民間投資環境整備や金融整備を重視し具体的な障壁を挙げた。UNDPとUNIDOは、技術指向の工業の高度化や多様化を課題に挙げ、UNIDOは繊維工業への集中からの脱却とともに、繊維産業自体の高付加価値化を重視16。 |
| 教育 | 日本は高等教育を含む教育の質の向上に向けた開発プロジェクトの実施を重視した。ADBは「市場のニーズに合った」人材開発を目的としていた。世銀やDFIDは、「教育格差の是正」と「教育改革」などの教育政策を重視していた。 |
| 保健 | 日本は地域病院の整備と医療技術者、看護士の人材育成の開発プロジェクトの実施を重視。ADBやDFIDは保健サービスの質の向上と地域格差是正を重視。把握していた基本的なニーズは共通していた。 |
| 環境 | 日本は、居住環境の改善を重視し、短期的なスリランカのニーズに応じる方向だが17、他のドナーは水質汚染を含む汚染防止や土壌悪化防止といった環境保護とそのための法規制整備や執行を重視。 |
2 イ)地球的規模の問題への取組み、(ロ)基礎生活分野(BHN)等、(ハ)人造りおよび研究協力等技術の向上・普及をもたらす努力、(ニ)インフラストラクチャー整備、(ホ)構造調整等
3 (1)環境と開発の両立、(2)軍事的用途および国際紛争助長への使用回避、(3)相手国の軍事支出などへの動向に注意、(4)民主化の促進、市場指向型経済導入の努力、基本的人権、自由の保障状況への注意を提示している。
4 ODA中期政策は1999年に策定・公表されたが、後述するように1996年にDACにより策定された「新開発戦略」の目標を念頭に策定されたもので、策定過程も1999年以前より始まっていたため、対スリランカの1999年の「国別援助方針」にこれを盛り込むことは可能であったと考えて、比較評価対象とした。
5 人々の生活の質向上を目的として、(1)2015年までの貧困人口割合の半減、(2)2015年までの初等教育普及、(3)2005年までの初中等教育における男女格差の解消、(4)2015年までの乳幼児死亡率の1/3までの削減、(5)妊産婦死亡率の1/4までの削減、(6)リプロダクティブヘルスに対する保健・医療サービスの向上、(7)2005年までの環境保全のための国家戦略の策定、(8)2015年までに環境資源を増加傾向へと逆転という社会開発上の具体的な目標を掲げている。日本は「新開発戦略」の策定に主導的な役割を果たした。
6 2章2.2.1で述べた1995年から1999年までの公共投資計画(PIP)をまとめた表2.1.1.を基に作成。5つのPIPで、ほぼ共通して挙げられている政策・分野をこの体系図にまとめた。
7 1995~1999年のコミットメントベース(OECD資料)
8 1997年の大使館の政策協議議事録より。
9 以下の分野別の体系図は、日本の援助方針(1995年~1999年)、スリランカのPIPで示された分野別の重点目標と政策(2章2.1(2))を基に作成。
10 第2章2.1.(2)1)農林水産業の概況で述べたように、スリランカの農業価格政策も、自給率向上を目指した一貫したものではなかった。
11 スリランカ政府の農業省での聞取り調査より
12 1997年のスリランカ援助実施体制評価では、「国の発展に貢献しうる人材が有効に活用されない。」ことが課題に挙げられ、中間管理職の育成が提言された。
13 ただし、1996年は「防災」がこの年のみ入れられた。
14 ここでは、世銀・ADBの他、スリランカの開発状況を分析しているUNDPやDFID等を挙げる。
15 2章で挙げた国別援助計画等を参照。
16 "Integrated Industrial Development Support Programme" 1999, UNIDO
17 案件実施レベルでは、1998年に契約された「環境対策支援事業」(円借款)が、国立開発銀行を通して、企業に環境防止装置整備のための融資を実施している。

