第2章 評価対象時期におけるスリランカの動向
2. 評価対象時期(1990年代後半)のスリランカ政府の開発計画の概況
2.1 1995~1999年までの動き
(1)重点分野と予算の推移
スリランカの開発計画として、大蔵計画省の国家計画局が原則毎年、5ヵ年に亘る公共投資計画(PIP)を策定している。1995~1999年には、4つのPIP の他、1999年に「開発6ヵ年計画(1999‐2004年)」(Six Year Development Programme 1999-2004)が発表された12。それぞれのPIPの第1章「経済実績と見通し」に示された内容を上位目標、横断的な重点政策、重点分野とその政策と区分すると表2.2-1のようにまとめられる。
| 上位目標 | 横断的な重点政策 | 重点分野とその政策 | |
|---|---|---|---|
| 1995 ~ 1999年 |
経済成長の加速 成長の公平な配分 |
* 民間部門の成長促進
* 投資環境の整備・平和構築 * 輸出振興、法・規制枠組み改善 * 公企業の改革・民営化 * 政府歳出計画の合理化 * 緊縮財政・金融政策 * 最貧困層の福祉・所得向上 |
・港湾・船舶・金融・資本市場の地域ハブへの育成
・農業・工業・サービス分野の国際競争力の強化 ・教育・保健・貧困削減・環境分野への投資 ・民活インフラの促進と民間参入までの経済インフラへの投資 |
| 1996 ~ 2000年 |
同上 | 同上 | 同上に加え、
・科学技術・農村インフラへの投資 ・北東部の復興開発 |
| 1997 ~ 2001年 |
経済成長の維持 成長の公平な配分 |
* グローバル経済・自由化への対応
* 外資の促進 * 公企業の改革・インフラ整備 * 主要分野での大統領タスク・フォース、作業グループの設置 |
・農業・工業・サービス分野の国際競争力の強化
・教育・保健・農村インフラ・水供給・職業訓練・環境分野への投資 ・南部開発・北東部の復興開発 |
| 1999 ~ 2001年 |
経済成長の復活 構造改革の促進 |
* グローバル経済・自由化への対応
* 民間主導型成長への政策/制度改革 * インフレ削減、貯蓄投資の増加 * 長期資本の動員、民営化の促進 * 人口構造の変化への対応 |
・経済インフラ投資を最優先
・輸出志向の製造・サービス業の多様化 ・環境保全 |
| 1999 ~ 2004年 |
経済成長の加速 成長の公平な配分 |
* 民間部門の成長促進
* 投資環境の整備・平和構築 * 輸出振興、法・規制枠組み改善 * 財政・金融政策の強化 * 公企業の改革・民営化 * 最貧困層の福祉・所得向上 |
・港湾・船舶・金融・資本市場の地域ハブへの育成
・農業・工業・サービス分野の国際競争力の強化 ・民活インフラの促進 ・保健・教育・職業訓練・科学技術・農村インフラ・環境分野への投資 |
| 指標 | 1995~1999年 | 1996~2000年 | 1997~2001年 | 1999~2001年 | 1999~2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP年間成長率 | 6~7.7% [4.9%] |
3.7~7.5 % [5.0%] |
6~8% [4.0%] |
4~6% [3.0%] |
5.6~7.0% |
| 一人当りGDP年間成長率 | 5.7% | 4.8% | N/A | N/A | N/A |
| 国内資本形成 (GDP比) | 26~27%(58~63%が民間) [25.3%(73.6%が民間)] |
24~28%(61~67%が民間) [25.8%(75.1%が民間)] |
25.7~30% (65~87%が民間) [25.4%(74.9%が民間)] |
28.1~28.2% (76~73%が民間) [25.8%(75.3%が民間)] |
27.7~28% (74~72%が民間) |
| 国内貯蓄率 (GDP比) | 19~22% [21.4%] |
18~24% [21.8%] |
21~25% [21.9%] |
23~24.5% [21.5%] |
22.7~26.1% |
| 政府消費 GDP比 | 7 % [9.9%] |
7% [9.7%] |
N/A [9.7%] |
N/A [9.8%] |
N/A |
| 経常赤字 GDP比 | 6.4~4.9% [3.7%] |
5.8~4% [3.8%] |
5~4.8% [3.3%] |
4.7~3.1% [4.1%] |
5~1.9% |
| 財政赤字 GDP比 | 7.5~5.1%* [8.8%] |
10~4%* [8.8%] |
7.3~4% [9.1%] |
8.8~7.6% [9.4%] |
5.7~4% |
| 財・サービス輸出額/GDP | 33.3~33.4% [35.8%] |
34.8~45.9% [36.4%] |
29.5~20.8% [36.8%] |
40.7~37.9% [37.2%] |
38.5~37.8% |
| 消費物価上昇率 | 8~5%(GDPデフレータ-) [8.4%] |
14.5~5.9% [8.1%] |
9.5~5.5% [8.2%] |
6% [8.0%] |
8~5% |
| 失業率 | 5% [10.5%] |
5% [9.6%] |
9.5~5% [8.9%] |
N/A [8.1%] |
9.9~5.5% |
注:目標値中、「 ~ 」とあるのは当該期間の初めと終わりの目標値、外は最終年の目標値を示す。
[ ]内には当該期間における年度ごとの実績値の平均を示した。2001年度の値は暫定値を用いた。
* の値は、経常支出の削減によるもので、資本支出はGDP8.6%を維持するとしている。
上記表2.2-1より、1995~1999年のスリランカ政府の開発計画については、以下のようにまとめることができる。
1)上位目標は、ほぼ一貫して(1)経済成長の加速と(2)成長の公平な配分だった。
2)この目標に向けた横断的な政策には、大きく分けて次の4つがある。
| (1) | 民間主導型の成長促進:そのための投資環境や法・規制・政策・制度の整備、外資導入の促進 |
| (2) | 公的部門の改革・合理化: 公企業の改革・民営化、政府歳出計画の合理化 |
| (3) | マクロ経済の安定: 財政・金融政策の強化、インフレ削減、貯蓄投資の増加 |
| (4) | 最貧困層への福祉: 最貧困層の所得創出能力の向上13 |
3)重点分野とその政策では、下記が挙げられている。
| (1) | 農業・工業・サービス分野の国際競争力の強化、輸出志向産業の多様化 |
| (2) | 民活インフラの促進と、教育・保健・農村インフラ・職業訓練・環境等の社会分野への投資の拡充14 |
| (3) | 港湾・船舶・金融・資本市場を、地理的条件を活かし、地域ハブへ育成する。 |
なお、1996~2000年、1997~2001年のPIPでは、北東部の復興開発と南部開発が重点政策に挙げられている。上記の横断的政策は、表2.2-2の指標目標からも見てとれる15。
それぞれの重点分野が金額面でどの程度配慮されたかを検討するために、PIPに示された政府公共投資計画(政府資本支出予算)の配分で見たのが次の図2.2-aである。なお、これら公共投資計画予算のGDP比は、1995年は9.7%だったが、1997年からは7.1~7.5%に減少している。
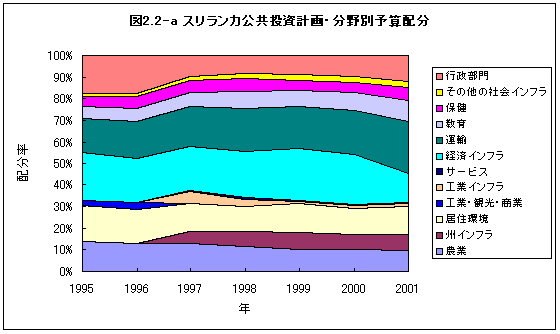
出所: PIP 1995~1999,1996~2000,1997~200116
図2.2-aから、以下が分析できる17。
| (ア) | 経済インフラ(電力・通信・港湾・復興開発)は、1995~2000年まで全体予算の17~24%と、最大の配分を受けていたが、2001年には13.3%となり、運輸分野が最大の24%を得た。経済インフラの配分減は、港湾分野の予算が2001年に大幅に削減されたことが大きな理由である。一方、復興開発予算は、1.5%程度だったのが、1999年と2000年にはそれぞれ5.1%、7.4%の配分が計画されている。 |
| (イ) | 教育・保健等の社会分野は、徐々に配分比率を増やし、特に教育分野の配分は1995~2001年で倍増している。 |
| (ウ) | 農業、居住環境、州インフラの分野は総計として、微増している。ただし、農業への配分は1990年代前半の約17%と比べると、12~10%と大きく減少した。これには1980年代の主要な農業プロジェクトだったマハヴェリ計画の縮小が影響している。一方、州・地域開発の配分は3.4~5.5%と増加している。 |
| (エ) | 行政部門予算は削減されている。 |
これらから、先に述べた重点分野とその政策も(1)経済インフラの民活導入による政府投資の段階的な削減、(2)社会分野への投資の増加、(3)北東部の復興開発、(4)政府行政機関の合理化-という点で予算にも反映されていると言える。
(2)各分野の概況と重点政策
1)農林水産業
a. 農林水産分野の概況
スリランカの農林水産業は、小農による「米」、プランテーション部門による茶・ゴム・ココナツ等の「輸出作物」、米以外と畜産を含めた「その他」、水産、林業に大別される。1990年代の農林水産業総生産に占める割合は、下記の表2.2-3の通りである。
|
|
農林水産業総生産に占める割合は、米・プランテーション作物が減少、その他作物と水産業が増加したが、下記に示すように、米・プランテーション作物の生産性や収益性の停滞もしくは低下、その他作物や畜産の生産量の低下が問題だった(表2.2-4参照)18。
| ア) | 米:1980年代中期の自給達成後、単位面積収量は3トン/haに留まり土地生産性が向上していない。米価も生産費の上昇に対応せず収益性が低下、生産意欲をそいでいる。 |
| イ) | プランテーション作物:単位面積収量の低さと低品質が問題で、その最大要因は1975年からの国営企業化だとされ、1992年に経営の民間委託、1995年に民営化が開始された。 |
| ウ) | その他作物・畜産:米自給達成後の作物多様化政策により、栽培が促進された。しかし、ほとんどの作物の生産量は1990年代後半を通して低下している(表2.2-4参照)。畜産も、養鶏・牛乳生産を除き、飼育数は減少・または微増に終わっている。 |
| エ) | 林業:国土に占める森林の割合は、1950年代の45%から1990年代初めには25%弱と激減し、植林・造林による回復が急務とされている。 |
| オ) | 水産業:特に沖合・遠洋漁業高が1990年代を通して5倍以上に伸び、水産品の自給率も70~80%に改善している19。水産業は、100万の雇用を抱えるという点だけではなく、国民の栄養不良を改善するという意味でも重要とされている。 |
下記表2.2-5で、主要輸入農産物を示した。米の自給率はほぼ90%を達成しているが、自給率の向上が期待される作物・産品として、砂糖(自給率15%)、牛乳(20~25%)、水産品(70~80%)、野菜・果物が挙げられる20。
|
b. スリランカ政府の開発計画における農林水産分野の重点政策
この期間の農林水産分野の上位目標は、(1)農業生産性・所得の向上と(2)食糧の低価格での国内供給だった。同期間の農林水産分野の政府投資は大きく減少したが、これは、灌漑を含む農業インフラについては、新規投資よりも既存資源の有効利用と効率的な管理が重要との考えに基づいている。同分野でのPIP予算の45~50%は依然としてマハヴェリ開発と灌漑に配分されているものの、政策としての重点は、農業研究・普及、加工・流通・農業金融などへの民間参入の促進に移り、農業補助金も段階的な削減の方向が示されている。プランテーションの民営化等、作物・種・苗木の生産からの政府の段階的な撤退も続いている。
しかし、世銀や研究機関からは、農業停滞の原因として、生産・流通両面における政府の過剰介入、農作物への関税政策に一貫性が無いことによる市場の不安定さ、土地利用の流動化を促す法整備の遅れ、厳しい労働法規制等などが指摘され、長期的な農業戦略の必要性が示されている。世銀は、人口の8割を占める農村人口の貧困削減のためには、農業部門の生産性の向上が重要であるものの、政府の農業市場への過剰介入がこれを阻んできたとしている21。
| 開発目標 | 重点政策 | |
|---|---|---|
| 1995 ~ 1999年 |
・伝統農業の生産性・所得の向上
・加工・市場の改善 ・農産物余剰の輸出 ・樹木農産物の生産性向上 ・農村部の雇用創出 ・生活コスト(特に食糧)の削減と安定化 |
・農業市場での競争促進、民間投資促進による生産インセンティブ・市場インフラの適正化、国際競争的な農産物価格の設定
・ニーズに合致した農業研究の改編と普及活動の強化 ・土地・水資源管理の改善、既存灌漑・農業インフラのリハビリ ・国営プランテーションへの民間資本参入による効率化 ・樹木農産物のリハビリ、間作物・畜産を導入した総合農業への支援 ・船・機材購入支援による沿岸漁業の促進、民間の内陸漁業への支援 ・既存農民組織の再組織化と構造改革 ・適切な農村金融機関を通じた農業・畜産・漁業への融資供与 |
| 1996 ~ 2000年 |
同上
・集荷・加工・貯蔵・マーケティング網の開発 |
・農業研究・普及活動、マーケティング、農業インプットの供給
・農業価格政策 ・土地市場の開発 ・農民による灌漑・農業用道路等のインフラの維持管理 |
| 1997 ~ 2001年 |
・農業生産性・所得の向上
・食糧の低価格での国内供給 |
・民間による種・苗木の商業生産の促進
・小農へのグループ融資制度、小・中・大規模投資家への中・長期農業融資の拡充 ・民間保険業者の農業保険への参入の促進 ・肥料補助の小農への限定と段階的削減、有機肥料利用への指導 ・農業研究・普及における農民との連携強化 ・市場への政府介入の最小化、収穫後処理・加工への民間参入の促進 |
| 1999 ~ 2001年 |
同上
・伝統農業の商業化と収益事業への転換 |
同上(金融は除く)
・種の多様化、土壌・水の保全のための森林保護 ・海洋環境保全を考慮した持続可能な漁業政策 ・畜産促進:動物性蛋白質摂取の向上、農村部の自営の促進 ・大・小プランテーション部門の生産性・収益性の向上 ・作物の多様化、生産性・品質向上・商業化による輸出作物の振興 |
| 1999 ~ 2004年 |
同上 | ・より効果の大きな農業研究:民間の研究への参加
・州・国レベルの農業普及活動の統合と有料化の検討、農民との連携 ・公機関の種・苗木の生産を研究に限定、商業生産・販売・流通は民間に委譲、そのために政府インフラを民間に貸与 ・商業農業への民間参入の促進:・商業銀行の農業融資、民間の農業保険、生産・開発補助の低利融資への転換、農村部での小規模農業加工の促進と加工技術の普及 |
2)鉱工業
a. 鉱工業分野の概況
下表2.2-7に示されるように、製造業の中でも衣類・繊維製品の輸出が好調である。これは途上国の輸出を支援するための、世界貿易機関(WTO)の繊維協定(ATC)の二国間数量割当によるところが大きい。数量割当の期間が2005年に切れることから、繊維製品の競争力向上と製造業の多様化がスリランカの大きな課題となっている23。
| 1991 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造業生産に占める割合(%) | 食品・飲料・タバコ | 28.9% | 23.3% | 24.7% | 23.4% | 23.6% | 23.8% | 22.8% |
| 繊維・衣料・皮革 | 32.6% | 44.3% | 42.6% | 45.3% | 44.9% | 45.0% | 46.6% | |
| 木製品 | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
| 紙製品 | 2.1% | 1.9% | 1.8% | 1.7% | 1.5% | 1.5% | 1.4% | |
| 化学製品 | 19.4% | 16.2% | 17.0% | 15.7% | 16.2% | 15.7% | 16.1% | |
| 非金属 | 7.9% | 7.1% | 6.9% | 6.6% | 6.5% | 6.7% | 6.1% | |
| 基礎金属 | 1.2% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | |
| 加工金属・機械・運輸機械 | 4.9% | 3.4% | 3.2% | 3.5% | 3.6% | 3.6% | 3.4% | |
| その他 | 2.3% | 2.2% | 2.2% | 2.3% | 2.2% | 2.3% | 2.1% | |
| 製造業付加価値に占める割合(%) | 食品・飲料・タバコ | 40.1% | 36.1% | 34.5% | 31.7% | 31.2% | 31.0% | 29.3% |
| 繊維・衣料・皮革 | 22.8% | 30.4% | 32.7% | 36.2% | 36.7% | 38.5% | 41.5% | |
| 木製品 | 0.2% | 1.4% | 1.3% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | |
| 紙製品 | 3.1% | 3.0% | 2.7% | 2.4% | 2.0% | 1.9% | 1.7% | |
| 化学製品 | 8.5% | 8.4% | 9.4% | 9.6% | 11.0% | 9.6% | 10.6% | |
| 非金属 | 13.1% | 11.9% | 11.0% | 10.4% | 9.6% | 9.6% | 8.5% | |
| 基礎金属 | 0.7% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | |
| 加工金属・機械・運輸機械 | 8.6% | 5.6% | 5.0% | 5.3% | 5.2% | 5.1% | 4.6% | |
| その他 | 2.9% | 2.8% | 2.9% | 2.8% | 2.6% | 2.6% | 2.4% | |
| 製造業輸出に占める割合(%) | 繊維・衣料 | 64.5% | 63.3% | 66.2% | 69.4% | 68.3% | 69.6% | 64.5% |
| 石油製品 | 3.0% | 3.4% | 2.8% | 2.0% | 2.1% | 2.3% | 3.0% | |
| その他 | 32.5% | 33.3% | 31.0% | 28.6% | 29.6% | 28.1% | 32.5% | |
しかし、下記に示すように、繊維・衣料・皮革と食品・飲料・タバコという労働集約産業が、スリランカの製造業生産の7割を占めており、製造業の多様化は進んでいない。
| ア) | 生産高、付加価値、輸出に占める割合を通して、繊維・衣料・皮革製品の比重が非常に高く、生産・付加価値についてはその割合を1990年代も増加させている。特に、全輸出に占める割合は、1991年の38.8%から2000年には54%になり、半分以上の輸出をこの分野が占めた24。 |
| イ) | 次には、食品・飲料・タバコが、依然生産高で2割強、付加価値で3割のシェアを維持している。 |
| ウ) | 非金属、基礎金属、加工金属・機械は、1990年代を通して、生産高・付加価値ともにそのシェアを減少させている。 |
b. スリランカ政府の開発計画における鉱工業分野の重点政策
1995年のPIPに示されているように、工業分野は、市場開放政策の中で生産・雇用の面で大きな成長が期待され、技術・生産性の向上と人的資源の最適活用が必要である。また、小国の国内市場を考えると、工業発展には輸出振興が欠かせない。その結果、この期間の鉱工業部門の主な開発目標は下記のようになった。
(1) 工業の拡大・多様化・レベルの向上・近代化
(2) 輸出振興
(3) 中小企業の育成・振興による雇用の創出
(4) 地方工業化の推進による、経済成長の平等な配分
(5) 鉱業・観光産業の育成と振興
そして、上記に対する政策は、主に次の通り。
| (ア) | 民間企業・海外直接投資による新産業・輸出への拡大や投資を促進するための環境整備25 |
| (イ) | 生産性や品質の向上・新技術導入・研究開発への支援と促進26 |
| (ウ) | 中小零細企業の支援 (例:融資、技術経営指導、大企業との連携推進) |
| (エ) | 地方への工業進出の促進(例:地方工業団地、未開発地域への産業進出の奨励) |
| (オ) | 輸出振興のための新市場の開拓 |
全体を通して、政府の役割は、民間企業による成長を促すための政策・制度・環境作りであるとし、具体的には規制緩和・税制改善等の他、工業団地を含めたインフラ整備、減税などのインセンティブ供与、融資制度の拡充などに焦点が合わせられている。特に、1997年以降は、ハイテクを含めた新技術やITの導入、科学技術の振興や研究開発、工業の近代化を強調している。新規産業・新技術導入・輸出拡大における海外直接投資の役割の重視や、外国援助による技術指導やインフラ整備への期待も見てとれる。
一方、JICAが2000年に実施した工業振興・投資促進計画調査(フェーズII)では、縫製業など限られた業種への過度の依存、中小企業の軽視、外国直接投資の地元産業への技術移転の少なさ、人的資源を活かした知識集約型産業の未開発のほかに、産業長期開発計画の欠如が問題として指摘された。
| 開発目標 | 重点政策 | |
|---|---|---|
| 1995 ~ 1999年 |
・工業の多様化、特にハイテク分野
・地域工業化の促進 ・中小企業の育成 ・鉱業輸出の付加価値向上 ・輸出振興・輸出製造業の競争力強化 ・技術・スキルの開発 ・観光産業の振興 ・海外直接投資(FDI)の促進 |
・多様化のための規制緩和、政府の収益企業からの撤退
・地方工業団地の整備 ・中小企業金融、技術・品質向上・マーケティングサービス等の整備 ・鉱業での調査・加工技術の向上 ・輸出市場の開拓、繊維・衣料製品の品質高度化 ・企業界と連携した研究者・エンジニア・技術者等の人材育成、政府研究機関による農業製品の研究開発や情報技術レベルの向上 ・観光設備への投資と人材育成 ・新輸出産業・サービス・インフラ・ハイテク分野への投資インセンティブ、東・東南アジアからの投資促進 |
| 1996 ~ 2000年 |
・民間企業の振興
・工業の拡大・多様化・レベル向上 ・中小企業の育成と雇用創出 ・FDIの促進 |
・民間と連携した安定した工業政策の策定、民間振興への制度枠組み
・技術指導・生産性向上・輸出振興への外国援助の活用、特別低利融資 ・規制緩和、新産業育成・FDI誘致のためのインセンティブ ・人材育成・インフラ整備・技術開発(特に中小企業)、工業団地の開発 ・国家品質政策の策定、科学技術・研究開発へのインセンティブ ・関税の低減と統一化、消費税(GST)導入による税制度の簡素化 ・貿易・通関検査の手続・規制の緩和と迅速化、輸出企業に輸入税を免税 ・中小企業金融の継続と農村部への拡大 ・全国鉱資源調査、観光産業開発計画(1992-2001)の実施と、人材育成 |
| 1995 新工業戦略 |
・工業の拡大・多様化・レベル向上
・物的・人的資源の効率的管理 ・農村・都市での雇用・所得創出 ・輸出振興 ・地方工業化 |
・マクロ経済環境の整備、資本市場の拡充、競争環境の整備
・行政手続きの簡素化、国営企業の民営化 ・インフラを含む民間投資へのインセンティブ、FDIの促進 ・研究開発の奨励、生産性向上 ・中小企業振興、中小企業と大企業との連関強化 |
| 1997 ~ 2001年 |
同上 | ・規制緩和、インセンティブ、技術インフラの供給
・伝統手工芸品の振興と保存 ・新技術・市場獲得のためのFDI促進 ・大企業との連関強化による中小企業の育成 ・生産性向上、研究開発の促進 ・未開発地域への産業進出の奨励 |
| 1999 ~ 2001年 |
・需要主導型の民間部門の生産振興
・産業の地域分散 ・小規模工業支援による雇用創出 ・工業の近代化 |
・ITを活用した民間企業の生産促進
・地方の物的・制度インフラの整備 ・科学技術への投資、研究開発の促進と商業化、人材育成、科学技術研究機関の近代化、先進技術への投資や技術移転の優先、資源・知識・エネルギーに基づく実用志向の研究 ・品質保証の強化 |
| 1999 ~ 2004 年 |
・工業の拡大・多様化
・資源の効率的管理 ・中小企業振興による雇用・所得創出 ・輸出振興 ・経済成長の平等な地域配分 |
・輸出促進のための規制緩和・インセンティブ
・未開発地域への産業進出の奨励、地域工業団地開発 ・伝統手工芸品の振興と保存 ・新技術・市場獲得のためのFDI促進 ・生産性向上、研究開発の促進、衣料産業の国際競争力の強化 ・技術・インフラの供給 ・零細小事業へのモニタリング網による支援 ・中小企業への技術・経営指導、自営業設立支援 ・鉱業への民間参入促進 |
3)経済インフラ・運輸
ここでは、PIPにおける主要な分野である電力、通信、港湾と船舶と運輸部門を取り上げる。下図2.2-bで1995年から1997年に策定されたPIPにおける各分野の予算配分を示す。

出所:PIP 1995, 1996, 1997
鉄道・道路の運輸部門への配分が増加している一方(1995~2001年で、それぞれ6.6~9.8%, 9.1~14.1%)、郵便・通信と港湾・船舶が減少(6.4~3.2%、7.0~0.02%)、電力は微増後減少している(7.5~1998年10.5~7.4%)。下記に、各分野の概況と開発政策を述べる。
(1) 電力
a. 電力分野の概況
スリランカの電力分野は、主に、発電・送配電一貫型のセイロン電力庁(CEB)と、1983年にCEBと州政府等の出資によって設立されたランカ電力会社(LECO)により運営されている。特徴として、水力発電への依存度の高さ(1991年79%~2000年63%)、CEBの占める割合の大きさ(1991年100%~2000年87%)が挙げられる(下図2.2-c参照)。水力発電への依存の高さは、自然燃料に乏しく石油・ガスを輸入に頼るスリランカの事情があり、1980年代の発電能力の増加のほとんどは水力発電所の増設によるものだった。しかし、1995年以降のCEBの発電能力の増加は火力によるもので、民間他による発電能力も、2000年には13%強に増加した。
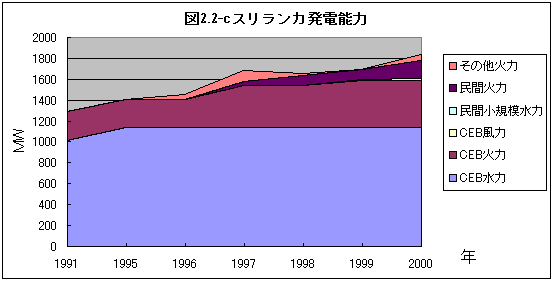
出所: Economic and Social Statistics of Sri Lanka 2001

出所: 図2.2-cに同じ
水力発電に依存した電力は、雨量の影響を受けやすいため、その電力供給が不安定になる。1991~2000年の間に発電量・消費量ともに倍増しているが、1996年は、少雨の影響により電力危機が起こり、3~9月まで計画停電が実施された。また、電力ロス(発電-消費)の割合は、1990年代を通しても約20%と高く、送配電網の改善によるロス率の低下が課題とされた(図2.2-d参照)。
セクター別の電力消費では、1991年には工業36%、家庭用24%だったのが、2000年には、各1/3を占めるようになり、特に家庭用消費が大きく伸びている。世帯電化率は、1988年の27%から1995年に46%、2000年には61.2%に増加したが、国民一人当りの電力消費量はインド・パキスタンより低い。地方電化は1990年代においても大きな課題で、ADB等の支援を受けて実施されてきた。特に、西部州の電力消費量は、1997~2000年の間に1.7倍に増加している。
b. スリランカ政府の開発計画における電力分野の重点政策
この期間の主な課題は、(1)年率8-10%で拡大する電力需要への対応と(2)より多くの人口に電力供給するための地方電化だった。そのためには、i) 発電能力の強化(特に火力)とii)送配電ロスの削減などによる効率の向上が必要だった。特に、1996年の大きな電力危機後は、安定した電力供給も課題となっている。
発電・送配電施設はともに、非常に資本集約的であり、収益を生み出すまでに長い期間を要し、高度技術も必要であった。そのため、建設だけでなく計画やシステムの開発についても、特にこの期間の初期は、外国援助への期待が高かった。一方、1996年以降は具体的に民間参入を課題目標もしくは政策とし、セクター改革として発電・送電・配電の分化も挙げている。また、エネルギー資源の少ない国内事情を反映し、需要・供給管理による省エネや適正価格の設定を挙げている。
| 開発目標/課題 | 重点政策 | |
|---|---|---|
| 1995 ~ 1999年 |
・増加する需要に対応した発電能力の拡充
・送配電ロスの削減、配電システムの合理化 ・2000年までの全村電化 ・需要管理・省エネ |
・新規発電所(火力/水力)の建設
・民間参入のための規制整備 ・CEBの送配電システムの改善 |
| 1996 ~ 2000年 |
同上
・民間参入の奨励 ・環境配慮 ・電力の安定供給(電力危機の回避) |
・長期発電拡大計画(1995-2010)に基づく、新規発電所(火力/水力)の建設(ディーゼル・石炭・ガス利用)
・送配電制度の開発/改善、短・長期の送電開発計画 ・小規模自家発電のインセンティブによる奨励 ・省エネ基金による啓蒙活動 |
| 1997 ~ 2001年 |
・経済社会発展を促す効率的・競争的な電力部門
・人口80%への電力供給(グリッド電化による) ・電力生産者・消費者間の適切なバランスを確立 ・信頼できる配電制度、送配電ロスの削減 |
・電力セクターの構造改革と民間参入の促進
・電力の安定供給による公・民間投資の維持 ・価格安定化 ・小規模水力発電と火力発電の民間への開放 |
| 1999 ~ 2001年 |
・経済成長に対応し、ベーシック・ヒューマン・ニーズ(BHN)としての電力供給
・民間参入の奨励 ・需要/供給管理と適切価格による省エネ |
・発電・送電・配電の分化による電力セクターの構造改革とそのための政策・法規制の改善
・5発電所計画(2が海外経済協力基金(OECF),3はBOO/BOOT)、風力発電 ・送電システム開発プロジェクト ・地方電化のための配電システムの開発/拡充 ・省エネの啓蒙/電化製品の電力消費基準の確立等 |
| 1999 ~ 2004 年 |
・需要に合う発電能力の拡大(1000MW増加)
・送電・配電システムの開発 ・価格合理化 ・需要管理による省エネ |
・6発電所建設計画(3がOECF・復興金融公庫(ドイツ)(KFW)、2はBOO(Build, Own and Operate)/BOT)
・既存送電網の改修/拡大、新規グリッドステーション建設 ・配電システムの拡大と補強、ロス削減、配電網管理向上 |
(2) 通信
a. 通信分野の概況
通信分野は1990年代に、飛躍的に拡大した(表2.2-10参照)。特に1990年代後半は、最大事業者スリランカ・テレコム(SLT)の電話回線数・電話普及率ともに3倍の伸びを見せたほか、携帯電話等での民間参入も活発で、携帯電話数は9倍に増加した。そして、携帯電話等を含む全体の電話普及率は、1991年と比べ9倍近く上昇した。有線電話・携帯電話の普及率は、インド・パキスタンを上回り、特に携帯電話の普及率はこれらの国々を大きく引き離している。
その要因として、次の2点が挙げられている。
- SLTが1993年に政府所有の有限会社となり、1997年には日本のNTTによる全株式の35%の資本参加を受け入れた。民間企業の資本・技術を積極に取り入れたことで、回線開設期間の大幅な短縮(1/3)や従業員一人当りの回線数の倍増等、SLTのサービス・効率が大きく向上した。
- 市場自由化により民間企業の参入が活発化し、特に参入容易な携帯電話事業では激しい競争が行われ、これが効率化と低価格の実現を可能にし、普及を進めた。
| 1991年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スリランカ・テレコム(SLT) | 電話回線数(1000) | 126 | 204 | 255 | 315 | 456 | 580 | 653 |
| 電話普及率(%) | 0.73 | 1.13 | 1.39 | 1.70 | 2.43 | 3.05 | 3.38 | |
| 国際電話コール(10万分) | 15.6 | 27 | 30.2 | 33.1 | 40 | n/a | n/a | |
| 他の民間セクター (単位1000) |
携帯電話数 | - | 51 | 71 | 115 | 174 | 257 | 451 |
| Wireless local loop phone | - | - | 0.5 | 26 | 68 | 92 | 114 | |
| E-mail/internet subscribers | - | 0.3 | 4 | 10 | 19 | 26 | 40 | |
| 電話普及率(携帯電話等を含む%) | 0.73 | 1.42 | 1.79 | 2.47 | 3.79 | 4.91 | 6.34 | |
b. スリランカ政府の開発計画における通信分野の重点政策
| 開発目標 | 重点政策 | |
|---|---|---|
| 1995 ~ 1999年 |
・需要に応じた通信サービスの全国供給
・コストに基づく料金設定 ・データ-通信を含めた、国内/国際通信の質向上 ・電話回線開設の迅速化、顧客サービスの向上 ・通信プロジェクトでの国内付加価値の増加 |
・市場開放による民間参入の促進
・外資によるSLTの新規回線プロジェクト |
| 1996 ~ 2000年 |
・通信需要への対応、アクセスと質の改善
・電話回線開設の迅速化 |
・外国援助を活用した既存通信設備・通信網の拡大・改修
・通信ネットワーク開発のための長期計画の策定 ・民間参入の促進と競争市場の構築、SLTの構造改革 ・上記のための法規制整備 |
| 1997 ~ 2001年 |
・需要に応じた通信サービスの全国供給
・コストに基づく料金設定 ・データ-通信を含めた、国内/国際通信の質向上 ・電話回線開設の迅速化 |
・SLTの政府企業への転換、株式の戦略的投資家への売却
・電話通信規制委員会による同部門の活動の規制 ・民間参入の促進 |
| 1999 ~ 2001年 |
・最適な通信政策の策定・規制環境の整備
・通信網の地方拡大 |
・通信部門の運営等の自動化
・通信網のレベル向上と既存設備の拡大・改善 |
| 1999 ~ 2004 年 |
1997~2001と同じ | ・通信規制委員会(競争的市場・質の管理を実施)の運営・技術能力の育成
・北部地域の通信ネットワークの拡充と改修 ・新技術・設備導入による国際通信サービスの向上 ・設備拡充等によるデータ-通信サービスの導入と拡充 ・サービスの質と顧客満足度の向上 |
この時期の主な開発目標としては、(1)需要への対応と通信網の全国拡大、(2)質・サービスの向上が挙げられる。そのためにも、携帯電話や無線電話等の新規分野への民間参入を促し、競争的市場を作っていくことが必要だとされた。また、国際通信にも耐えうる質を確保するには新技術・設備の導入が不可欠として、SLTでは外国投資の導入を図っている。1996年からは、法制度整備も重視し、規制担当機関の能力育成の必要性が指摘された。一方、1999年からの6ヵ年計画では、北部地域の通信網の拡充と改修も重点政策の中に含まれた。
1990年代後半の郵便・通信分野の公共投資予算配分(主に通信分野)は、全体の3~6%と少なく、1995~2000年で半減している(図2.2-b参照)。これには、SLTが1992年に独立した機関となり自己資金を開発に利用するようになったこと、その後の外資導入や民間参入が活発であったことが影響していると考えられる。
(3) 港湾29
a. 港湾分野の概要
スリランカには、スリランカ港湾局(SLPA)の管轄の下、コロンボ、トリンコマレ(Trincomalee)、ゴール(Galle)、カンケサントゥライ(Kankesanturai)の4つの港があるが、国際積替え港として拡大する需要に応える施設を持つのは、コロンボ港のみである。1990年代を通し、コロンボ港は全貨物取扱量の9割を占めてきた。
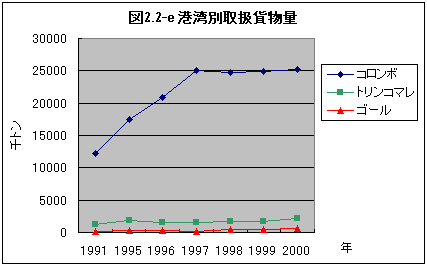
出所:Economic and Social Statistics of Sri Lanka 2001
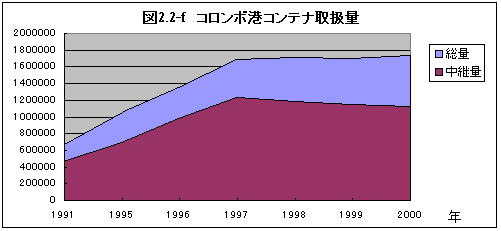
出所: 図2.2.eに同じ
コロンボ港の貨物取扱量、コンテナ取扱量はともに、1991~1997年までは大きく増加したが、以降の取扱量は停滞しており、中継量の全取扱量に占める割合も、低下傾向にある30。その理由として、新規設備投資の停滞、中東諸国の港湾の台頭、国内の民族紛争の激化があげられる。1998年のコロンボ港のコンテナ港としての実績は世界第24位である。
港湾分野の収益状況は、1991~2000年にかけて総従業員数が微増だったのに対し、収入・収益は大きく伸びた(表2.2-12参照)。しかし、他国の港湾と競争していくためには、効率性の改善が必要とされている31。
| 1991年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入 (百万ルピー) |
コロンボ | 3,609 | 4,582 | 8,775 | 10,731 | 13,221 | 14,552 | 14,079 |
| ゴール | 51 | 75 | 81 | 81 | 218 | 225 | 320 | |
| トリンコマレ | 92 | 163 | 151 | 162 | 199 | 311 | 318 | |
| 合計 | 3752 | 4,820 | 9,007 | 10,974 | 13,638 | 15,089 | 14,717 | |
| 収益(百万ルピー、税引き前) | コロンボ | N/A | N/A | N/A | 2.924 | 5,059 | 5,236 | N/A |
| ゴール | N/A | N/A | N/A | -71 | 32 | 35 | N/A | |
| トリンコマレ | N/A | N/A | N/A | -73 | -42 | 52 | N/A | |
| 合計 | N/A | N/A | N/A | 2,780 | 5,048 | 5324 | N/A | |
| 従業員数 | コロンボ | 16,486 | 14,851 | 15,589 | 17,101 | 16,964 | 17,075 | 17,411 |
| ゴール | 701 | 779 | 841 | 831 | 769 | 777 | 758 | |
| トリンコマレ | 1,125 | 862 | 1,046 | 1,101 | 1,044 | 1,078 | 1,175 | |
| 合計 | 18,312 | 16,910 | 17,476 | 19,033 | 18,777 | 18,930 | 19,344 | |
収益はAnnual Report 1999 Central Bank of Sri Lankaによる
b. スリランカ政府の開発政策における港湾分野の重点政策
1990年代中盤までの港湾施設の拡張は、日本からの援助に依存していた。それ以降は民営化路線に転換し、1995年のPIPでも商業的コンポーネントの開発はBOO/BOTでの民間投資で行うとしている。
1995~1999年の間の主要な開発目標は、(1)コロンボ港の規模拡大と効率/生産性の改善による地域ハブ港への転換と、(2)地方港の開発・整備だった。そのためには、施設拡充と基盤整備、技術・マーケティング面の向上が必要であり、外国援助だけではなく、BOO/BOTによる民間参入を積極的に促進する方向が明確に打ち出されている。
| 開発目標・課題 | 重点政策 | |
|---|---|---|
| 1995 ~1999年 | ・コロンボ港の規模拡大
・効率/生産性の改善と、国際競争力の向上 ・地方港(ゴール、トリンコマレ)の開発 |
・資金・技術・マーケティング面での民間参入
・コロンボ港開発計画の更新 ・セイロン船舶会社の民間とのJVによる財務改善 |
| 1996 ~2000年 | 同上
・コロンボ港の地域ハブ港への転換、中継港としての能力拡大と近代化 |
・コロンボ港の施設改善と拡充、ソフトウェアーの向上
・BOO/BOTによる民間参入の促進 ・SLPAによるマーケティング戦略の採用 ・コロンボ港開発計画の更新 |
| 1997年 港湾セクター政策 |
・コロンボ港の地域ハブ港への転換
・地方港の開発・整備 ・新港の建設 |
・国内貨物積替え施設・効率的な貨物取扱の基盤の整備
・沿海域の航行支援施設の整備 ・港間の相互補完機能の充実 |
| 1997 ~2001年 | ・コロンボ港の地域ハブ港への転換
・地方港の開発 |
・民間投資の促進 |
| 1999 ~2001年 | ・コロンボ港の規模拡大と効率改善
・地方港の開発 ・海洋汚染防止 |
・コロンボ港の施設拡充(民間開発業者も含む)
・安全航行のための港湾整備 ・海洋汚染防止局の強化 |
| 1999 ~2004年 | 1997年の港湾セクター政策に同じ
・港湾セクターの能力増強と効率改善 |
・民間参入の促進(11計画中、2計画がBOT)
・港間の相互補完機能の充実 ・ジャヤ(Jaya)・コンテナ・ターミナルの分社化 |
(4) 運輸
a. 運輸分野の概況
運輸分野は、1995年は、GDPの1割、公共投資の3割、就業者数の1/7を占める32。設備投資・維持に大きな資金を必要とする運輸分野は、1990年代前半、政府投資支出の4割がドナー援助でまかなわれ、政府の負担を減じてきた33。
ア)道路
図2.2-gは、スリランカの道路網の状況を、AからEの道路区分とともに示す。1985~1995年の間に、Bクラスの主要道路が4割延長し、Cクラス道路が減少しているほかは大きな変化は見られない。これは、政府の道路・鉄道部門への公共投資が主に既存設備の改修維持に回され、外国援助も中央と地方を結ぶ幹線道路の改修・修繕に焦点が合わせられていたこと、したがって、新規道路の建設がほとんどなされなかったことが影響している。州別では、A・Bクラスの道路は西部州から南部地域にかけて広がり、北部・東部での密度は低い。スリランカ全体の舗装率は1997年で40%で、インド・パキスタンより低いがバングラデシュよりは高い34。
一方、車両台数は1997~2000年にかけても年々増加しており、人口千人当りの車両保有数、道路1キロ当りの保有数ともに、インド・パキスタンを大きく上回っている35(図2.2-h参照)。1999年には、バスも含めた道路交通の割合は、全交通利用者の9割以上に上った。車両の増加や違法駐車などにより、都市部での交通渋滞や交通事故の増加が起こっており、中央銀行はバイパスや高架道路の建設、交通管理システムの整備、鉄道などの公共輸送の充実を対策として指摘している36。
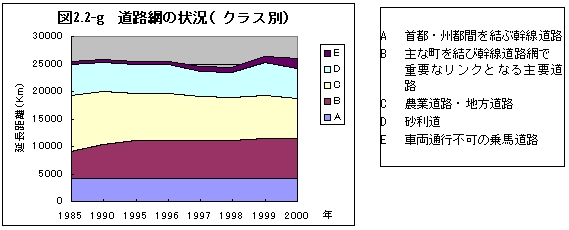
出所: Economic and Social Statistics of Sri Lanka, 2001
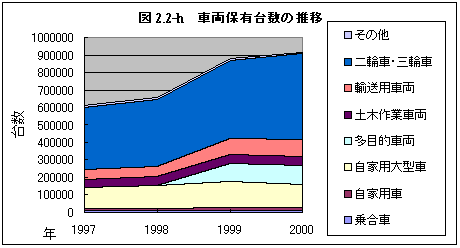
出典: 図2.2-gと同じ
注: * 人キロ数=総収入/キロ当たりの平均料金 (単位 百万人キロ) ** 乗車率=乗客キロ数/座席キロ数 |
公共輸送としてのバス交通は、1979年に民間参入を認めてから、大きく伸びた。一方、 1989年以降に国営会社から人民企業(Peoplized Bus Companies)となった93のバス企業は、1995年に11の地域バス会社に再編され、リストラ計画が実施された。このリストラ後、運行率の低下が見られたが、1999年以降は回復している。しかし、地域バス会社は、1998~1999年にかけても赤字が拡大した37。小規模で多数存在する民間バス会社は、運行実績・キロ数ともに地域バス会社を上回っているが、定員オーバーでの運行や暴走、サービスの悪さ等が指摘されている38。
イ)鉄道
鉄道は、スリランカ国有鉄道(SLR)が運営している。軌道総延長は、1991年の1,462キロに対し2000年も1,463キロと変わっていないが、車両数は減少している39。鉄道旅客数が全道路旅客数に占める割合は、1976年から1995年に18%から6%に低下したが、旅客数そのものは減少していない40。ただし、設備の老朽化・劣化を原因としたダイヤの乱れや定員を上回る混雑率などサービスの質の低下が指摘されている。一方、貨物輸送距離は、トラック輸送の台頭を受けて距離数でも大きく減少した(図2.2-i参照)。SLRの営業赤字は常態化しており、1990年代前半も年間7億ルピーという大きな負債を抱えていた。
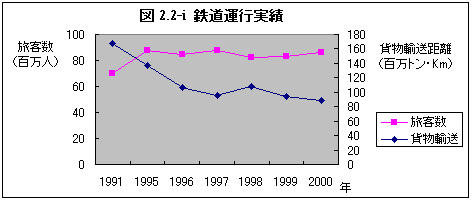
出所: 図2.2-gと同じ
ウ)空港・航空
スリランカ空港・航空公社(SLA)が管理する2空港(バンダラナイケ(Bandaranayake)国際空港、ラトマラナ(Ratmalana)空港)の他に11の軍飛行場がある。その空港/航空部門は、国際線を主としており、国内では唯一の民間航路だったコロンボ-ジャフナ線が内戦の影響で長らく運休している。
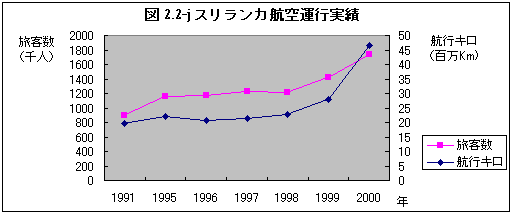
出所: 図2.2-gと同じ
1990年代、スリランカ航空は旅客数・航行キロ数ともに伸ばしてきた。特に1998年の民営化後の1999~2000年は、年間伸び率が22%、66%と大きい(図2.2-j参照)。スリランカ航空がスリランカに入出国する全旅客に占める割合は、1995年の48%から1999年には60%に拡大した。しかし、これは民営化当時の旅客機増加によるもので、その間の稼働率は内紛激化の影響も受けてむしろ低下した41。
b. スリランカ政府の開発計画における運輸分野の重点政策
この期間の運輸部門での開発目標は、下記にまとめられる。
- 拡大する需要への対応
- 生産性・効率・競争力の向上
- サービスの質の改善
- 農村部の運輸サービスへのアクセスの改善
- 環境汚染の削減
上記に対する主な政策は次の通りである。
- 既存インフラ・設備の改修・維持・規模拡大・近代化
- 新規インフラ・設備・機材への投資
- 民間投資の拡大、民間業者の参入や競争の促進、国内関連産業の育成
- 事業機関の制度の整備と能力の強化、商業化とビジネス志向の強化(鉄道)
- 企業合併・統合、会社化や組合化など、業界の再編成(バス)
- 適切な料金設定、社会性・公共性の高い非採算部門への政府補助
| 開発目標 | 重点政策 | |
|---|---|---|
| 1995 ~ 1999年 |
・需要増加に対応する効率的な運輸システムの供給
・近代技術・資源の合理的利用による生産性・運営効率の向上 ・各運輸サブセクターの相互補完性の拡大 ・環境汚染を起さない人/物の移動システムの開発 ・農村部の運輸アクセスの改善とそれによる都市/農村地域の統合 |
・運輸インフラ(鉄道・道路・セクター計画調整)への民間投資、そのための法規制整備やインセンティブの供与・指導
・運輸インフラにおける国内建設産業の育成 ・既存設備の改修/維持, 新規投資でのコスト削減/資本収益性の分析 |
| ・SLRの商業化と財務改善・能力拡大、車両の計画的な更新
・コロンボ国際空港の拡充、国内空港開発への民間参入 ・地方道路への投資 |
||
| 1996 ~ 2000年 |
・需要増加への対応と効率改善 | ・既存インフラ/設備の維持
・構造改革による資源投入の確保 ・規制枠組みの計画/実施、開発計画の策定 ・民間投資の拡大 ・コスト・投資収益を反映した料金設定 |
| ・SLRの商業化とビジネス指向化、車両の近代化
・人民バス会社の再編成によるサービス改善と拡大、バス事業者の会社/組合設立の奨励 ・地方道路の改修 ・道路建設/運営へのBOO/BOTによる民間参入 ・コロンボ国際空港の拡充、国内空港開発への民間参入 |
||
| 1997 ~ 2001 |
・サービスの顧客指向・効率・競争力の向上
・農村の運輸サービスへのアクセス改善 ・主要地帯での交通渋滞の緩和 ・環境汚染の削減 |
・事業者・利用者に適切な料金設定
・(社会的義務としてのサービスは政府が補償) ・サービス・ルート決定に国民・乗務員・事業者が参加 ・公共インフラを利用しての民間による運営 |
| ・既存道路網・橋の改修、州・地方道路の改善
・主要地帯/高速道路へのBOO/BOTによる民間参入 ・非採算バスルートへの補助金増加、バス車両の供給 |
||
| 1999 ~ 2001年 |
・質の高い運輸サービスの供給と維持、そのための効率向上・競争的環境作り
・道路システムの改善と維持 ・農村の運輸サービスへのアクセス改善 |
・正当と見なされる公共交通への政府の資金供給
・農村部など非採算ルートへの補助金 ・民間参入の奨励、コントロールした自由化 |
| ・スリランカ航空の構造改革による競争力の強化
・国際空港の設備改善と国内空港とのリンク促進 ・国内線の自由で競争的な環境作り ・スリランカ鉄道の能力増強、制度強化、乗客設備の改善 ・機材購入や設備改修によるバスサービスの質の改善 ・道路舗装の強化と維持、道路網の運送能力の拡大、既存の橋梁の改修、高速道路の開発、州・地方道路の改善 ・交通管理システムの導入による渋滞緩和 |
||
| 1999 ~ 2004年 |
1997年のPIPと同じ | 1997年のPIPと同じ
・民間参入の奨励 |
| ・既存設備の改修や新規車両・インフラ導入によるSLRの能力増強、SLRの赤字削減、鉄道事業の商業化、不動産開発
・公的・民間バス会社の制度能力の強化、地方バス会社のビジネス計画の作成 ・交通管理システムの導入、道路の質改善・改修 |
なお、環境汚染の削減に対しては、交通管理システムによる渋滞緩和の他に、特に目立った政策は見られない。
1996年のPIPでは、運輸部門での過去の政策や公共投資は、拡大する運輸需要への対応や効率改善が十分でなかったと分析し、理由として、不適切な投資、一貫した政策の下での革新的な計画の欠如、構造改革への意思のなさを挙げている。そして、短期的には既存のインフラ・設備を維持するための投資を行うが、中期的には、需要に見合う資源投入を確保するための構造改革が必要としている。また、政府資金のみでは限界があるため、民間投資の拡大がより重要性を持つと結論付けている。
一方、民間投資の拡大や民間参入は、政府の料金政策に左右されることも指摘されている。運輸サービスへの民間参入では、民間部門の収益性と利用者の利益のバランスをどう取るかが課題だとしている。実際、スリランカ国有鉄道と地方バス会社は、赤字体質が常態化しており、その理由に低料金が挙げられている。1996年のPIPでは、コストだけでなく投資収益をも盛り込んだ料金設定が政策に含まれたが、1997年以降は、「事業者・利用者に適切な料金設定」を行うとした。社会的義務としてのサービスは政府が補償するとの考えから、正当化される場合は非採算部門・ルートへの政府補助は行うと明記し、農村部でのバス交通を例に挙げている。
道路部門では、既存設備の改修・維持を重要視するものの、州・地方道路への新規投資や、高速道路の建設も政策に挙げている。料金徴収が可能で収益性のある高速道路にはBOO/BOTによる民間参入、州・地方道路にはドナー支援を求めているのも特徴である。また、道路建設・改修を行う建設業者が国内で育っていないことが高コストの要因だとして、その育成を促している。バス交通では、零細規模の民間業者の質を改善するために会社化・組合化を奨励するとともに、最低バス保有数を含む規制を検討している。
鉄道部門では、SLRの民営化によって経営・財務体質の改善を図るとともに、車両等の近代化や拡充をドナー支援も含めて計画している。しかし、地方バス会社もSLRも、料金制度の改定には慎重な態度をとっている。
空港・航空部門では、スリランカ航空の民営化が実施されたが、これがうまくいったのは、民営化前の段階で既に収益を上げられる体制になっていたことが大きいと考えられる。国際空港の拡充とともに、民間参入も含めて国内空港の開発・整備を行い、国内航空路線を拡大する計画を持っている。
4)人的資源開発
a. 人的資源開発分野の概況
スリランカの初等中等学校教育の制度は、小学校5年、中学校6年、高等学校2年に分かれている。このうち義務教育は、中学校前期4年を含めた9年間である。教育は小学校から大学まで、国または地方自治体が運営する公立校では授業料が無料である。スリランカは多くの途上国と比べ、高い教育指標を示し、1999年度における男女の識字率はそれぞれ92.8%、88.0%だった42。初等中等教育と高等教育における女子の就学率は他の途上国に比べて高く、ほぼすべての女子が初等教育を修了し、多くが中等教育を修了している。大学教育における女子の就学率も、男子とほぼ同水準である。しかし、政府の教育支出のGDPに占める割合は減少(1960年代の5%から現在は3%)しており、他の途上国の平均値よりも低い水準となっている。このため、全般的な教育の質の低下や教育の地方格差が問題となっている。大学・技術職業訓練が労働市場の需要に適応していないことも指摘されている。
ア)初等中等教育
スリランカの初等中等教育に関する指標を下表2.2-16に示した。
| 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総学校数 | 10520 | 10583 | 10710 | 10779 | 10888 | 10936 | 10983 | 10722 | 10694 | 10611 |
| (公立校) | 9998 | 10042 | 10160 | 10191 | 10283 | 10312 | 10358 | 10088 | 10057 | 9972 |
| (その他) | 522 | 541 | 550 | 588 | 605 | 624 | 625 | 634 | 637 | 639 |
| 総生徒数(千人) | 4258 | 4289 | 4303 | 4328 | 4350 | 4254 | 4260 | 4279 | 4277 | 4337 |
| (公立校、千人) | 4135 | 4159 | 4172 | 4194 | 4216 | 4119 | 4124 | 4136 | 4134 | 4190 |
| (その他、千人) | 123 | 130 | 130 | 134 | 134 | 134 | 136 | 143 | 143 | 146 |
| 入学者数 | 388315 | 359228 | 354390 | 343279 | 330426 | 322858 | 347787 | 345531 | 343230 | 331643 |
| 総教員数(千人) | 177 | 182 | 193 | 195 | 195 | 193 | 187 | 196 | 196 | 199 |
| (公立校、千人) | 170 | 175 | 18 | 187 | 187 | 185 | 179 | 188 | 188 | 191 |
| (その他、千人) | 6.5 | 6.9 | 7.0 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 8.6 |
| 生徒対教員比 | 24.0 | 23.5 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.0 | 22.7 | 21.8 | 21.7 | 21.7 |
各指標の、年代による大きな変化は見受けられない。初等教育就学率は1985年の時点で既に100%を達成しており、生徒対教員比も21.7と適正な水準にある。しかし、適切な訓練を受けた教員の不足、遠隔地域における教員や教育設備の不足等の問題点が指摘されている。
イ) 大学教育
スリランカの大学教育に関する指標を以下の表に示した。
| 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 学生数 | 22260 | 31447 | 30637 | 30764 | 31241 | 32800 | 38594 | 40174 | 41584 | 48296 |
| 教員数 | 2090 | 2285 | 2384 | 2525 | 2808 | 2927 | 3108 | 3113 | 3228 | 3241 |
| 入学者数 | 8970 | 8900 | 7849 | 8015 | 8663 | 9787 | 10450 | 10779 | 11896 | 11805 |
| 卒業者数 | 5386 | 4419 | 5059 | 5750 | 4206 | 6233 | 6705 | 7834 | 8787 | - |
| 総支出(百万ルピー) | 1470 | 2351 | 2581 | 2597 | 2914 | 3434 | 4386 | 5127 | 4995 | 4780 |
| (開発支出) | 390 | 966 | 772 | 548 | 630 | 970 | 1331 | 1519 | 1353 | 1395 |
| (経常支出) | 1080 | 1385 | 1809 | 2049 | 2284 | 2464 | 3056 | 3608 | 2642 | 3385 |
1990年代初めに大学は9校あったが、その後4校が新設され、現在では合計13校になっている。学生数も1990年代初めから現在までに約2倍に増加した。2001年度は大学受験資格を持つ者のうち、16%が大学へ入学している。しかし、労働市場のニーズに大学教育の内容が必ずしも適合しておらず、大学卒業者の多くが失業していることが報告されている43。スリランカでは、今後の政策としてIT産業の進展を企画し、その人材育成のために、大学におけるIT教育の整備が進められている。
ウ) 技術・職業教育
スリランカの職業教育機関のほとんどは政府によって運営されている44。技術・職業教育の受講者層や分野は多種多様で、受講者には失業者、農村女性、学校中退者、貧困層なども含まれる。
b. スリランカ政府の開発計画における人的資源開発分野の重点政策
この期間の主な開発目標としては、(1)教育の地域格差の是正、(2)教育の質の向上、(3)就学率の向上、(4)高等教育の労働市場の需要との適合性の向上が挙げられる。これらの目標を達成するためには、遠隔地域への適正な予算配分、教員派遣、教員の採用・研修制度の改善、義務教育制度の強化、非就学児童や中途退学者への教育支援、労働市場を考慮した高等教育プログラムの策定が必要とされた。1997年からのPIPには、政府の教育支出を4.5%に増加させることが具体的に提言された。さらに、教育関連政府機関の行政構造の改善が必要であることが1999年からのPIPに含まれている。
| 開発目標 | 重点政策 | |
|---|---|---|
| 1995~1999年 | ・学校施設の地域格差の減少
・教育の質の向上 ・初等教育の就学率向上 ・国家の科学技術力向上に対応できる高等教育の実施 |
・遠隔地域への教育サービスの拡張、就学者数による予算配分の設定
・義務教育制度の強化 ・公式、非公式の教育施設の設備拡張、人材の確保、教員の質的向上支援 ・初等教育で識字、算術、問題解決能力向上を支援し、中等教育における選択肢、可能性を拡大 ・適切な教員採用制度による教員採用の推進 ・高等教育と労働市場の連携を保ち、適正な技術力養成を推進 ・大学教育の機会の拡大、設備拡張、カリキュラム改善の推進 |
| 1996~2000年 | ・学校施設の地域格差の減少
・教育と教員の質の向上 ・中等教育の修了率向上 ・労働市場における人材の需要と供給の適合性の向上 |
・遠隔地域への教育サービスの拡張、就学者数による予算配分の設定
・中等教育中途退学者を対象とした教育施設設置の支援 ・教員候補者の研修制度の改善 ・生徒対教員比の増加(22:1から30:1へ)、遠隔地域赴任のインセンティブ創出による遠隔地域への教員派遣の推進 ・労働市場のニーズを把握し、技術・職業教育のカリキュラムの改善 |
| 1997~2001年 | ・教育の質の向上
・教育施設の地域格差の減少 ・大学教育の機会の拡張 ・技術・職業教育の効率向上 |
・義務教育制度の強化
・教員採用制度、配置制度の改善による、教員の遠隔地域赴任、経費削減の推進、教員候補者の研修制度の改善 ・教育施設のインフラ整備推進 ・入学試験制度見直しによる高等教育機会の拡大 ・カリキュラム見直しによる、大学教育の改善 ・大学の技術・専門分野への入学者数の増大 ・政府の教育支出をGDPの4.5%に拡大 ・セクター別の予算配分設定で、技術・職業教育の適切な資源活用を推進 ・技術・教育機関と労働市場の連携を推進 |
| 1999~2001年 | ・教育機会の拡大
・教育と教員の質の向上 ・大学教育の質と労働市場の需要との適合性の向上 ・技術・職業教育の質と労働市場の需要との適合性の向上 |
・非就学児童のための学校施設の拡張と成人への識字教育支援
・初等中等教育におけるカリキュラムの改善と教材や設備の充実 ・教員、教員候補者への研修制度の改善、研修施設や研修プログラムの充実 ・教育関連省庁の行政構造の改善 ・大学における設備の拡張、コースワークの多様性の推進 ・技術・職業教育機関の計画と行政部門の強化、カリキュラムや教育プログラムの改善 |
| 1999~2004年 | 同上 | 同上 |
5)保健医療
a. 保健医療分野の概況
スリランカの人口統計と保健医療指標を表2.2-19に示す。
スリランカは保健医療部門で、比較的高い成果を上げている。1999年度の平均寿命は、南アジア地域平均の1961年と比べ高い水準であり、人口増加率は1%以下となっている。周産期死亡率も、GDPが同水準の途上国と比べ、非常に低い。スリランカでは、早い段階から乳児死亡対策、周産期死亡対策、感染症対策を実施しており、近隣諸国の中では比較的良好な保健指標を達成している。
しかし、児童の栄養失調、妊産婦の鉄分欠乏症、ヨウ素欠乏症、マラリアといった問題は依然として残されており、この期間もこれらの問題への対応が必要とされた。平均寿命の増加にともなって、糖尿病や心臓疾患のような成人病の増加も報告され、これらへの対策も課題だった。
| 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総人口(万人) | 1743 | 1765 | 1789 | 1814 | 1834 | 1855 | 1877 | 1904 | 1936 |
| 出生率(1000人あたり) | 20.5 | 19.9 | 19.9 | 18.9 | 18.6 | 17.9 | 17.4 | 17.3 | 17.3 |
| 死亡率(1000人あたり) | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6.5 | 6.1 | 5.9 | 6.0 | 5.7 |
| 周産期死亡率(出産1万あたり) | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | - | - | - | - |
| 乳児死亡率(1000人あたり) | 17.9 | 16.3 | 16.9 | 16.5 | 17.3 | 16.3 | - | - | - |
| 平均寿命(男/女) | - | - | - | 69.5/ 74.2 | - | - | 71.0/ 76.0 | 71.0/ 76.0 | 69.5/ 74.2 |
| 医師一人あたりの人口 | - | - | - | 3914 | - | - | 3150 | 2739 | - |
| 保健医療セクター支出の政府支出に占める割合 | - | - | - | 5.59 | - | - | 5.68 | 5.62 | 6.17 |
b. スリランカ政府の開発計画における保健医療分野の重点政策
この期間における保健医療分野の開発目標は、1)保健医療サービスの地域格差の改善、2)保健医療サービスの質の向上であった。これらの目標を達成するためには、病院施設の改善に加え、ニーズを把握し適正な医療サービスを施すことが必要とされた。1998年に策定された「貧困フレームワーク」の中では、農村部における保健医療サービスの質の向上を貧困削減戦略として挙げ、予防保健の強化を打ち出している。また、資源の有効的な活用、医療機関の構造調整による効率改善が提言されている。
| 開発目標 | 重点政策 | |
|---|---|---|
| 1995~1999年 | ・保健医療サービスの地域格差の改善
・保健医療サービスの質の改善 |
・マラリアを含む感染症対策の推進
・メディアを活用した啓蒙活動の推進 ・障害者、高齢者、その他の特別なニーズを持つ人々のための保健医療サービスを供給 ・プライマリー・ヘルス・ケアの充実 ・専門医の技術向上の推進 ・データに基づく適正な政府支出の推進 |
| 1996~2000年 | ・保健医療サービスの質の向上 | ・マラリアを含む感染症対策の推進
・医療従事者の技術向上・保健医療教育施設の改善 ・病院施設の設備拡張 ・学校での健康促進プログラムの推進 ・IT導入による国家保健医療情報システムの開発 |
| 1997~2001年 | 同上
保健医療サービスの地域格差の改善 ・保健医療サービスの拡張 |
・研究活動と研修制度の強化
・ニーズを把握し、適切なサービスの供給を推進 ・保健医療関連機関の行政制度調整による効率の改善 ・資金調達、運用方法の改善 |
| 1999~2001年 | ・保健医療サービスの地域格差の改善
・保健医療サービスの質の向上 |
・各州の病院施設の改善
・特別なニーズを持つ人々への保健医療サービスの拡張 ・予防・教育プログラムの強化 ・地域でのサポート制度医療機器供給、輸血サービス等)の強化 ・資源の効率的な活用の推進 |
| 1999~2004年 | 同上 | ・各州の病院施設の改善
・特別なニーズを持つ人々への保健医療サービスの拡張 ・学校における健康促進プログラムの推進 ・保健医療関連機関の行政構造調整による効率の改善 ・資源の調達、運用方法の改善 |
6)環境
a. 環境分野の概況
スリランカでは、開発規模が小さかったこともあり、20世紀初頭まで環境問題が開発の持続可能性に影響を与えることはなかった。しかし、その後の人口増加や経済発展は、自然資源への悪影響を強めており、環境の質を低下させ、その持続可能性に多大な影響を与えるまでになっている。自然資源への悪影響は、(1)貴重な外貨収入源である茶とゴムの生産性低下、(2)森林資源と水資源の質的低下 (3)不適切な沿岸域の観光開発、(4)公害対策が不十分な工業開発、(5)都市域の劣悪な居住環境などの直接的、間接的な原因となり、国民への影響が懸念されている45。
b. スリランカ政府の開発計画における環境分野の重点政策
PIPに示された環境分野での重点政策を下記に示す。
この期間の環境分野では、国家の持続的発展の維持、健全な居住環境の整備が開発目標とされ、重要な政策として位置付けられていたと考えられる。そのことは持続的発展のためには、開発ニーズと環境保護のバランスを保ちつつ維持していくことが不可欠であり、この目標を達成するには、公害や環境破壊の抑制と住民の環境・経済の問題に対する意識の向上等が必要であるとPIPで言及され、政府・公共機関・民間企業・一般市民、それぞれを対象とした政策が提言され、環境関連法規の整備についても言及されていることからも明らかである。
健全な居住環境の整備では、(1)住居施設の整備、(2)上下水道・都市排水・廃棄物処理等のインフラおよびサービスの整備、(3)建設産業の効率化、(4)都市開発計画推進が重点政策とされた。特に、居住設備の整備では、農村部・都市部それぞれにおける異なった所得層の人々のニーズを汲み取り、質・量的な改善を推進することが必要だと考えられた。
具体的な環境政策の優先課題は、1995年から1998年の国家環境行動計画(NEAP)で打ち出されている。これらの課題には、(1)土地・水資源の一体管理、(2)森林と生物多様性の保持、(3)都市・産業汚染の管理、(4)沿岸資源管理、(5)エネルギー保全が含まれる。国家および地域レベルのすべての開発プロセスで、これらの項目を考慮することを目標としている。
| 開発目標 | 重点政策 | |
|---|---|---|
| 1995~1999年 | ・開発ニーズと環境保護のバランスを保ちつつ持続的発展を維持
・居住環境の整備 |
・環境分野関連機関の役割分担を整備し、機関の権限を拡大
・経済・社会状況の変化に即した環境資源の管理の推進 ・環境を維持、改善するための適正な政策や制度を推進 ・環境整備への住民の参加を推進 ・都市・農村部の居住ニーズを汲み取り、居住設備の質的・量的改善を推進 ・制度改革、適正な資金運用、利用者の積極的な参加による上下水道サービスの効率改善 ・建設企業の適正な公共事業参入による資金の有効利用と、建設産業の効率向上 |
| 1996~2000年 | 同上 | ・政府機関と民間企業における環境対策の策定と実行促進
・環境に関する法律、政府の組織構造、行政構造を改善 ・環境に関する政府権限の地方分権、地方政府職員の研修の推進 ・民間投資促進による都市部の住居施設の増加と、政府援助による貧困層住宅設備の推進 ・建設技術向上、建設企業の適正な公共事業参入等による資金の有効利用と、それによる建設産業の効率向上 ・上下水道インフラ整備と、地方政府による水管理・運営を支援 ・有効な土地利用を推進 |
| 1997~2001年 | ・経済発展による環境への悪影響を最低限に維持
・居住環境の整備 |
・公共機関と民間企業における環境への配慮を推進
・土地の適切な利用推進 ・環境問題の現状と、開発活動が居住環境と資源に及ぼす影響に関する正しい情報を一般市民に提供 ・民間企業による環境保護関関連の法律の遵守を促進 ・国際条約に基づいた環境・資源保護の推進 ・環境保持の概念をすべての開発プロジェクトに反映 ・民間投資促進による都市部の住居施設の増加と、政府援助による貧困層住宅整備の推進 ・建設技術の向上、資金の有効利用による建設産業の効率改善 |
| 1999~2001年 | ・公害、環境破壊の抑制
・居住環境の整備 |
・環境に関する意識向上教育の国家計画の策定
・土地の適切な利用推進 ・児童、都市住民、企業、政治家を対象とした環境教育プログラムの実施 ・関連機関の環境整備に関する能力向上 ・上下水道・都市排水・廃棄物処理のような環境インフラの整備 |
| 1999~2004年 | ・公害の抑制
・居住環境の整備 |
・公共機関と民間企業における環境への配慮を推進
・環境問題の現状、開発活動が居住環境と資源に及ぼす影響に関する正しい情報を一般市民に提供 ・民間投資促進による住居施設の質的・量的改善を推進 ・持続的開発への配慮をすべての経済社会開発プロジェクトとプログラムにおいて推進 ・上下水道・都市排水・廃棄物処理のような環境インフラの整備と、地方政府による水管理・運営を支援 ・建設技術の向上、資金の有効利用による建設産業の効率改善 ・都市開発計画に則った資金投資の促進 |
12 World Bank, Country Assistance Strategy 1998, p.3
13 1997年以降の開発計画では、グローバル経済/自由化への対応が重視されている。福祉プログラムについては、貧困層が生計を創出できる力を動員することを目的とし、新に脆弱な貧困層をターゲットにするとしている。
14 1998年に経済成長率が4.6%と鈍化した後の1999~2001年のPIPでは、経済成長の復活により重点が置かれ、経済インフラへの投資が最優先分野と明記された。しかし、その他のPIPでは、経済インフラについては民活参入を促進し、政府投資は民間が参入するまでの期間において行うこと、これにより、政府投資のより多くを社会分野(教育・保健・農村インフラ・環境等)に振り向けることが示されている。
15 例えば、国内資本形成での民間投資の割合の増加、国内貯蓄率の増加、財政赤字/GDP比の削減、輸出/GDP比の増加等である。
16 1995年の数値は1995~1999年のPIP, 1996年の数値は1996~2000年のPIP, 1997年から2001年までの数値は1997~2001年のPIPによる。1999~2001年のPIPと1999~2004年の6ヵ年開発計画にはこのような公共投資計画予算は示されていない。1997年より追加された州インフラ予算は、それまで農業予算に含まれていたプランテーションインフラ、居住環境予算に含まれていた総合農村開発計画と州・地域開発予算、そしてサムルディ貧困対策からなる。
17 ただし、予算の大半が実施中のプロジェクト予算であるため、予算配分は過去の政策に大きく影響され、その時期の重点分野や政策がすぐに反映される訳ではない。
18 Central Bank of Sri Lanka, 1999、Institute of Policy Studies 2002、World Bank 2002, 各PIP他
19 増加の理由として、漁民への船・機材の援助が挙げられている。
20 Central Bank of Sri Lanka, 1999
21 例えば、1995~1999年の関税は、米(7.63~46%)、ジャガイモ(28~148%)、玉ねぎ(28.75~138%)と大きな範囲で、7回に渡り上下しながら変動している。("Policies and their Implications for the Domestic Agricultural Sector of Sri Lanka: 1995-2000", Institute of Policy Studies, 2002と"Sri Lanaka: Promoting Agricultural and Rural Non-Farm Sector Growth (draft)" World Bank, 2002より) 現地調査においても、果物・野菜栽培の普及が進まない理由として、市場価格の不安定さが第一に挙げられていた。(ガンバハ農業普及改善事業の対象グループ、ペラデニア大学農学部長への聞取りより)
23 ATCは、EUのように繊維・衣類製品の輸入規制を実施している国を対象に、4段階による自由化を規定している。まず1995年1月1日に1990年の輸入数量の少なくとも16%(第1段階)、1998年に17%(第2段階)、2002年1月1日に18%(第3段階)、残りを2005年1月1日までに自由化(第4段階)するスケジュールとなっている。
24 なお、繊維・衣料については、糸・生地等原料の輸入依存度の高さが指摘されているが、繊維・衣料・皮革の付加価値は、1991年の23%から2000年には41%と増加し、改善傾向を見せた。
25 例:規制緩和、貿易・通関手続き等の簡素化と迅速化、関税の統一、税制の簡素化、減税等のインセンティブ、工業団地等のインフラ整備
26 例: 技術経営指導、人材育成、インセンティブ、研究開発の商業化、科学技術研究機関の近代化
29 PIPには、港湾は経済インフラとして運輸とは別に挙げられているため、本節でも同じ扱いをする。
30 1991~2000年の間で70~65%と低下している。
31 Annual Report 1999, Central Bank of Sri Lanka
32 1996~2000のPIPより
33 1995~1999のPIPより
34 1997年の道路舗装率、パキスタン58%、インド46%、バングラデシュ12%、フィリピン20%と比較したもの。(World Development Indicators 1999, World Bankより)
35 2000年の人口千人当たりの車両保有数は、インド・パキスタン両国が8台であるのに対し、スリランカは34台、道路1キロあたりの車両保有数は、インドが3台、パキスタンが4台であるのに対し、スリランカは7台である。(World Development Indicators 1999, 2002, World Bank)
36 Annual Report 1999, Central Bank of Sri Lanka
37 地方バス会社の赤字は、料金値上げが認められにくいという問題が背景にあると考えられる。(Annual Report 1999, Central Bank of Sri Lanka)
38 JICA内部資料。
39 同期間において機関車(270~216両)、客車(1338~1,103両)、貨車(2,857~2,090両)共に、減少している。
40 JICA内部資料。
41 旅客の稼働率は71.7%から67%へ、貨物の稼働率は68.8%から66.5%に低下している。
42 国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)統計局
43 Annual Report 2001, Central Bank of Sri Lanka
44 主な教育機関としてはDepartment of Technical Education and Training (DTET)、Sri Lanka Institute of Advanced Technical Education (SLIATE)、Vocational Training Authority of Sri Lanka (VTA)、National Institute of Technical Education (NITE)が含まれる。
45 国別環境情報整備報告書・スリランカ(平成7年3月・JICA企画部)

