4-3.日本の青少年の人材育成・日本社会への還元
ここでは、下記のA~Cの点検項目に基づき「日本の青少年の人材育成・日本社会への還元」対する評価分析を行っていく。
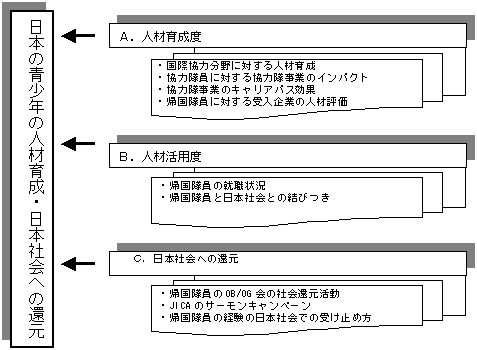
(1) 国際協力分野に対する人材育成
帰国隊員のアンケート調査結果によると、「派遣前に協力隊の活動に期待していたことは何か」(複数回答あり)という問いの中で、“国際協力関係の仕事に就くためのステップ”と回答した割合は9.2%であった。しかしながら、現在国際協力の仕事に携わっていない帰国隊員を対象に、国際協力分野の仕事に対する興味を確認したところ、“できれば国際協力に携わる仕事をしてみたい”という項目に対する回答は全体で58%、隊次別には昭和56年度の割合が一番多く76.7%であった。このことは、協力隊に参加したことにより国際協力分野に関心を抱き、できればこの関係の分野に就職先を求めたい人材が潜在的に多くいることを示している。しかし「協力隊に参加したことが人生に影響しているか」(複数回答あり)という問いに対して、“国際協力分野で働くきっかけとなった”との回答は13.0%で、協力隊事業への参加がきっかけとなり実際に国際協力分野での就職ができる割合は低い。
協力隊員にとって協力隊事業への参加は必ずしも“国際協力分野での就職”を目指すものではないが、協力隊の活動を通じて国際協力分野に興味を持ち、この分野での仕事を希望する人材の育成にはつながっている。また、協力隊に参加したことで “国際理解が増した”との回答は帰国隊員全体で75.5%であり、協力隊に参加することによって帰国隊員の国際理解度の向上に貢献しているといえる。
JICA側の取組みとしては、国際協力分野における人材育成の一貫として、25歳~35歳までの協力隊員などの経験者に国内での1年間の実務研修に続き、海外派遣を2年以内で行い、JICAの技術協力業務で活躍する機会を与えるジュニア専門員制度を設けており、若手人材に経験と機会を提供する場としている。この他国際協力分野の人材育成としてJICA研修が実施され、国際協力分野での活躍を希望する帰国隊員のキャリアアップの場となっている(3-3-2帰国隊員の支援にかかるJICA研修等参照)。また、平成13年度には帰国隊員等人材育成奨学金制度を設けるなど、帰国隊員の人材育成には積極的に取り組む方針である。このため“日本の青少年の人材育成”という協力隊事業の目標に対して、帰国隊員への支援事業を中心に明確に取り組んでいるといえる。
(2)協力隊員に対する協力隊事業のインパクト
協力隊に参加したことにより“国際協力分野で働くきっかけとなった”や“国際理解が増進した”以外には、協力隊に参加したことで“価値観が前向きに変化した(59.2%)”、“人間的に強くなった(60.5%)”など精神面での成長に向上が見られたと回答する割合が過半数を超えている。隊員活動を通じて“成長した”“やや成長した”と答えた割合が95%に上るため、多くの隊員は協力隊事業への参加により何らかの正のインパクトを受けているといえる。また“ボランティア活動に積極的に関わるようになった”との回答も21.4%あった。このボランティア活動への関与に対する数値はけして多くはないが、隊員へのインタビューによると協力隊への参加以前からボランティア活動に取り組んでいる隊員は少なくない。
その一方で“マイナスの影響があった”と回答する割合は5.9%(S56年度隊次5.0%、H3年度隊次8.5%、H8年度隊次4.4%)あった。今回のアンケートではこのマイナスの影響が何であったかは言及していないが、帰国後数年が経過しても協力隊事業への参加にマイナスの影響を感じている帰国隊員に対しては何らかのフォローアップが必要と思われる。
(3)協力隊事業のキャリアパス効果
帰国隊員に対する「協力隊の経験がこれまでキャリアパスとして役立っているか」との問いに対し、“役立っている”(33.2%)と“やや役立っている”(23.9%)の計は全体で57.1%であった。新卒参加者に限るとこの割合は高まり“役立っている”が42.4%、“やや役立っている”が28.8%であった。新卒隊員については社会経験をすることなく協力隊事業に参加するため、現職参加や退職参加以上に協力隊員としての経験が即キャリアパスとして何らか形で役立つ割合は高くなる。
しかしながら、退職参加の隊員にとっては協力隊の経験がキャリアパスとして“役立っている”との割合が33.3%、また“やや役立っている”が24.7%と新卒参加に比べて減少している。その一方で“あまり役に立っていない”(19.4%)、“役に立っていない”(17.2%)と回答する割合は増えている。現職参加の隊員についても“役立っている”が23.7%、“やや役立っている”が19.7%とキャリアパスとしての効果は退職参加以上に減少しているが、殆どの現職参加の隊員は復職するためか、この設問での無解答率が27.6%となっている。
帰国隊員の過半数以上は協力隊事業での経験が何らかの形でキャリアパスにつながっており、社会経験が乏しい新卒隊員にとってはその経験が重要なキャリアパスとなっている。しかしながら、退職参加と現職参加にとってはその効果はあまり大きくない。
(4)帰国隊員に対する受入企業の人材評価
帰国隊員の就職希望先の一つでもある民間の開発コンサルタント(国際協力関係)を対象としたアンケート調査では、協力隊経験者を“海外経験があり、即戦力として期待する”と評価する意見が聞かれる一方で、“個人差がある”“より良い人材であれば、協力隊であろうがなかろうが採用していく”“海外留学経験者の方が協力隊員より能力に勝る場合が多い”など厳しいコメントをあげるコンサルタントが多かった。また、開発コンサルタントの立場から協力隊員の採用を検討した場合、“開発援助分野に対する専門性や学術的知識が低い”“2年間現地で活動した割には語学力が低い(交渉能力、現地語での報告書作成)”など、協力隊員の語学力と専門性に対する能力向上への要望が多く出された。
(5)結果
協力隊事業は、多くの隊員達の国際理解度の向上に貢献し、国際協力分野での就職を希望する人材を創出している。しかしながら、協力隊事業の活動内容をある程度理解し、現地で隊員と接触する機会の多い民間の開発コンサルタント側の評価では“協力隊事業に参加している”ことだけでは採用条件とはならず、人物重視の能力評価を行っている。このことは開発コンサルタントへの就職だけに言えることではなく、国際協力分野以外の民間企業への就職についても“協力隊事業に参加した”だけでは十分なキャリアパスとはなっていない。
帰国隊員のすべてが、協力隊の経験をキャリアパスとして活用することに期待はしていないが、協力隊の経験が精神面の成長だけでなく、技術・知識面などにおける人材育成につなげ、日本社会の中で適切に評価されていくことも検討していく必要がある。
JICAでは帰国隊員支援室を設け、帰国隊員の国際協力分野での人材育成に積極的に取り組んでいる。国際協力にかかる人材育成は、質の高い援助を効率的に実施していく上で重要な要因の一つであることから、協力隊事業の参加を通じて国際協力分野への興味を抱いた帰国隊員からODA事業の担い手となるべき人材を発掘・育成することに今後も積極的に取り組んでいくことが大切である。
(1)帰国隊員の就職状況
平成12年度に帰国した隊員の進路状況によれば帰国者1,131名のうち帰国1年~2年間(平成14年3月31日まで)に進路の決定したもの(就職、自営、復職)は718名(約63.5%)で、前年の63.7%とほぼ同水準である。しかしアルバイト・非常勤などの短期就労者は169名(14.9%)と前年の13.1%よりも増加傾向にある。復職を除く就労者のうち教員(地方公務員)となったものは46名(9.8%)で前回の9.1%とほぼ同じであった。また、JICAおよび関係機関への就職は81名(17.2%)で、国際協力分野への進路を希望する帰国隊員は多いとのことである(以上、JOCVホームページより)。
しかしながら近年の雇用情勢を反映し、帰国隊員に対する求人件数は全盛時の5分の1程度まで落ち込み、特に大企業からの求人件数は大幅に減少している。中小の企業でも継続的に帰国隊員の採用を行っている企業はなく、過去3年間に5人以上の採用を行ったのはヤマハ発動機(株)の5名1件のみであり、それも数年ぶりのことであった。このため就職率としては6割以上を確保しているものの帰国隊員達が希望する職業や職種に就くことは非常に難しい状況である。
また、開発コンサルタントを対象に行ったアンケートでは、帰国隊員の採用を決定する上で重点を置くポイントは語学力と行動力で、途上国における長期間の活動経験を即戦力として活かせることを重視している。ただし、先の項目3-4-1(d.)で述べたとおり、協力隊経験者だから採用するという採用基準ではなく、企業側が求める能力を満たした人材であることが評価されている。
(2)帰国隊員と日本社会との結びつき
バングラデシュの帰国隊員は日本国内において頻繁に法廷通訳としての召集を受けている。これはベンガル語を理解するということに加え、相手国の事情に精通しており当事者の事情を理解しやすいと言う背景もある。協力隊バングラデシュOB/OG会らが把握しているだけでも、年間にして10件程度の依頼がありそれに可能な限り対応している、ということである。この他、日本社会に生活する途上国の人々に対し、帰国隊員達が様々な形で積極的に支援・協力している例は多い。また、地方自治体との結びつきとして、地方自治体職員が現職参加として協力隊事業に参加している(1999年度実績で94名)。協力隊事業を通じて国際協力への理解を深めた自治体職員が、復職し国内の各地域の国際協力への理解度向上に貢献していくと期待できる。
その他、“途上国の基礎教育の向上”に貢献するために現職教員の協力隊事業への参加を促進させることが文部科学省より提言され、現職教員の派遣人数が2002年度より大幅に拡大される予定である(項目3-5参照)。現職教員の協力隊への参加経験は復職後に生徒、生徒の父母や同僚に直接開発教育や国際理解教育を行うことができるため、国内の教育現場での活躍の場を十分に検討し、その効果をモニターしていくことが必要である。またここでの帰国隊員の活躍を社会的に評価することによって帰国隊員の人材としての評価の向上にもつながると考えられる。
(3)結論
帰国隊員の就職率は約60%程度を維持しているが、協力隊事業に参加した経験だけでは企業の採用条件とはならず、また帰国隊員に対する求人は日本の経済情勢を反映して大幅な減少傾向にある。JICA側では、帰国隊員の就職を促進するために全国18ヵ所に進路相談カウンセラーを設け(増設予定)、帰国隊員の支援を行っている。また協力隊のOB/OGであることを原則に47の都道府県に国際協力推進員を配置する、ハローワーク(公共職業安定所)との連携、企業懇談会を通じた就職支援依頼、企業に対する「帰国予定隊員名簿」の送付など様々な取組みを行っている。このようにJICA側では帰国隊員の人材活用のために明確な投入を行っているといえる。しかしながら、国際協力分野への進路を希望する帰国隊員が、実際にJICA関係などに就職できるのは2割弱である。
近年増加している地方自治体職員や現職教員の協力隊事業への参加は、職場や学校、さらに地域の国際化に貢献しているとされている。しかしながら、これまでは一部の活動を取り上げて評価するに留まっているため、総合的にはどの程度活用されているのかを継続的にモニタリング・評価していくことが望ましい。復職後にどの程度人材が活用されているのかを適切に評価することで、人材育成に対する協力隊事業の貢献度が明確になるはずである。
(1)帰国隊員のOB/OG会の社会還元活動
帰国隊員のうち約3分の1は各都道府県のOB/OG会(47ヶ所)、派遣国別のOB/OG会(14ヶ所)および職種別OB/OG会(7ヶ所)に所属しており、これらのOB/OG会の中心機関として(社)青年海外協力協会(JOCA)が存在する。OB/OG会の活動は派遣国での経験を社会に還元すること、および帰国隊員間の親睦を図ることが大きな目的で、国際交流関係へのイベントへの参加、開発教育への取り組み、協力隊の募集説明会等JICA事業への協力などを行っている。以下は青年海外協力隊茨城県OV会の活動内容15についての記載である。しかしながら活動内容は各OB/OG会により異なり、また活動が活発に行われている会とそうでない会とで格差が見受けられる。
| 青年海外協力隊茨城県OV会は、青年海外協力隊帰国隊員の茨城県出身者または、茨城県在住者が組織している団体です。・・・中略・・・ 現在(平成11年度末)、茨城県には、350名程度の帰国隊員がいます。全てが会員になっているわけではありませんが、多くの帰国隊員が入会しています。帰国隊員の会ですから、活動は、任国での経験を社会に還元することを中心に行っています。特に教育現場からの講演依頼は、総合的な学習の時間をみこして、増える傾向にあります。・・・中略・・・青年海外協力隊関係では、年2回の募集に合わせて、説明会が行われていますが、各会場にOV会員が行き説明をしています。・・・中略・・・ OV会は、上述したように自分たちの体験の社会への還元と会員の親睦という2面性を持っています。・・・ 後略 |
(2)JICAのサーモンキャンペーン
帰国した隊員たちは様々な手段を用いて自分たちの経験を日本社会へ還元しようと試みている。日本国内における開発教育の需要の高まりもあり、JICAの実施するサーモンキャンペーンでは学校、地方自治体および各都道府県の国際交流団体等に年間に600回以上の講演を帰国隊員達が講師として行っており、講演数は年々増加している。このサーモンキャンペーンにより帰国隊員の講演を聴いた人は約10万人以上に上っている。さらに広尾訓練センターや(社)青年海外協力協会においても開発教育への取り組みがなされている他、地域内で個人に直接講演依頼をするケースを含めると相当数に上ると予想される。帰国隊員を対象としたアンケート調査では90%が帰国後何らかの形で派遣国や国際協力についての紹介をしたことがあるとの回答を得ている。インタビューでその実施回数を確認したところ、各人の実施回数には2~3回から数十回、対象人数も5名~数百名と大きな開きが見られる。
(3)帰国隊員の経験の日本社会での受け止め方
帰国隊員の開発教育や国際理解教育への貢献が大きく期待される中で、現役教師の帰国隊員に対するインタビュー調査から「開発教育には自身の経験をぜひ役立てたい。しかし学校の体制の中では未だ開発教育への積極的な取り組みは認められていない。ともすれば(職場で)変わり者扱いを受けてしまう」との声が聞かれた。これは教師だけに限らず帰国隊員の多くが日本社会の中で感じているようである。つまり、協力隊員が途上国で体得してきたことが日本社会の中では十分に評価されず、また隊員達が学んできたことを日本社会にスムーズに還元できるだけの土壌が育っていないことを示している。
例えば、アメリカの平和部隊と青年海外協力隊とを比較した場合、その相違点としてまず“派遣人数の規模”と“アメリカ社会での受け止め方”があげられる。平和部隊は1961年8月の派遣よりこれまでに累計で約15万人派遣されているが、協力隊は1965年の派遣より2万人である。また、平和部隊の参加者にはハーバード大学の卒業生が派遣当時より多く、政治・経済・文化などの各界で活躍するものも少ないない。さらに、創設段階から国民を巻き込んだ国民参加型事業として成功しており、おそらくアメリカ人にとって平和部隊は非常に身近な存在であると考えられる。一方、日本国内では“青年海外協力隊”という名前は聞いたことがあっても、具体的に何をしているかを答えられる人は少ない。平成13年度に行われた地方自治体を対象としたアンケート調査においても、いまだに自治体における青年海外協力隊の認知度は、“名称を知っている程度”67.1%、“良く知っている”31%である。
協力隊員の経験を受け止める社会を築いていくための対策について検討していくことも大切である。
(4)帰国隊員が保有する情報の活用状況
帰国隊員達が2年間現地で生活しながら得たものは経験だけでなく情報もある。現時点では、この情報はほとんど有効活用されず、日本社会に還元されていない。隊員の情報は報告書に集約されているともいえるが、隊員報告書は事務局・在外事務所や後任者などに向けての報告の形式をとっており、効率的に情報として利用することは難しい。隊員が活動期間中に得た現地の生きた情報を貴重な情報とし、情報収集を隊員の活動内容の一つとして位置付けることも検討していくべきである。また、派遣国別や職種別に現地の情報を蓄積・整理していくことが可能なシステムの構築、および効率的な活用方法(要請背景調査やその他スキームの調査などへの利用)についても考慮が必要である。
協力隊事業において帰国隊員達は、開発途上国での2年間に渡る協力活動を通じて成長し、日本社会にとって貴重な人材であると位置付けられている。そして帰国隊員達がスムーズに社会復帰を果たし、様々な分野で活躍することによりその経験が社会に還元されることを期待し、帰国隊員への支援事業、特に帰国後の進路問題を中心に取り組んできた。また、サーモンキャンペーンは、国民に対する開発教育や国際理解教育への貢献を日本社会への還元の一貫と考えて実施している。このため「日本の青少年の人材育成・日本社会への還元」に対しては、協力隊事業として帰国隊員への支援事業を中心に明確に取り組んでいるといえる。しかしながらその方針や目標については特に明示されておらず、時代の変遷により「人材育成」などに対する重要度は変わってきた。現在は「日本の青少年の人材育成・日本社会への還元」の重要度は高く、協力隊事業として非常に積極的に取り組んでいるといえる。
その一方で、帰国隊員達は自身の経験を日本社会に還元しようと試みながらも、うまく実施できない状況に陥る場合がある。帰国隊員達が進路決定に困窮していることもこの一例である。また協力隊員が体得してきた相手国の異文化や多様な価値観を日本社会に還元しようとする際におこる摩擦も、日本社会に帰国隊員の経験を十分に受け入れる状況が十分に整備されていないことを示している。帰国隊員に対する帰国支援事業を促進するとともに、日本社会が隊員の経験を適切に評価し、できるだけ多くのものを受け入れることが可能となるよう、協力隊事業の理解度の向上や国際理解教育の推進などに積極的に取り組んでいく必要がある。
15 JICAホームページhttp://www.jica.go.jp/branch/tbic/cooperate/cooperate06.htmlより抜粋

