4-2.国際交流・二国間関係の増進
ここでは、下記のA~Bの点検項目に基づき「国際交流・二国間関係の増進」対する評価分析を行っていく。
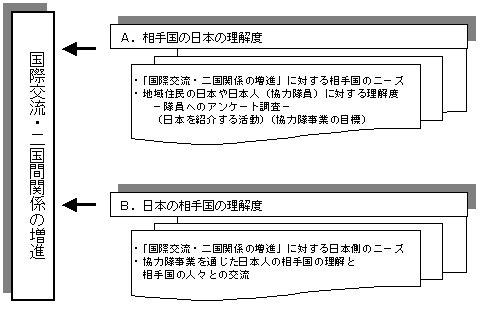
(1) 「国際交流・二国間関係の増進」に対する相手国のニーズ
バングラデシュ国とニジェール国において実施した協力隊員の配属先関連の現地アンケート調査によると、協力隊事業の目的を「文化交流」「日本の理解」「二国間の友好関係」など国際交流・二国間関係の増進に関連した回答(複数回答あり)はバングラデシュ国が87%、ニジェール国が89%であった。このため両国ともに、協力隊事業を介しての国際交流・二国間関係の増進に対するニーズは高いといえる。しかしながら、バングラデシュ国とニジェール国では、社会的背景や地理的条件が異なるため、国際交流に対するニーズが同様に高くても、相手国の人々が協力隊員に求める国際交流の形には違いが生じている。以下にバングラデシュ国とニジェール国を日本との地理的条件や日本に対する理解などの観点から比較した表を示す。
| 国 別 | 地理条件 | 人的交流 | 経済協力の規模 | 日本に対する既存の理解度 | |
| バングラデシュ国 (1973年8月より協力隊の派遣開始 2000年6月の派遣実績累計715名) |
南アジア バングラデシュ国から日本は比較的近い。 |
民間レベルでの日本人との人的交流がある程度ある。 日本のNGOが多数活動し、日本企業の進出もある。 |
日本の主要な援助国の一つであり、援助規模も大きい。 | 日本のテレビや映画が一般向けに放映され、日本や日本人に対する知識が一般庶民まで浸透している。 | ダッカ大学等3つの大学と民間語学学校で日本語を学習することができる。 |
| ニジェール国 (1984年8月より協力隊の派遣開始 2000年6月の派遣実績累計260名) |
アフリカ ニジェール国から日本は比較的遠い。 |
民間レベルでは日本人との交流が比較的少ない。 日本のNGOは活動していない。 |
フランスが最大の援助国ではあるが、ドナー国全体でも援助規模は小さい。 | “日本”という言葉が、電気製品や車のブランド名という域をでない。 | 大学機関においても日本語は学習できない。 |
表4-6のように、バングラデシュ国とニジェール国では、協力隊員が国際交流を行う上での環境が大きく異なる。このことは同時にバングラデシュ国とニジェール国が協力隊事業に求める国際交流の形に相違点を生じさせている。
例えば、バングラデシュ国での協力隊派遣は、国家独立の翌々年(1973年)から開始され、その歴史は30年と長く、これまでに多くの隊員が国際交流を実施してきた。また、在バングラデシュ大使館では1972年に日本語学校を設立する(現在は民間の日本語教育機関として活動)など、バングラデシュ国への経済協力が始められた頃から“相手国が日本に対する理解を深めること”に力を入れてきたといえる。現在ではダッカ大学等で日本語が学習でき、日本への国費留学希望者も多い。つまり、バングラデシュ国の場合は、協力隊事業だけでなく様々な形での国際交流が活発に行われてきた結果、日本に対する理解が進んできたといえる。このような変遷の中で協力隊員達は、日本に対する高い知識を持つ人々、隊員との交流を長年続けてきた人々、また農村部のあまり日本を知らない地域住民など多様な人々と直接触れ合いながら国際交流活動を行ってきた。配属先の上位機関でのインタビューでは「隊員達は住民と非常に仲良くなれ、住民達は隊員達に信頼をよせている」との声が多く聞かれた。このため、バングラデシュ国側では、協力隊員が主に交流するカウンターパートや地域住民など草の根レベルでの密接な友好関係の構築に期待を寄せている。今後はこれまでの30年におよぶ協力隊の派遣実績を踏まえ、協力隊事業が得意とする国際交流の方法で、日本とバングラデシュ国との持続的な草の根レベルでの結びつきや相互理解を深めていくための活動が協力隊事業として求められているといえる。
一方、ニジェール国への協力隊派遣は1984年より開始され、隊員の派遣数はバングラデシュ国と比較すると累計で約3分の1程度である。日本の在外大使館はなく、大学でも日本語を学ぶことはできない。またバングラデシュ国では協力隊員の他にも日本人の援助関係者や民間企業職員などが数多く駐在しているが、ニジェールでは協力隊員以外の日本人が駐在することは非常に限られている。つまりニジェール国では日本との交流が白紙に近い状態から協力隊事業が開始され、協力隊の派遣とともに日本との本格的な国際交流が進められてきたといえる。このことは現在においても変わらず、協力隊事業はニジェール国が日本との交流を深めていくための主要な手段となっている。このため、ニジェール国側にとっては、協力隊員達の国際交流活動が日本人との相互理解を深めるために重要な役割を果たしており、協力隊事業に求めるニーズの一つであるといえる。今後は日本に対する理解をニジェール国内で面的に広げていくとともに、日本とニジェール国との関係の向上に貢献できるような国際交流が望まれる。
今回現地調査の対象とした国は2カ国のみであるが、その他協力隊員が派遣されている国々においてもそれぞれに社会的背景、地理的条件また援助環境などが異なる。このため相手国の「国際交流・二国間関係の増進」に対するニーズが存在していても、協力隊員が派遣される国の状況によってその方針や目的などに相違が生じてくるはずである。各派遣国が求める日本との「国際交流・二国間関係の増進」の中で、協力隊事業としてどの部分に貢献できるのかなどを十分に相手国と協議し、明確な方針と目的を持って相手国のニーズに応えていく必要がある。
(2)相手国の地域住民の日本や日本人(協力隊員)に対する理解度
a.隊員の日本を紹介する活動
隊員へのアンケートによると「日本を紹介するような活動を行ったか(行っているか)という問いに対し、帰国隊員の約70%、派遣中隊員の約60%が行った(行っている)と回答している。その活動内容は、日本語教室、スポーツや文化活動を通じた派遣国の地域の人々との交流や地域ボランティア活動への参加が中心となっている。また、「現地の人の日本に対する理解度が深まったか」、という問いに対しては、帰国隊員では約80%、派遣中隊員では約70%が深まったと感じている。但し、帰国後も派遣国の人との交流が続いているかについては、全体で54%に留まり、年次が古くなるにつれて、その割合は下がっている。また交流の手段は文通が大半である。
このように、協力隊員達の国際交流活動により協力隊員を取り巻く現地の人々の日本に対する理解度は少なからず向上し、協力隊員(=日本人)との現地の人々との相互理解は高まっているといえる。しかしながら、隊員の離任後は隊員個人との交流がしだいに遠のいていくケースが多い。
b.地域住民と隊員との相互理解
隊員へのアンケートによると、隊員自身が考える協力隊事業の3つの目標に対する重要度は、「社会経済の発展への寄与」を“重要”11とする回答は帰国隊員が39.9%、派遣中隊員が38.6%、「国際交流・二国間関係の増進」は帰国隊員が52.9%、派遣中隊員が48.2%、また、「人材育成・日本社会の還元」については帰国隊員が49.2%、派遣中隊員が41.1%であった。このため、協力隊員は3つの目標の中で「国際交流・二国間関係の増進」を一番高く位置付けていると言える。現地調査における隊員でのインタビュー調査でも、3つの目標の中で「国際交流・二国間関係の増進」が一番重要だとする回答が約7割あった。
このことは、協力隊員達は相手国の人々との交流や相互理解を重視して、協力隊事業に参加していることを示している。しかしながら、「国際交流・二国間関係の増進」は協力隊事業の目的として明確に位置付けられていない。相手国の日本に対する理解度を高めるための活動は、一部の職種(日本語教師、武道など)を除いて要請背景調書には記載されず、協力隊員が行うべき活動ともされていない。ただし、多くの国では隊員主導による日本紹介イベントが在外事務所の支援のもとで実施されている。しかし、隊員達がそれぞれの活動地域で行う日本を紹介するような国際交流活動は、個々の隊員の余暇時間を利用した活動として行われ、後任隊員に活動内容が引き継がれることもなく隊員の離任と同時に終了していく。隊員が活動した地域の人々により深く日本や日本人のことを理解してもらうには継続した交流活動が必要である。また、現在の国際交流活動のほとんどが個人ベースで行われているが、隊員間が連携した国際交流活動が展開できれば、協力隊員達が望む“相手国と日本との相互理解”を全面的な広がりをもって進めていくことができるはずである。
(3)結 果
協力隊事業の職種の中で要請件数が1位(平成13年度秋募集 表3-3参照)であった日本語教師は、日本語という言語を相手国の人々が学ぶことで、日本や日本文化に対する興味が生まれ、ひいては友好・親善を深めることもにつながる職種の一つである。またスポーツ交流(柔道、剣道など)や文化芸術交流(バレエ、舞台芸術など)といった形で相手国のスポーツや文化芸術分野に貢献しながら、より高いレベルで相手国の人々との相互理解を進めていく職種もある。しかし協力隊事業として最も一般的な国際交流の形は、協力隊員(=日本人)と現地の人々とのふれあいから始まる、人と人との交流である。協力隊事業に参加している隊員達は隊員自身と相手国の人々との相互理解から進展していく「国際交流・二国間関係の増進」を協力隊事業の目的として最も重視している。また、相手国側もそれぞれの派遣国によって協力隊事業に期待する形態は異なるものの「日本や日本人を理解したい」というニーズは存在している。相手国にとって協力隊事業は、日本の青年層が発信する日本の生きた情報を直接得ることができる貴重な手段の一つでもある。
しかしながら、協力隊事業として相手国の日本に対する理解を深めていくことは、一部の職種を除いて協力隊員達には特に求められていない。殆どが協力隊員の自主性に任され、その多くが個人ベースの“点”としての国際交流活動に終わっている。相手国が日本に対する理解や友好を深めていくことは、国際協力を効率的かつ効果的に行っていく上で重要な潤滑油ともなり、日本側にとってもメリットは大きい。例えば、協力隊事業が得意とする相手国の草の根レベルの人々との相互理解を広く展開していくことができれば、協力隊事業が直接関係していない日本の他の援助スキームに対しても間接的に正のインパクトを与えていくことが考えられる。こうした相手国の日本や日本人に対する理解を高める活動は、ODA事業における協力隊事業として担うことができる役割の一つとして検討していくことも可能である。
(1) 「国際交流・二国間関係の増進」に対する日本側のニーズ
協力隊事業が対象としている国々はそれぞれに抱えている社会的背景や日本との交流状況などが異なる。このため、派遣国の状況によっては、日本側のニーズとして「国際交流・二国間関係の増進」を協力隊の活動内容として前面に出して国際協力が進められている場合もある。例えば、ある程度の技術・技能を有する東欧諸国への派遣は1991年より始められているが、派遣開始時に「アジアやアフリカで展開してきたような従来型の協力活動を踏襲するのか、隊員の技術・技能レベルで通用するかどうか」12が検討された。そして東欧諸国への派遣については、「(相手国と日本の)相互の交流を重視し、互いが学び合う面を強調する方向が適切」と考えられ、「日本語教育、柔道・剣道等の武道、その他のスポーツ交流という文化交流的要素の濃い職種を中心とした派遣が開始された。」13
東欧諸国の例は、協力隊事業全体から見れば非常に小さな部分ではあるが、「相手国と日本との相互の交流を重視し、互いが学びあう」という姿勢は、これまでに多くの協力隊員達がすでに実践してきたことである。例えば、帰国隊員へのアンケート調査によると「教えるものよりも教えられることのほうが多かった」というコメントが非常に多く書かれていた。つまり、派遣前の予想以上に、相手国から得るものが多かったということであろう。これは現地の人と一緒になって活動する協力隊事業の特性を示すものであり、「相手国の人々と交流し、日本青年と現地の人々が互いに学び合う」ことは、協力隊事業を展開する上での日本側のニーズの一つであると考えられる。今回現地調査においても、バングラデシュの職業訓練センターで活動する隊員が「ここで担当している技術工程は、日本の消費社会の中では全てを交換(買い替え)してしまうものだが、この国ではそれを全て修理し大切に使っていく。ここには既に日本では無くなってしまった技術と、その背景には価値観がある」ということを述べていた。また、バングラデシュ国のカウンターパート達は隊員達から得た知識・技術を独占したがる傾向にあり、互いに交換する習慣がないため、十数箇所に点在する職業訓練センターの指導者層を一箇所に集め、指導者講習会を開催し、一斉に知識・技術を指導することに努めたと、隊員報告書に書かれている(バングラデシュ国職業訓練センター)。つまり、技術移転を目指して活動しながら、実は多くのものを現地の人から学び、相互理解を深めているといえる。
相手国と日本の文化や社会制度の仕組みの違いが、途上国での開発プロジェクトを進めていく上での障害(=開発の阻害要因)となることはよくある。特に相手国側の労働時間の制約、頻発するカウンターパートの離職また既存の技術水準といった社会環境の相違を互いに理解し、歩み寄らなければ日本側の技術・知識の移転を効果的に伝えていくことは非常に難しい。協力隊員達も配属先の上司との軋轢、カウンターパート達や地域住民との異文化コミュニケーションに悩まされ、また、協力隊員が持っている技術・知識(=日本の技術・知識)を相手国の適正技術に転換することに任期の多くを費やしている。しかしながら、協力隊員達は相手国の人々との交流を深め、相互理解を進めながらこの阻害要因を取り除く努力をし、その結果として協力隊員達は非常に多くのものを相手国から学んでいる。このように、明示的ではないながらも、「国際交流・二国間関係の増進」に対するニーズは存在する。
「国際交流・二国間関係の増進」は、相手国側のニーズだけでなく、日本側にとっても相手国との相互理解を深める上での重要なニーズとして再認識していくことが必要である。また協力隊員達と相手国の人々との交流により得た相手国の有用な情報を協力隊事業全体、あるいは日本の他の援助スキームにも活用していくべきである。
(2)協力隊事業を通じた相手国に対する理解の向上と相手国の人々との交流
協力隊員達の相手国に対する理解と人的交流については前述のとおりであるが、ここでは協力隊員以外の人々の相手国に対する理解度について考察する。
協力隊派遣20周年を記念して(社)協力隊を育てる会が実施を開始した「視察の旅」では、隊員の留守家族や友人が任地を訪問し、協力隊員の活動を視察している。計画は年1回で、毎年約300名が参加し、全隊員の派遣国に対し行っている。参加者の9割は隊員の両親で、隊員達の活動を通じて相手国の人々と交流することで、相手国への理解や親しみを増しているようである。しかし、参加者の多くは協力隊員の身内に限られ、その目的も“隊員達の様子を知ること”が主で、国際交流の範囲は非常に狭いものである。また、この視察の旅は“(社)協力隊を育てる会”が主催で、青年海外協力隊事業の中で実施されているものではないため、協力隊事業として“協力隊員以外の人々”が相手国の人と直接人的交流を図る手段は殆んどない。
“協力隊員以外の人”の相手国に対する理解度については、これまであまり関心のなかった国に友人・知人、家族、同僚や学校の先生などが派遣されることで、その国に対する興味や関心が高まるきっかけとなり、個人差はあるものの理解度の向上ははかられている。また、協力隊員自身が派遣国から日本に向けて積極的に情報を発信しているケース(インターネット等の利用)の場合は、さらにその効果が高いといえる。特に現職参加の教員達の中には教え子達に向けて任国情報を積極的に発信しているケースも見られ、現地の生きた情報を子供たちに与えることで、相手国の理解度向上に貢献している。しかしながら、それらの活動は協力隊員自身の自主性に任され、活動に対する支援やアドバイスなども特に行われていない。協力隊員達が行っている“協力隊員以外の人”が相手国に対する理解度を深めるような活動については、今後必要に応じて支援していくことも必要である。また、協力隊事業として、派遣中隊員が日本に向けて相手国の状況を積極的に発信することも検討していくべきである。
協力隊事業における国際交流は、相手国の人々と協力隊員との接触を持った時点から始まっている。そして協力隊員達は日本に関する生きた情報を相手国の人々、特に草の根レベルの人々に直接発信していく重要な役割を担っている。本調査では、国際交流に対する潜在的なニーズが確認されたが、派遣国の状況によっては協力隊事業が主に日本人との人的交流を行える手段となっている国もあり、協力隊事業が、相手国と日本との相互理解を深め、二国間関係の増進に少ながらず貢献してきたことが確認された。相手国と日本との相互理解が深まっていけば、相手国の住民が有する潜在的なニーズを見出すことができ、日本側は相手国の協力に効率的かつ効果的に貢献していくことができるはずである。さらに、相手国の人々が協力隊員の活動を通じて日本人に対する理解を何らかの形で深めてもらうことは、経済大国という部分だけが前面に出がちな日本の援助に対するイメージを“日本国民が協力している援助”つまり“顔の見える援助”へと変えていくことも可能である。しかしながら、現在行われている協力隊員の国際交流活動は個人ベースでの自主的な活動が主体となり、協力隊事業として明確な目標と方針をもって推進されていない。このため、協力隊員を取り巻く人々に限らず相手国の人々全体を視野において、日本人の文化や思考などを理解してもらえるような事業展開を検討していくべきである。特に協力隊員が得意とする草の根レベルの人たちと持続的に交流していくことは大切である。
相手国の地域住民と協力隊員とはこれまで多くの友好関係を築いてきた。また、活動期間中に協力隊員自身が相手国の地域住民を理解しようとすることで、相手国の文化、芸術、スポーツや言語などを学び相互理解を深めてきたといえる。このため協力隊員達が草の根レベルの人々との相互理解を深めることで、協力隊事業としても日本が相手国の理解を深め、また人的交流を図ってきたことに大きく貢献してきたと評価できる。しかしながら、国際交流・相互理解の範囲は協力隊員自身に限られ、協力隊事業として協力隊員以外の人々が相手国の人々と直接人的交流を図ることにはあまり貢献していない。
以下は平成13年10月に南アフリカの大統領夫妻が来日した際に発表された「日・南ア コミュニケ」(仮訳)であるが、これによると青年海外協力隊事業は、二国間の相互理解を深め、関係の増進を図るための有効な手段として国内外ですでに認められているといえる。
平成13年10月2日 前略
|
世界の中の日本として、諸外国との友好的な関係を発展させていくには、今まで以上に日本に関する情報の発信と相手国の情報を受信していくことが求められている。協力隊事業は、相手国にとっても日本にとってもテレビや書籍などでは得られない生きた情報を発信、また受信することができる存在である。協力隊事業として明確に位置付けられていないが、「国際交流・二国間関係の増進」に対する効果はすでに国内外で認められた効果であると評価できる。しかしながら、現在の個人レベルでの交流活動を国と国との国際交流のレベルへと発展させていくためには、協力隊事業としての「国際交流・二国間関係の増進」の方針、目的、目標を設定し、今後の事業展開を図っていく必要がある。
11 回答欄の選択肢は重要、やや重要、あまり重要でない、重要でないの4段階。
12 「」内は協力隊20世紀の軌跡 第4部より抜粋
13 「」内は協力隊20世紀の軌跡 第4部より抜粋
14 外務省ホームページより www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/yojin/arc_01/s_af_commu.html

