4-1-2.青年海外協力隊事業の成果と効率
(1)ケーススタディからの考察
バングラデシュ国とニジェール国において行った計8件のケーススタディを有効性および効率性の観点から評価した結果を表4-4に示す。また、有効性に影響を与えた主な促進要因と阻害要因については表中の右側に示した。
| 国名 | 案件名 (職種) |
妥当性 | 有効性 | 効率性 | 促進要因 | 阻害要因kk | |
| バ ン グ ラ デ シ ュ |
カルポリ計画 (シニア隊員、手工芸、市場調査、婦人子供服、 在庫管理、経済)) |
** | ** | * | ・女性隊員の派遣
・最終裨益者(貧困女性)のニーズの高さ ・地域性(伝統的手工芸品)を活かした計画 ・シニア隊員の派遣 |
・計画デザイン(目標が多い)
・活動に消極的な配属先上層部の姿勢 |
|
| ダッカ子ども病院 (看護婦) |
** | ** | * | ・最終裨益者(患者と患者の母親)のニーズの高さ
・現地看護婦の日本での研修 |
・長期的な派遣計画・目標が無い
・医療従事者(特に看護婦)の社会的地位の低さ ・配属先の人員不足 ・前任者と後任者の引継ぎ不足 ・病院内部の多様な問題 ・看護に対する個人的・社会的解釈の相違 ・日本の医療機材供与との連携不足 |
||
| 技術訓練センター (婦人服、電気機器、電子機器、冷凍機器・ 空調、配管、溶接、 図学 他) |
** | * | * | ・日本の先進技術に対するニーズの高さ | ・長期的な派遣計画・目標が無い
・政策変更(センターの位置付け) ・前任者と後任者の引継ぎ不足 ・組織やシステムの問題 |
||
| ニ ジ ェ | ル |
ポリオ対策 (シニア隊員、ポリオ対策隊員、 自動車整備) |
*** | *** | *** | ・明確な計画デザイン
・最終裨益者(地域住民)のニーズの高さ ・シニア隊員の派遣 ・国際機関の援助方針に合致 ・日本の援助政策に合致 |
・人口の移動 | |
| 就学前教育 (幼稚園教諭、保育士) |
** | ** | ** | ・教育政策との合致
・省レベルのニーズの高さ ・現地幼稚園教諭の日本での研修 |
・就学前教育概念の相違
・国内での就学前教育の未定着 |
||
| 農村生活向上 (果樹、野菜、栄養士) |
* | * | ** | ・最終裨益者(地域住民)のニーズの高さ | ・不明確な計画デザイン
・必要とする農業技術の水準 |
||
| 青 年 育 成 |
青少年活動 (青少年活動) |
** | ** | ** | ・最終裨益者(地域住民)の潜在的ニーズの高さ | ・隊員離任後の継続が難しい活動内容 | |
| 体育(体育) | ** | ** | * | ・最終裨益者(中学校の生徒と地域住民)のニーズの高さ | ・中長期的な目標が不明確な派遣計画
・現地側との連携不足(体育教員の育成、増員) |
||
[***:妥当性(または効率性、有効性)が非常に高い、**:妥当性は高いが一部問題点を有する、*:妥当性は一部高いが問題点も多い、なし:妥当性が非常に低い]
以下に各ケーススタディの評価結果を総合的に考察した結果を示す。
(a) 有効性
計画デザインが明確で、妥当性が高い案件(ニジェール国ポリオ対策)については目標達成度も高くなっている。しかしながら、長期的な派遣目標や上位目標が明確に設定されずに隊員派遣が同地域や同配属先に複数あるいは継続して派遣されている案件については、個々の隊員達が立てる活動目標に一貫性がなく、また隊員同士の横の連携も乏しい。このため数多くの隊員が派遣されているメリットが十分に生かされていない。
また、隊員の活動成果を促進させるための支援体制に不足が見られた。例えば、組織の中でカウンターパートや同僚達とともに活動していく中で、組織全体あるいは上位組織の問題点に気づいていく隊員達は少なくない。しかしながら、配属先の組織や体制などの問題点を隊員の力だけで改善していくことは困難であり、隊員達が想定する活動目標や上位目標への達成を阻害する要因となっている。このため組織の“個”としての活動は非常に高い成果をあげていても、それを受け入れる配属先側に問題があるために、その成果が最大限活用されない状況を招いている。
(b) 効率性
効率性は、全体的に低い結果となった。その理由としては、まず前任者と後任者の引継ぎ不足があげられる。この傾向は特に派遣が長期化している案件に目立ち、前任者がすでに行っている現況調査を次に続く隊員が同様に新たに繰り返すことが何度も行われている。現況調査を行うことはけして悪いことではないが、前任者が残した功績を後任者が最大限利用し、現況調査に費やす時間を短縮していかなければ、効率性という点からは低い評価となってしまう。
また、派遣が長期化している案件については、投入量(隊員数)と成果の関係から派遣を長期に亘らせることが検討されていないケースが多い。このため、明確かつ長期的な派遣計画に基いて派遣が行われていれば、同様の投入量で、現状を上回る成果が得ることができたとも推測できる。また、隊員の報告書からは、派遣が長期化する以前から、後続派遣の問題点が指摘されているにもかかわらず、派遣の形態を変えることにはつなげていない。この点も非効率な派遣を招く一つの要因となっている。
(2)協力隊員の活動状況
(a)要請背景調査・要請開拓と調整員
ケーススタディの妥当性、有効性および効率性に対する評価の結果、協力隊の当初派遣計画の曖昧さ、特に目標・上位目標の設定や中長期的な展望が十分計画に加味されていないために、「最終受益者のニーズに合致」という協力隊事業の特色が活かされないことが明らかとなった。このため、ここでは協力隊の要請開拓から要請採択に到るプロセス、およびJICA在外事務所の協力隊調整員の業務に対する分析を行い、協力隊事業における現地体制について分析を行う。
協力隊の要請開拓から要請採択に到るプロセスは、各在外事務所や案件によって異なるが、概ね一案件の調査には1名の担当調整員が当たり、適宜事務所内で協議することはあるものの、ほぼ調整員の判断で採択が決まっていくケースが多い。相手国側(受入先)との協議も担当調整員のみが行っている場合が主となる。要請開拓から要請状況に到る主な流れは以下の通り。
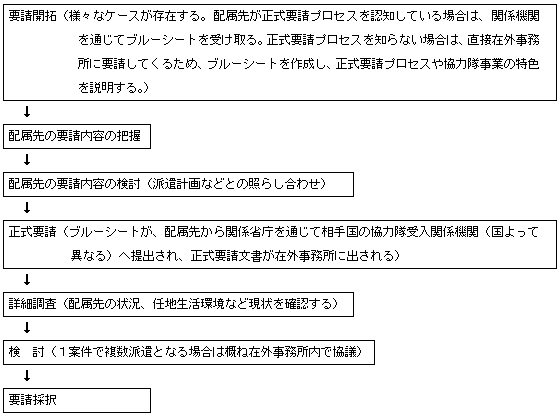
バングラデシュ国とニジェール国の調整員に対するアンケート調査によると、調整員が要請開拓時に留意する点として主に以下が挙げられている。
- 人手不足の解消のために隊員を要望してはいないか、現状を見極めて判断すること
- 相手国(受入先)から出た要請が本当に必要なものか、見極める判断をすること
- 上司の発言が絶対である途上国の組織では、上司の協力隊に対する理解が必須であること
- 隊員が生活する場合の周辺環境(治安、住居、交通、通信など)や活動する場合の職場環境(人など)に注意すること
- 相手国側、配属先への協力隊派遣に対する理解促進に時間を費やすこと
- 隊員の担当業務に関する協議に時間を費やすこと
- 要請提出後から隊員派遣までに期間の要請内容の変化に対する調査を実施すること
- 同じ任地や勤務先に同職種の隊員を配置しないこと
- 一つの任地において援助重点課題を中心にムラのない隊員配置をすること
また、今回アンケート調査において帰国隊員および派遣中隊員から寄せられた自由記述欄への意見で一番多かったのが、要請と実際の活動の不一致に対する不満であった。派遣中隊員へのアンケート結果では、“在外事務所の対応に関し改善すべき点があるか”で“ある”と回答した70%の隊員のうち、73%の隊員が「要請背景調査を十分に行い、本当に必要とされる任地に派遣すべき」と回答している。また、「調整員の支援体制に問題がある」という回答は20%あり、特にマンパワー提供型(30%)と現職参加(27%)が高かった。具体的には、要請に起因する業務内容や配属先の環境への不満に対する支援不足である。さらに、「在外事務所の対応が一貫していない」という回答も多く、全体では26%で、マンパワー提供型(36.7%)が一番高かった。
一方で、“在外事務所の対応に関し改善すべき点があるか”で“特になし”と回答した隊員は、目標達成度が高く(指導型とマンパワー提供型)、求められる技術・知識が一致している傾向(指導型とマンパワー提供型)が見られる。
(b)協力隊への参加動機と青年海外協力隊事業の目標
今回アンケート結果より、現在派遣中の隊員が派遣前に協力隊の活動に期待していたことは、「技術や労働力を提供し、現地に役立つこと」、つまり技術協力的な側面が一番多く全体の77%を占めている(複数回答可)。しかしながら、新卒者のみでは、技術や労働力を提供し現地に役立つこと(72%)、異文化経験による自己啓発(73%)、現地の人との交流(82%)と、3つの目標の中では技術協力に対する期待が最も低くなっている。一方で、現職参加は、技術や労働力を提供し現地に役立つこと(85%)、異文化経験による自己啓発(68%)、現地の人との交流(62%)と新卒参加とは逆の傾向が見られる。退職者は、新卒者と現職参加者の中間に位置し、技術協力面に対する期待は、新卒者より高い。
また、上記のような参加動機の違いは、派遣地域別に分類した場合にも見られ、例えばアジア地域の派遣中隊員は、「社会経済の発展への寄与」を“重要”10とする回答は34%であるが、「国際交流・二国間関係の増進」は58%が重要と回答していることから分かるように「社会経済発展への寄与」に対する期待は小さい。一方、アフリカ地域の派遣中隊員は、「社会経済の発展への寄与」と「国際交流・二国間関係の増進」で重要とする回答はそれぞれ43%と44%と大きな格差は見られないが、“重要でない”、“あまり重要でない”と回答する割合が2割以上あった。これは、ある程度経済力・技術力を備え始め、日本と密接な関係にある派遣国では、「社会経済の発展への寄与」よりも「国際交流・二国間関係の増進」を重視する傾向が強く、逆に経済的にも社会的にも途上段階にあるが、日本との関わりが少ない派遣国では、「社会経済の発展への寄与」を重視する傾向が強いことが確認された。
(3)結果
要請段階で明確な目標が出されている派遣については、妥当性も高く、また目標達成度も高くなっている。その一方、要請段階での計画デザインが不明確なものについては、多く隊員が派遣されてもそれに見合っただけの成果が得られ難い。在外事務所や調整員への不満の多くも要請背景調査や要請開拓に起因するものであり、要請段階の改善がなされれば協力隊員の在外事務所や調整員への不満は大きく解消されていく。要請段階の改善点は、すでに調整員が要請開拓時に留意したいとする事項(前項(2)-(a))に集約されており、内部で問題点がある程度明確になっているようである。また過去の調整員議事録からも、ある程度問題点の蓄積がされており、それがうまく現場でフィードバックされていないように見受けられる。
協力隊員の活動を促進する調整員の業務は要請開拓、隊員と配属先との調整、隊員のアドバイザーなど多岐に渡り、協力隊員の個性や業務内容に大きく左右される。それだけに調整員が隊員に及ぼす影響は非常に大きい。現場の調整員からは、時間的な余裕があれば、“新しい職種、派遣先の開拓”に取組みたい、“隊員達と共同で何かを開発・普及したい”などの声が聞かれた。調整員業務の範囲、内容、分量および役割に対するバランスに留意しながら、調整員の能力が最大限に活かせる環境作りが大切である。
但し、要請背景調査や要請開拓の改善は、現場の調整員(事務所)の問題だけに起因するものではない。協力隊事業全体を見渡し、相手国の協力隊に対する理解度の促進、相手国の現状のニーズに即した派遣計画、在外事務所と事務局の温度差のない円滑な連携体制、隊員の活動の目標達成度の向上、配属先でのカウンターパートと協力隊員とのコミュニケーションの向上、調整員の業務環境の向上などに対する改善点がなされれば、より質の高い要請背景調査や要請開拓につながり、「相手国の社会経済への寄与」のみならず、「国際交流、二国間関係の増進」に対しても効果を及ぼしていくと考える。
10 回答欄の選択肢は重要、やや重要、あまり重要でない、重要でないの4段階。

