第4章 プログラム(施策)評価
ケース・スタディ調査(添付資料1参照)、アンケート調査(添付資料2参照)および既存資料から得た情報を分析し、青年海外協力隊事業の3つのプログラム(施策)目標「相手国の社会・経済発展への寄与」、「国際交流・二国間関係の増進」、「日本の青少年の人材育成・日本社会への還元」に対する評価を行った。
以下に評価分析結果を述べていく。
ここでは、下記のA~Cの点検項目に基づき「相手国の社会・経済発展への寄与」に対する評価分析を行っていく。
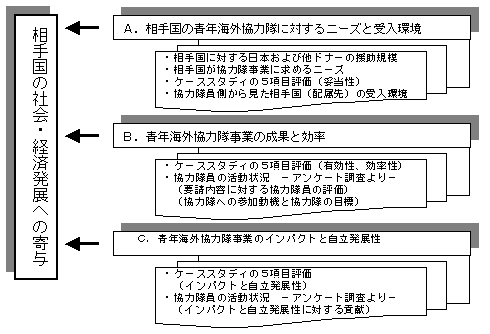
4-1-1. 相手国の青年海外協力隊に対するニーズと受入環境
今回現地調査の対象としたバングラデシュ国およびニジェール国でのヒアリングの結果から、協力隊に対する評価は各関係機関(省庁・配属先など)および各関係者(カウンターパート、配属先同僚、裨益住民など)のいずれのレベルにおいても高く、同時にそのニーズも高いとしている。「今後も継続的に協力隊派遣を望むか?」という問いに対しても100%が「望む」と回答している。しかしながら、バングラデシュ国とニジェール国、また配属先の規模・組織形態の違いなどによって協力隊に求められているニーズの質には違いが生じている。例えば、バングラデシュ国では協力隊員により高い技術力・知識力を望む声や明確な成果を期待する意見がケーススタディの対象とした全ケースで聞かれたが、ニジェール国においては現況以上の技術力・知識力を望む声や今以上の成果を求める意見は聞かれなかった。今回調査では2カ国のみの現地調査であることから、アジアとアフリカという地域性から考察することはできないが、我が国の援助実績(表4-1~表4-2参照)と相手国の関係者に対するヒアリングの結果からニジェール国とバングラデシュ国の青年海外協力隊事業に対するニーズの相違について考察を行っていく。
| 年度 | 技術協力 | 年度 | 技術協力 | ||||
| ニジェール国 | バングラデシュ国 | ニジェール国 | バングラデシュ国 | ||||
| 95年度 | 7.63億円 | 13.33億円 | 99年度 | 5.52億円 | 20.86億円 | ||
| 研修員受入 | 20人 | 231人 | 研修員受入 | 24人 | 215人 | ||
| 専門家派遣 | 1人 | 40人 | 専門家派遣 | 2人 | 72人 | ||
| 調査団派遣 | 28人 | 71人 | 調査団派遣 | 14人 | 114人 | ||
| 協力隊派遣 | 20人 | 32人 | 協力隊派遣 | 32人 | 26人 | ||
| 機材供与 | 27.5百万円 | 80百万円 | 機材供与 | 23.5百万円 | 117.5百万円 | ||
| プロジェクト技協 | 1件 | プロジェクト技協 | 3件 | ||||
| 開発調査 | 2件 | 2件 | 開発調査 | 2件 | 8件 | ||
| 96年度 | 4.35億円 | 16.10億円 | 技術協力 開始年度から 99年度までの 累計 |
97.53億円 | 351.53億円 | ||
| 研修員受入 | 19人 | 285人 | 研修員受入 | 254人 | 3,453人 | ||
| 専門家派遣 | 50人 | 専門家派遣 | 31人 | 867人 | |||
| 調査団派遣 | 9人 | 55人 | 調査団派遣 | 541人 | 2,391人 | ||
| 協力隊派遣 | 14人 | 31人 | 協力隊派遣 | 270人 | 726人 | ||
| 機材供与 | 10.9百万円 | 129.9百万円 | 機材供与 | 612.4百万円 | 4,640.6百万円 | ||
| プロジェクト技協 | プロジェクト技協 | 12件 | |||||
| 開発調査 | 1件 | 2件 | 開発調査 | 16件 | 54件 | ||
| 97年度 | 5.42億円 | 18.66億円 | 95年度~ 99年度 までの累計 |
29.71億円 | 87.62億円 | ||
| 研修員受入 | 22人 | 299人 | 研修員受入 | 108人 | 1,302人 | ||
| 専門家派遣 | 1人 | 32人 | 専門家派遣 | 6人 | 235人 | ||
| 調査団派遣 | 41人 | 87人 | 調査団派遣 | 115人 | 427人 | ||
| 協力隊派遣 | 14人 | 35人 | 協力隊派遣 | 112人 | 149人 | ||
| 機材供与 | 11.7百万円 | 111.6百万円 | 機材供与 | 132.5百万円 | 662.4百万円 | ||
| プロジェクト技協 | 1件 | プロジェクト技協 | 0件 | 6件 | |||
| 開発調査 | 3件 | 3件 | 開発調査 | 9件 | 17件 | ||
| 98年度 | 6.79億円 | 18.67億円 | |||||
| 研修員受入 | 23人 | 272人 | |||||
| 専門家派遣 | 2人 | 41人 | |||||
| 調査団派遣 | 23人 | 100人 | |||||
| 協力隊派遣 | 32人 | 25人 | |||||
| 機材供与 | 58.9百万円 | 223.4百万円 | |||||
| プロジェクト技協 | 1件 | ||||||
| 開発調査 | 1件 | 2件 | |||||
| 暦年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | うち日本 | (%) | 合計 | |||||
| 96 | フランス | 86.8 | ドイツ | 18.3 | 米国 | 12.0 | オランダ | 9.3 | ベルギー | 7.2 | 4.8 | 2.9% | 163.2 |
| 97 | フランス | 94.6 | ドイツ | 17.4 | 米国 | 16.0 | 日本 | 13.6 | イタリア | 11.0 | 13.6 | 7.5% | 181.2 |
| 98 | フランス | 66.1 | ドイツ | 20.5 | 日本 | 11.4 | 米国 | 10.8 | オランダ | 7.8 | 11.4 | 7.9% | 144.6 |
バングラデシュ国 (支出純額、単位:百万ドル)
| 暦年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | うち日本 | (%) | 合計 | |||||
| 96 | 日本 | 174.0 | ドイツ | 84.0 | 英国 | 71.4 | オランダ | 67.2 | 米国 | 41.0 | 174.0 | 27.0% | 644.5 |
| 97 | 日本 | 130.0 | 英国 | 70.3 | オランダ | 63.7 | カナダ | 52.4 | ドイツ | 47.3 | 130.0 | 24.1% | 539.0 |
| 98 | 日本 | 189.1 | 英国 | 99.0 | ドイツ | 65.1 | オランダ | 57.9 | カナダ | 53.5 | 189.1 | 30.3% | 623.8 |
(1)バングラデシュ国およびニジェール国に対する日本および他ドナーの援助規模
表4-1は、1995年度から1999年度までのニジェール国とバングラデシュ国に対する我が国の技術協力部分の実績である。金額ではバングラデシュ国はニジェール国の約3倍、研修員受入では約10倍以上多い。また青年海外協力隊事業同様に「顔の見える援助」に貢献している専門家派遣については5年間でニジェール国が6名、バングラデシュ国が235名である。
次に表4-2は、DAC諸国のODA実績をニジェール国とバングラデシュ国で比較した表である。ここからは、バングラデシュ国にとって日本は最大の援助供与国であることがわかる。また、バングラデシュ国の1999年(暦年)までの支出純額累計は、我が国の援助対象国において第6位の受取国で、特に無償資金協力については、第1位(1999年)の受取国である(但し、無償資金協力の70~80%は債務救済無償が占める)。一方、ニジェール国に対する援助は、1998年においてはドイツに次ぎ第3位の援助供与国となっているが、全体に占める割合は約8%、その額もバングラデシュ国と比較した場合は16分の1の規模となる。ニジェール国における最大の援助供与国はフランスであり、政治経済面で大きな力を及ぼしている。
一方、1995年~1999年の協力隊派遣についてはニジェール国が累計112名、バングラデシュ国が累計149名とこの5年間(表4-1参照)では、両国にそれほど大きな差は見られない。また、バングラデシュ国は比較的規模の大きな在外事務所、ニジェール国は駐在員事務所(所長以下調整員4名)であるが、協力隊員を支援する調整員の数は両国ともに協力隊調整員が3名、医療調整員1名と同じである。
現在のバングラデシュ国とニジェール国の援助状況は、青年海外協力隊の派遣についてはほぼ同じような規模で実施されているが、その他の援助スキームについてはバングラデシュ国の方が圧倒的に大きな援助を受けている。
(2)相手国が協力隊事業に求めるニーズ
上述(1)の援助状況の相違は、バングラデシュ国とニジェール国がそれぞれ協力隊に求めるニーズの質に影響を及ぼしている。
例えば、バングラデシュ国のバングラデシュ農業開発局(BRDB)には1976年以降累計215名の協力隊員が配属され、同時に日本人専門家も随時1名~3名が派遣され続けている。BRDBにおけるインタビューでは、これまで派遣された協力隊に対する評価は概ね高く、また今後も様々な農業・農村開発分野に協力隊員の派遣を望む要望が出された。しかしながら、専門家と比較し協力隊は機材供与が少なく、また協力隊の技術レベルはTrainer's Training(指導者養成)をするには不十分な部分があるので今後の派遣には専門家をリーダーとしたチーム派遣6を望む声が聞かれた。このように、協力隊に対しより高い技術力を望む声はBRDBのみならず、バングラデシュ国で今回対象とした職業訓練センターやその上位機関の労働人的資源省でも同様の意見が聞かれた。また協力隊の技術力を補う理由で専門家の派遣を望む声はダッカ子供病院も含めバングラデシュ国で対象とした全ケースで同様の意見が聞かれた。但し、専門家派遣を望む背景には、より高い技術と知識を望むと同時に、その専門家が携行する豊富な資機材と調査費に大きな期待が向けられている。この理由として、バングラデシュ国側からは、「協力隊員から良いアイデアが出てきても、協力隊員の調査費は少ないので協力隊員の力では実施できない。そのため、隊員はバングラデシュ国側に支援を要請してくるが、そのような予算はない。しかし専門家であれば独自の調査費があるので、アイデアが推進し易い」との意見であった。
また、バングラデシュ国における「協力隊事業の目的」に対する現地アンケートでは、「技術協力」および「指導者の養成」とする回答は93%(28/30人)、「文化交流」「日本の理解」「二国間の友好関係」とする回答は87%、「日本の青年育成」は60%であった。単にバングラデシュ国の開発に直接貢献することだけでなく人と人との交流、日本に対する理解、また青年育成という観点からも青年海外協力隊事業の独自性はある程度受入れられている。「日本の青年育成」とする回答は、所属先の上司や責任者だけでなく、同僚レベルからも回答されていた。これは、同僚レベルの年齢が協力隊員よりもかなり年上であることが理由の一つともいえる。現在バングラデシュ国では中央の公務員の新規採用が一部ストップ(BRDBでは1985年以降雇用がほとんどなく、一番若くても40代)しているため、例え同僚レベルであっても協力隊員よりもかなり年上であることが多く、経験も豊富な場合が多い。また、このことは、協力隊よりも専門家を望む意見を促進する要因の一つとも言える。
一方、ニジェールにおいて青年海外協力隊事業は日本の援助事業の中で中心的な存在の一つと言える。日本人専門家や調査団の数がバングラデシュ国と比較すれば非常に少ないことから、日本人=協力隊であり、協力隊に寄せられる注目度や期待度は当然のことながら高い。また日本人専門家がほとんどいないことから、専門家と協力隊を比較する発想はほとんどない。但し、バングラデシュ国同様に協力隊が持ち込む資機材に対する期待は非常に高かった。隊員の報告書からは、配属先が、人(隊員)よりも物(資機材)に対する興味が高いことが、協力隊員達の活動志気を最初に落ち込ませる要因の一つになっていることが明らかとなっている。
農業省におけるインタビューでは「将来的には協力隊の派遣計画を農業省のアクション・プランに組み込めることを期待するので、要請から派遣までの期間をなるべく短縮してほしい」との意見が聞かれた。現在までに延べ100名以上の隊員が農業省所属で活動しているが、この意見は協力隊の活動成果を評価した上で、農業省としては協力隊の活動を計画の中に取り込んでいきたいという、期待を示すものといえる。またプロジェクト型の協力隊派遣(チーム派遣:カレゴロ緑の推進協力プロジェクト)が実施され、成果を出してきた経緯があることから、協力隊の活動成果についても高い評価をしている。
ニジェール国における「協力隊事業の目的」に対する現地アンケートでは、「技術協力」および「指導者の養成」とする回答は85%(23/27人)、「文化交流」「日本の理解」「二国間の友好関係」とする回答は89%、「日本人の青年育成」は15%であった。ここからは、「技術協力」に対する協力隊への期待も高いが、“日本”という国を理解したい、あるいは友好関係を築きたい、という意見が若干ではあるが「技術協力」への期待を上回る結果となった。バングラデシュのように日本人(専門家、調査団、また日本企業の駐在員など)が多く滞在し、日本のテレビ番組(例:おしん他)が放映され、日本が最大の援助国となっている国と比べれば、ニジェールにとって“日本”はとにかく遠い国であり、日本の風土や文化を知る機会は限られている。また、ニジェール国で直接日本人と知り合う機会は、協力隊員が主となる。この点については次の「国際交流・二国間関係の増進」に対する評価で詳細述べていく。一方、青年育成に対する回答は27名中4名で、すべてが地方の配属先の責任者であった。このため、日本の青年育成という観点はほとんど認識されていないと言える。
以上をまとめると、バングラデシュ国では協力隊の継続的な派遣を望み、「技術協力」や「指導者育成」に対するニーズは高いが、現状の協力隊派遣を今後も期待しているのではなく、より高い成果を求め、技術力の向上や調査費・資機材の投入を望む傾向が明らかになっている。この理由の一つとしては、協力隊事業が日本の他の援助スキームと比較した場合、非常に小規模であり、得られる成果も小さいことがあげられる。また、日本を始め、イギリスやドイツからも多くの協力を得、NGOの活動も盛んな国であることから、近年の援助事業の成果を重視する傾向及びその評価に対する重要性が浸透してきていることも一つの要因と考えられる。この成果主義の潮流は、特にバングラデシュ国の中央省庁にとっては“協力隊員は実務経験が少ない”、“技術・知識の面から不足”との評価を促進させている。一方、協力隊を受入れてきた歴史が長いこと、協力隊の同僚が隊員よりもかなり年上であることから、協力隊事業の目的を「日本の青年育成」とする点についても理解が進んでおり、「国際交流・二国間関係の増進」を含め協力隊事業に対する総合的な理解がされている。しかしながら、協力隊事業に量よりも質や成果の改善を望む声が多いことから、バングラデシュ国側にとっては、「日本の青年育成」や「国際交流・二国間関係の増進」について理解は示すものの、その重要度が高いとは言えない。
ニジェール国においては、協力隊事業がニジェール国全体に対する日本の援助の中でも中心的な役割を担っており、他の援助スキームと比較しても代表的な存在である。このため、ニジェール国側が協力隊事業によせる期待は高く、中央レベルから受益者レベルまで協力隊に対するニーズは高い。また協力隊員の存在はニジェール人が初めて日本を知る機会にも貢献している。さらに、バングラデシュ国のように協力隊に対し今以上に高い技術や知識を求める意見はほとんど聞かれず、改善点としてはコミュニケーション能力の向上(語学力)が多くあげられた。当然ながら、このことはニジェールに派遣される隊員の方が、バングラデシュ国に派遣される隊員よりも技術・知識力が上回っていることを示すものではない。協力隊の受け止め方の相違に影響を与える要因は、バングラデシュ国とニジェール国の援助環境の違いがあげられる。前項の(1)でも述べたが、バングラデシュ国とニジェール国では、日本を含め他ドナーの援助規模に大きな相違があり、ニジェール国の援助規模はバングラデシュ国と比較すれば非常に小さい。このため、協力隊事業に期待する度合いは必然的に高くなる。しかしながら、ニジェール国において、協力隊に関係する担当以外での協力隊の知名度は低く、同じ所属先機関でも担当が違うと「協力隊のことなど全く知らない」というケースが見受けられた。また、協力隊事業が「日本の青年育成」という要素を含んでいる点については、ほとんど意識されていない。
(3)ケーススタディの5項目評価(妥当性)
今回の調査では、バングラデシュ国とニジェール国において計8件のケーススタディ行った。ここでは、5項目評価における妥当性から協力隊事業に対するニーズの検証を行う。表4-3は、各案件を要約した結果である。
| 国名 | 案件名 (職種) |
妥当性注) | 要 点 | |
| バ ン グ ラ デ シ ュ |
カルポリ計画
(シニア隊員、手工芸、市場調査、婦人子供服、 在庫管理、経済)) |
** | ・地域の社会的弱者である農村女性達のニーズを拾い上げ、女性達の潜在能力(伝統的手工芸品)に目を向けた協力隊派遣であった。このため、最終受益者層のニーズには合致した派遣計画であったといえる。
・また、当時日本の援助スキームにおいて、WID(開発と女性)や女性のエンパワーメントに対する配慮がやっと進められようとしていた中では非常に先駆的な計画であったと言える。 ・しかしながら、派遣の長期化とともに達成しようとする成果が多様化し、目標や最終目標を不明確化させている。またバングラデシュ国側の上位機関との計画調整に不十分な点があった。このため計画のデザインには問題があったといえる。 |
|
| ダッカ子ども病院 (看護婦、臨床検査技師) |
** | ・バングラデシュ国において、唯一の子供専門の病院であることから、患者である子供達と患者の母親のニーズに合致した派遣であったといえる。
・日本の医療機材供与が数回に渡り行われている。これらの機材の維持管理や使用方法の指導を隊員に期待することができるが、隊員の派遣計画・内容と医療機材供与の連携は取れていなかった。 ・長期的な派遣計画がなく、また最終的な目標も不明確なまま派遣が続けられていた。 |
||
| 技術訓練センター (婦人服、電気機器、電子機器、冷凍機器・ 空調、配管、 溶接、図学 他) |
** | ・開校当時は、国外(特にアラブ諸国)への技術者ニーズが高かったため、技術訓練センターの強化につがなる協力隊の派遣はバングラデシュ政府方針とも合致し、ニーズも高かった。
・日本の先進技術を習得したいとするニーズは高い。 ・しかしながら、長期的な派遣計画や目標がないままに、20年以上派遣が続いている。またセンターの位置付けが技術訓練から進学学校へと変化しているにもかかわらず、派遣計画の見直しは行われていない。計画デザインの妥当性は低い。 |
||
| ニ ジ ェ | ル |
ポリオ対策 (シニア隊員、ポリオ対策隊員、 自動車整備) |
*** | ・明確でシンプルな計画デザインであるため、成果や目標がわかり易い。
・ポリオ撲滅に対する最終裨益者(地域住民)のニーズは高い。 ・国際機関の援助方針や日本の援助政策とも合致している。 |
|
| 就学前教育 (幼稚園教諭、保育士) |
** | ・就学前教育に対するニジェール国の教育政策と合致した派遣であった。このため特に省レベルのニーズは高い。しかしながらニジェール国において幼稚園に入学できる子供は非常に限られた存在であることから裨益者層の規模は限定されているといえる。
・語学教育中心の就学前教育の現場に対して、情操教育導入の重要性を説き、浸透させることを隊員達が一貫して目標として取り組んでいる。 |
||
| 農村生活向上 (果樹、野菜、栄養士) |
* | ・農村生活の向上に貢献する分野への派遣であることから最終裨益者(地域住民)のニーズは高い。
・派遣計画では、同地域に異なる職種の3名の隊員を配属することで、有機的に結びつき活動していくことが期待されているが、実際には各自の活動目標に従って活動しているため、3名が同地域に派遣された意義が不明確である。後続隊員も同職種で3名派遣されているが長期的計画・展望は不明確である。 ・JICA国別事業実施計画(協力プログラム)と隊員活動とのギャップが大きい。 |
||
| 青 年 育 成 |
青少年活動 (青少年活動) |
** | ・地域住民側から提示されたニーズではないが、地域住民と一体となって地域の潜在的ニーズを拾いあげた活動計画は、最終的には地域に受け入れられたものとなっている。
・長期的な派遣計画や展望がないままに、後続隊員の派遣が行われている。 |
|
| 体育(体育) | ** | ・体育教員の育成が遅れているため、体育教員の不足を補う、という点ではその妥当性は高い。
・最終裨益者(中学校の生徒と地域住民)にスポーツを浸透させることで最終裨益者層の新たなニーズ(バレーボール活動の推進)を生み出している。 ・長期的な派遣計画が不明確で、ニジェール国側の体育教員の育成を目指した派遣計画にはなっていない。 |
||
[***:妥当性が非常に高い、**:妥当性は高いが一部問題点を有する、
*:妥当性は一部高いが問題点も多い、なし:妥当性が非常に低い]
ケーススタディの妥当性に対する検証から、「最終受益者のニーズの高さ」が協力隊事業の特徴として明らかになった。この理由は、協力隊員が住民と直接の接点を持ち続けながら協力活動を行っているため、最終受益者のニーズがごく自然に取り込まれ、配慮されているためでろう。このことは協力隊員の活動の特質を示すものといえる。また、協力隊事業は日本の援助スキームの中において、相手国の“最終受益者のニーズとの整合性”という点で特に重要な役割を果たしてきたといえる。
しかしながら、計画デザインの妥当性はほとんどの案件で低い。目標や上位目標が明確な案件(ポリオ対策)については、計画デザインがシンプルで相手国の開発方針や政策とも日本政府の援助方針とも合致し、その妥当性が高いことが明確にわかる。一方で、隊員の派遣が中長期化している案件(特にダッカ子供病院、職業訓練センター)については、長期的な派遣目標や上位目標が明確に打ち出されていないため、個々の隊員の活動目標に一貫性や方向性がなく、同地域や同配属先に複数あるいは継続して派遣されているメリットが阻害されている。また、計画デザインに対する改善がなされれば、「最終受益者のニーズの高さ」という特徴が最大限に活かされるはずである。
また、協力隊員の要請が現場レベルから出された場合、配属先の上位機関が協力隊員の具体的な活動内容をあまり把握してない場合が見られた(ニジェール農村生活向上など)。要請内容だけでなく、協力隊員の実際の活動目標や活動内容は相手国の上位機関に把握され、相手国の開発方針などとの妥当性を見定めることも大切である。さらに、JICA国別事業実施計画(ローリングプラン)における協力隊員の位置付けと、実際の隊員活動との間にギャップが見られるケースがあった。例えば、ニジェール農村生活向上は、ニジェール国別事業実施計画の重点分野における協力プログラム(農業農村基盤整備支援)の位置づけで同地域に3名派遣されたが、隊員達の活動内容は隊員個人の自主性に任され、協力プログラムでの目的は全く意識されていなかった。このため、隊員活動としては何ら問題ないが、協力プログラム(=日本側の援助方針)という位置付けから考えた場合には、この派遣の妥当性は非常に低いと評価せざるを得ない。協力プログラムの中に協力隊員を盛り込むことは相手国に対する効果的な援助を実現する上で大切であるが、協力隊員の技術力、相手国側の開発課題における重要度および日本側の援助方針の重要度などを十分に見極めた上で中・長期的な派遣計画を策定するとともに、実際の隊員活動についても支援やモニタリングできる体制が必要である。
(4)協力隊員側から見た、配属先の受入環境 -協力隊員の活動に対するニーズ-
帰国隊員に対し実施したアンケート結果から「配属先の協力隊員の活動に対するニーズ」が“低かった”“あまり高くなかった”とする回答は36.8%あった。また、この問いに対し、“その他”とする意見が10.6%あったが、その多くは「ニーズが最初から無かった」「隊員は必要とされていなかった」「要請と求められる活動が異なっていた」などの記述意見が目立った。さらに、この帰国隊員アンケート結果をクロス分析すると、“ニーズがあまり高くなかった”=“隊員の活動の目標達成度が低い”=“配属先の活動計画と役割分担が無い”=“技術・知識のレベルが一致していない”という構図が明らかとなる。相手国や配属先のニーズと協力隊の派遣との整合性は、派遣の妥当性を評価する上で重要な要因である。また、隊員の“活動の目標達成度”は、「相手国の社会・経済発展への寄与」に対する有効性を測る要因であり、“技術・知識レベルの一致”は効率性を測る要因である。このため、アンケート結果からのみ判断すれば、約3割以上の協力隊派遣の妥当性は低く、また効率的かつ有効に社会・経済発展への寄与が行われていない、との評価結果になる。
しかしながら、活動開始時点での配属先のニーズが低いことは協力隊事業が他の援助スキームとは異なる特色の一つともいえる。隊員活動は、着任してから現地の社会文化を体得し、配属先の同僚や受益者層の人との交流の中から現地のニーズを知り、その中で活動計画を立案し、配属先の同僚の協力を得ながら活動していく場合が多い。このため配属先が協力隊員に求めるニーズが低く、活動計画や役割分担が無くても、隊員は自身の力でニーズを調査し、活動内容を決定していくことがある程度求められている。
但し、アンケート結果にもあるように、配属先のニーズが低い、と隊員が受け止めることは、目標達成度を低く抑える要因である。相手国の社会・経済事情や援助事情の変化の速度は、国や地域によって大きな違いがあり、求められるニーズも異なる。この中で、隊員自身がニーズを探し、活動し、成果出すことを2年間という協力期間で求めることは非常に困難となっている。また、現地の協力隊調整員からのヒアリングでは、最近の隊員と以前の隊員と比べた場合、「ニーズを自分の力で調べ、活動内容を決定していくことに悩む隊員が増加する傾向にある」とのことであった。逆に、ある程度活動内容が明確に提示されている場合には、「目標に向かって活動を進めていくことが得意である」、とのことであった。
帰国隊員の目標達成度に対するアンケート結果を配属先での位置付け(1.マンパワー提供型7、2.指導型8、3.共同活動型9)で分類した場合、マンパワー提供型が、指導型や共同活動型よりも、目標達成度が高い結果がでた。隊員報告書によると、従来、マンパワー提供型の活動は、配属先の中で協力隊員自身が歯車の一つとなって活動を行うため、カウンターパートや同僚への技術・知識の移転が難しいとされ、協力隊員達はマンパワー提供型の活動に陥ることを何とか回避しようと努力する傾向が見られた。ケーススタディにおいても、隊員達の活動がマンパワー提供型に陥り、苦悩する様子がいくつかの案件の隊員報告書から明らかになっている。
しかしながら、マンパワー提供型はアンケート結果から増加傾向(S56年次:6.7%、H8年次:13.2%、派遣中:21%)にあり、逆に指導型は減少傾向(S56年次:56.7%、H8年次:46.2%、派遣中:45.2%)にある。ここには、途上国側の協力隊に対するニーズとして、途上国の人材では補えないポジションを補うために、協力隊員の投入を求める形態が増加していることが考えられる。このことは、帰国隊員へのアンケート結果からも考察でき、配属先のニーズが高かったとする割合はマンパワー提供型(68.9%)が指導型(59.8%)や共同活動型(47.6%)よりも多くなる結果がでている。
(5)結果
相手国の援助規模や受入環境の相違が、相手国の協力隊に対するニーズの質に何らかの影響を与える一要因となっていることが明らかとなった。例えば、バングラデシュ国では、配属先によっては高度な知識・技術を有する協力隊員の派遣を望む傾向にあり、また他ドナーの援助方針の潮流を受け、“成果”や“評価”を意識した受入環境となってきている。このため、今回調査中にバングラデシュ国側から、30年間の協力隊事業に対する日本側との合同評価調査のアイデアが出された。一方、ニジェール国では、協力隊事業が関係省庁レベルにおいて、その成果が高く期待されているが、協力隊事業に対する理解度や知名度については、バングラデシュ国に比べて低く、どちらかといえば受身の姿勢が強く、協力隊事業に対するオーナーシップが低い受入環境となっている。ニジェール国の開発課題と協力隊事業との妥当性を高めていくためにも、ニジェール国側の各レベルを巻き込んだ積極的な議論展開が必要である。また協力隊事業の知名度や理解度を適切にニジェール国内で高めていくことは、隊員達の受入環境を整えるとともに、協力隊事業に対する“横の広がり”、例えば隊員の配属先間の連携やネットワークの構築、他ドナーやNGOとの意見・情報交換などにつなげていくためにも重要である。
アンケート調査からは約3割の帰国隊員が配属先の協力隊員の活動に対するニーズは高くなかったとしており、その場合の隊員自身の目標達成度は低くなる傾向にある。しかしながら、相手国側からは、日本の青年が持つ技術・知識を移転してほしい、というニーズが非常に高い。加えて、現地の言葉や文化・慣習を理解し、地域社会に溶け込みながら地道に協力活動を行う隊員達の姿勢は、カウンターパート、同僚、および地域住民に非常に好印象・好影響を与えている。
また、ケーススタディに対する妥当性の検証から、協力隊事業の特徴として「最終受益者のニーズの高さ」が明確になっている。このことは、日本の援助スキームの中で協力隊事業が“最終受益者のニーズとの整合性”という点に対し重要な役割を果たしてきたものと評価できる。しかしながら、中長期的な派遣目標や上位目標が明確に策定されていないために、結果として「最終受益者のニーズの高さ」という利点が十分に活かされていないケースが今回多く見受けられた。いずれも当初計画のデザインに対する改善がなされれば、最終受益者のニーズを十分に反映し、かつ相手国の開発課題への取り組みに合致した派遣が可能であると考える。
さらに協力隊員側と相手国側とのニーズに対する認識の格差についても、派遣計画の策定段階で配属先を適切に巻き込んでいくことができれば、その格差を埋めていくことが可能であり、協力隊の国別派遣計画や要請背景調査・要請開拓の質的向上(派遣目標や上位目標などの明示)にかかっている。相手国側が協力隊事業を正しく理解した上で、協力隊に求めるニーズを合致させ、また日本側は相手国の受入環境や援助動向を十分に把握していく必要がある。特に同配属先への協力隊派遣が長期化される場合には、配属先のニーズの変化や協力隊員の受入環境をモニタリングし、後任隊員の要請開拓に反映させていくことが重要である。
6 チーム派遣:職種の異なる、あるいは同一職種を複数派遣し、有機的かつ総合的な協力活動を目的として、より大きな協力効果をめざした派遣形態の一つ。受入国側に対してもいっそうの参画を求め、協力隊事務局(または在外事務所)と受入国政府との間でプロジェクト実施に関する合意文書が作成される。
7 マンパワー提供型:配属先の人材では補えない役務を担うために、協力隊員の投入を求める活動形態
8 指導型:配属先のカウンターパートや同僚に隊員が有する技術・知識を指導していく立場にある活動形態
9 共同活動型:配属先のカウンターパートや同僚と共同で協力活動を行い、その活動を通じて隊員が有する技術・知識が共有されていく活動形態

