3-4. 青年海外協力隊事務局の取組み
近年事務局が取り組んでいる課題から「相手国への社会・経済発展への寄与」に関連する1.新規派遣と2.ボランティア事業の国別地域別アプローチに対する方針、及び「人材育成、日本社会への貢献」に関連する3.隊員への支援と4.現職参加の促進に対する取組みについて述べていく。また、5.として事務局が協力隊創立30周年を契機に取り組んだ「協力隊事業の総点検」についての概略を整理する。
平成13年度当初実施計画では1,250名の派遣予定が、実績では1,050名であり、応募者が年々増えているにもかかわらず、新規派遣人数はここ数年横這い(平成10年1,093名、平成11年1,248名、平成12年1,135名)状況である。この背景には応募と要請のアンバランス、つまり国内ニーズと相手国側のニーズのマッチングが必ずしもうまくいっていないという問題点や健康診断での不合格者の増加(全体で約28%)の問題などがある。ここでは特に要請職種と応募職種の不均衡について、平成13年度の秋募集の選考結果から考察していく。
(1) 応募職種と要請職種の不均衡
相手国側からの要請は、途上国の産業構造に比例して第一次産業および加工部門・工業部門の技術に対する職種が依然として多い。しかしながらこれらの職種については年々国内の応募者数が急速に減少傾向にある。一方、下図のように平成13年度秋募集の応募者4,256名のうち1,528名(36%)が村落開発普及員、日本語教師、青少年活動の3職種に集中し、非常に高い倍率(村落開発普及員10.5倍、日本語教師6.7倍、青少年活動27.1倍)となっている。これらの職種の応募者はいわゆる文科系のバックグラウンドを持つ青年達である。また、応募が多い上位7職種で、応募者の約50%が占められるなど、応募が集中する職種と応募が極端に少ない職種との偏りが大きくなっている。
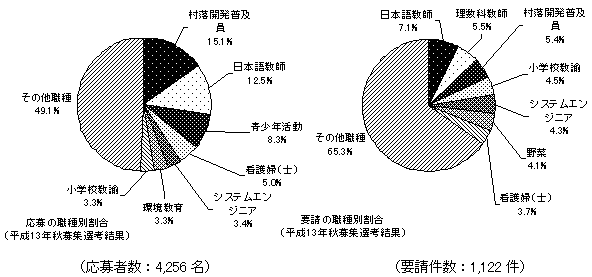
図3-2 応募と要請の職種別割合
一方、要請職種においては、上の図3-2のとおり日本語教師、村落開発普及員、システムエンジニアなど応募が多い職種と要請が多い職種が一致している職種もあるが、これらは一部の職種に限られ、応募側のように特定職種への偏りは小さい。また職種によっては応募者がゼロの場合もある。
下表3-2は、平成13年秋募集において応募数が要請数に満たなかった職種を不足数が多いものから順に示した表である。1位にあげられている理学療法士は、要請件数が26件と全要請件数の中でも要請が多い職種である(表3-3参照)。また、合気道、体育競技、新体操は、要請件数に対し応募人数が数ないだけでなく、2次合格者がゼロとなっている。
| 順 位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
| 職種 | 理学 療法士 |
作業 療法士 |
臨床検 査技師 |
木工 | 合気道 | 体操 競技 |
新体操 | 電子 機器 |
義肢装 具士・ 作成者 |
花き |
| 要請件数 | 27 | 16 | 17 | 10 | 19 | 6 | 6 | 19 | 4 | 5 |
| 応募人数 | 16 | 10 | 12 | 5 | 14 | 2 | 2 | 18 | 3 | 4 |
| 不足数(要請-応募) | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2次合格 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 順 位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
| 要 請 数 が 多 か っ た 職 種 |
職 種 | 日本語 教師 |
理数科 教師 |
村落 開発 普及員 |
小学校 教諭 |
システ ムエン ジニア |
野菜 | 看護婦 (士) |
体育 | 養護 | 理学 療法士 |
| 要請件数 | 80 | 62 | 61 | 51 | 48 | 46 | 41 | 39 | 29 | 27 | |
| 応募人数 | 533 | 127 | 643 | 140 | 144 | 78 | 213 | 92 | 55 | 16 | |
| (倍率) | (6.7) | (2.0) | (10.5) | (2.7) | (3.0) | (1.7) | (5.2) | (2.4) | (1.9) | (0.6) | |
| 2次合格数 | 44 | 32 | 61 | 29 | 28 | 27 | 35 | 25 | 15 | 7 | |
| 充足率 | 55.0% | 51.6% | 100% | 56.9% | 58.3% | 58.7% | 85.4% | 64.1% | 51.7% | 25.9% | |
| 応 募 数 が 多 か っ た 職 種 |
職 種 | 村落 開発 普及員 |
日本語 教師 |
青少年 活動 |
看護婦 (士) |
システ ムエン ジニア |
環境 教育 |
小学校 教諭 |
理数科 教師 |
ポリオ 対策 |
観光業 |
| 要請件数 | 61 | 80 | 13 | 41 | 48 | 7 | 51 | 62 | 4 | 6 | |
| 応募人数 | 643 | 533 | 352 | 213 | 144 | 142 | 140 | 127 | 115 | 98 | |
| (倍率) | (10.5) | (6.7) | (27.1) | (5.2) | (3.0) | (20.3) | (2.7) | (2.0) | (28.8) | (16.3) | |
| 2次合格数 | 61 | 44 | 13 | 35 | 28 | 8 | 29 | 32 | 4 | 4 | |
| 充足率 | 100% | 55.0% | 100% | 85.4% | 58.3% | 114%注) | 56.9% | 51.6% | 100% | 66.7% |
図3-3は、部門別の要請件数に対する2次合格者数を充足率として示したものである。全体では55.6%で、前回の平成13年度春募集とほぼ同じである。しかしながら、全体平均を上回る農林水産部門の充足率59.5%には応募数と要請数ともに多い充足率100%の村落開発普及員(要請・合格とも61名、表3-3参照)が大きく貢献しており、この村落開発普及員を除いて充足率を算出すると45.9%と平均を下回る。また、農林水産部門の特長としては、職種が非常に多岐に渡っていることがある。例えば今回秋募集で充足率がゼロ(合格0名)であった職種をあげてみると、漁業生産(要請7名、応募7名)、きのこ(要請7名、応募0名)、土壌肥料(要請7名、応募0名)、飼料作物(要請1名、応募2名)、農業協同組合(要請2名、応募1名)、漁業協同組合(要請1名、応募2名)、園芸作物(要請2名、応募1名)、乳製品加工(要請1名、応募2名)と8職種にのぼっている。多くの途上国において農林水産分野は基幹産業であることからこの分野への派遣は相手国側にとっては期待される派遣である。事務局としては、途上国の基幹的な分野に対する対応をさらに検討し、例えば農業部門であれば農業大学校等に通っている農業後継者をターゲットにして、将来日本の農業を担っていく人材に、海外での活動を経験してもらうような方策も検討している。 注)農林水産部門Aは村落開発普及員を含めた充足率、農林水産部門Bは村落開発普及員を除いた充足率。
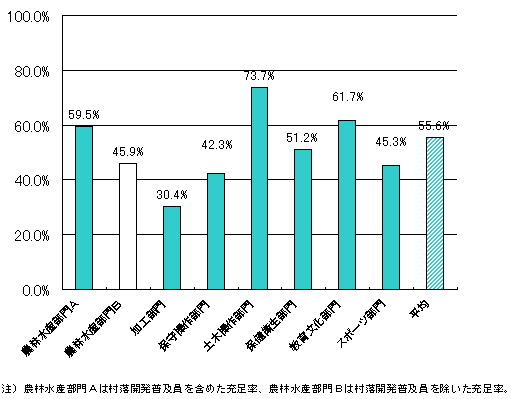
図3-3 部門別充足率(2次合格者数/要請件数) -平成13年秋募集選考結果-
(2) オファーと登録制度
この要請と応募のアンバランスを解消するために、事務局では要請技術を持った人材を探す努力を続ける一方で、協力隊に参加したい人たちが持つ技術内容・知識で、実際に相手国で役立つ要請を開拓するという方法にも力を入れ始めている。これは“オファー”と呼ばれ、青年海外協力隊事務局より在外事務所に候補者データを送り、候補者にあった要請を出してもうらうよう依頼することである。つまり日本側の人材データを持って要請開拓に行くことである。
しかしながら応募者が多い「村落開発普及員、青少年活動、日本語教師、システム・エンジニア」と言った職種は歴史が浅く、また現地側のニーズに沿って具体的な活動内容を策定することは時間と労力を必要とすることから、限られた調整員達でこれらの職種に対する要請開拓を行うことは現地事務所側の負担になっているのが現状のようである(現地インタビュー調査)。
事務局としては、これらの職種の成功例(例えば、相手国側で喜ばれているケース)を取りまとめたものを各派遣国政府に提示し、日本側から容易に出せる職種の売り込みを行っていくことを検討している。
また、合格ラインには達しているが要請数が少ないか足りないために不合格となっている人材を積極的に登録・確保する「登録制度」が進められている。この登録制度は、平成13年度春募集より本格的に導入されオファーや繰上合格用として活用されている。
平成13年度の秋募集においては春募集の約2倍の197名が登録された(右図参照)。登録が多い職種は、応募倍率にほぼ比例しており、村落開発普及員と青少年活動で登録者全体の45%を占めている。部門別でも応募に比例し、教育文化部門と農林水産部門に登録者が多い。
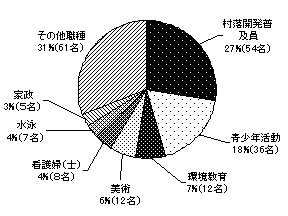
図3-4 登録の職種別割合 -平成13年度秋募集選考結果-
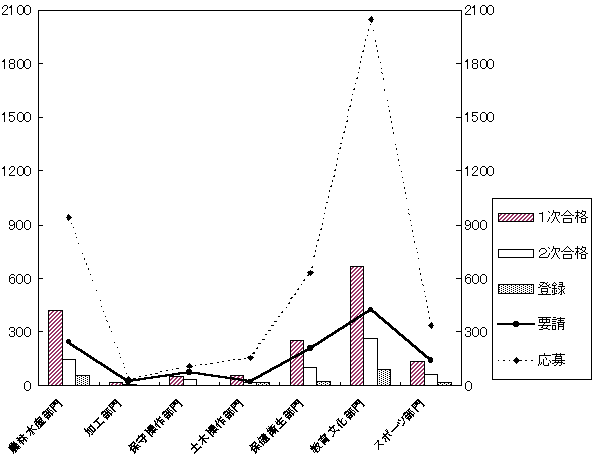
図3-5 部門別の応募、要請、合格、登録 -平成13年度秋募集選考結果-
3-4-2.ボランティア事業への国別・地域別アプローチの適用
「ボランティア事業への国別・地域別アプローチの適用 調査研究報告書」4によると、JICAは国別・地域別アプローチを推進するために、2001年1月より地域4部の新設を始めとする組織改革を行い、国別・地域別アプローチを推進するツールとしてすでに平成9年度より課題別要望調査の導入、平成10年度からは国別事業実施計画の策定を行っている。また、課題別要望調査においては、従前のスキームごとの検討を改め、セクター/課題の全体的把握・分析から出発し、開発課題を抽出し、右解決のための適切な援助スキームの組み合わせを検討し、「JICA協力プログラム」として要請を取りまとめる方式がとられている。JICA協力プログラムの定義は、「特定の開発目標達成のために投入が計画された相互に直接的な関係を持つ案件群」とされている。
国別事業実施計画には、JICA全体として、ある国や地域に対してどういう分野を重点的に協力していくかが戦略的に策定されている。また、課題別要望調査と連動し、今後の予定を含む5年間のローリングプランが、協力隊の派遣計画を含めて形で記載され、JICAによる協力の中期的な方向性を対外的に提示している。ただし、協力隊事業のようなボランティア事業には、技術協力以外の側面(ボランティア自身の成長、国際理解の促進等)があること、及び国民参加型事業で公募制のため、人材の確保・派遣時期等に不確定な要素があることから、厳密な計画に沿った計画に困難が伴うこともJICA内では想定している。このため、ボランティア事業を国別事業実施計画のなかでの「JICA協力プログラム」として全面的に位置付けることには無理が生じる可能性がある点について留意する必要があると「ボランティア事業への国別・地域別アプローチの適用調査研究報告書」にも明記されている。また、国別事業実施計画のなかで援助重点分野とはされていないもの、例えば文化・スポーツ部門等については、広い意味での相手国の“人づくり”に貢献しているととらえることが可能であるため、援助重点分野に入らない協力隊の派遣分野に関してもその優先順位が低いことを意味しない、とされている。
ボランティア事業への国別・地域別アプローチの基本方針5は以下のとおり。
| 当該国におけるボランティア事業の特性・過去の知見を有効に活用し、かつ今後のボランティ事業の展開を明確にしたうえで、国別事業実施計画との整合性を保った新しい派遣計画の様式(案)を事務局で作成する。国別事業実施計画策定49か国(JICA在外事務所所在国)についてはその別冊として添付し、全事業団および外務省の認知度を高めていくことを検討する。 また、国別事業実施計画策定49か国以外の国ですでに派遣計画を作成している国(駐在員事務所、調整員事務所所在国)については、協力隊事業を中心とした国別事業実施計画の一部(開発マトリックスと事業ローリングプラン)を作成することを検討する。 |
この取組みは平成13年度国別派遣計画より試験的に導入が開始され、平成14年度からは本格的に実施されることになっている。今後は、協力隊の隊員の活動分野を可能な限りその国の重点事項に投入させていく方針である。特に日本人専門家が少ないアフリカは、日本の技術協力の中で協力隊員の占める部分は非常に大きい。また、その国の重点事項と協力隊員の活動分野を重複させると、隊員にとっては大きなやりがいになることもボランティア事業への国別・地域別アプローチの適用調査研究の結果から明確になっている。
しかしながら、現時点においては、現場レベルの国別・地域別アプローチへの対応は、必ずしも容易ではないようである。隊員派遣計画を担当業務や職種別にJICA国別事業実施計画に合わせていくことは比較的簡単にできるが、隊員個々の活動内容や活動成果を熟慮すると必ずしも国別事業実施計画の開発重点課題に貢献してない派遣も一部含まれてしまう。また、協力隊事業予算と隊員派遣数の関係、新制度(教員特別参加制度など)の導入で、隊員要請確保の依頼が事務局より現場にくるが、現地インタビュー調査結果によると、それらの要請は必ずしも国別事業実施計画や隊員派遣計画に即したものでなく現場では矛盾が生じているようである。
専門家や協力隊員をバックアップする目的でJICA本部に「派遣支援部」が平成12年度新設された。その結果、福利厚生・健康管理体制の拡充や協力隊OB/OGといった若手人材の活用・育成等を一元的に支援する体制が強化されている。また、青年海外協力隊事務局内には帰国隊員の進路開拓および社会活動の支援などを目的として平成12年度から「帰国隊員支援室」が設置されている。支援室では、国際協力分野における人材育成を図るため、帰国隊員の総合的なキャリアパスの仕組み作りのための関係機関との調整・協議も実施している。
(1) 健康管理と安全対策
これまでの健康管理室は、JICA職員、専門家および協力隊員それぞれ別々に機能してきたが、これを一本化し、医療面においても総合的に支援することが可能となった。平成14年度においては、セクター別、専門別に加え、地域別の健康管理体制を構築し、それぞれの地域に特有の疾病に対する対応を強化していく方針である。また、平成14年度予算では健康管理員を9名から18名に拡大されることになっており、特に健康管理に問題のある地域に配置される予定である。
平成12年度においては、交通事故等により4名の隊員が死亡している。こうした事故は隊員の赴任直後と離任直前に集中する傾向があることから、この時期に焦点を合わせながら事故防止に取り組んでいる。この結果平成13年度は病気による死亡が1名あったが、事故による死亡はゼロにおさえられた。
(2) 帰国後支援
協力隊OB/OGを優秀な人材として位置付け、環境整備を強化していく方針である。特に就職問題、日本社会への還元、および人材育成に力を入れている。
就職問題
帰国後の隊員が就職問題で苦労しないよう、1.企業や地方自治体に現職参加制度の導入、2.進路相談カウンセラーの増員、をしていく。
また、昨年度から始まり全都道府県に配置されることになっている国際協力推進員(JICA予算の国民
参加協力推進費より拠出)には原則として協力隊のOB/OGが配置されることになっている。来年度は26名配置されることになっており、これで全47名が都道府県に配置されることになる。
また、地方や都道府県の国際交流センター、国際交流協会などの団体への就職も促進していく。
日本社会への還元
帰国隊員の経験を日本社会へフィードバックしていくシステムの構築(総合的な学習時間の国際理解教育の講師など)についても検討している。特にサーモンキャンペーン等による開発教育の促進は、地方自治体が協力隊のOB/OGに期待するところでもある。
さらに、草の根技術協力事業費は国民参加協力推進費に中に新設され、例えば帰国隊員がNGOを起業する場合の経費を支援していく方針である。
人材育成
平成13年度に帰国隊員等人材育成奨学金制度をもうけ、国際協力共済会から年間1,000万円程度寄付し、協力隊を育てる会で運用し、帰国隊員の人材育成を支援していく。また、国際協力分野を目指す協力隊のOB/OGのために、各種セミナー、研修を積極的に実施していく。
要請開拓・背景調査の精度向上を目的とし、帰国隊員を対象とした要請開拓短期派遣の募集が2001年11月に実施され、帰国隊員の経験と見識を活用するテストケースと位置づけられている。
また、協力隊事業発足当時からの大きなテーマの一つでもあり、またこれまで多くの帰国隊員から提言されてきた「要請背景調査の記載内容と着任時の受入状況の相違を極力なくすこと」に、帰国隊員とともに取り組もうとする事務局側の姿勢でもある。
要請開拓・背景調査は本来現地事務所の調整員の役割であるが、調整員は全職種、全分野の専門性を持ち合わせていないこともあり、派遣中の同職種の隊員に同行を依頼するなどの工夫は重ねられている。しかしながら、抜本的な改善には到っていない。
隊員として活躍した視野、視点で、「日本の青年層の持つ技術・知識レベルに適した要請か」「活動内容や規模は実現可能か」といったまさに現場レベルの調査を行い、必要に応じて隊員活動のデモンストレーションを行い、配属先の理解や受入体制を整備することが期待されている。
4 「ボランティア事業への国別・地域別アプローチの適用調査研究報告書 2001年3月」は JICAのホームページ(http://www.jica.go.jp/activities/report/etc/200103_02.html)よりダウンロード可能。
5 「ボランティア事業への国別・地域別アプローチの適用調査研究報告書 2001年3月」より抜粋

